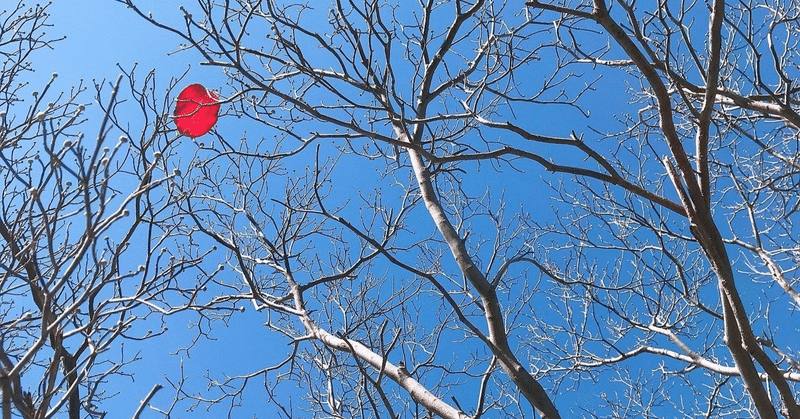
身軽になる読書
僕は、読書記録を「今は」つけていない。
数年前はiPhone付属のメモアプリにただひたすら読んだ本のタイトルと著者名を記録していた。そのときは「いかに多く」読むかに躍起になっていたので、読書に費やしたお金と時間をこえることは今後もうないような気がする。
ただもちろん、そのことが無駄だったかというとそんなことはない。
ないんだけど僕は読んだ本のタイトルがわかったとしても、内容や感じたこと、それを受けてどう影響されたか、のほうが大切だとおもっている。
「◯◯って本読んだ?」
「読んだけど内容はあんまり覚えてない」
僕もこういうときがよくある。ほんとうに悔しい。
だからこそ、noteに1000文字ほどで感想を書けるような本でないと「読んだ」とはいえないような気がしてしまう。
書けば頭に残りやすいし、もし内容を思い出せない場合でも「noteに書いたこと」自体を忘れることはあまりないのでまた読み返せばそれでいい。
−−−
今年、初の読書はこの本だった。
「感性は才能でもセンスでもありません。習慣で身につけられます。」
それがこの本のメインテーマ。そして以下の5つの習慣で身につけられるという。
・観察する
・整える
・視点を変える
・好奇心をもつ
・決める
習慣が大事という本は世のなかには山ほどある。そのなかでこの本いいな、とおもった理由をいくつか挙げる。
−−−
著者プロフィール
著者は、330年続く京都の窯元の家でうまれた陶板画作家。現在は銀閣寺のちかくの京町家で器を販売しているらしい。
芸術家だからなのか、京都にたいする贔屓目からなのか、本のなかで出てくるたとえがいちいち魅力的に映える。
茶道の点前、伊藤若冲の花鳥図。
たとえの端々にはその人の個性がよく現れるからこそ、日頃の「好奇心」が肝になるんだとおもう。
引き算の文章
文章の余白。
あえて語らずに読者に解釈してもらう。読み手はその想像をしているあいだに感性が養われているという。
そこで重要になるのが「短歌」である。
「5・7・5・7・7」で綴られる文章。
文字の数がかぎられているから書き手は取捨選択がむずかしい。それはこのnoteで身をもって実感している。
でもそのいい文章が、読み手の感性をつよく刺激する。無駄なことは書かない。いい習慣だとおもう。
新年を丁寧に心地よくむかえたい方にはぴったりのいい本だとおもいます。
−−−
去年はnoteに身も心も費やした感じがあった。
もともと書く習慣なんてなかったのに、楽しくて成長している実感があるから嬉しくて続けられた。
今年は「書かないように書く」を意識する。だから文字数は1000文字をきるぐらいが僕にとってはちょうどいいのかもしれない。
心地よく、気軽に。
僕の記事をここまでお読み頂きありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 頂いたご支援は、自己研鑽や今後の記事執筆のために使わせていただきます。
