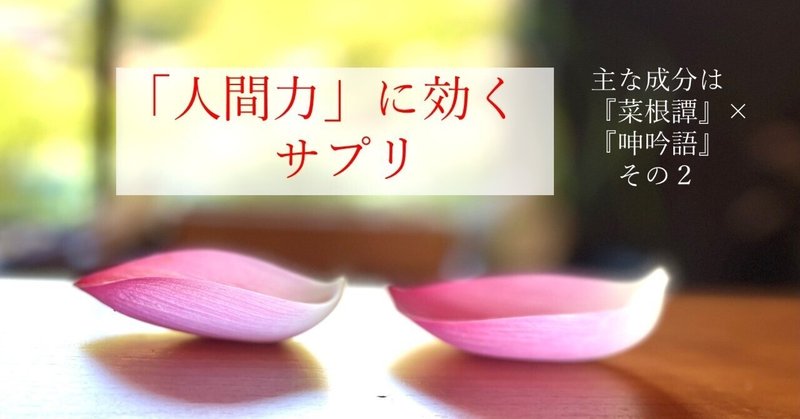
「理想」を下げれば「幸せ」に近づく―『老子』の考え
「無為自然」の境地が「幸せ」への近道⁈
「真の幸せとは何か」。中国思想の研究者、湯浅邦弘大阪大学名誉教授(以下、湯浅先生)のテキスト『別冊100分de名著「菜根譚×呻吟語」』をもとに、前回に続いて「幸せ」について考えていきます。
「幸せ」をより感じるためには、「理想」と「現実」のギャップを少なくすること。しかし、「現実」がなかなかレベルアップせず「理想」に近づいていかない、あるいは逆に隔たりが大きくなると、いまよりも「不幸せ」を感じてしまう。
そのリスクは避けたい。となると、夢や理想の大きさ(レベル)を調整し、「現実」に近づけることで「幸せ」を感じるアプローチをするのが、東洋的な考え方ということでした。
さて、東洋的な考え方を押し進めていくと、「理想」を引き下げて「現実」に近づけるほど、「幸せ」を感じやすくなる、ということになります。
それを突き詰めたのが、『老子(ろうし)』です。湯浅先生によれば、その説くところは、「無為自然(むいしぜん)」、作為がなく、宇宙のあり方に従って自然のままであること。そういう暮らし方をすることで、より「幸せ」を感じやすくなる、というのです。
ここで湯浅先生のテキストを離れて、『老子』の考えに触れてみたいと思います。
『老子』四十八章にはこう書かれています。まずは訳から。
知識を万能とする考えを、学問に志す者は日々に強めていく。だが、「道」にのっとる者は日々に弱めていく。弱めに弱めた究極に、無為の境地が開けてくる。無為の境地に達すれば、そのはたらきは自在である。
読み下し文です。
学を為せば日に益し、道をなせば日に損す。
これを損してまた損し、もって無為に至る。
無為にして為さざるはなし。
無為の境地に達すれば、そのはたらきは自在である。ということは、現実に縛られない暮らしや境地を目指しなさい、ということを言外にいっていて、それが「幸せ」を感じる秘訣である、と読み解くこともできそうです。
「足るを知る」ことで「現実」に満足する
もう一つ、「足るを知る」について述べている、『老子』四十六章を見てみましょう。まずは訳から。
かくも大きな厄災が起こるのは、なぜであるか。
かくも大きな罪悪が横行するのは、なぜであるか。
足るを知らぬ心と、飽くなき欲望とが、その原因にほかならない。
足るを知るとは、何かを得てそれに満足することではない。
あるがままの現実に常に満足することである。
読み下し文です。
禍は足るを知るより大なるはなく、
咎(とが)は得るを欲するより大なるはなし。
ゆえに足るを知るの足るは常に足るなり。
あるがままの現実に常に満足すること。つまり目の前にある日々の暮らしに常に満足するということは、読み替えれば、「現実」(の暮らし)がかぎりなく「理想」に近づいて、日々「幸せ」を感じて暮らしている。これぞ理想の暮らし方にほかなりません。
ところが、ついつい周りに目を向けて、他人の生活を比較するから、「幸せ」だという認識が薄れてしまう。幸せでいる自分を見失ってしまっているのです。
それはそれとして。
あるがままの現実に常に満足するために、「無為自然」な生活、「足るを知る暮らし」をすることを、現代に置き換えると、どんな暮らしをすることなのでしょうか。
理解が間違っているかもしれませんが、イメージできるのは、次のようなものです。
□短時間、実社会のなかで
デジタルデトックスをする
マインドフルネス、坐禅
物質的な豊かさよりも心豊かな暮らしを優先
□長期、都市生活を離れて
エコロジカルな暮らしをする
あるコミュニティで暮らす、または自給自足の生活をする
現代文明なかで「幸せ」を感じるには?
「無為自然」を実践する。1日のなかでは短い時間かもしれないけれど、1分1秒でも長くし、持続していく、というのなら、できそうです。
しかし、それは真の「無為自然」を実践していることにはならない。実社会から離れた生活をしないといけないとなると、「理想」をどんどん下げていくことで「幸せ」に近づくはずのことが、かえってハードルが上がってしまうように思えます。
これが万人向けの解決策としては、おすすめとはいえません。
では、現代文明のなかで、「幸せ」を感じるには、どういう考え方を参考し、実践していけばよいのでしょうか。
そのヒントとなるのが、『菜根譚』と『呻吟語』です。次回から、湯浅先生の解説をもとに、その教えに触れていきます。
『菜根譚』著者:洪自誠(こうじせい)。書名は、宋代の王信民(おう・しんみん)の言葉「人常(つね)に菜根を咬みえば、則ち百事(ひゃくじ)做(な)すべし」に基づいています。「菜根」とは粗才な食事のことで、そういう苦しい境遇に耐えた者だけが大事を成し遂げることができる、ということです。
『呻吟語』著者:呂新吾(ろしんご)。
書名の「呻吟」とは重病人のうめき声のこと。ただし、呂新吾自身が病気に苦しんでいたわけはなく、社会の混乱や腐敗に向けて発した嘆きを、「呻吟」という言葉に託した、ということです。
『老子』著者:老子(ろうし)
老子は無私無我を理想とし、「自然のまま、あるがまま生きよ」と説いた春秋時代の思想家。ことさらに知や欲をはたらかせず、自然に生きることをよし、としました。その著者とされるのが『老子』(正確には『老子道徳経』)です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
