
もっと優秀になる必要のあるZ世代
最近テレビでやたらと教育いびりが起こり、謎の教育評論家が今の教育の問題点について語っている.
最近の若者をみるとやたらに疲れているのが目に見えて分かる.僕は高校生だから大学生のことはよく分からないけど同世代の日常を見ていると凄い実感する時がある.
土曜日に学校に行って午前中に授業を受けて月曜日からは通常授業となる.毎日7時間弱、通学を合わせれば8時間以上が学校に使われ、土曜日も同じようなサイクルで動いている高校生は相当疲れると思う.
テレワークが社会で採用されて多くの企業で働くワークマンは仮想世界に移住しているのにも関わらず高校生は未だに移住の計画すら立っていない.それなのに社会ではAIが騒がれ、政治が騒がれ、経済が騒がれている.
言うならば高校生は社会から隔離された存在なのかもしれない.
だが、高校生は浪人しない限り3年間で終わってしまう.大学に向かう者も居れば就職する人も現れると、高校に入学するよりも多岐になると思われる.
社会は常に変化しているのにも関わらず教育は何十年間も変化せず未だ整列の文化が根強く残っていたり、宿題の文化が残っていたり、デジタル機器の使用が認められていなかったりなど第三者視点から見ても古い文化を感じることが多い.
なぜ古来のやり方を尊重したがるのか?理解し難いがそこに疑問を持っていても何も始まらないのも事実だ.
AI社会がのし掛かる人材の育成難
去年の10月にOpenAI社がChatGPTと呼ばれるAIツールをリリースし、あれから約10ヶ月が経とうとしている.今ではAIを利用したサービスは数え切れないほど存在し、利用は企業だけにとどまらずAIを利用したアルゴリズム政治家の確立や新薬の開発など国規模でのイノベーションも起こっている.
しかしAIが社会の中心となっていく今大きな問題が発生している.それが人材不足だ.AIに従事する人の数は以前もいたが実際は研究者が多く、企業でAI応用人材として働いていたのは大企業が一般的であった.
AIの利用はコストが大きく低下しスタートアップ系事業者に留まらず一般人の利用も可能となっている.
そこで注目されるのが、AI人材の育成という課題なのだがAI人材の育成など正直企業に数人程度、いうならば経営者だったりエンジニアの延長線的に数理的モデルで考える.
正直応用以外のAIの中身を見れば理系のオンパレード要素が大きい.視覚モデルのネオコグニトロンは人間の脳回路における視覚認識をネオコグニトロンによって多少のバイアスがかかっても正常に認識できるようなモデルなのだが、使うとなると理系人材に限られる.(使うも何も理論なのだが....)
応用であればAIサービスの使い方くらいで十分だろう.ましてや一般人や中小企業のAI利用であればプラグイン機能でいくらでもサービスの構築は可能な話だ.
ではAI社会の人材育成での難点は何か?
それは優秀な人材の不足である.
君のことを悪くいうつもりはないが、実際にそうなのだ.
AIの認識錯誤
AIに「ネオコグニトロンとCNNの違いについて述べてください」と質問してみた.すると2021年の情報までしかないため具体的な情報については把握していないと返してきた.
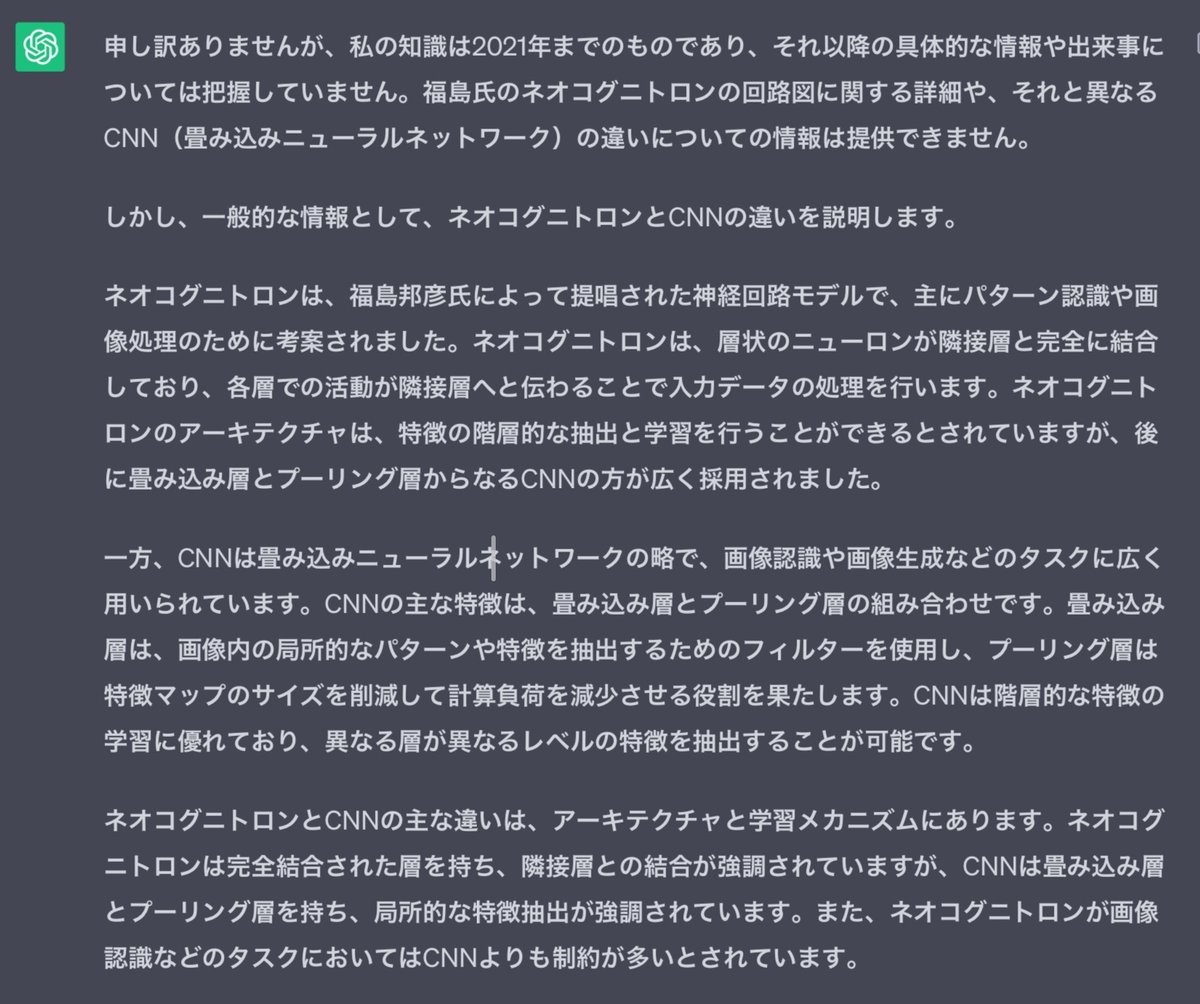
何か保険でもかけているかのような解答に少し戸惑いもありながら解答に目を向けてみる.かなり十分な情報が返ってきて少し驚いたがアーキテクチャと学習メカニズムという抽象的な言葉を使って少しあやふやないし解答にはなってしまっている.
実際、ネオコグニトロンは、「add-if silent」という学習方法を用いているのに対し、CNNは誤差逆伝播法(back propagation)と呼ばれる学習モデルを利用している.
C細胞とS細胞を交互に配列させており、可変結合パターン最適化が、CNNにおける畳み込みフィルタ最適化と同じ意味を持っているという話だ.
要は学習方法に大きな違いがあるのだが、その部分が上手く説明されていない.
少し前に安宅先生の自民党会合のpdf資料を見た時に概念的な部分で「『賽の河原とシーシュポスの神話の類似性』の認識が仏教的な世界観である賽の河原とギリシャ神話(シーシュポス)、エジプト神話を明らかに混同していた」とする説明があった.
要はChatGPTなどネット上にあるデータを分析しアルゴリズムで設計されたディープラーニングには大きな欠点が存在しているということだ.それが認識の錯誤問題.正当性があるように解答してくるのも少し戸惑いはあるがAIに関して言えば正当性を示しているわけだから当たり前の話だ.
労働者の重要性
「君はなぜ働くんだ?」という質問に対して君は答えるだろう?
「お金を稼ぎたいから」「生活をしていくため」が上位の回答になってくるだろう.
しかし実際に本当に「働きたい」、「仕事が好きだから」と回答する人はマイノリティになってくる.我々の中で働くという意識は「当たり前」となってくる.逆に働いていない人を見ると「社会のお荷物だ」という認識に自動的になるかと思う.
別に人間として地球にいる限り「働く」という必要はないはずだ.
それが今後の社会の考え方として主流になっていくのではないかと私は予想している.正直Z世代α世代は働くという観念は変化しないだろうが、それ以降の2世代3世代先となれば常識は大きく変化しているだろう.
その上で働くということを認識しておく必要があるのだ.
働くと聞いても頭の中には「働くという常識が消えるはずないだろ」と懐疑的に思う方が多いと思う.
しかし案外そうではない可能性が高いようだ.下の図に表しているのはAIが我々の仕事を代替させる可能性を示唆したグラフだ.もちろん日本もその可能性に含まれている.
AIが我々の仕事を存在となることを示している.世界全体の規模で見ると16%程度だが、日本を見ると25%弱となっている.確率が高いのは先進国を中心とした国なわけで、経済の中心がインターネットいわば仮想世界にあることが挙げられる.

この話は可能性の話であり、実際にはもっと代替されるかもしれない.Z世代が5、60代になった時には産業の半数以上はAIによって行われ経済はAIがAIを助けながら発展していく構造も考えられる.
AIが社会の中心となり我々はカスタマーとしてかAIの僕としてなのか.あるいは存在意義を果たせず人間だけの農耕社会を築き始めるのか.何もわからない.
しかし一つ言えるのは我々にとっていい結果が必ずしも待っているわけではないということだ.ベーシックインカムが導入され人は働かなくなるかもしれないが、実際に働かない何もない毎日を過ごし始める時、我々は何を目標に生きていくのか.
はたまた幸せとは何か?1から思考し直す必要がある.そんな未来が待っている可能性が高いのだ.
学ぶことへの過剰なリソース配分
労働者の重要性の部分への意欲的な部分の話をしてみた.しかし実際に完全な代替となると3世代後の話にも思える.
では25%弱が代替されても社会の中で生き残れる人材の特徴には何があるだろうか?
すぐに思いつく部分で言うと現場作業員と言われる建設業に従事する職人のような物理世界での職人は必要になってくるといえる.
AIによって図面の作成やデザインは可能になる可能性が高い.しかし、実際に建設となるとAIではなくロボットが必要となってくる.機械の制御部分では人間よりも優秀だが、釘を打つ、ペンキを塗る作業は人間の方がコスト面で見ても未だ優秀だ.
他にも警察や医療現場でも同じようなことが言える.全自動まではいかないがシステム的な部分はAIに代替され身体性を求めるような部分では人間による支えが必要になってくるだろう.
もう一つは優秀な人材である.優秀と言っても優秀の視点は多いが私の言う優秀は「物知り」の方の優秀である.例えばエジプト神話について問われたときに君はスラスラと語れるだろうか.私がネオコグニトロンについて話し出して君は理解して頷くことはできるだろうか.
それが今後の社会では必要とされる人材となってくる.別に全ての話ではなくAIを利用する上で優秀かどうかの話である.
質問をして間違いを見つけられるか.が重要な部分である.
間違いを見つけられない、そのまま鵜呑みにするならば君はAIに使われる情弱として使われることになるだろう.
1番最初に最近の高校生は疲れていると述べたが今後のα世代、さらに向こうの世代はさらなる苦行を行う必要が出てくる.AIによって社会構造は今後さらに複雑化され人々の行動原理はアルゴリズムによって確立される.
その社会の中で通用する人材の条件は一つだけ.「優秀かどうか」なのだ.
優秀な人材かそれ以外か.の時代に入って来る.それ以外はホワイトカラー職を手放しブルーカラー職として働けばいい.別にブルーカラー職を非難するつもりは全くない.ただ必要となる人材のクオリティは今後さらに高くなるという話なだけだからだ.
その中で揉まれるだろうZ世代とα世代が何を体験していくのか.それは予測に過ぎないが可能性では十分に考えられる.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
