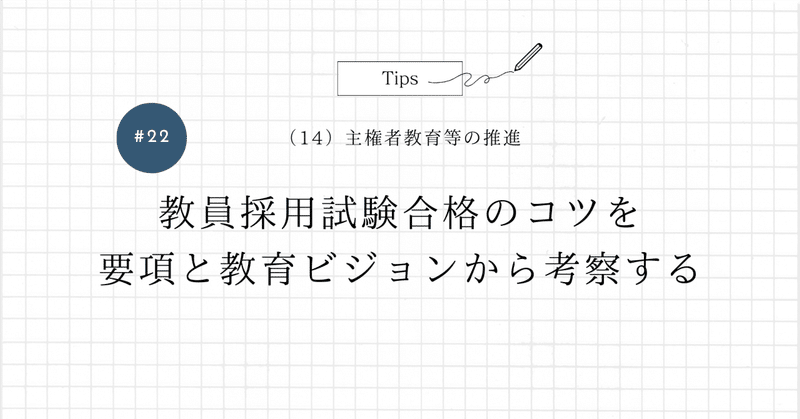
教採合格のコツ 主権者教育等の推進 解説と試験官へのアピール方法 【あいちの教育ビジョン2025 -第四次愛知県教育振興基本計画-より】教員採用試験対策
私たちは、未来の教育を担う者として、社会の中で自立し、他者と協力しながら生き抜く力を身に付けることが大切だと考えています。学校では、主権者としての資質や能力を育てるために、法や政治・経済に関する知識を学び、公正な判断を下せるよう教育が進められています。
主権者教育は、発達段階に合わせて進められるべきであり、学校の中立性を保ちながら、児童や生徒が地域の課題について理解し、解決方法を考える機会を提供することが重要です。また、家庭や地域との連携も大切であり、地域の行事などを通じて主体的に取り組む機会を増やすことが求められています。
これからの教員として、教育ビジョンを理解し、それをもとに話し方や考え方、書き方を学び、教育現場での実践に生かしていただければと思います。これは絶対の答えではありませんが、一つの考察として、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
現状と課題、施策の方向
○ 主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付けさせるため、2015年の18歳への選挙権年齢の引き下げを契機として、また、2022年には成年年齢が満18歳に引き下げられることになっており、小中学校から体系的に主権者教育を進めていくことが、より一層求められています。
○ 主権者として必要な資質・能力の育成に当たっては、法やきまり、政治・経済に関する知識等の習得に加え、事実をもとに多面的・多角的に考察し、公正に判断する力、課題の解決に向けて協働的に追究し、根拠をもって主張し合意形成を図る力、よりよい社会の実現を目指し、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質等を、教科等横断的に育んでいくことが重要です。
○ また、主権者教育は、発達段階に応じて進めていく必要があり、学校の政治的中立性を確保しつつ、例えば、小学校では、地域の身近な課題を理解し、その解決方法を考えたり、中学校や高等学校では、実際の投票箱を用いて模擬選挙を行ったりするなど、現実の社会事象を取り扱いながら、国際的に見て低いとされる若年層の政治への関心を高め、行動につながるような効果的な取組を進めていきます。
○ さらに、家庭・地域との連携も重要であり、地域の行事等で児童生徒が主体的に取り組む機会を作り出していくことなど、家庭や地域と連携した取組を進めていきます。
主権者: 主権者とは、国家の最終的な意志決定者であり、通常、成人した国民が選挙権を持つことから、彼らの意見や考え方が国の方針を左右することができる存在です。記事にあるように、2015年には18歳からの選挙権が認められ、2022年には成年年齢が18歳に引き下げられるため、若者が社会の主体的な役割を担っていくための教育が一層求められるようになっています。
主権者としての資質・能力: 社会を良くするためには、ただ選挙に行くだけではなく、法や政治、経済に関する知識が必要です。また、それだけではなく、情報を公平に判断する能力や、他者と協力して問題解決をする力、自らの意見をしっかりと持ち、それを根拠をもって伝える能力など、多岐にわたる資質や能力が求められます。これらを育むためには、学校の教育だけでなく、教科を超えたアプローチが必要です。
発達段階に応じた主権者教育: 学年によっては、小学校で地域の問題を考えたり、中高では模擬選挙を実施するなど、子供たちの年齢や成熟度に合わせた教育が必要です。特に若者の政治への関心は国際的にも低いと言われているため、実際の社会事象を取り入れることで、関心を高め、実際の行動につなげる取り組みが進められています。
家庭・地域との連携: 学校だけでなく、家庭や地域との連携も重要です。地域の行事に積極的に参加することで、子供たちは社会の一員としての役割や責任を実感することができます。このような取り組みを通じて、子供たちが社会に対する興味や関心を深めることができるのです。
施策の展開
① 主体的に社会参画する態度の育成、体験活動の推進
○ 幼児教育においては、きまりの大切さに気付き、守ろうとする態度や、地域の行事や公共施設等、生活に関係の深い事柄・場所に興味・関心をもつ態度を育んでいきます。
○ 小学校では、生活科の中で、集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切に行動する態度、自分と身近な人々、地域の様々な場所、公共物等との関わりに関心をもち、地域のよさに気付き、愛着をもつ態度を育んでいきます。
○ 「法やきまり」について理解し考察する力を育成するため、小中学校では、社会科や「特別の教科道徳」の中で、日本国憲法における国民の権利・義務、基本的人権の尊重、法やきまりの意義、公正、公平、社会正義、社会参画、公共の精神を学ぶ教育を進めます。さらに、高等学校では、公民科、特に新設科目「公共」の中で、公共的な空間における人間としての在り方、基本原理等を学ぶ教育を進めます。
○ 「政治や経済」について理解し考察する力を育成するため、小中学校では、社会科、家庭科、技術・家庭科の中で、地方公共団体や国の政治の動き、我が国の産業、市場の動きと経済、身近な消費生活が環境や社会に及ぼす影響、世界平和と人類の福祉の増大等を学ぶ教育を進めます。また、高等学校では、公民科や家庭科の中で、現代の民主政治や政治参加の意義、現代の経済社会と経済活動、財政と税、社会保障、国際平和等の現代社会の諸課題、持続可能な消費生活等を学ぶ教育を進めます。
○ 「自発的・自治的な活動」について理解し、思考・判断する力を育成するため、小中学校、高等学校では、学級活動や児童会・生徒会活動、学校行事でのボランティア活動や職場体験活動等を通じて、集団の一員としてよりよい学校づくり、社会づくりに参画する態度を育む教育を進めます。さらに、小中学校の総合的な学習の時間や高等学校の総合的な探究の時間の中で、地域の教材や事例を活用しながら、地域の特色に応じた課題について学ぶ活動を進めます。
この部分は、子供たちが社会の一員としての自覚と責任を持ち、主体的に社会に参加することの重要性を示しています。教員採用試験では、このビジョンを理解し、具体的な体験活動を通じてこれを実現する方法を提案できると良いでしょう。
幼児教育 この段階では、ルールの重要性や地域社会に対する関心を育てることが重要です。試験では、どのようにしてこれらの要素を幼児教育に取り入れるかを考え、具体的な方法を提案できると良いでしょう。
小学校 小学校の段階では、集団や社会の一員としての役割を理解し、地域社会に対する愛着を育てることが重要です。試験では、どのようにしてこれらの要素を小学校の教育に取り入れるかを考え、具体的な方法を提案できると良いでしょう。
中学校と高等学校 この段階では、法やルールの重要性を理解し、それに基づいて行動することが求められます。試験では、どのようにしてこれらの要素を中学校と高等学校の教育に取り入れるかを考え、具体的な方法を提案できると良いでしょう。
政治や経済:「あいちの教育ビジョン2025」においては、子供たちが政治や経済について理解し考察する力を育てることを強調しています。具体的には、小中学校の段階では社会科や家庭科、技術・家庭科の授業の中で、地方公共団体の動きや国の政治の動き、我が国の産業や市場の動き、さらには経済の動きについて学びます。これに加え、私たちの身近な消費生活が環境や社会にどんな影響を及ぼすのか、また、世界の平和や人類全体の福祉の向上についても学ぶことが挙げられています。一方、高校の段階では、公民科や家庭科の授業を通じて、現代の民主政治や政治参加の意義、経済活動や財政、税に関する内容、社会保障、国際的な平和など、現代社会の様々な課題について学びます。
自発的・自治的な活動:このキーワードは、子供たちが自ら進んで、また自分たちの判断で活動を行う能力を育てることを目的としています。このため、小中学校や高等学校のいずれの段階でも、学級活動や児童会・生徒会の活動、さらには学校行事でのボランティア活動や職場体験活動を通じて、集団の一員としての責任や協力の重要性を学ぶことが強調されています。これにより、良い学校や社会をつくるための参画の態度を身につけることが期待されます。加えて、小中学校の総合的な学習の時間や高校の総合的な探究の時間では、地域の教材や事例を活用して、その地域の特色や課題に合わせた学びが進められます。
これらの要素を理解し、具体的な方法を提案することで、教員採用試験において高い評価を得ることができるでしょう。また、これにより未来の教育を担う教員としての資質を示すことができるでしょう。
教員採用試験で、試験官にアピールするには
幼児教育の経験を活かし、地域の行事や公共施設の利用に関する知識や興味を示す。
小学校の生活科で学んだ集団行動や地域のよさについての考察を共有する。
日本国憲法や基本的人権の尊重、公正、公平、社会正義についての意見や考えを述べる。
高等学校の公民科や新設科目「公共」で学んだ公共的な空間における人間の在り方についての理解を示す。
実際の教育現場での体験活動や主体的な社会参加に関するエピソードを共有する。
「政治や経済」に関する授業内容について、実際に小中学校や高等学校でどのように教えるかの具体的な教案やアイディアを持って試験に臨む。
我が国の産業や市場の動き、身近な消費生活の影響など、具体的な現地の事例やニュースを取り入れた授業案を提示する。
現代社会の諸課題、例えば財政と税や社会保障についての知識をしっかりと押さえて、それに関連する授業の提案をする。
「自発的・自治的な活動」に関する取り組みや経験を話題に出す。例えば、過去のボランティア活動や職場体験活動の経験を共有し、それがどのように教育に役立つかを説明する。
地域の特色に応じた課題について学んだ経験や、地域の教材や事例を活用した授業内容のアイディアを提案する。
学級活動や児童会・生徒会活動に関する実績や経験を挙げ、それがどのように集団の一員としての態度を育てる教育に役立つかを話す。
総合的な学習の時間や総合的な探究の時間に関する実践的な教案や取り組みを提案し、それが生徒の思考・判断力を育てる手助けになる理由を述べる。
② 政治的教養を育み、平和と公正を学ぶ教育の充実
○ 主権者として必要な政治的教養を育成するために、ICTを活用したアクティブ・ラーニング型授業を行い、生徒の政治への関心や参加意識を高める取組を進めます。
○ 高等学校・特別支援学校高等部では、総務省・文部科学省が作成した副教材「私たちが拓ひらく日本の未来」等を活用し、政治的教養を育むとともに、外国人生徒の多様な主権にも配慮しながら、選挙制度の理解を図ります。
○ 国政選挙の投票率が18歳から19歳にかけて低下する傾向が見られることから、大学における高大接続を意識した主権者教育の取組を、県内大学に呼びかけていきます。
○ 家庭において選挙への関心を深めるため、選挙管理委員会などの関係機関と連携しながら、家庭への啓発活動を進めます。
○ 学校教育における政治的中立性の確保に関する研修を継続的に行い、教職員が不安なく主権者教育を行うことができる環境を整えます。
○ 児童生徒が、日本や世界の政治・経済の情勢、地域の課題等について深く学べるよう、行政機関や経済団体、大学・研究所などの学術機関、報道機関等と連携し、社会の第一線で活躍する人たちと児童生徒が語り合いながら、過去と現在に学び、自らの将来の姿、社会への参画、平和と公正等について深く考える機会を充実していきます。
政治的教養:「政治的教養」とは、市民としての責任や役割を理解し、自らの意見や考えを持つための基本的な知識や考え方を指します。あいちの教育ビジョン2025では、この政治的教養を育成するための授業や取り組みが強調されています。
アクティブ・ラーニング型授業:ICTを使用して、生徒が積極的に参加し、自ら考えることを促す学びのスタイルです。この方法を通して、生徒の政治に対する興味や参加意識を高めることが狙いです。
「私たちが拓ひらく日本の未来」:これは総務省・文部科学省が作成した副教材です。高等学校や特別支援学校の高等部で使用され、政治的教養を育成する目的があります。特に外国人生徒の多様な背景を考慮しながら、日本の選挙制度の理解を促進する内容が含まれています。
国政選挙の投票率の低下:18歳から19歳の若者層で、国政選挙の投票率が低いという現象が確認されています。これに対応するため、県内の大学と連携し、高大接続を意識した主権者教育の取り組みが推進される予定です。
家庭において選挙への関心を深めるための啓発活動:この点は、家庭の中で選挙への関心や意識を高めるための取り組みを示しています。具体的には、選挙管理委員会などの専門的な機関と協力し、家庭向けの情報提供や啓発活動を進めることを指します。このような取り組みは、家庭内での政治に関する議論や意識の向上を促進し、選挙における投票率の向上や、より質の高い選挙活動へとつながる可能性が考えられます。
学校教育における政治的中立性の確保:ここでは、学校において行われる教育が、特定の政治的な立場や意見に偏らないようにするための取り組みが強調されています。具体的には、教職員向けの研修を継続的に実施し、教職員が主権者教育を行う際の不安や疑問を解消することを目的としています。政治的な中立性は、学校教育における公平性や信頼性を保持する上で非常に重要な要素であり、これにより学生たちが偏った情報や意見に基づく判断をせず、多様な視点や意見を理解し、自らの意見を形成する力を養うことが期待されます。
児童生徒と社会の第一線で活躍する人たちとの対話の機会の充実:この部分は、児童や生徒が社会のさまざまな分野で活躍する専門家や経験者と直接対話する機会を増やすことの重要性を強調しています。具体的には、行政機関、経済団体、大学や研究所などの学術機関、報道機関などとの連携を強化し、それらの機関の専門家や経験者と児童生徒が直接対話する場を設けることを提案しています。このような対話を通じて、児童生徒は日本や世界の政治・経済の情勢、地域の課題などについての深い理解を得ることができるとともに、自らの将来の姿や社会への参加、平和や公正についての考えを深めることが期待されます。
教員採用試験で、試験官にアピールするには
ICTを活用したアクティブ・ラーニング型授業の実施経験や知識を持っていることを強調し、生徒の政治への関心や参加意識を高める方法について語る。
高等学校や特別支援学校高等部での「私たちが拓ひらく日本の未来」等の副教材の使用経験や知識を共有し、その教材を使って政治的教養をどのように育成するかを提案する。
外国人生徒の多様な主権に配慮した授業の方法や経験をアピールすることで、多様性を尊重する態度を示す。
18歳から19歳の若者の投票率が低い問題に対して、教育の場での取り組みや提案を持っていることをアピールする。
大学との連携を意識した主権者教育の取り組みについての知識や提案を共有し、教育の連携強化に貢献できる姿勢をアピールする。
選挙管理委員会などの関係機関との連携を強調し、家庭教育における選挙への関心の重要性を語る。
学校教育の中での政治的中立性の確保に取り組んでいることを明示し、そのための研修を継続的に受けている経験や意識を伝える。
児童生徒の政治・経済の情勢や地域課題に対する理解を深めるための方法や取り組みを示す。特に、行政機関や経済団体、大学や研究所などの学術機関、報道機関との連携の重要性を強調する。
社会の第一線で活躍する人たちとの対話の機会を児童生徒に提供する取り組みや経験を紹介する。
児童生徒に過去と現在を学ばせ、自らの将来や社会への参画、平和や公正について考えさせる活動やプロジェクトの実績を共有する。
おわりに
主権者教育の重要性やその具体的な内容、取り組みを深く考察する機会を持ちました。現代の若者は、多くの社会的変化や新しい情報にさらされており、その中で自らの役割や意義を探求することが求められています。主権者として、法やきまり、政治・経済に関する知識を持つだけでなく、事実を基に多角的に考察し、公正な判断を下す能力や協働的な取組みを進める力は、より良い社会を築くための基盤となります。
学校教育の中で、様々な年代や教科を通じて、主権者としての資質や能力の育成が重視されていることがわかります。具体的な活動や取り組みを通じて、児童や生徒は自らの役割や社会の仕組みを理解し、社会参画の意識を高めていくことが期待されています。また、学校だけでなく、家庭や地域、さらには社会全体との連携も強調されています。これは、主権者教育が一人ひとりの個人だけの問題ではなく、全ての人が関わり合いながら築いていく社会全体の問題であるという認識を示しています。
それに加えて、教職員の研修やICTを活用したアクティブ・ラーニング型授業、外部機関との連携など、さまざまな取組が紹介されています。これらの取組は、主権者としての資質や能力をしっかりと育成するための具体的な方法として示されており、今後の教育現場での実践が期待されます。
最後に、私たち一人ひとりが持つ役割や責任を深く理解し、その上で行動することが、より良い未来を築くための鍵であると感じています。この考察が、皆様の教員採用試験の準備や、教育現場での実践に役立つ一助となれば幸いです。何か困難や挫折を感じた時、この記事の内容を思い返し、自らの教育のビジョンを再確認してみてください。
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
もし、この記事に対して
「なるほど!」
「面白かった!」
「他の記事も読みたい!」
と思ったら、
「❤スキ」を押していただけると嬉しいです。
そして、これからも役立つ情報や考えを共有していく予定なので、フォローもお願いします。
また、あなたが感じた「記事の価値」や「応援の気持ち」に応じて、サポートをしていただけると本当に嬉しいです。あなたの貴重なサポートは、より洗練された記事の作成や、深いリサーチのために活用させていただきます。
よろしくお願いいたします。
あなたが感じた「記事の価値」や「応援の気持ち」に応じて、サポートを選択してください。あなたの貴重なサポートは、より洗練された記事の作成や、深いリサーチのために使用されます。あなたが感じる最適な金額をお選びください。
