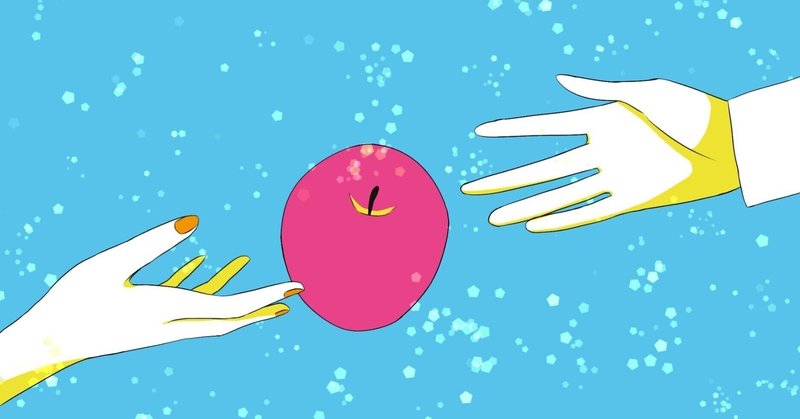
短編小説「りんごの乙女」
人は見た目が9割だって言うけど、あたしは中学校に上がるまで、それも昨日のあの瞬間まで、人の見た目なんかまったく気にしたことがなかった。
だって、世の中何でも個性の時代。世界は多様性に溢れていて、一人一人違うのは当たり前、ちょっと他の人と違うからって理由で嫌ったり、意地悪したり、そんなことはしちゃ駄目なんだって、両親や先生にはそういうふうに教わってきたし、そもそも見た目で人を判断しちゃいけないってのは、古今東西の物語もちゃんと教えてくれてたから。
例えば、ぼろをまとった汚い老人が家を訪ねてきて、一晩泊めてくださいとか、食べ物をくださいって頼む話。たいていの人は老人の頼みを断るんだけど、最後にはそうじゃない人がいて、親切に老人の世話をしてくれる。そうすると、その親切にした人の家には幸せが訪れる。なぜかっていうと、実はその汚い老人は神様や仏様が姿を変えたものだったから。
つまり、これは人を見た目で判断しちゃいけませんよっていう訓話なんだ。本が好きなあたしはこういう話をちゃんと信じて、それで「人は見た目じゃない、そこに価値を置くべきじゃない」って、ずっと思ってた。だって、世界中にそういう昔話があるってことは、それが人間にとってすごく大事なことだよってことだろうから。
そこに加えてもう一つ、あたしはもともと人の見た目に興味がなかったってこともある。変な例えかもしれないけど、例えばじゃがいもを見て「これは綺麗なじゃがいもだな、特別扱いしよう」とか思わなくない? あたしにとって、人の見た目ってそうだった。みんな同じ人間なんだから、ほぼ同じ、変わらないじゃんって、ほんとにそう思ってた。周りに比べて幼かったとも言えると思う。あの人がかっこいいとか、好きな人ができたとか、周りの女の子は早いうちから言ってたけど、あたしはそういう話にも興味がなかった。思えば「佐原さんの好きな人って誰? 芸能人で言うとどういうタイプが好き?」ってな質問に、あたしが常に返す「いない、わかんない」って答えに、友達は鼻白んでた気がしないでもない。でも、それでもあたしは「興味がないんだからしょうがないでしょ、あなたたちもあたしが好きな本の話をしたって、全然食いつかないじゃない」くらいにしか思ってなかった。
でも、今日は分かる。女の子たちの恋愛話と私の本の話は、まったく釣り合わない話だったってことが。世の中における恋愛話——見た目の話はとても大きな価値が置かれているもので、本というものはある一定の層が価値を置いているというだけの、ちっぽけなものだったっていうことが。
だから、あたしの世界は昨日よりも少し狭くなって、あたしも少し小さくなった——今日はそんな気分がする。もしかして、そうやってみんな大人になっていくんだろうか。だとしたら、大人って何だか嫌だ。あたしはそんな大人にならないまま、大人になりたいと思うのに。
でも、昨日の競歩大会で、あたしは「りんごの乙女」になれなかった。人は見た目が9割、ううん、すべてなんだって、それであたしは思い知らされた。
そもそもりんごの乙女っていうのは、競歩大会の上位10名に、賞品のりんごを渡すっていう役の名称だった。下らないって笑われるかもしれない。でも、あたしはちっちゃいときからずっとその役目に憧れていた。
中学の競歩大会は、30キロ。小学校のときとは比べものにならない距離を走った後、みんな一つずつ、りんごがもらえる。けれど、男女の上位10名だけは特別だった。大会の後、表彰式が行われて、そこでりんごと賞状が手渡されるのだ。
あたしは決して目立ちたがり屋じゃなく、むしろその反対で、人前に立つことは避けてきたような人だった。けれど、このりんごの乙女だけはどうしてもやりたかった。なぜそこまでやりたかったのか、昨日の今日だというのに、あたしにはもう分からない。けど、りんごの乙女という言葉の響きとか、賞状を渡す側になれることが嬉しかったとか、そんな理由だと思う。とにかく、あたしはりんごの乙女がやりたかった。だから一月前、その役目を決める学級会のとき、勇気を振り絞って手を上げたのだ。
多分、ほかの女子にとって、りんごの乙女なんて役目は恥ずかしさの塊でしかなかったのだと思う。あたしが手を挙げたことで、みんながほっとしたような雰囲気が漂った。よくやるね、なんて囁きも聞こえた。けど、そんなことよりも嬉しくてしょうがなかったあたしは、クリスマスを待つ子供みたいに、その日を待った。当日もその長い30キロの距離を、表彰式だけを楽しみに乗り越えた。あたし自身の順位は、中の下だったけれど、そんなことはどうでもよかった。いよいよ、クラスでりんごが配られて、みんなが式のために校庭へ移動を始めた。あたしはもう嬉しくって顔がにやけてたと思う。
でも、そのときだった。廊下へ飛び出したあたしを、クラスの女子が呼び止めたのだ。
『りんごを渡す役、ユリと代わってあげてくれない?』
そう言ったのは、マキとヒナコという気の強いタイプの女子だった。2人の言うユリという子の仲良しで、そのユリはマキとヒナコに挟まれるようにして、はにかんだようにあたしを見ていた。突然のことに、あたしは『どうして』と聞き返した。すると、彼女たちは声を潜めてこう言った。
『ユリと大野くん、良い感じなんだよね。で、大野くんは10位以内だからさあ、だから』
『だから?』
『えーと、だからユリが大野くんにりんご渡したいから、代わってって言ってるんだけど』
そんなの知らないよ、とあたしは言ったような気がする。誰か渡したい人がいるなら、最初から立候補すれば良かったじゃん、と。このあたりは正直、あまり記憶にない。なぜなら、彼女たちが次に言い放った台詞こそが、あたしの世界を吹き飛ばしたからだ。
『そもそも、あんたみたいなやつが「りんごの乙女」なんて似合わなすぎでしょ』
マキが言った。続けて、ヒナコが笑いながらこう言った。
『そうだよ、「乙女」なんだからさ、ユリみたいに可愛い子がやるべきに決まってるじゃん。ブスがしゃしゃり出てくんなってんの』
そう言って、3人は顔を見合わせ、くすくす笑った。
世界が色を変えたような、そのときの感覚をどう表現したらいいだろう。あたしは驚いてその場に立ちすくんだ。2人の言葉はまるで、いままであたしという端末に入っていなかったソフトが急にインストールされたような、電波障害か何かで出来てなかったアップデートが突然されてしまったような感覚で、あたしの中に急激に入り込んだ。
そのアップデートの過程で、あたしは毎朝、鏡で見る自分の顔と、目の前ではにかんでいるユリの顔を初めて比べるという作業をした。そして、そこに美しく良いものと、醜く悪い物の価値を見つけた。あたしはブスで、ユリは美人。それをきっかけに、あたしの記憶の中の人たちもまた、ブス、美人、イケメンというように、さまざまに分かれていった。お父さんお母さん、弟、妹、親戚、近所のおばさん、パン屋のお姉さん、先生、クラスメイト、すれ違う人々、テレビで見る人々——。すべての人が仕分けされて、あたしは世界の秘密を知った気になった。つまり、人間は平等なんかじゃない。みんな違ってみんないいなんてことは絶対にない。見た目で人を判断することは良い悪いとかじゃなくて、ただ世の中にいる人たち全員が自然としてることなんだ。
ブスのあたしが何も言わないうちに、美人は自然と美人のやるべき役目についた。あたしが楽しみにしていた表彰台、綺麗なユリはそこに立って、堂々とりんごを手渡した。例えば、テレビアナウンサーが美人揃いであるように、りんごの乙女も美人がやるべき役だった。前に立ったり目立ったりするのは、彼女たちの役目なのだ。見た目で人を判断する多くの人たちが、確かにそう望んでるから。それがとても自然なことで、おかしなことだとは思わないから。
その瞬間を境に、あたしはいままで信じてた「汚い老人」の訓話を捨てた。ブスなあたしは日陰を歩いて、一生顔を上げないと決めた——と、それだけなら良かったかもしれない。でも、話はもうちょっとだけ続く。
表彰式の終わったあと、肩を落として歩く帰り道で、あたしはまた声をかけられた。
『佐原さん! やっと見つけた』
振り向くと、大野くんがそこにいた。ユリが良い感じだという、例の大野くんだ。彼女たちに会うまではじゃがいもの一人だった人だけど、アップデートを完了したいまや、学年一イケメンの大野くん。そんな人にどうしたの、と聞く気力もないあたしは、大野くんをじとっと睨んだ。しかし、大野くんはそんなことも気にせずに、『俺のりんご、ある?』と言った。
『表彰式さ、俺、腹痛くてトイレ行ってたら終わってたんだよね。だから、俺だけりんごもらってなくてさ……佐原さんでしょ、りんごの乙女』
大野くんがあたしに向かって手を差し出す。美人のユリじゃなくて、ブスなあたしをりんごの乙女だって、そう思って。
さっき手に入れたばかりの価値観で、あたしはおののきながら、おずおずとカバンに手を入れた。そこには1個しかりんごはない。言わずもがな、あたしの分だ。でも——あたしはりんごの乙女として、そのりんごを大野くんの手に置いた。
『よっしゃ、さんきゅー』
嬉しそうに大野くんは言うと、りんごをぽーんと宙に投げて、そのまま上手にキャッチした。そうしてにこっとあたしに笑うと、疲れを感じさせない足取りで、軽やかに走り去っていった。
——ユリは大野くんにりんごを渡せなかったんだ。
可笑しくてたまらなくなったのは、それからしばらく後だった。どうしてもこみ上げる笑いに口元が歪んで、あたしはそれを隠しながら家までの道のりを歩いた。そうしながら、どこか頭の隅っこで、これって意地悪な笑いだなあと、そんなことを思っていた。いままでのあたしなら、きっとすることがなかった笑い方だとも思った。そしてやっぱり訓話を思い浮かべた。
もし、いま、汚い老人が道の向こうからやってきて、あたしに声をかけたとする。そしたらあたしはどうするだろうか——逃げるように行き過ぎるだろうか、知らん顔で無視するだろうか、それとも睨み、罵声を浴びせ、石を投げつけさえするだろうか。
あたしはもちろん、何ですか、と足を止めたい。何かお困りごとですか、と自然と手を差し伸べたい。でも、あたしの少し狭くなってしまった世界では、そうすることのほうが悪いことだって、そんな価値があるような気がして、いまのあたしはきっと逃げるように行き過ぎる。だって、相手はあたしと同じ人じゃない、「汚い老人」なんだから。あたしがユリよりブスだというなら、あたしも誰かを下に見て、意地悪して、笑って、そうして生きるべき、ここはそんな世界だから。
これから大人になるうちに、世界は変わっていくだろうか。一晩経ち、昨日よりも暗い顔で登校したあたしは教室へ向かう。アップデートを繰り返して、最新の状態になった世界は、昨日よりも良く、自由であればいい。でも、あたしはアップデートされる度、いままでよりも悪く、狭い世界で苦しまなきゃならないんじゃないかって、いまはそんな風に怯えている。
何かを恐れるように、いままでにないびくびくとした態度で、あたしは自分の机へ向かう。存在感を消すように、ひっそりと椅子に座る。けれど、そんなあたしを待ち構えていたかのように、マキとヒナコと、それからユリは、怖い顔でこちらに近づいてくるのだった。
「りんごの乙女」了
短編シリーズ「りんごのある風景」より「りんごの乙女」。
最後まで読んでくれてありがとうございます🍎
よかったら「スキ」も押してくれると嬉しいです❤️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
