
はじめての沖縄暮らしと、創作活動について
こんにちは。ライターの神代(くましろ)です。
去年、ADDress卒業記をアップして以来の久しぶりの投稿ですが、実は2022年8月から2023年6月まで十ヶ月のあいだ沖縄で暮らしたので、そのことについて書こうと思います。
沖縄暮らしについてというよりは、そこでの創作活動について。
別の記事で書いたかもしれませんが、わたしの生まれは北海道で、真冬の早朝にはまつ毛と鼻毛と鼻水が凍り付くような極寒の土地で育ちました。全国をふらふら旅していたこともあったとはいえ、「ハイビスカス」を「ハーゲンダッツ」と覚えていたような道産子が、どうしてふるさとと正反対にある沖縄で暮らすことにしたのかというと、それは沖縄(というか主に名護)がモチーフの小説を書きたいと思ったからです。
こう書くと、さぞ沖縄が好きなんだろうと思われるかと思いますが、それまでのわたしは……
実は、沖縄にはまったく行ったことがありませんでした!!
そう、修学旅行ですら行ったことがなくて、それなのに移住を決めてしまったのです。
そもそも、わたしが沖縄という土地に興味を持ったのは、三年ほど前、精神科医の蟻塚亮二さんの著書「沖縄戦と心の傷 トラウマ診療の現場から」を読んだことがきっかけでした。
もう七十年以上も前の戦争のトラウマが体験者をいまだに苦しめているということ、そして後の世代の家庭環境や精神育成にも影響を与えているということ、何よりそういう土地があるのだということが、当時のわたしには衝撃だったのです。
ちょうどそのとき、パラオが舞台の小説を畫こうと思っていたので、「主人公を沖縄出身にしてはどうか」という構想が浮かびました。パラオは沖縄と同様、アメリカと日本の戦場となった土地なので、沖縄の血を引く日本人とアメリカ人がパラオで心を通わせていく様子を描くことで、より深い人間ドラマになると思ったのです。
それからというもの、わたしは沖縄に関する本を読みまくり、沖縄料理店を探しては行き、上野で開かれていた琉球展に行ったりしました。
何かと話題になった「ちむどんどん」はもちろん、「NHKスペシャル」も沖縄が取り上げられているものはオンデマンドで遡って見ました。あんまりピンと来なかったけど、「テンペスト」も見ました。
行ったことがないので憧ればかりが膨らみ、頭の中で「沖縄」像を作り上げていたような感じです。
沖縄に関する情報を集めるのは、もはやライフワークとなっていました。でも、沖縄というのは調べれば調べるほど複雑な土地で、本で読んだだけでは、米軍基地や戦争に関することでも、ユタやマジムンに関することでも、
「それぞれで書いてあることが違う!」のです。
これはもう実際に沖縄に行って土地の人の話を聞くしかないと思ったし、「3泊4日の観光旅行」では、この土地のことは理解できないだろうという確信みたいなものがありました。それで、「沖縄に住んでみたい」という思いが、徐々に強くなっていったのです。

実際に行ってみてどうだったか?
「本だと書いていることが違う」と書いたけれど、じゃあ実際に沖縄で暮らして、沖縄の人の話を聞いてみてどうだったのかというと、
あれ……なんか、人によって言ってることが違くない?
と、いう感じでした。
「沖縄のことがわかりたい」と思って沖縄に来たわたしだけれど、結果、わかってしまったのは、「わからない、掴みきれないのが沖縄なんだ」ということだったのです。
よく入り浸っていた国頭村のカフェのオーナーにそれを話すと「まったくその通りだよ」と言われました。ちょっと掴めた気になったとたん、するするっと手のひらから逃れていくのが沖縄なのだと。そのくらい、あの土地はディープで独特な文化、複雑な歴史背景が存在しているのです。そして、そこが強烈な魅力でもある。
思えば、オンラインで蟻塚先生に取材したとき、彼もおっしゃっていました。「三年は住まないと、沖縄は理解できない」と。
あ、もちろん、沖縄のことをわかろうとする気持ちを放棄していいという意味ではありません。わたしたちナイチャーがあの土地に関心を払う必要があるというのは、今も変わらないと思っています。

移住後の生活と創作活動
念願の沖縄(名護市)に移り住んだわたしですが、最初からうまく行ったわけではなく、最初の2ヶ月くらいは、
もう北海道に帰りたい……
と、心の中で泣いていました。
だって、暑いし、沖縄の老舗企業に転職したはいいけど仕事はガチガチに公務員的で楽しくないし、暑いし、住む家はすぐに見つからないし、暑いし。体調もずっと悪くて、生理が近くなるたびに右の腎臓が腫れて痛くなる謎症状にも苦しめられました。「わたしにはこの土地は合ってないんじゃないか」と、そう思ったこともあります。
それでも帰らなかったのは、「ここで帰るとわたしの小説はだめになる」という思いがどこかにあったからだと思います。
やり遂げるまではこの土地を離れてはいけない。
どうしてかわからないけれど、そう感じていました。
それに、沖縄にいるあいだずっと苦しかったわけではなくて、少し車を走らせるだけで、ものすごくきれいな海が見えたりして、花も内地ではあまり見かけないものが力強く咲いていてきれいで、そういうちょっとしたものがわたしを助けてくれました。
つらいつらいと思いながらも、気に入ったおうちに引っ越したり、仕事の手の抜き方なんかも覚えてきて(笑)。もともと海のきれいな土地が好きだったのもあって、わたしは少しずつ少しずつ、沖縄の暮らしに慣れていきました。
そして生活が落ち着くと、本来の移住の目的であった小説に力を入れたいという思いが強くなっていきました。応募しようとしていた新人賞の締め切りが翌年6月に控えていたこともあります。
ちょうどそのころに出会った人に紹介されて、やんばるにある某ホテルで働くことになりました。「ホテルの仕事を一日あたり4時間だけするのを条件に、ホテルの部屋に住めて、ちょっとした食事がついてくる」という非常にうまみの強い仕事です。
わたしは言われた通り4時間だけ働いて、あとはホテルの部屋に籠もってひたすら原稿を書き続けました。ホテル暮らしを始めたのは2月でしたが、4月末には原稿のほとんどが書き終わり、結果、6月の新人賞の締め切りにも間に合わせることができたのです。
つまるところ、やんばるでのわたしは、商業作家としてデビューしていないのにも関わらず、
「生活の心配がない状態で、一日のほとんどの時間を原稿執筆に費やす」
という暮らしを味わうことができたのです。
これは、おそらく作家を目指している人には大切な体験なのではないかと、個人的には思っています。
なぜなら……
・何も邪魔するものがない状態で、自分が一日にどれくらい(何文字くらい)執筆できるのか
・長編小説を一本書き上げるのに、どれくらいかかるのか
・執筆を生活の中心にするにあたり、どういう環境(部屋やデスク、椅子など)が自分に合っているのか
そういう、ものを書き続けるために大切なベースが感覚的にわかってくるのです。それは、やんばる暮らしでの大きな収穫の一つだと思っています。
※わたしの創作のベースについては長くなりそうなので、今度、別の記事で詳しく書こうと思います。
それに何より、やんばるにはもう沖縄南部や中部にはあまり残っていない昔からの自然が残っていて、住んでいる人たちもやわらかく、あたたく、本当の沖縄のよさを知ることができました。やんばるで見た自然の美しさや力強さ、そこで生きる人たちとの会話を通して得たものは、わたしが小説を通して伝えたいことやテーマにも通じていて、それまでよりもずっと作品に説得力を与えてくれたように思います。
小説の中で、お疲れ社会人だった主人公の光(ひかり)がパラオの自然を通し、子どもの頃に沖縄で暮らしたときののびのびした感覚を取り戻したように、わたしもやんばるの自然に力をもらったのです。

覚悟を決めると、人生が「その方向」に向かっていく
わたしの場合は、「北海道に帰りたい」と思っているあいだ、つまり沖縄に向き合うことを放棄していたあいだはずっと体の具合が悪くて、「この土地で小説を書き上げよう」と覚悟を決めると道が開けていきました。
沖縄は神様との距離が近い土地だというのはよく言われていることですが、なんだか、それを身を持って思い知らされた気持ちです。
思えば、実際に沖縄に引っ越す前から、わたしとあの土地の縁は繋がっていたように思います。
たとえば、沖縄に引っ越すまでのわたしは「今の仕事を辞めて沖縄に行きたい、自分の小説に全力を尽くしたいという気持ちがあるけど、その勇気がない」という状態だったのですが、そういうときに、たまたま、本当にたまたま行った横浜のシェアハウスで吉本ばななさんの「なんくるない」という小説に出会いました。そして、そこに書かれていたとある一文が、迷っていたわたしの背中を押してくれ、「沖縄に行こう」と決意することができました。
横浜でのあの出会いがなければ、わたしは沖縄に行くことはなかったかもしれない。それに、「わたしも迷っている人の背中を押せるようなものを描きたい」と、心からそう思うこともできました。
沖縄に移住してからは、こんなことも起こりました。
・小説の主人公があとになって水族館の広報の仕事をするようになるので、わたしも沖縄の某水族館の事務職に応募して「ここで働きながら広報の人と仲良くなって、あわよくば取材できたらいいな」と思っていたら、事務職は落選し、なぜか偶然空いていた広報の仕事に回された。
・ダイビングインストラクターをしているキャラクターが小説に登場するので、イントラに取材したいと思っていたら、たまたま入ったバーで隣に座った人がイントラだった。
・何気なく行った知人宅にたまたま泊まっていた夫婦と親しくなり、彼らが捕獲・捌いた野生のイノシシを料理して一緒に食べたら、その経験が小説のキャラクターづくりに多いに役立った。
そんな感じで、まるでわたしの創作活動を後押ししてくれているような、そんなできごとにいくつも恵まれました。
もしかしたら、沖縄にはクリエイターを応援してくれる神様がいて、本人に「沖縄で創作活動をやり遂げる」という覚悟さえあるのなら、何らかの形で応援してくれるのかもしれない。こじつけかもしれませんが、そんな風に思えたことも沖縄で頑張れた一つの理由です。

創作活動の結末
上記のイノシシを捕獲した夫婦とのご縁はその後も続き、彼らとの会話、過ごしたひとときが、結果的にわたしの創作活動の大きな力になりました。
わたしは彼らのことがすぐに大好きになり、二人が沖縄にいるあいだはよく一緒に出かけたりごはんを食べたりしていたのですが、彼らは本当にありがたいことに、わたしの書いた原稿を読んでくれました。
こう書くとなんだか普通のことみたいだけど、原稿はおよそ500枚。作家志望の方は知っていると思いますが、それを最初から最後まで読んでくれる友達というのは、そうそう、そうそういません。ありがてえ。
原稿を読んだ二人は、わたしにじっくりと感想を聞かせてくれました。そのときわたしたちは離れた場所にいたので、わざわざオンラインで話す時間を作って。本当にありがてえ。
そして、そのオンライン会議で、またとんでもないことが起こりました。
二人と話しているうち、次第に、
「これ……結末を変えた方がいいんじゃない?」
という流れになってきたのです。
詳しくはネタバレになるので話せませんが、わたしは「男性、女性という枠組みを取っ払って生きている人たちを描きたい。いろんな人生、いろんな生き方があるということを小説を通して肯定したい」と思っていたはずが、今のままだと、結果的に主人公の光がその枠組みの中にとらわれているラストになっていたのです。
「これはわたしの描きたい世界じゃない!」ということに気づき、ものすごく悩んだ結果、ラストの展開を変更することになりました。
どうして、ここでわたしが悩んだかというと、
……新人賞の応募締め切りの前日だったからです。
小説とか脚本を書いたことがある人ならわかると思いますが、それまで想定していたラストから変更するとき、結末だけ書き直すわけではなくて、全体を通した会話やエッセンスをラストに合わせて修正する必要が出てきます。つまり、原稿を最初から最後まで全部チェックして齟齬がないように調整するわけです。
時間に余裕があるのならまだいいですが、もう締め切り前日。しかも夜中。
シナリオライターの仕事で経験したことがあるのでわかりますが、「締め切り前日に結末を全変更することになった」というのは、物書きにとってはかなりの修羅場です。「みぎゃーっ!!」てなります。発狂してもおかしくないです。
おかしくない、のですが……。
ラストを書き直すことに関しては、なぜか、それほど苦労しませんでした。
いま思い出しても不思議なことですが、夫婦とオンラインで会話をしている最中から、書くべき言葉がぽこぽこと浮かんできたのです。まるで、何か見えない手に引き出されるみたいに。
小説を書いていると、「キャラクターが勝手にしゃべり出す」という現象がしばしば起きるのですが、このときもそうで、もうひとりの主人公である「レイ」が、わたしの頭の中でバーっとものすごい勢いで喋りはじめたのです。
レイが言っていることを忘れないようにメモしながら、わたしは「ああ、君たちはこういう結末を迎えたかったんだね」と思いました。
わたしがそれまで書いていたラストは「黒か白か、どちらかを選ばないといけない」というものでした。でも、レイは「なんでグレーじゃダメなの? っていうか、色を決める必要なくない?」というようなことを言い出したのです(具体的なセリフはもちろん違うけど)。
黒か白かなんて決めなくてもいい、そういう自由がわたしたちにはある――。これは間違いなく、わたし自身の本音であり、本当の望みでもありました。でも、変な常識とか、古い価値観に縛られて埋もれてしまっていた。それが、夫婦との会話を通して、するするっと引き出されてきたのです。レイの言葉として。
この不思議な流れは、沖縄で出会ったこの夫婦とのご縁や、これまで培ってきた二人との関係性、そして、レイをはじめとするキャラクターをわたしの中で大切に大切に育ててきたこと、そういう小さな要素のひとつひとつが合わさらなければ、きっと生まれなかったものです。
新しい結末は、キャラクターたちにとっての新しい未来。「これまで誰も歩んでいない、自分たちの手で作っていく未来」です。そういう世界を彼らに見せてあげられたことが、わたしは嬉しくてたまりません。
ラストを新しく書き換えた原稿は、ギリギリのところで賞に応募することができました。結果はまだわかりませんし、いま読み直すと文章が気になるところもたくさんありますが、それでも心から満足できる原稿になりました。物語を書くこと、人間を描くことの幸福の極みみたいなものを、これ以上ないほど味わわせてもらいました。

最後に
ちょっと本題から逸れてしまった部分もありますが、これが、わたしの沖縄での創作活動の一部始終です。
執筆にあたり、ここに書ききれないくらいたくさんの人に協力していただきました。取材に応じてくださった蟻塚先生やイルカの獣医さんたちはもちろんですが、他にも名護や国頭、パラオで出会い、時間をともにした人たち。「小説を書いている」と話すのはけっこう照れくさかったりするのですが、ほとんどの方が応援してくれ、励ましてくれました。そういう出会いが増えるほどに、「書き上げなければ」という思いが強くなり、最後までやり遂げることができました。
つらいこともあったけれど、沖縄でモノづくりに没頭できたことは、わたしの人生にとって大きな幸福です。
「ごめんなさい」や「すみません」よりも、「ありがとう」「会えてよかった」……そんな言葉が自然と出てくるような、愛に溢れた沖縄暮らしでした。
いつか、あの土地で出会った一人一人にお礼を言って回るのがわたしの夢です。願わくば、本になった自分の小説を携えて。
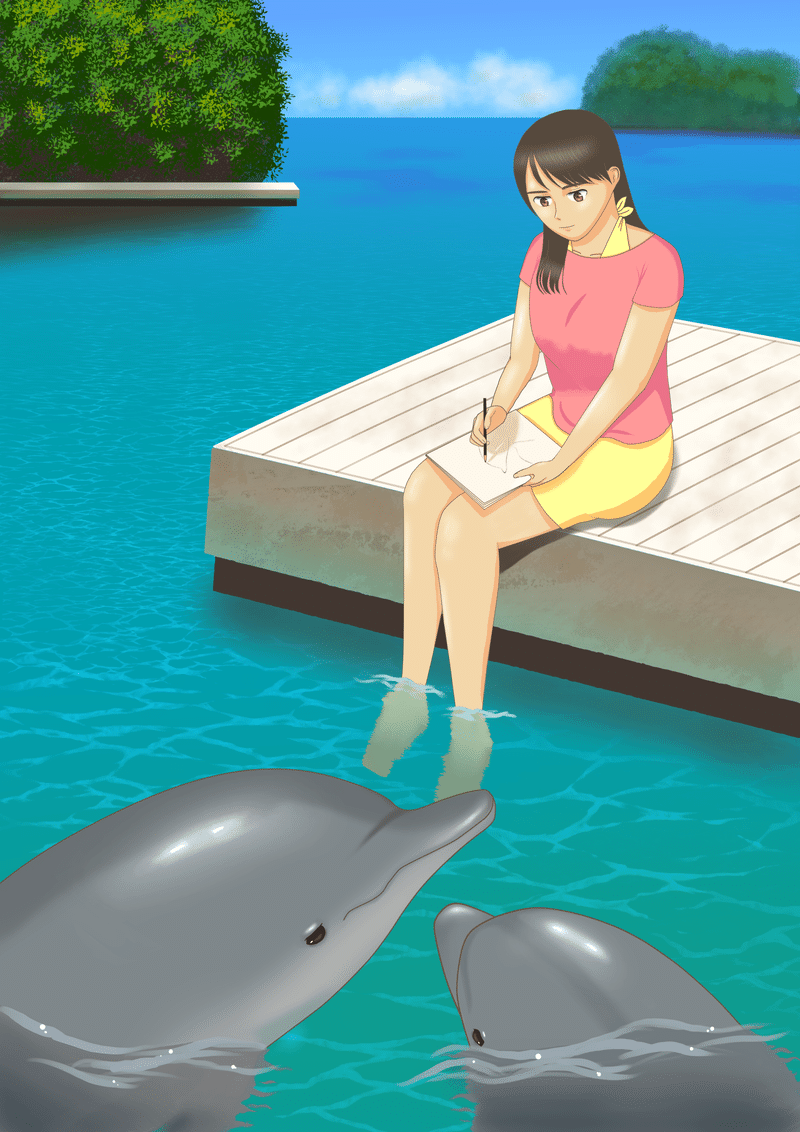
最後に、今回の小説の執筆にあたり大いに力になってくれた、こはるちゃん・はるぽん夫婦に改めて感謝します。二人のおかげで、光とレイにまったく新しい世界を見せてあげることができました。「創作活動は孤独なもの」と思い込んでいましたが、そうじゃなかった。素敵な友達との出会いが作品を磨いてくれるのだということを、二人が教えてくれました。本当に本当にどうもありがとう。
ちなみにこの二人もかなり面白い生活をしていて、その様子はこちらで垣間見ることができます。
↓
はるぽんのインスタグラム
最近作ったというホームページ
二人こそ、「夫」「妻」という既存の役割にとらわれない生き方やパートナーシップを模索・実行している、尊敬できる友人たちです。
わたしは「結婚」という制度にいいイメージがありませんでしたが、二人のおかげで「夫婦っていいなあ」と思うことができました。そういう意味でも、どうもありがとう。この場を借りて、お礼を伝えます。
2023年夏 神代さわ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
