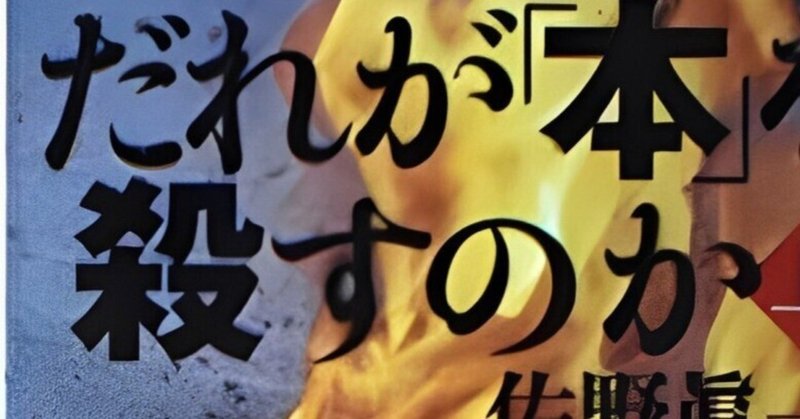
【序】だれが「書店」を殺すのか?
『街の書店の数が減っている』っていう話題は
もうみんな聞き飽き話題なんじゃないかな?
詳しくは各自でググってちゃんとした記事でも参照してもらうとして、
ここで話題にしたいのは『書店の数が減っている』という話題に
それなりの訴求力があるという事だ。
ウェブ上のニュースや話題としてちょくちょく目にするし、それなりの数のコメントや各々の意見が記されることも多い。
加えて読書の方法や本の内容を紹介する書評記事もWEB上で定番の人気テーマと言えるほどみんなの関心が高い。
みんなの関心はあるのに数が減り続けている書店、でも読書が否定されている訳でもない。。
紙の本を真っ向から否定する論調もそんなにない。。
みんな書店や読書に興味はあるっぽいのだけど、ビジネスとしては書店はとても厳しい状況にある。。
どーしてこうなったんだ?
書店が減るのはAmazonのせい?
さて書き手には20年以上の書店や書籍販売に関する職務での勤務経験がある。因みに私が初めて書店でバイトを始めた1996年が出版業界としての売上のピークであり、そこから先は右肩下がりでほぼ順調に売上減を続けている。
雑誌と書籍の合計=紙の印刷物だけなら1996年対比で2022年は半減以上なので、そりゃ書店も減るだろうって話になる。
各種の『書店減ってるよね』記事はその原因&問題についてはAmazonをはじめとしたECの勃興と電子書籍の普及に触れておしまいがほとんどだ。
でも、ここで思考停止しては重要な事実を見過ごすことになる。
上記の出版販売額の記事のグラフをよく見ると、顕著に売り上げが減っているのは『雑誌』だ。最盛期に比べると売り上げは三分の一以下にまで落ちている。
なるほど。。んで雑誌が売れなくなったはAmazonとか電子書籍のせいだっけ??みんなそんなにAmazonで雑誌を買うようになったのかな?
雑誌の売上減少って、別にAmazonとか電子書籍って関係なくない?(笑)
さらに世間には書店の存在しない自治体が増えてどーこーっていう論調があるけど、Amazonのおかげで本屋のない場所に住んでる読者が便利に本が購入できる現実については、みんなどのように考えているのかな?
しかも日本のAmazonは再販制に基づいた書籍雑誌定価販売を順守している。送料無料にいちゃもんつける人もいるが、別に文句を言うような話じゃないよね。純然たる企業努力なだけだし消費者=読者にも悪い話じゃない。
かつての雑誌の売れ筋は週刊誌のゴシップ記事、オジサン大好きヌードグラビア、赤文字青文字のファッション雑誌、旅行雑誌、高齢者が大好きなテレビ情報誌、健康雑誌、パズル雑誌とNHKテキスト、子供達は小学一年生や漫画雑誌等など。。
いまは上記の情報は、ほぼすべてウェブ上で流通していてみんなスマホやタブレットで情報を取得し愉しんでいる。
文春オンラインやインスタグラムやTikTokにYouTube、更に各種マンガアプリまで。
かつて雑誌上で流通していた情報の、そのほとんどがネット上いろんなサービスに移行したのが雑誌の売り上げ減の大きな原因だ。
雑誌の情報に価値がなくなった訳ではなく、雑誌に載るような情報の流通経路が大きく変わっただけなんだ。
これ結構重要な変化なんだけど、書店や出版業界でボーっと働いているオジサンたちの中には、未だにこの事実すら理解出来ていない人が存在する。
そんな馬鹿な。。と思ったそこのあなた。
近場の書店の売場レイアウトを思い出してみて欲しい。
書店の雑誌売り場って入口から近場の良い場所&結構大きな床面積をドーンと専有していると思いませんか??
これって、かつての主力商品だった雑誌売り場をそのまま惰性で継続してるだけなんだ、、壊滅的に無自覚に、、
多層階の大型書店でも大抵は雑誌売り場って1階にあるでしょ。
ネットワークとスマホがこれだけ普及して、情報流通速度&範囲でも決して適うことが出来ない雑誌。そりゃ売れなくなるよね。。
雑誌が売れないのは本屋のせいだけではないのだが、売れない理由にあまりにも無自覚、無頓着なのもまた書店だ。
出版業界ってオワコンなの?
そして無自覚なのは書店だけでもない。
ネットの発達は出版業界全体の長年の慣習にも変化をもたらしている。
もうクドクド説明する程でもないが、ネットの普及によって既存の出版システムに頼らず誰でも自由にタイムリーに情報を発信できるようになった。
かつての出版は言論の自由を担保するための重要な手段と考えられており、
その為なのか再販売価格維持制度や委託販売制度など特殊な商習慣が許容されてきた経緯がある。
書店は売れ残った雑誌書籍を取次軽油で出版社に返品出来る代償として、注文もしていない大量の新刊駄本が委託商品として取次から日々大量に送品されてくる。
そして書き手が今あえて『新刊駄本』としたのには勿論根拠がある。
出版社には売り上げが下がると、刊行点数を増やして売上を確保しようとする習性がある。とても売れそうもない粗製乱造の雑誌や書籍でも出版して取次に納品すると取り合えず売上が確保出来てしまうのが、現在の出版流通の構造的な問題点だ。
書店で売れ残って返品された分は後日の清算となる。
書店から返品が戻って来る頃には、また次の粗製乱造の新刊駄本を刊行する。。
実は出版業界は、この絵に描いたような自転車操業を数十年と繰り返しているだけなんだ。
日本の出版刊行点数は年間約7万点と言われているが、そのうち結構な部分をこの不毛な自転車操業に費やしている現実がある。
この特殊な商習慣を著作で『取次制度依存業界』と看破した偉大な編集者もいましたが、ようやく忌むべきこの特殊な商習慣を変革するチャンスがいま訪れようとしている。
現代の言論の自由は様々なメディアにより担保されていて、出版業界は良い意味でone of themになった。
じゃあ出版や書店はその役目を終えたのかというとそんな事は全然ない。
雑誌はこれまで説明した通りであれな感じだが、じゃあ紙の本、書籍はどーなのか?
冒頭の出版販売額の記事のグラフをもう一度見て欲しい。
『書籍』の販売額も漸減しているが、実は構成比は電子書籍の伸長にも関わらずほぼ変わらず約40%を維持しており、販売額も2016年以降は雑誌を上回っている。記事中のサマリーでは「健闘している」なんて表現だけど本屋の活路はここしかない。
寧ろ消費者、すなわち読者は『書籍』に期待しているのだ。
それは本稿冒頭のとおり、本が売れてないのに本屋が好きな人が結構いたり、本や読書に関するウェブ記事に結構な需要があることで証明されている。
書店に雑貨やカフェやカレンダー、手帳は必要なの?
紙の書籍や読書にはある程度の人気や関心はあるっぽいんだけど
ビジネス的に苦境に立たされている書店では実際にどんな対策や工夫をしてるんだっけ??
大手の書店チェーン等で良く見かけるのは、雑誌書籍以外の商品の展開だ。
夏休みが終わってすぐの9月の書店には、びっくりする位に大量の手帳にカレンダーが送り付けられる。そしてみんな本棚を撤去してイソイソと手帳やカレンダーをお店の一等地に山積みする。。。
他にも文具やこだわりの海外雑貨やファッション小物。
CDやDVDは一昔前から併売もあったが、最近はバンダイのガチャガチャやアニメグッズ売り場や絵本のグッズ、キャラクター商品の売り場が流行っている。
あと書店にカフェを併設するのも、かなり一般的な光景になった。
でもこれって、何か違うんじゃないの?(笑)
だってリアルの書店が好きな人や紙の本の読書を愉しみたい人たちって、書店で雑貨買ったりとかガチャガチャをしたいのかな??
書店で手帳やカレンダーを買う人ってきちんとした本も読んでくれるのかな?
勿論完全に不要とまでは言えないけど、この微妙な対策の根本は取次や大手チェーン書店の自分たちの都合優先の施策だ。
つまり粗利の低い本より、高い粗利の商品を置いたり、手帳やカレンダーを書籍(※書店で売ってるほとんどのカレンダーや手帳は実は『書籍』として流通してるんだ!)として書店流通に乗せて流通網の維持に繋げたい事情があるんだ。
勿論、そこには本好きの読者の意向や希望なんかはまったく関係なし。
結果本当に本が好きで読書に興味がある、とても貴重で重要な客層をむしろ書店から遠ざけているんじゃないかな??
しかも雑貨や文具はたしかに粗利は高いけど雑誌や書籍と違って売れ残り在庫リスクが存在する。片手間の素人仕事できちんと在庫管理や利益確保をできるのかな?
この状態は、まさに貧すれば窮する。
僅かで不確実な粗利向上に目がくらんで、本当に大切な客層ががっかりするような施策になっていることを、取次及び書店の経営者たちは気がついているのかな??
出版業界反省会
さて、こんな感じで出版業界は20数年続けて右肩下がりに売上が減り続けてるのだけど、中の人たちは現状認識すら怪しい状態なんじゃないのかな?
出版業界のお偉い既得権益オジサン達はみんな、現状を肯定するための言い訳探しに終始してるだけで、既存のお気楽短絡な結論に理由をこじつけることだけを考えている ようにしか見えない。
そしてありふれた結論に導けただけで、安心してそこで思考停止に至る。
勿論、まともな打開策や改善策なんて全然考えてない。
変化に対応しようとせずにただ自社を維持しシステムを延命することだけに執着してるようにしか見えない。
何か動いたと思ったら、こんなおねだり作戦だけ。
この車座ヒアリングとやらの中で、参加者の一人の某取次の経営者は厚顔無恥にも、自社で行っている無人書店の取り組みに経産省から補助金を出すように提案したらしい。
このことを知った大阪の良心的な書店主が、その心情を吐露するNoteを公開し大きな反響を呼んだ。
無人書店の詳細については稿を改めるが、営業時間が延びる以外に何の本質的な解決に繋がらない、びっくりする位に本当に安直な施策だ。
品揃えのつまらない、粗利の変わらない書店が24時間営業になっただけで、現在の書店を取り巻く諸問題の解決になるというのか?
このように安直な結論には『それって本当?』的な怪しい予定調和にすぎないことがとても多い。
先ほどの経産省の書店プロジェクトの記事の見出しを見直して欲しい。
『補助金・無人書店・キャッシュレス』
話題になったらしい、これらの言葉の空虚な安直さ&予定調和具合が絶妙なことこの上ない(笑)
こんな状況を見ていると、ある名作日本映画で語られた以下のセリフが本当に身に沁みてくる。
『戦線から遠のくと楽観主義が現実に取って代わる。
そして最高意思決定の段階では現実なるものはしばしば存在しない。
戦争に負けている時は特にそうだ。』
もちろん実際に戦争で負けている訳ではないけど、
出版、書店業界は確実にビジネスで負けているだよね。
出版、書店業界のお偉いさんたちは、この敗戦の現実すら直視できていないのが現状なんじゃないのかな?
でも最前線で読者と接し、日々様々な書籍と向き合っている書店員は違うはずだ。
出版業界の今後について声を上げるべきなのは、現場を知らない既得権益者でも無能な経営者たちでもない。
今こそ、現場の書店員がそれぞれの立場や知見から知恵を絞って、現状の不合理な状態を是正すべく動くべきじゃないのかな?
書店退化論
一方で最近、大手勤務の書店員や一般の本好き方が起業して『独立系書店』や『シェア型書店』を開業するケースが増えてし話題になっている。勿論現在の出版、書店業界の現状に問題意識を持っているのは書き手だけではないので、これは当然のことだし、その気持ちもとても良く理解できる。
そして何より、『独立系書店』や『シェア型書店』は読者にとても好意的に迎えられている。
減り続けているいままでの『書店』と『独立系書店』や『シェア型書店』は何が違いうのかな?
この違いについては2011年に刊行された書籍の中で、既に明確な回答が述べられていて、読者の不満点も明確に指摘されている。
本書の第二章ではネット普及に伴う情報流通の拡大を契機とした、人々の消費行動の変容について述べられているが、その中でとても印象的なのがかつて存在した大型CD店HMV渋谷の衰退について。少し長いんだけど簡単に紹介すると、
HMV渋谷はバイヤーと呼ばれる店員ひとりひとりの意識の高さとセンスの良さ熱意を源泉として、音楽好きの顧客達から絶対的な信用を誇っていた。
バイヤーは独自の企画で様々なムーブメントを熱いながらも的確な批評解説を手書きPOPで掲示、顧客はバイヤー手製のPOPを参考に自分の音楽の知識を広めることが出来た。
しかしHMVの売り場は本部の主導で変質する。店舗の洗練との名目で熱い手書きPOPは印刷された全店共有POPのものに変更された。さらに本部は共有POPをパッケージ化された広告としてレコードレーベルに販売、ビジネス化した。
本部の主導で全国のHMV店舗は画一化され、バイヤーたちが持っていた個性は失われていった。HMV渋谷も無個性な店になり顧客の信頼は失望にかわり、ついには2010年10月に閉店することになった。
HMV渋谷の閉店は大きく報道されたが閉店の理由は『インターネット配信に押されて売上が落ち込んだ』とされた。
既視感の強い衰退の過程に、書き手は強い寂寥感を感じてしまう。。
現場の価値を理解できない経営陣による安直な愚策の施行と情報流通の形式が変わったことによる影響が重なっての大幅な売上減は出版業界とほぼ重なる事象だ。
そして一番重要なのは、本当の読者や消費者が、書籍や音楽に求めているのは画一的なマス向けの流行りの品ぞろえではない、ということだ。
『独立系書店』や『シェア型書店』が支持されているのは、それぞれの店主、スタッフが熱を持った拘りのある、コアな商品をお勧めしているからだ。
さて、この10年以上前に刊行された書籍に記載されているこの事実を出版業界のお偉い既得権益オジサン達は理解出来ているのかな?ちょっと試しに大手取次経営のご自慢の無人書店のHPを見てみようか?
はい、もう上のリンクだけでダメダメな品揃えのが分かってしまうのが何だか、とても可哀そう(笑)
いちいち突っ込むのも面倒なんだけど、サクッと、トレンド、旬、ニュースアプリのホーム画面のような空間って、そんな流行りの当たり障りのない情報が欲しければ、それこそスマホでXやYouTube、TikTokを見るだけでいいのよ。リアルの書店の必然性はもっと別な場所にある。
この空虚な無人書店の出現の理由は、大手取次や出版業界のオジサン達には現実や現場が理解出来ていない事に加えて、今までの一方通行的な出版流通や販売施策を無理やり維持しようとする意志表明に他ならない。
ライトユーザー向けに作った書店のつもりっぽいけど、東京メトロの溜池山王駅に読書ライトユーザーって多いのかな?
何もかもチグハグで、頓珍漢なこの無人書店は今の出版業界を象徴しているのかもしれない。
そしてこれは根拠のない確信なんだけど、出版業界の偉い経営者の皆さん、ちゃんとした本を読んでないよね(笑)
あなたたちの会社の経営課題、売り上げ減の真因、あなた達の店先にある本にいろいろ書いてますよー
経営者たるもの、ビルゲイツまではいかなくとも、それなりの読書は嗜みだと考えますが如何でしょうか?
出版物の情報流通の歴史
さて、ここまで出版業界の売上が右肩下がりで書店が減っている原因についてネットの普及によってこれまで販売比率が高かった雑誌が売れる見込みがなくなったのと、おもにチェーン書店の頓珍漢で画一的&短絡的な品揃え、売場作りの結果、読者に愛想を尽かされている状況についてざっくり解説したんだけど、もう一つ触れなければならない大きな要因がある。
それは、ネットがこれだけ普及しても一向に洗練されない『本に関する情報の伝え方』だ。
これを読んでいるみんなは普段、本を買いたい思うきっかけはどのようなものだろうか??
因みに古き良き昭和の場合だと『新聞広告』で見た『新聞書評』で見た、が大きな構成比を占めていた。まだほとんどの家庭が新聞を宅配で購入し電車の中でもサラリーマンは新聞を折りたたんで読む時代は新聞と出版業界の蜜月時代でもあった。新聞の広告欄は毎日新刊と売り筋本雑誌の広告で埋まり、お父さんもお母さんも高齢者も本や雑誌の話題は毎日の新聞から摂取していた。
新聞社は上客の広告主である出版社へのサービスとして書評欄を創設、拡充したともいわれている。
マスメディアを通した一方通行の情報しかないこの時代は牧歌的でビジネスもシンプルだった。新聞広告や書評に載った本を店先に準備するだけで商売として成り立つのだから。
平成になると新聞経由の情報が減って、TV経由の情報の比率が上がるが、基本的にマス経由の一方通行な情報流通に変化はまだない。
みのもんたの番組で取り上げた健康本やTVCMを大量投下するディア〇スティー〇的な雑誌、ジャニーズが表紙の雑誌、年末に出る強面のおばちゃんの占い本等、団塊世代向けの販売比率が高まった時代だ。
んでミレニアムを境としてネットの普及と共に様相は一転する。
本好きの読書家は自ら膨大な書籍のデータベースにアクセスすることが可能になり、書店に行かずとも読みたい本に次々と見つけることが出来るようになった。
フツーの読者はネット上でバスった本、情報に興味を持つことが多くなった。最初はmixiだったのが程なくFacebook、Twitterになり、更にYouTube、インスタ、Tiktokが情報源として加わった。
ここで雑誌の価値は大きく損なわれ、コンビニで漫画を立ち読みしてた人たちはスマホアプリで漫画を読むようになる。
またここまでの読者は新聞の記事は読んだとしてもネット上でしか読まず、紙媒体としての新聞広告、新聞書評欄の価値は大きく棄損した。
高齢読者、情報弱者は新聞からの情報に残留したが、主にリテラシーの低い層向けの情報が流通するようになった。
ちなみに本題からは逸れるが、新聞も雑誌書籍と同じく再販売価格維持制が認められている品目で売上減も同様に顕著な業界だ(笑)
売上減の要因もほぼ雑誌と一緒で、扱う情報がほぼニュースである性質上ネットでの情報流通にさらに適しており、紙の新聞の必然性は、雑誌よりさらに乏しい。
ここまでとてもざっくりと、ネット普及以降の出版物の情報流通の流れをまとめたんだけど、んで出版業界や書店は何処でどんな感じで、本に関する情報発信をしてるんだっけ??
そう、高度経済成長期からネット普及までは新聞広告&新聞書評での本の情報流通が、たまたまうまく機能していた。だがネット普及による情報流通の変化は商品としての雑誌だけでなく、新聞という出版業界の広報手段もオワコン化させていた。あ、ついでに地上波TVも何処見ても通販番組の延長戦みたいなバラエティばかりになって陳腐化した。王様のブランチに筑摩書房の著名な編集者が出演していたのが、遠い過去になってしまった。
そして、いつもの事だが出版業界は、この状況の変化に有効な対策を打てないままに現在に至る。
各出版社では自社の刊行物紹介のオウンドメディアを立ち上げたり、大都市圏の電車内広告を強化する等の手段を講じたところもあったが、効果は限定的に過ぎず、コンテンツとして魅力があるとも言えないものが大半を占めている。
新聞各社も書評ページをネットにあげたが、無数の情報が氾濫するネット上での新聞社の書評は、かつての影響力には遠く及ばない。
読書や本の価値って?
そもそも出版業界は年間に何万点もの出版物を刊行しているにも関わらず、刊行した出版物を読んでも貰う努力が慢性的に不足しているのではないか?
大手出版社から零細出版社まで、かつての出版物のマーケティングといえば、新聞広告を出して自社媒体に告知を出すくらい。新聞書評に取り上げられたらラッキー。これだけだ。
ネットが普及し情報流通が複雑化し、SNSが登場しても、出版業界のマーケティングはさほど代り映えしない。
出版物という情報を扱う業界なのに、自分たちの商品の情報についてどうしてこんなに無頓着なんだろう?
勿論たまには無頓着ではない人もちゃんと存在する。でもちゃんとした人の大半は出版物の著者自身や編集者等の当事者であり、当事者が主体となって上手にプロモーション出来た本は、その成果が売上に反映されている。
読者が、この本を読もうかな?どうしようかな?と思っているときに、参考になる追加情報があるだけで、売上に繋がる確率は大きく上がるはずなのに、その追加情報が圧倒的に提供できていないのではないか?
またもっと根本的な部分で『読書や本は、いいものである』という考え方自体が思考停止している現実がある。
なんで読書が良いのか?
良い読書はどのように行うのか?
どの本が良い本なのか?
取次や書店は、この問いに答えるような取り組みを何か行っているのかな?
因みにこの辺の啓蒙活動は、他の業界ではどのようにしているのだろうか?
例えば、スタバ。
スタバは各店で『コーヒーセミナー』を実施している。
このセミナーの源流であったと思われる様子が1999年刊行の下記の書籍で紹介されている。※リンクは文庫版
スターバックスのコーヒー豆の仕入れの親分がいて、(中略)かれはボストンでコーヒーの講義を毎月やっているのだ。実はかれは、スターバックスと双璧をなすコーヒーベンチャーの雄だったコーヒーコネクションの創業者だけど、ある日自分の会社を「コーヒーの仕入れは任せろ」という条件でスターバックスに売ってしまった。曰く「ビジネスには飽きた。おれはコーヒーが好きで、いいコーヒーを売るのに専念したいんだ。そしていいコーヒーを売るためには、コーヒーの味がわかる客を育てなくてはならない。きみたちにコーヒーをわからせなくてはならない。だからこうして講義もするんだ。」
コーヒーと本を入れ替えて意訳すると、『本が好きで本を沢山売りたいのだが、良い本を売るには、本の事をわかる読者を増やさなければならない。』って感じだ。
さて本の場合は『講義』の部分をどうやって解決しようか?
最後に
書店が減っている原因について、一通り考察して問題提起するだけで結構長い話になってしまった。
全部まとめて丸っと解決!、ってお気楽な結論に至るわけもないので、一つずつ地道につぶしていくしかないだろう。
このNote連載では今後、それぞれの課題ごとにもう少し掘り下げて考えていく。その中で『kumartbooks』という実験的なサービスがどの部分の問題解消に繋がるかも触れていく。
このエントリーもこれからの記事の一人の元書店員の個人的な経験を基にした論考と解決策の提示に過ぎない。
異論反論、ご意見苦情等皆さん思うところは色々あるのは承知の上だし、むしろ大歓迎だ。先ずはそれぞれが既存の考えや固定概念に捕らわれず、状況を変えようと考え行動することが大切だと考えるからだ。
それぞれの立場で考え動く、その中で論を交え、実践を繰り返すことで新たな方策にたどり着くこともあるだろう。
そして一番重要なのは、現場に近い多くの人間がボトムアップで動くことではないかな?
いまの出版業界の経営層=既得権益層に何か良い解決策が思いつくと仮定して、それを実行に移す時間は充分すぎるほどにあったはずだ。
出版業界の売上がピークだった96年から、ネットが普及しはじめてから20年は経過しているのに、出版業界は時代に対応するために何かしたのかな?
出版業界の諸問題は今の日本の人口減少問題と全く同質なんじゃないかな?
今の出版業界の状況は、だいぶ前からいずれそうなると充分に予測出来ていたのに、何もしてこなかった結果なのだから。
では、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
