
紺野登の構想力日記#12
イノベーションのためのジャーナリングの教科書【4】
人工知能はジャーナリングするか ー 歴史的構想力とジャーナリング
◇ ジャーナリングとAI
ぼくらの感情知能(EQ)を、自分と他者の感情を認識する能力だとしよう。
最新のアップルウォッチは運動量、心拍数や血中酸素濃度まで測ってくれるが、それだけではユーザーが健康かどうかはわからない。それらのデータを記録し追跡してはじめて健康状態がわかる。
同じように、ぼくらの「感情データ」を測って、追跡することで感情的に健康な状態、つまり幸福(自分だけの幸福だけでなく、他者に好感を与えることも含めて)などの状態を生み出し、保つことができる。
ジャーナリングはある意味で感情データの記録なのだが、人工知能(AI)を使ってジャーナリングの質を高めようという試みも面白い。
AIはどうやって感情を測るのか?
IBM Watson の「Tone Analyzer」は、ぼくらの書く文章中の感情を自動検出しようとする試みだ。
ぼくらが言葉で何かを書いても、それは必ずしも感情を表しているとはかぎらない。たとえば「今日はすごい一日だった」とジャーナルに書いたとしよう。その一文には、周囲の言葉との関連、前日やずっと過去の記録から、つまり文脈からして、喜びや恐れの感情がともに含まれているかもしれない。この Watson の感情分析 API は、喜び、恐れ、悲しみ、嫌悪感、怒りの 5 つの感情を検出する。
こうした感情データをトラッキングするアプリもある。
Reflectly は感情チェッカーやジャーナリングのペースメーカー機能を持っていて、長い文章が苦手でも一日の気分や感情の動きを捉えてくれる。
ここから類推されるのは、まず、ぼくらは実は自分の感情を表現するのがそんなに得意でないことだ。それから自分にも嘘をつくかもしれない、ということ。そしてそこにAIの活用が可能であること。
そして人工知能がだんだんぼくらの内面について理解して、そのうちぼくらに変わって、さまざまな「感情センサー」を介して、ぼくらのジャーナリングを始めるかもしれない、という未来だ。
「一般的に信じられている」現代の人工知能の弱点といえば、「今この世の中を身体を用いて生きていない」ことだ。だから個々のタスクについての深層学習はできても、それが全体としてどのような人間の生活や人生にとっての意味があるのかがわからない。
つまり、「彼ら」は瞬時瞬時のビットの情報処理で生きている。だから、全体が見えない。全体を見る(意味がわかる)には「自己」意識が必要だ。だからやっぱり人間と違う、人間は生きているんだ!となる。
けれども、もし人工知能がジャーナリングを覚えたら、新しい神的な人工知能グルが生まれるかもしれないと考えるのは、ユヴァル・ノア・ハラリだけではないだろう。
AIが自己を認識して、過去-現在-未来を通じての歴史的認識や歴史的構想力を持つときなどは来ない、とは言い切れない。
◇ ジャーナリングにおける自由意志
そこで問われるのは自由意志ではないかと思う。
以上のような人工知能の世界となると、おそらく人工知能の世界では人間の自由意志など存在しないと考えているだろう。しかしそこには一瞬の隙間がある。これについては『イノベーション全書』(紺野登、東洋経済新報社、2020)の冒頭で述べた。
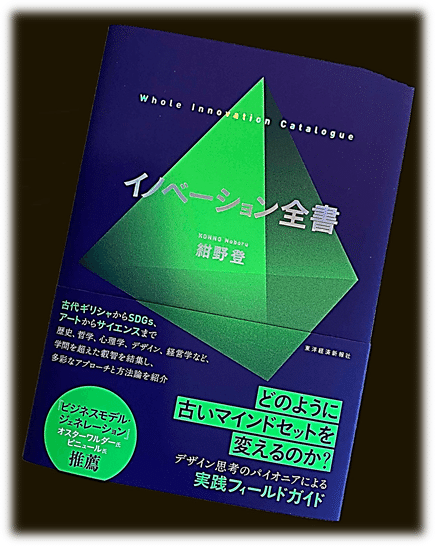
0.2秒の自由意志の隙間
生命の躍動ともいうべき人間の自由意志が、幻想ではなく、ほんのわずかの時間に限り存在するという研究結果が、最近になって発表されました。ドイツのベルリン大学付属シャリテ病院による脳科学の最新研究によるものです。そのことを報じた『WIRED』の記事が話題になりました。
そもそも自由意志にまつわる論争の発端となったのは、1980年代に米国の生理学者ベンジャミン・リベットが行った「運動準備電位」についての研究です。リベットは、人間が腕を動かそうと意識し、腕が動くまでの過程を、電気的に測定しました。その結果わかったことは、次のようなものでした。
「平均的に、われわれが『動作』を始める約0.2秒前には、『意識的な決定』を表すシグナルが現れる。しかし、われわれの脳内では、『意識的な決定』を示す電気信号の約0.35秒までには、それを促す無意識的な『準備電位』が現れているのだ。つまり、われわれ『こうしよう』と意識的な決定をする訳0.35秒までには、すでに脳により決断が下されていることになる」
……この実験欠陥が、自由意志は存在しないとう決定論的な見解の科学的根拠とされたわけです。……
しかしリベットは、(その後の)約0.2秒という時間差にも注目していました。このわずかな間に、意識が、腕を動かすという脳からの指令を拒否する権利を持つのではないか、と。……すなわち、脳が決断した後にも、私たちの自由意志が発揮され脳の決断を拒否する隙間があるということです。
ここに、私たちが「機械」であることから抜け出す瞬間があるのです。
(『イノベーション全書』pp.025-027)
この一瞬のきらめきの中に、活路があるかもしれない。そのきらめきを繋ぐための「アリアドネの(赤い)糸」となるのがジャーナリングではないか。
少なくとも、今のところは、人工知能とぼくらを分け隔てているのは、自由意志とジャーナリングによる「意識の持続性」である。それは、社会において人生として継続している「私」である。
もっとも「ヘンゼルとグレーテル」の寓話では、迷子にならないように光る小石やパン屑を道々に巻いておくのだが、パン屑のほうは翌朝小鳥たちに食べられてしまう。良いアプリを探す甲斐はありそうだ。
自由意志に関しては、これはもう長いあいだ哲学の中心課題の一つであり続けている問題であり、現代では脳科学、物理学、生物学などの領域でも先端的課題として解明が進められ、さまざまな立場からの論争がたえることなく続いている。
人間に自由意志は可能か?
人間が自分の決断や判断に対して、自由にコントロールをおこなうことができるか否か?
この問いに対しては、じつは結論はない。
しかし、本当に考えなければならないことは、自由意志があるか否かといった二元論的な話とは別次元のことなんじゃないかとぼくは思っている。
17世紀の偉大なる哲学者スピノザに否定されようが、先端科学の知見によりそれは幻想だと言われようが、おそらく意識的に日々を生きているすべての人は、自分が与えられた運命をただ機械的になぞっているのではなく、自らの手で未来を切りひらいているという「自覚」を持っているのではないだろうか。
だとすれば、それはなぜなのか、人間はなぜそういった自由を感じるのか?
その自覚は、幻想とか妄想といってしまうには、あまりに生々しく根強い感覚だ。単に無知ゆえに幻想を抱いているにすぎないというのではなく、何らかの生まれついての能力に端を発していると考えるのが妥当のように思う。
自由意志が本当に存在するのかはわからないとしても、その存在を信じるのが人間なのではないだろうか。なぜなら、未来は私たちに属しているからである。
しかし、本当のことをいえば、「私」はそんなにうまく持続していない。私というのは断片化していて継続もしていない。人工知能に対して人間が有利だというのは単なる観念的な問題だ。
しかしそれでもわれわれは統合的な自己を目指そうとしている。
だからジャーナリングは自分自身を見つめ直し、まとめ直す、自己を再生する秘法なのだ。
◇ 賢慮の「型」の追求
ジャーナリングは思考の「型」を身につけるための鍛錬にもなる。ということについて、ぼく自身の体験を通して考えたことを書いてみよう。
前回、「賢慮のリーダーシップ」について研究を続けるなかで、リーダーがジャーナリングを活用していることを書いた。
賢慮とはすなわちフロネシス、この世の中における人生を円満、幸福、安全に終えるための卓越した人間の知的資質である。アリストテレスが著した「フロネシス」には賢人の思慮分別「Prudence」と、実践的智慧「Practical Wisdom」の2つの意味が見える。2つを合わせたものが「実践知」としての賢慮である。
これは、価値や倫理の思慮分別を持ちながら、刻々と変化する個別具体の状況や文脈のただ中で、最善の判断と行動ができる能力、ということができる。単に正論を語って不言実行を謳うのではない。人生は複雑なのだ。
その意味で賢慮は高質な暗黙知である。リーダーの身体や習慣の中に埋め込まれた、きわめて深い共通感覚(コモンセンス)である。
したがって、いわばブラックボックスのような面がある。だから、アリストテレスはあまり言葉でそれを解説するのを避けていて、賢慮の人(フロニモス)の生きる様から賢慮を学べ、といったのだ。
人が言葉だけから想像したものは、経験によって裏切られる。そして経験したあとではじめて、事前に言われていたことが、そのとおりだったとか、まったく違っていたと分かる。
要は、言葉はその背後にある行動や行為とともにあってこそ、力を持つということだ。これはインターネットの時代になりますます顕著になっている。「こう思う」とか「こう考える」みたいなことだけでは価値は生まれず、「こういうことをやってみた」「こういうものをつくった」という行動や行為の事実が価値を生む。そうでないと言葉に重みや熱さがないと言われる。
その実践と自己観察のフィードバック・システムを駆動するエンジンがジャーナリングである、ということはこれまで(#09、#10、#11)述べてきたとおりだ。
この繰り返しが、イノベーター、あるいは知識創造のプロデューサーには不可欠である。
知識創造は信念の形成、持続的な自覚の努力である。
それは言い方を替えれば「型」の修得ともいえる。
「型」は、能や武道などにみられるもので、その道を探求する者が身につけるべき基本的な所作である。とはいえ「型」は固定的なものではなく、「守・破・離」のように進化していく。
ちなみにかつての日本企業はこのプロセスを日常の業務、現場において実践してきた。
イノベーター、イノベーション・リーダーの表層での資質や特徴は実に千差万別だが、こういった賢慮の「型」の追求と教養への志向性は共通したものではないかと思われる。
ジャーナリングのより具体的な活用法として、プロフェッショナル・サービス・ファーム(PSF)のグル、デービッド・メイスターは次のような「プロフェッショナルとしてのレビュー」をすすめている。
・ あなたは個人的に、どんな点からみて、昨年に比べて市場にとってより価値ある人になっているでしょうか?
・ あなたが、過去に比べて市場にとってより価値ある人となるためのプランは何でしょうか?
・ あなたはこの一年、具体的にどのような新しいスキルを身につけたり強化しようとしていますか?
・ これから先3年間のあなたのキャリアについての個人的な戦略は何でしょうか?
・ あなたが、少し先に、市場にとってより魅力的になるためには何ができるでしょうか?
・ 厳密に言って、あなたは何によって知られたいのでしょうか?
(『脱「でぶスモーカー」の仕事術』デービッド・メイスター 著、紺野登 解説、加賀山卓朗 訳、2009)

◇ アイデアの工房としてのジャーナル
一方、ジャーナリングには創造性との相関があるといわれる。
それは、自分自身のアイデアや記憶を貯めて醸成していくプロセスでもあるからだ。その過程でアイデアの背景や自分の意識も変わる。
よくインスピレーションが重要だというが、「一番いいアイデア」は必ずしも勝たない。イノベーションのためには、異なった光で自分のアイデアをみることが有効なのだ。
つまり、自分のこだわりや思い込みから一端離れる。それには時間による醸成が必要となる。プロトタイピングとは捨てることでもある。自分が出したアイデアに愛着、固執、アタッチしないで、しばらくしてからアイデアに戻る。そのときこそジャーナルの記憶が有用になる。
イノベーションというのはインスピレーションや天才性でなく、こういった工房のような仕組みや仕掛けから生みだされるともいえる。
パーソナルコンピュータの父、とも言われる科学者・教育者のアラン・ケイは「トポス会議」のなかで、人間はまったく新しいアイデアを理解できない。ニュースは実際には新しいことではない。それらを理解するためにはあらたなコンテクスト(文脈)を備えていることが重要だ、という意味のことを語っている。(『賢者たちのダイアローグ 「トポス会議」の実践知』野中郁次郎・紺野登 編著、2019)
既存の思い込みや知識から一旦抜け出さないといけないのだ。
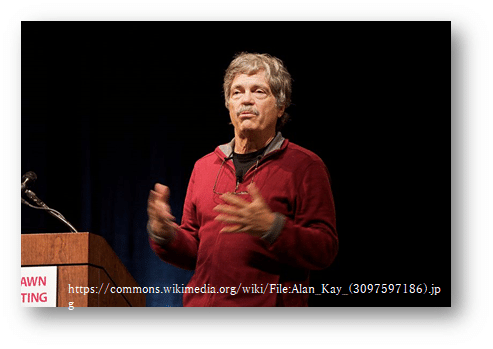
だから、賢い創造的な人々の作法というのは、いったん出したアイデアをしばらく放っておいて、しばらくしてからみたときに、湧き上がってくるようなアイデアを掴む。新たなコンテクストで見ると初めて意味が見える。
映画監督のウッディ・アレンも同じようなことを言った。自身のドキュメンタリー映画『映画と恋とウディ・アレン 』のなかで、どうやって新作映画のアイデアを考えるのか、と聞かれてこう答えている。
すでにアイデアはあったんだ。アイデアはいろんなところからやってくる。それを書き留めて引き出しに投げ入れておくんだ。その中にはいろんなアイデアが詰まっている。それをあるとき眺めていると、まだ自分でやったことのないアイデアにぶつかるんだよ。
(映画『映画と恋とウッディ・アレン』(下動画は予告編)より)
イノベーターにとってはジャーナリングやノートとりは重要なツールだ。
あるジャーナリストが100人の科学者、プログラマー、研究者を対象に、アイデア探索するときに好きなテクニックは何かを聞いた。答えとしては、ブレーンストーミング、実験、プロトタイピング、コラボレーションなどと並んでジャーナリングは高位に上がった。
アインシュタインは高校生のときからいつでも手帖をポケットに入れ、観察結果、問題、実験のデザインや計画などを書き留めていたという。
レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿は、500年の時を経ていまなおぼくらの脳を刺激する。
◇ ジャーナリングが未来を創る
賢慮のような暗黙知を自己のなかに育てるには、マニュアルは通用しない。
日々のフィードバックの継続を通して、日常的実践の中で身につけるしかないのだ。
その過程で、おそらく誰もが気づく、というか必然的に到達する理(ことわり)がある。それは、そうした実践を支えるのは教養(リベラルアーツや哲学)だということである。
教養とは?といった解説書を数多目にするけれど、その解説を読んで教養が身につくわけではないだろう。むしろその逆で、日々のフィードバックのなかで、教養が実践を自覚させ、行動を変えていくことに気づくのだ。
日常の実践を続けながら、数学、幾何学、天文学、音楽などの基礎と哲学、歴史、文学、芸術などの要素が、私たちの大局観や観察眼を養うものとなる。ということが明らかになるのである。
リベラルアーツの中核は、人間や都市や社会を共感し、想像し、実践する構想力にある。賢慮を備えたリーダーだけが都市(社会)をデザインし、政治力を発揮できる。
ジャーナリングを通じたフィードバックは、自分の哲学を問うものになる。それは結果的に歴史・世界のなかでの自分の再発見・再構築につながるといえる。
それは過去を振り返りつつ未来を見て、今を生きようとする物語りを語ることでもある。
このレンブラントの自画像では、レンブラントがアリストテレスに扮し、アリストテレスが『詩学』で賞賛した盲目の吟遊詩人、叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』の作者とされるホメーロスの胸像に手を置いて見つめ、沈思黙考している。それは、「はじめ、途中、終わり」という歴史、物語りを想うことなのである。
それはただ過去を見てその延長線上で現在と未来を考えることだけではない。いかにぼくらが過去にとらわれているかを思うことでもある。
その過去の自分や歴史から逃れるためにも、ジャーナリングは有効なツールとなるだろう。

紺野 登 :Noboru Konno
多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。著書に『構想力の方法論』(日経BP、18年)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、18年)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社、20年)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) 、『美徳の経営』(NTT出版、07年)などがある。
Edited by:青の時 Blue Moment Publishing
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
