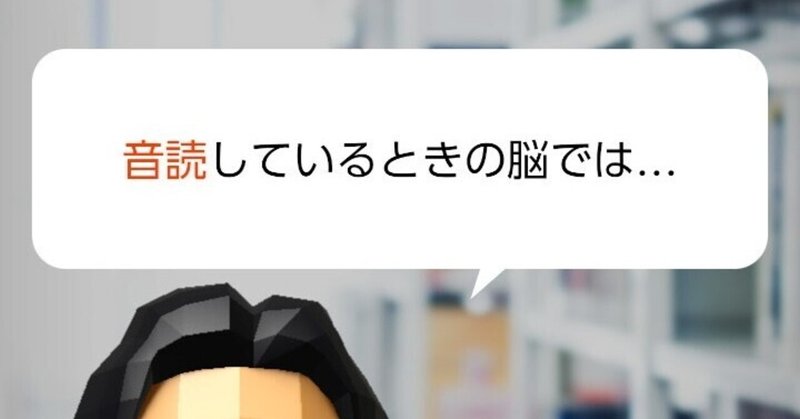
経営戦略の全体像を把握する
「経営戦略の全体像」を勉強する。これだけでも、しっかりとしたドキュメントに展開できれば、もうお金になるところではあると思う。ほんのちょっとの実務経験が積めるかが、お金になるかの分水嶺だと思う。コンサルタントの仕事って、「業務SE」みたいなもんですよね。「業務SE」と、そんなに遠くないですよね。こういう理論に基づいていない、中小企業がなんと多いことかと思う。こうした経営理論が、経営者のみならず、一般社員にまで、浸透している会社なんて、ほとんどないと思う。学問的には、非常に、貧弱な会社が多いということですよね。どの会社も「理論派」というより「体力派」ということですよね。では逆に、ひるがえって、たとえ、経営者のみならず、一般社員にまで、こういう経営理論が浸透したとしても、その「浸透」は、オーナー経営者(株主兼経営者、又は原始株主)の、配当収入を出す、お金儲けの幸せのために、働く、命を捧げる、人生を捧げるということになるから、そういう理論を透徹したとしても、従業員は、バカバカしいったら、ありゃしないというところでしょう。私は、本当は、大学で、企業ファイナンス(経済学・法学・経営学)の専門家になりたくて、配当政策やストックオプションや株主やステイクホルダー(株主・債権者・従業員・消費者・社会)について考えるということをやりたかったのですが、ブログでも、その中でも、このnoteブログなら、研究を続けられるはずである。
経営学も、行政が、個別具体の企業活動まで統制したいという要請(cf.たとえば行政法は社会の統制)から、発展してきた学問だと、私は捉えています。簿記とか会計学(管理会計や財務会計なんて違いはあるものの)なんてのも、そうでしょう。それが、個別具体の企業の経営者や構成員の素養にもなっていったというところだと思います。経営学が勉強できるところは、日本だと、国立大学(日本で国立大学で経営学部があるのは2つだけ)や私立大学の経営学部というところだとは思いますが、市井(しせい)にあっても、中小企業診断士みたいな試験勉強で、勉強することも可能である。中小企業診断士の企業経営理論の試験問題は、「単純な用語の説明の入れ替え」や「単なる国語の問題」などが見られる。
法人について議論する前に、たとえば、将棋好きな私が気になる、日本将棋連盟なんかは、「公益社団法人」(=人の集まり→「将棋のプロ棋士の集まり」に法的地位を与える)なんです。今度、東京将棋会館と関西将棋会館を建て替えるらしいんですけど、これって、日本将棋連盟が「企業」活動類似の行動、たとえば、出版活動、将棋のプロ棋士の対局の放映権料などの徴収をして、得たお金を将棋のプロ棋士の給料として、フローにすべて分配するだけでなく、東京将棋会館と関西将棋会館を建て替えるお金もストックしておいたということなんですよね。これって、将棋のプロ棋士が新しいビルで、気持ち良く、将棋を指せるようにという要請もあるでしょうけど、将棋ファンも集える新しいビルにしたいという将棋ファンのためにという要請もあったと思うんですよね。ここでは、日本将棋連盟という公益社団法人のステイクホルダーは、①将棋のプロ棋士(→社団法人なので、四段以降のプロ棋士全員が経営者であり、株主であり、従業員ということになる。引退したら、社団法人の構成員からは外れるのだと思う)、②テレビやYouTubeやネットテレビで、プロ棋士の将棋を観るのを楽しみにしている将棋ファンが、ステイクホルダーと言っても良いと思うんですよね。日本将棋連盟は、おそらく、無借金経営だと推測されるので、債権者(主に銀行)はいないはずです。
だから、一般の普通の企業で、問題なのは、ステイクホルダーの従業員が、会社法上も、会計学上も、何の法的地位もないということなんですよね。だから、一般の普通の企業も、日本将棋連盟みたいに、従業員も社団の構成員にしてしまえばいいんですよね。従業員は、ボロクソに言われて、小規模企業の経営者の世襲のためだけか、大企業(→大企業なら福利厚生や大企業で働いているというプライドが中小企業より保てるメリットがあり、中小企業より、従業員でも十分満足が得られる)でも原始株主のために粉骨砕身に働くということになりますよね。ただ、市井(しせい)にある人も、学歴がある人から、学歴がない人まで、色々いるから、一律には同列には扱えないですよね。たとえば、国立大学を出た人(北海道大学から琉球大学まで)なら、小規模企業から、大企業に入っても、社団の構成員になれるというのなら、技術的に可能ですよね。昔に聞いた話なので、記憶も正確かどうかはわからないんですけど、フランスなんかじゃ、「国立大学以外、大学じゃない」という風潮すら、あるらしいですよね。
株式会社の制度は、経済学者からは、「資本主義、最大の発明」などと持ち上げられますが、イギリスが発祥の制度で、船が無事帰ってくるかどうかがわからなくて、投資にギャンブル性があった「胡椒貿易」の頃に出来た遺物で、中央省庁が何でも決める、現代社会には合わなくなってきています。成功して当たり前、という状況で、スタートすることがほとんどだからです。ユニクロだって、ニトリだって、そうでしょう。もう少し、知力がある人を、引き上げる会社法制が必要だと思っています。そうならないとすれば、何か戸籍上の理由があるのかもしれません。戸籍が良い人は、経営者、そうでない人は、従業員になるしかないのかもしれません。あるいは、地縁みたいなものがあって、そのグループに入れない人は、経営者になることはできなくて、従業員になるしかないということなのかもしれません。
GHQの三大改革じゃないですけど、たまに、超・法規的な改革をやらないと、社会の既得権益者が固定化(資産家・資本家・地主など)されちゃって、社会に勢いが無くなっちゃうんですよね。
江戸時代は、身分制度があって、「士農工商」だったわけですよね。
現代社会にも、身分制度は、隠れてるだけであって、「資産家・資本家・経営者・地主・原始株主」と「サラリーマン」という厳然とした身分制度が存在しているわけですよね。
「原始株主」というのは、どんな大企業にもいて、テレビ局のフジテレビにも、ラジオ局の文化放送にもNack5とかにもいるんだろうと思われます。Jリーガーの三浦和良選手のカズダンスも、会社法的な解釈をすると、最後は、必ず、どこかの原始株主にたどりついて、その原始株主に配当を出すために、カズダンスをしていることになるわけです。
ただ、中小企業などは、初代の社長って、まさに「叩き上げ」で、才能や経験や人間的な面で、魅力的な人が多いのは事実だとは思います。その仕事を上の「行政」から割り当ててもらったのは、私だという自負はあると思います。上の「行政」も、長年の訓練や経験で、人の上に立っても、恥ずかしくない、人の上に立てる、魅力的な人間をそういう中小企業の社長になるようにしているというのはあると思います。そういう小規模な会社に、いきなり来た人間が、給料以外の「残余財産」(配当や利益など)にアクセスするのは、経営者側からすると、違和感を感じるのは、もっともな思考だし、自然な考え方だと思います。誰の会社だと思ってるんだ、誰が作った会社だと思ってるんだという思考になるのも、もっともだと思います。
合理的なシステムを持っている「日本将棋連盟」を参考に、「職業分類」なども参考にしながら、日本の会社法制を再考すべきだと考えます。
日本の会社法は、民法の特別法ながら、民法の共有や組合という考え方から、随分、遠い内容になっているような気がします。商法・会社法は、本当に民法の特別法ですか。
私は、「会社のお金」と「経営者のお金」を明確に分けて、経営者の給料は、最高3000万円まで、内部留保がある場合、会社が解散したら、従業員に渡してもいいし、お金は国に返してもいいという方法が良いのではないかと思っています。会社法って、取締役とか株式発行って、登記事項で、国に報告しなくちゃいけないんですよね。それって、国にお金を返す、根拠ともなりうる、法律事象ですよね。それは、もちろん、大規模・中規模・小規模な企業を問わず、医療「法人」もです。ストックはもちろん、フローで余ったお金は、職業分類にもよるが、株主以外の各ステークホルダー(主に、従業員・消費者)に分配すべきです。
「医者なんかに、金を払ったて、女房の襟巻きになるだけだ」という名言を吐いた厚生省の事務次官もいましたが、おっしゃる通りだと思います。
単に、民間にいる人の給料を1000万・3000万円・1億円の人の3クラスに分類すれば、いいだけの話である。企業ファイナンスの観点からは、簡単な話だ。残余財産の余り(利益)は、税法か、会計法で、国に配当で返すか、従業員に分配するか、職業分類などを参考に、決めればいいだけである。
将棋の羽生善治さんだって、7冠を制覇したときの年収だって、税金を引かれて、1億円くらいじゃないでしょうか。
【関連記事】
・話は、結局、「価格決定理論」に戻るのではないか?→経営学的価格決定理論・経済学的価格決定理論・マルクス経済学的価格決定理論
「スキ」「フォロー」など、大変有難いものだと思っています。当ブログはAmazonアソシエイトに参加しており、アマゾンでのショッピングが楽しめるネットショップになっています。ぜひ、お買い物もお楽しみください。
