
【掌編小説】最後の饗宴

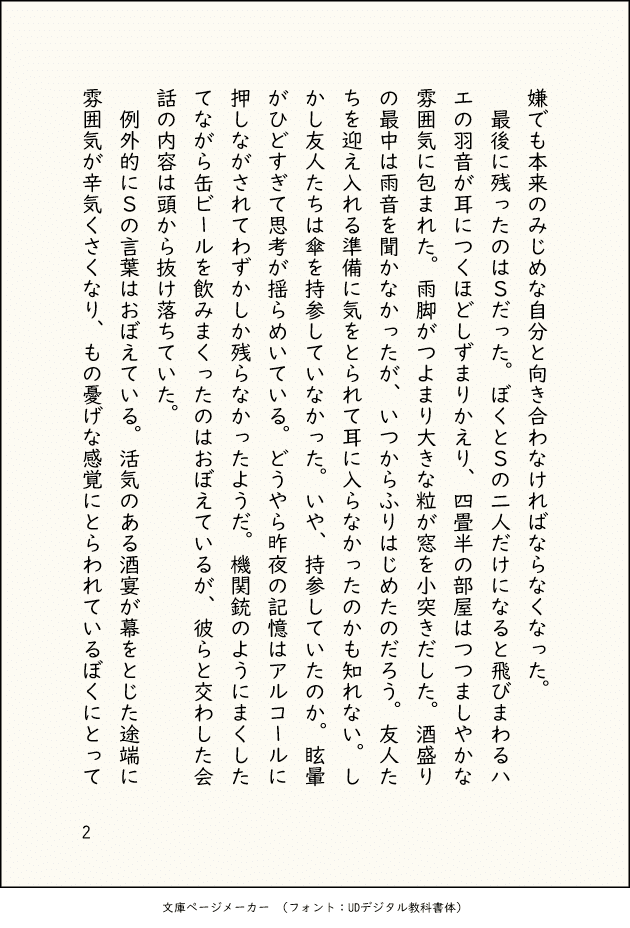






寝つけないまま夜明けをむかえようとしていた。昨夜友人たちと酒を飲み交わした名残で血液はアルコールの大河になり、はげしい動悸をうながしながら頭から爪さきまで駆けめぐっていた。脈打つたびこめかみに亀裂が走りそうになるし、胃袋をしぼられているような嘔気にも辟易させられた。われながら無謀な飲みっぷりだった。けれどもひさしぶりにどんちゃん騒ぎを楽しめたから悔いはなかった。近所迷惑もかえりみず酒を浴びるのは爽快だった。ぼくは古代ローマ人となって酒池肉林の快楽に耽り、柄にもなく長広舌をふるい饗宴をとりしきっていた。
しかし、たけなわをむかえた饗宴には終焉の道しか残されていない。視点が定まらないほど酒がまわった頃、一人がもう帰らないといけないといって退散した。間もなくもう一人も座をたち、四人でおこなわれていた酒宴はしめやかな語らいにかわった。豪奢な装飾品もご馳走も泡のように消えてなくなり、さびれたアパルトマンの一室が鮮明にあらわれる。ぼくは嫌でも本来のみじめな自分と向き合わなければならなくなった。
最後に残ったのはSだった。ぼくとSの二人だけになると飛びまわるハエの羽音が耳につくほどしずまりかえり、四畳半の部屋はつつましやかな雰囲気に包まれた。雨脚がつよまり大きな粒が窓を小突きだした。酒盛りの最中は雨音を聞かなかったが、いつからふりはじめたのだろう。友人たちを迎え入れる準備に気をとられて耳に入らなかったのかも知れない。しかし友人たちは傘を持参していなかった。いや、持参していたのか。眩暈がひどすぎて思考が揺らめいている。どうやら昨夜の記憶はアルコールに押しながされてわずかしか残らなかったようだ。機関銃のようにまくしたてながら缶ビールを飲みまくったのはおぼえているが、彼らと交わした会話の内容は頭から抜け落ちていた。
例外的にSの言葉はおぼえている。活気のある酒宴が幕をとじた途端に雰囲気が辛気くさくなり、もの憂げな感覚にとらわれているぼくにとって相手をしてくれるSの存在はありがたかった。彼は陰湿でうすぎたない部屋にぬくもりをもたらす小さな灯火だった。Sはちびりちびりと缶ビールに口をつけ、呂律がまわらなくなっているぼくの言葉に相槌を打つ。彼もおだやかな口調で近況をはなしていた。前後不覚に陥ったぼくを見つめるSの顔は妙に白みがかっていた。Sと最後に会ったのは彼が神奈川県から愛知県に引っ越すまえなので、面と向かうのはかれこれ四ヶ月ぶりだった。移住さきは観光地としても知られる知多半島だし前途洋々だと皆ではやしたて、一抹のさびしさを飲みこんだのをおぼえている。引っ越し後もぼくたちは頻繁に連絡をとり合った。SNSやメールをとおして送られてくる彼の便りには新天地に対する称賛の言葉がならべられていた。いわく海岸から見わたせる湾の景色は見事で夕日に照らされたときの美しさは息を呑むほどだと。饒舌に語るSの文章には束縛ばかりする地元のせせこましさから解放された歓喜と安堵が明瞭にあらわれていてほほえましかった。同時に小躍りするSに共感と羨望を抱いた。両親に命令されるまま惰性的に学問をおさめ、欲求不満に耐えながら腐れ金を稼ぎ、ネズミもそっぽを向く汚いアパルトマンにとじこめられる人生を送っている自分をかえりみると暗然たる気持ちになるではないか。あまつさえぼくは情緒に欠けるつまらない人間なのだ。夕焼けに染まる湾の風景に感嘆したり、海風の匂いや茜色の空に感銘を受ける心理は理解の範疇をこえていた。それだけに花鳥風月を愛でられるSの感性が羨ましかった。
酩酊したまま腕枕をし、相変わらず淡々としているSのようすを見やる。彼は帰ろうとも眠ろうともせず居座っていた。いつの間にか口をつぐみ、酒宴の残骸だらけの部屋を憂鬱そうにながめている。ゆっくりぼくに向けられたまなざしはかなしみをたたえている。
いや、ちがう! 突発的に慚愧の念がわきあがり、胸を切り裂かれるような苦痛におそわれる。ぼくはSの背後に目をそらした。カーテンの隙間から朝の光が入り、染みだらけの壁を照らしていた。ちがう。ぼくは絶叫しながら頭を何度も殴り、アルコール漬けの脳から昨夜の記憶をしぼりだした。はじめからSは一言も喋っていないし、一口もビールを飲んでいない。彼から近況を聞かされたのではなく、ぼくが彼の近況を想像したのだ。何故なら彼には口を利くことも酒を飲むこともできないからだ。
幻想に抱かれながら夜をあかしたことを自覚する。ぼくは非情な現実に耐えられなくて真夜中に酒盛りをはじめ、束の間のまぼろしに身をゆだねていたのである。しかし、どれだけ自分をごまかしても饗宴が終わるといやでも眼前の事実を受け入れなければならない。小刻みにふるえる体を起こそうとした拍子に肘が缶にあたり、イグサの散らばる畳に倒れた。ころころと転がる缶からはビール一滴こぼれなかった。タブがとじたままの缶を見ているとふたたび胸が痛み、その場にうずくまると、無駄なあがきとわかりながらも目をとじて耳をふさいだ。
先月。友人の一人が知多半島の魅力を語るSに触発され、連休中に皆で彼の新居に訪問しようと発案した。満場一致で決まったのはいうまでもない。ところが出発前日に職場で骨の折れるはなしが持ちあがり、急遽休日を返上しなければならなくなった。上司の不始末が絡んでいるだけに無視するわけにはいかず旅行は辞退を余儀なくされた。ぼくは上司への殺意を胸に秘めたままS宅に向かう友人たちを見送った。彼らは口々にはげましの言葉をかけてくれた。
また機会を作ろう。
土産は買ってくるからな。
やがて二人は海岸で撮影した画像をダイレクト・メッセージで送りつけてきた。ぼくは精一杯眉間にしわを寄せた自撮り画像に「飯の写真なんかよこしたら呪詛してやるからな」という文句を添えて返信する。二人が帰ってきたら手荒く出むかえてやろうとおもった。けれども出むかえることはなかった。彼らと語り合う機会は永遠に奪われてしまったのである。頭のなかを知人から受けた連絡がよぎる。それはSの新居で火災が発生、家は全焼してSをふくむ三人が焼死したという訃報だった。現場検証と死体検案がおこなわれた結果、泥酔して煙草による出火に気づかなかったものと判断された。あまりにも唐突な報せにぼくは眩暈をとおりこして魂が抜ける心地だった。信じられなかった。信じたくなかった。上司にはおまえは急務に命を救われたのだと説得されたが、ぼくはその言葉を絶対に受け入れようとおもわなかった。もしかしたら彼らを助けられたかも知れないし、呪うなどと縁起の悪い言葉を吐いたせいで彼らに不幸がふりかかったのかも知れない。あるいはぼくも彼らと運命をともにするべきだったのではないかともおもった。理性をなくして冷静に状況をとらえられる状態でないのは自覚していた。けれども混乱する思考を整理する術がなくて、袋小路に入ったような焦燥と恐怖にさいなまれたまま仕事も放棄してふさぎこみ、気づけば大量の缶ビールをならべて一人騒ぎだしたのであった。
ぼくは部屋中を見まわした。先刻まで畳のうえであぐらをかき、酔いつぶれているぼくを見まもっていたSをさがした。せっかく酒盛りにきてくれたのにかけるべき言葉をかけられなければ悔やんでも悔やみきれない。嗚咽を漏らしながらあおむけになって天井を見あげ、うつぶせになって畳を這いまわる。手足にぶつかった空き缶が四方八方に転がる。Sが座っていた場所に手を触れても人のぬくもりは感じられなかった。ふとぼくは一本の缶ビールに視線を向ける。それは彼が飲んでいた缶ビールだった。よく見るとタブがあけられていて、炭酸がぬけてぬるくなったビールが残っている。ビールは数口飲まれたようで、ほんのすこしだけ減っていた。
※2011年脱稿・2018年改稿
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
