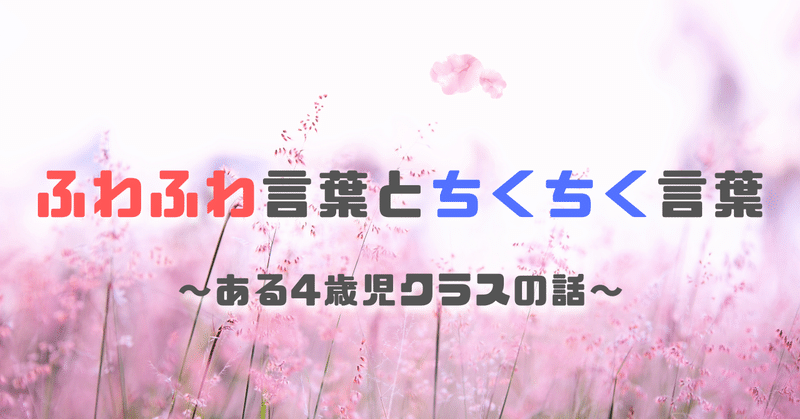
ふわふわ言葉とちくちく言葉
子どもたちの気になる言葉
あなたはお子さんの子育てしていたり、
クラスの担任をしている中で、
子どもたちの乱暴な言葉づかいが気になったりしませんか?
保育園では相手が嫌な気持ちになる言葉を
とげのある言葉としてちくちく言葉と表現していました。
こういう言葉は、大人でも直接相手に言ってしまうと
関係がぎくしゃくします。
子どもたちにも人間関係を教えるために
ちくちく言葉は言わない方がいいと伝え続けていました。
これをすると、
クラスで何が起こるか?
女子からの告げ口が増えます(笑)
「せんせーい!○○くんがバカっていったぁ!」
保育園児が使うちくちく言葉は、
大体小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんからの受け売りで、
「ばーか!」とか「うぜぇ」とか「えぐい」を
そのままマネして使ってみたいんだけ。
わかりますよ。
こんな時期は誰でも通る道なのです。
(4歳~5歳ぐらいでよくみられる)
ただ、そういう言葉を誰にも
咎められないで使い続けていては、
その子にとってよくない。
だから、クラスでお話をします。
ふわふわ言葉、ちくちく言葉集め
ちくちく言葉とは逆で、
人に言われて嬉しくなる言葉もあります。
それがふわふわ言葉です。
子どもたちに説明する時は
わかりやすくイメージできるよう、
ピンク色で雲のような形に切った紙に
いい言葉を書いて視覚化していきました。
人に言って嫌な気持ちがする言葉は、
ちくちく言葉として、
灰色など少し暗めの色でとげとげな形の紙に
言葉を書いて視覚化していきました。

上記の写真は、
実際に私が担任した4歳児のクラスで
話し合って子どもたちから出てきた言葉たちです。
こういう言葉は
クラスによって出てくるものが変わります。
集団とは偶然その場所に集まった
一人ひとりの経験の集まりなので。
出てくる言葉もまちまちでおもしろい。
子どもたちは基本的に騒がしい存在です。
周りから「うるさい」と言われることが多いです。
この話し合いでは、ふわふわ言葉として
「静かにしてね」が入ってきました。
(どうやら、子ども自身が騒がしい事を自覚している)
これをみていると、
大人側が気をつけるポイントも見えてきます。
大人たちの願いは、
ただ、子どもたちの騒がしいトーンを落としてほしいだけ。
怒る必要はありません。
事実を伝える時の伝え方や
言葉のチョイスは、なるべくふわふわで。
これを繰り返していくと、いつの間にか、
それが伝染して子どもたちに広がっていく。
優しい言葉のループが創られます。
まぁ、とはいうものの、
今の世はそんな優しい言葉づかいを
する人だらけではないのです。
子どもの世界でもそれは同じで、
女の子同士でままごとしている所に
入ってきた男の子が断られ
「やだよ」と言われてしまう。
(まぁ、その子が片づけを
さぼるからだったりするんですけど…)
別の所では、一緒に遊んで楽しくないから
「もう、いっしょにあそばない!」
とフラれてしまっている。
こんなことが続き男の子は先生の所へきます。
「せんせー、○○ちゃんがちくちくことばをいう!ダメなんだよ!」
または、男の子同士でおもちゃの取り合いになったり、
鬼ごっこで圧倒的な差をつけられ悔しすぎて
「バカ!」と叫ぶ瞬間だってあります。
その場面を見ていた近くの女の子から
「あのね、○○くんがちくちくことばの”バカ”っていったの。」
と告げ口が入りました(笑)
私は、まずはこれでいいと思います。
子どもたちが、言葉に敏感になってきているから。
やっと、言い方に気づいたという事です。
何事もまず、気づかないといけません。
日常から、言葉に対しての感度をあげます。
その後で、周りにいる大人や保育士はその次を一緒に考えます。
ちくちく言葉を言われてしまった子に
どうしてそんな状態になったか?を。
言ってしまった子と一緒に状況を考えます。
嫌だったよね、じゃあどうするといいのかな?
どういう伝え方だとよかったかな?と。
保育園はこういう毎日の連続です。
すぐには変わりません。
でも、保育ではこの積み重ねを
とっても大事にしています。
子どもの世界は何度も何度もやり直しをしながら学ぶのです。
自分の想いを言葉とリンクさせる力をつけるため。
言葉の裏にある本当の気持ち
大人だって、ちくちく言葉を言われたら
(言い方も含め)ムカつく事はあると思います。
そんな時は、まず心をおさめることが必要です。
その次に理解。
その理解のために紙に書き出して
ふわふわ言葉とちくちく言葉の視覚化です。
いつも目の前に書いてあれば意識しやすくなります。
大人だってやり直せばいいのです。
誰だって、リカバリーするチャンスはあっていいはずです。
子どもたちの言葉づかいが気になる
というお悩みはいつもでてくるもの。
正直、それを気にできる人は
家で言葉を気をつけている。
礼節を大事にしているご家庭が多いです。
だからこそ、そのお悩みがでてくる。
もうこの時点で保育士は心配していません。
保護者の方の意識があるから大丈夫。
この記事を読んでくれているあなたの家庭も大丈夫です。
本当に心配なのは、
何の気もなしにちくちく言葉が自然にでてきてしまう子たち。
そういう子たちの環境が、
他の子たちに強い影響を与えてしまうこともあります。
そこをいかに防ぐか、
ルールを守ることをどう伝えるか?
が公の教育の役目なのかなと思っていました。
きちんと叱ってくれる人が
周りにいないというのもかわいそうなのです。
僕を見てほしい!
かまってほしい!
きちんと叱ってほしい!
と心の底では思っているのかもしれません。
ちくちく言葉の裏の気持ちです。
人に言ってはいけない言葉をつい言ってしまう心の奥。
あの子たちは、寂しいだけ。
子どもたちは、
みんな愛情を求めていて、
子どもたちはみんな愛情を返してくれる存在です。
どんな形であれ、言葉は表現の1つ。
その言葉をそのまま受け取るのではなく、
その子の背景も含め見守っていく。
わかってあげることで
初めて見えてくる世界もあります。
愛情表現が苦手な親子がいて、
そっくりだな、って思うこともありました。
基本の言葉を使えるように
保育士だけはその子たちの背景を知っていても、
ただ同じクラスになっただけの
子どもたちはそんなことは知りません。
愛情不足の子どもたちがいる。
本当は全部伝えてあげられると
子どもたちがよりよい手段を思いついて、
配慮ができるようになっていいのでしょう。
クラスのメンバーにもよりますが。
守秘義務。
個人情報保護を守るため、
公にはできないこともあります。
私はいつも思っていました。
これ、邪魔だなって。
確かに、守る権利とか黙秘権とかは
大事かもしれない。
でも、本当の所を知らないと
人間関係って逆に悪くなるんじゃないかなって。
単純な私はすべて透明にすればいいって思いました。
ただ、本当に隠しておきたい人もいるのは事実。
誰だって、人に知られたくない事が1つや2つあります。
愛情不足のあの子がいる背景は、
もっともっと複雑で、
保育士が立ち入ってはいけない事もあったのです。
保育園の立場からできることは、ちっぽけ。
基本的な挨拶をしっかり使いこなせるように
してあげることぐらいなのかもしれません。
「ありがとう」「ごめんね」「いいよ」「だいすき」が
場面ごとに言えるように、
子どもと一緒に使っていくしかありません。
この言葉たちは、感謝と謝罪と許しが入っています。
人は自分のやったことを認めることが一番難しいと言われています。
だから、そのサポートをこの言葉でやっていくのです。
頑固な子はすぐ変わりません。
それでも伝え続けていく意味はあると思いました。
「ありがとう」「ごめんね」「いいよ」「だいすき」
簡単な言葉だけど、本気で言うのは難しい言葉たち。
言わされるのではなく、本気で思って発言するのは難しい言葉です。
人に心から感謝して、「ありがとう」って言えますか?
人に心から謝罪の気持ちで「ごめんね」って言えますか?
人を心から許して「いいよ」って言えますか?
人を心から想って「だいすき」って言えますか?
これができる人が世界中に溢れたら、きっと平和になります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
