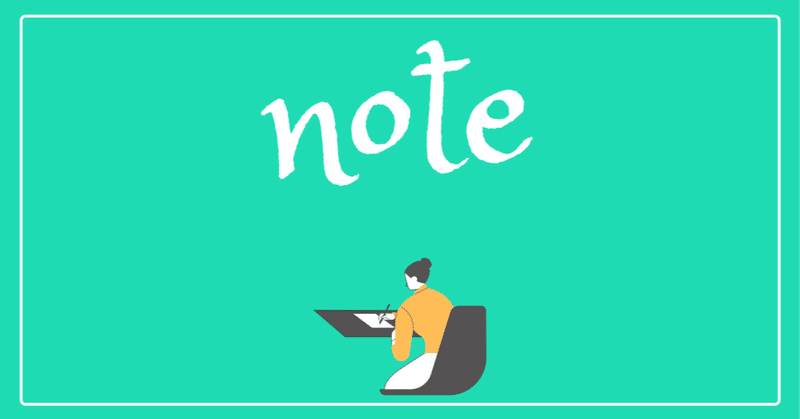
note毎日投稿をふりかえりつつ、今後のワークビジョンを考える。
初めての毎日投稿もあっという間に30日突破です😊めでたい!!
1ヶ月毎日noteを続けてみて記事への反応がどう変わったのかを考えてみます。
今日は、かなりざっくりとした、雑感です。
投稿記事を、ダッシュボードで振り返る
▶︎月間PV数ベスト5
1:大人になった卒業生のみなさんへ
2:先生が語りたい学歴の話①
3:中高教員がヨシタケシンスケの絵本に背中を押された話
4:スタンフォードが中高生に教えていること
5:あの頃の私へ、憧れのラジオやってみてるよ
▶︎月間スキ数ベスト5
1:スタンフォードが中高生に教えていること
2:自己紹介 7つの習慣と私
3:悩みフリー!アプリmuuteを激推ししたい
4:教員が学校教育について悩んでいること
5:先生が語りたい学歴の話②
ふたつのランキングに共通している記事は、次の通り!
「スタンフォードが中高生に教えていること|読書ノート」
これを元に、自分なりに振り返ってみます。
なぜこの記事が伸びたのか?ざっくばらんに考える。
▶︎スタンフォードというワードに「エビデンス臭」がする。(いい意味で)
▶︎タイトルがキャッチー。
▶︎著者が元々ヒットセラー(『スタンフォード式 生き抜く力』)なことも相まって、教育本のなかでも話題の本だから。
▶︎最近叫ばれる教育改革(思考力判断力とか主体的学習とか、ICTとか)とは少し異なり、心・身体の健康や社会を生き抜く力という視点に程よいずらしがあった?
▶︎私自身がテーマにしている、「自己肯定感」「自己受容」「生きにくいを生きやすく(自己一致、他者協働)」「教育改革」とマッチした記事だったから。
私が今後、思考テーマにしていきたいこと。(熟成下書きメモ)
▶︎はたらく大人のウェルネスに興味があり、勉強したい。
▶︎さらに子供のウェルネスとSELを、日本の教育の中で実現したい。
これらを教育の一つの軸とした時に、その手段として適切なのがPBLや探求型授業、
さらにそれを叶えるための個別到達度学習。
(基礎知識の効率的定着&主体性育成)。
▶︎以上を支えるための教員スキルがコーチング・ファシリテート・ICTデザイン。
チーム教員における心理的安全性の研究。教員のウェルネス。教員同士のSEL。
▶︎大人と子供、教員と生徒は入れ子構造になっている。
サポートは美味しいおやつとコーヒーで心をみたすことに使わせていただきます☕️
