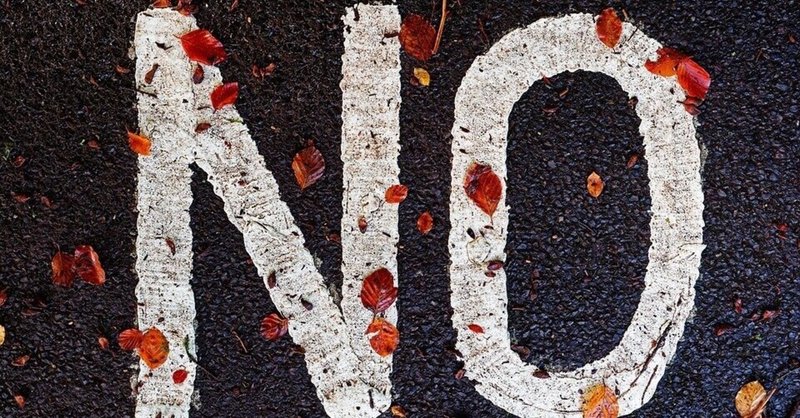
「NO‼」は最後に取っておく
ビジネスでもプライベートでも、私たちはいつだって時間に追われていますよね。
「もっと時間があったら…」
そう思うこともありますが、時間は足りないからこそ尊いのだと思います。
無限に時間があったら、人は懸命に生きることを止めてしまうのでしょう。
時間に追われたくないと思う方も多いでしょうが、私は追われるストレスが嫌いではありません。
「いつか追いかけてやる‼」
バカみたいですが、そんなことをモチベーションにしたりもします。
ということで、今回は「決断前の選択」について書いてみようと思います。
毎回恒例の私見となりますので賛否あると思いますが、よろしくお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
さて、時間に追われる私たちは、選択をしなければなりません。
膨大な情報が降り注ぐ現代は、選択の連続です。
ムダなことに費やす時間も脳のリソースもありませんから、できる限り最適な選択をしたいと思わずにはいられないでしょう。
そのために必要なのが「NO‼」と決断する勇気です。
幾つもの仕事を抱えている状態で別のやりがいのある仕事の依頼が来たとき、家族との外出予定日に友人から魅力的なお誘いを受けたとき。
私の場合は基本的に、すでに予定で埋まっている日は新たな予定をキャンセルしますが、それでも後発の予定が将来的にプラスに働くようなら選択の天秤にかけることをします。
その上で考えるのが「YES」か「NO」という決断の前に別の選択の余地がないか?ということです。
「決断前の選択」とは、この余地のことを指します。

ーーーーーーーーーー
選択において、もっとも容易なのが二者択一です。
「(゚Д゚;)…え、毎回選択に苦心してるんですけど…⁉」
世の中には「究極の選択」といって、どちらも選べないような決断を迫られる機会も確かにあります。
しかし、すでにある回答を選択するというのは、生きていく中で考えれば容易だと思うのです。
もっとも困難なのは選択肢のない選択です。
少し話が逸れますが、「クローズドクエスチョン」と「オープンクエスチョン」をご存知でしょうか?
「クローズドクエスチョン」とは、多肢選択法を用いた質問手法で、「オープンクエスチョン」とは思想や信条を語ってもらうなど、相手に論述させる手法です。
「赤と青のどちらが好きですか?」が「クローズドクエスチョン」で、「選んだ色が好きだと答えた理由は?」が「オープンクエスチョン」です。
やってみると分かりますが、「オープンクエスチョン」のほうが自分で考えなければならないので、思考にかける時間が「クローズドクエスチョン」よりもかかります。
そして、なかなか「NO‼」と言えないのも「オープンクエスチョン」の特徴です。
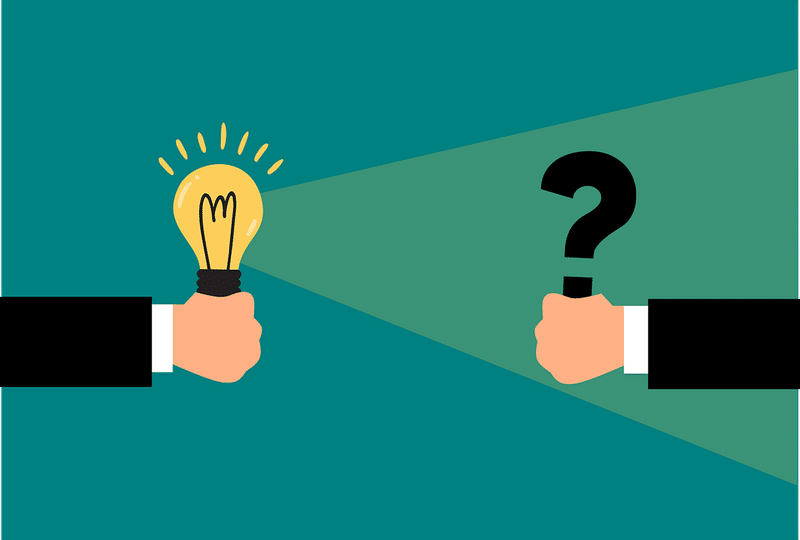
ーーーーーーーーーー
選択について話が右往左往しましたが、本題に入ります。
私たちは、選択には「解答」があると思い込んでいるケースがよくあります。
例えば、「幾つもの仕事を抱えている状態で別のやりがいのある仕事の依頼が来たとき」は、受けるか断るかの二択で選んでしまう傾向が強いのではないでしょうか?
抱えている仕事を別の人間に任せることが出来るかもしれませんし、やりがいのある仕事の依頼には期限を延ばせる猶予があるかもしれません。
「決断前の選択」
それは「交渉の余地を模索する」ということです。
個人的な見解ですが、物事を二択で考える人が増えてきているように感じます。
というよりも「グレーゾーン」を毛嫌いし過ぎなのかもしれません。
一方で「中庸」の概念を好む方もいるのですから面白いものです。
「グレーゾーン」を白か黒か決断するするのも「決断前の選択」ですし、決断せずに「これは白でも黒でもない」と捉えることもあっていいのではないでしょうか?

ーーーーーーーーーー
ときに選択をするという行為は、人に自己陶酔感を与えます。
「決断した」ということを過度に自己賞賛することは危険です。
なぜなら、人は自分が正しいと思いたい生き物なので、決断を正当化してしまえば、例え不利益を被る選択であったとしても、軌道修正が出来なくなるからです。
「決断前の選択」は「交渉の余地の模索」だけでなく「覚悟を決める」という側面もあると私は考えています。
「NO‼」は勇気のいる選択です。
しかし、大きな決断ほど「NO‼」とは言えないこともあるでしょう。
そんなときは、可能な限り決断をする前に選択の幅を検討することも必要だと思うのですが、あなたはどう感じたでしょうか?
ーーーーーーーーーー
ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
