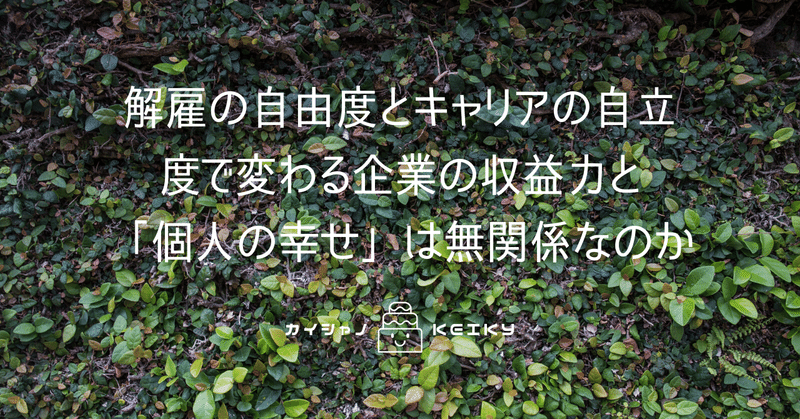
解雇の自由度とキャリアの自立度で変わる企業の収益力と”個人の幸せ”は無関係なのか
日本の雇用の在り方も徐々に変わってきている感じはあるものの、基本的に一部IT系はベンチャーを除いて雇用の流動性は担保されていない結果、大企業志向、安定志向もこの数年むしろ強まっている雰囲気がある。
ぼくの30代の世代も当然昔の高度成長期をしらない世代だし、就職氷河期で本当に大変な就活を乗り切った時代でもあって、完全に売り手市場の今の子とは就職環境が違っている。
今も50-60のオジサン世代が会社ではかなり滞留していてポストを独占しているので閉塞感がかなり強いが、あと10年もすれば一気に若返る可能性もあるので、転職しようかこのまま居続けるのかというのを悩んでいるのはぼくだけではないはず。
ぼくらが転職を考えるときに躊躇するのは、日本の独自の採用システムによるネガティブな影響を考えるからだ。
今日はそんな日本の雇用環境についてMercer Japanという人事コンサル会社の方のセミナーを聞く機会があって考えてみたので、日本の雇用システムの問題点を振り返りながら、実はいい面もあるんじゃないかということについても少し考えてみたい。
■日本の雇用の在り方は束縛と安定にある。
一言で言ってしまうと、日本の伝統的な雇用の在り方は「会社が雇用を保障する」というところにある。
最近は確かにこの部分はかなり揺らいでいる。事業を他の会社に社員ごと売却してしまったりするし、大規模リストラを大手電機メーカーや銀行がバンバン何千人単位で人を解雇している例も出てきているのでこの雇用関係は揺らぎつつある。
日本の経団連やTOYOTAなどの大企業も終身雇用は約束できないというコメントをしているくらいなので流れは変わりつつある。一方で、企業はいまだに副業を禁止していたり、転職するということは「裏切り行為」といわれている企業の方がまだまだ多いといえる。
—— 〻 ——
企業はダメな社員も含めて雇用を保障することで何を得ていたのか。それは会社都合で人を自由に操る権利を得られるということを得ていた。社員は雇用を保障してもらうかわりに「会社の命令は絶対」というルールができあがり、言い方を変えれば「自立的なキャリアをあきらめる」ということを社員も認めていたことでこの関係が成り立っていた。
異動や転勤は会社の裁量で決めることができたので企業は非常に事業展開をやりやすかった。一方で整理解雇はいまだにハードルが高く困難であることも変わっていない。会社の法的、道義的な責任が重く雇用調整をすることはとても困難なのが日本のシステムといえる。
■このシステムを成り立たせているのは一括採用モデル
こういった会社が自由に個人を動かし、個人はキャリアを会社にゆだねるという関係を可能にしていたのは新卒一括採用という仕組みだ。
新卒で学校のように社員を雇って毎年会社に送り込む。同期という仕組みで何年入社という話が常についてまわる。
こういったことがベースになってりるのは長期勤続が前提となっていて、新卒採用で就職は人生で一度きり、ジョブローテーションで転々と部署を移動して定年を迎えるという仕事の仕方を何年も日本はしてきており、いまだにほとんどの企業がそういった状況にある。
■このモデルで育まれる社員の思考回路
実際にぼくの会社もそうだが、こういった会社に勤めているとどういうことが起きるか。さすがに僕の世代は結構転職をする人も増えているし、会社に従属的な思いを抱いている人は少ないが、ちょっと上の40前半くらいはまだこのモデルのど真ん中を言っているように感じる。
冒頭記載したように、個人は会社の雇用を保障してもらうかわりに、会社のキャリアをゆだねるということで、結果として個人のキャリア意識は低下した状態が普通である。人事異動でちょっと希望を言ったりすることはあるにせよ、基本的に会社の辞令待ちをしている状態に全員がいる。
こうなると問題なのはスキルアップしようとか、スキルを新たに作り出すリスキルという意欲が沸くわけがない。ちょっとしたらまったくやったことがないところをやらされるのでキャリアがスパイラルアップしている感じはないし、何年かおきにゼロに戻っては積み上げているようなキャリアになっていく。それでもちょっと我慢すればまた別の部署に異動ということになるのでみんな我慢してしがみつくスタイルが定着していく。
そしてこういった環境にいると当然、内部の公平性が求められる。例外は許されないので飛び級はありえない。年長者が引退するまで我慢して付き合うしかないのが現状である。その代わり会社はまるで保護者のように社員を守ろうとするしケアするようなところがある。
一方で海外ではオープン採用でポストに応じて採用するので新卒で一括採用ということはしない。職種別に採用するし、異動は本人同意のもと異動をしてもらうかやめてもらったりするし、キャリアも外部でも通じるような競争力をつけることを社員は求めるし会社もそれでいいと思っている節がある。会社と個人は対等の関係を前提としている。
■日本型雇用の弊害は計数に現れる。
世界の企業の時価総額を比較すると、1989年、日本企業は上位50社には33社あったが今は1社(TOYOTA)のみ。アメリカは13社だったのが今は30社。中国は0社だったのが8社も入っている。
株価もこの1989年から2019年までの30年間で日本はたったの0.9倍、インドは12倍、アメリカ3倍、ドイツ5倍、中国5倍といった状況にある。
海外では最近は「日本人は安い」といわれていてとても重宝されている。特にアメリカでは優秀で勤勉な日本人をアメリカ人の6割の給料で雇えるということで積極的にとる会社もある。日本の労働力は安いと世界から思われているのだ。
■日米欧で異なる解雇の自由度とキャリアの自立度
国の収益力や成長力にこういった雇用形態が影響しているという調査をMercerは行っている。
アメリカは解雇の自由度が高く、キャリアの自立度も高い。その結果として大きな格差を生むという問題点こそあるが、経済成長は続いているし、一部のトップ層は比べ物にならないくらい超高収入になった。
欧州はアメリカと異なり、解雇の自由度はとても低い。フランスなど労働者に手厚すぎて事業がやりづらい国もあるしとにかく解雇をするとなると大きなコストがかかる点では日本と同じだ。
ところが、欧州はキャリアの自立度が高いということを実現している。自分からは自分の意志でやめられるし、雇用も流動的なので再就職もしやすい。どうやってこれを実現しているかというと、厳しい職種別の給料があって、コントロールされた状態を維持している、ある意味階級社会のような仕組みが出来上がっている。
—— 〻 ——
一方の日本はどうか。日本は解雇の自由度はとても低く、キャリアの自立度もとても低い状態となっている。いわゆるぶらさがり社員が多く出来上がってしまう組織であり、これは日本全体が伸びている間は全員で伸びていたので良かったが今の状況には合っていない面が毎年強くなっている気がする。
日本人は元来、欲が薄いことから物価が上がらず、賃金もあがらない。それなのに素晴らしいものに囲まれて環境もとてもきれいできちっとしているという世界でもまれにみる素晴らしい点をたくさんもっている。そんな日本人は勤勉で上がらない給料でもまじめに働くとして、バリバリ成長を遂げている会社から重宝されるようになってきている。
この違いははっきり企業の業績にも出ている。売上高営業利益率10%以上の会社の割合はアメリカが72%、次いで欧州が34%となっている。
一方の日本は9%の企業しか10%を達成していない。
日本はとにかくリスク回避型が基本にあるため大きく成長もしないしダメージも受けないというスタイルが特徴といっていい。
■日本企業の特徴と個人の幸せは無関係。
欧米の会社より利益率が低かったり、給料が低いということに対して負けていると思う場合もあるし、あまり関係ないと思うかもしれない。
特に日本で生活をしているうえではきれいな環境で住めるし、あまりほしいものもないし便利なので不自由はないということで個人は十分に幸せにはなれる。
そんな日本を好きになってくれてきてくれる海外の人もたくさんいて、日本の良さというのは世界に通用している。
確かに株式投資をしようと思ったら日本の企業に投資しようかと思うと微妙かもしれない。テクノロジーはいまや中国とアメリカの一騎打ちであり、日本は基本的にただの部材のサプライヤーにありつつある。世界のテクノロジーは今はカルフォルニアか中国のシンセンといわれているくらいだ。株価の30年間の伸び率を見ても、企業の収益率をみても伸びる気配がないので投資をするなら日本は避けるかもしれない。
でもそれは株の世界であって、ぼくらの生活は自分たちで豊かにしていくkとができるとぼくは信じている。海外生活をしていたこともあってぼくは本当に日本が好きだと思える。だから外資よりは日本企業に頑張ってもらいたいとおもって働いているのだが、企業側の社員への態度が変わってきたのでいろいろと考えるようにもなった。
少なくともキャリアの自立度はあげていかないといけないと思って入社以来ずっと勉強は欠かさずやって社外で通用するスキルを上げることは一応やってきたつもりだ。
基本的には日本の企業で頑張っていきたいが、企業が社員を切りすてるとき、ぼくは少なくとも他の選択肢をもてるようにしたいと思いつつ、きっとそのまま働くような気がしなくはない。
まあ何とかなるさ。
keiky.
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
