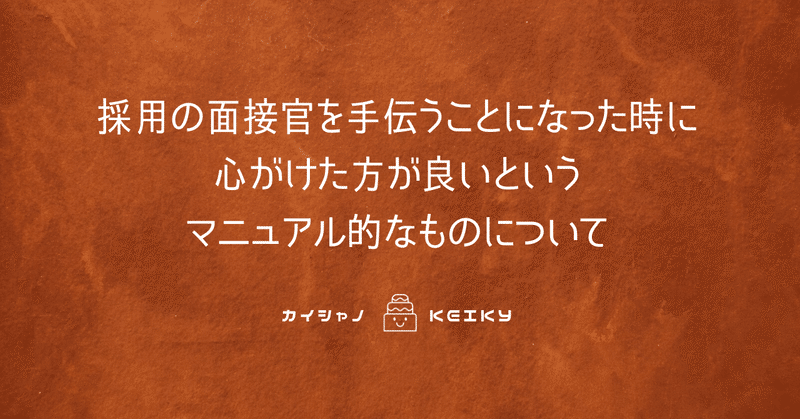
採用の面接官を手伝うことになった時に心がけた方が良いというマニュアル的なものについて
ときどき人事部に付き合って新卒の採用面接をやることがある人も多いかもしれない。
そんなぼくも時々やることがあるが、毎回まったく慣れずに緊張するものだ。一日中いろんな学生に会うことになるがきっと笑顔が引きつっているに違いない。
そして毎回とても疲れる。もっと気楽に適当にやれればいいのだが、本人の人生がかかってるし親御さんの顔が浮かんでしまったり、それぞれ色んな事情かかえてるんだろうと思ったりしてしまう。
なるべくいいところを見たいと思うし、ぼくが人を評価できるほどの人間なのか?とか考えてしまうこともある。性格的に向いていないかすごく向いているのかどっちなんだろうか。
人事部門はサバサバしたもんで手慣れているのでこんなことは思ったりはしないだろう。まさに回転寿司チェーンといった感じだろうか。
そういった対応に慣れていないぼくとしては毎回全部の人に向き合って考えるような作業が続くとヘロヘロになる。
こちらは普段は会社のおじさんとしか付き合わない。なので若い学生に慣れてないし、面接するこっちの方が緊張したりするのだ。
だいたいどの会社にも人事部門には面接対応マニュアルというものがあって毎回やる前にレクチャーをしてくれる。例えば聞くべき質問として志望動機や、他にどこ受けてるとか、優先度とかは聞くことリストになっている。
そんなレクチャーの中でも面接官をがもつべき心構えについて指導があり一般的なものらしい。少し考えさせられたのでポイントをシェアしてみたい。
1)取引先と思って笑顔であいさつ、リラックスの場をつくる
SNSが発達した現代ではお客様と思って接して欲しいと言われる。面接官一人の対応で影響が大きいらしいというような話を聞いたが後半はあまり覚えていない。
まあ確かに今は売り手市場なので来てくれてありがとうって感じというのはわかる。大手や一流企業に優秀な人をまずもっていかれるから仕方がないのだろう。
この間もまだエンジンがかかる前の最初の子の面接で「お忙しいところお越しいただきありがとうございます」といったぼくの顔は引きつった笑いになっていたことだろう(その後慣れて徐々にナチュラルになったと思うが)。
2)組織の活動より本人の行動を確認する。
学生に力を入れて取り組んだことや、成果をあげた体験について聞いたときに組織としても成果しか言わない子がいるので、その中でその子がなにをしたかを掘り出せということだ。
まあ確かにこれは大事かもしれない。学生の経験なんてたかが知れていて、バイトか学業かサークルや部活か旅行くらいしかアピール点はないのだから学生も個性を出そうと大変だと正直思う。
個人的には特別なことは別にしている必要はないしコミュニケーションがある程度できればそれでいいという考えだが、一応本人がどのような役割でどのように活動・行動して周囲に影響を与えたかという点や、その人の活動が成果にどう貢献したのかを確認してほしいということだった。
3)過去の「行動」と「内面」を捉え、「再現性」を確認する
表現が若干ディープで一瞬チーンと時間が飛んだ。
ようは学生の過去の行動とその行動をとった背景にある考え方、思考、 価値観、過去の体験などの内面を引き出すことで、入社後に同じ行動ができるかということをみたいらしい。
頑張ったエピソードとか面接で聞くときになにをどう頑張ったかということを聞きながら、その人が責任感があるとか行動力があるとか、分析力があるとか、そういった個性を引き出せば良いんだなとぼくなりに解釈した。
まあこれは気をつけるようにしよう。
4)先入観や思い込みにとらわれない。
これは割とできるかもしれない。海外経験があったので多様性を認めてなんでもありな感覚で人と接する感覚は慣れているし、いろんな人種の中で揉まれたので人に対して思い込みを持たないクセはついている。
よく聞くと人によっては出身大学とか、理解が文系かとか、スポーツやってたかとかそういったバイアスをかけて面接わする人が結構いるので色眼鏡で見ないように一応毎回依頼しているらしい。人事も大変だ。
他には例えばサークルで部長をやってました!というアピールに対してリーダーが複数いる場合もあるとか、実は3人しかいない部だったり、活動が年に数回もしれないとか、アピールを冷静に仕分けしていく感覚でみてほしいということだ。
ぼくからしたら学生にもとめすぎな気はする。まぁ面接にくる子も少ない経験からなんとか捻り出して説明をしているのでぼくはあまりここは攻めてもしょうがないと思ってスルー気味で対応しよう。
5)クローズド質問とオープン質問を活用する
これは交渉術として多用するので人事がいいたいことはよくわかる。相手に対してYES/NOで回答できる質問をクローズ質問といって、回答する際に 具体的な言葉を重ねる必要がある質問をオープン質問といっている。特にwhy?的な質問や説明を求めるような質問がオープン質問の代表格だ。
オープンばっかりだと学生も緊張して答えづらいらしいので最初はクローズ質問をしながら徐々にオープン質問を増やして「なぜ〇〇の仕事を選んだのですか」
「部活で一番大変だったエピソードを教えてください」など説明をさせる質問をしていくといい。
オープン質問は論理構成力や、本人がどういう思考をしているかより実像が明確になるので大切な質問だと思っている。理系の子に多いのはYESとNO以外あまりしゃべってくれない場合もあるのでなんとかその子のいいところは引き出そうと心がけたい。
■ 心がけつつも、、、
こういった指導は受けつつも、最後はフィーリングでいいですよと言われたのでホッとしたが、ぼくとしては会社の度量や受け皿次第ではないかと感じる。
何より人事が採用する本人の良さの基準と事業の現場の良さは異なっている場合が多い。
最終面接などに事業の方も出ることはあるがかなり上層部だったりすると当然変わり種は受け付けず、正統派な優秀で大人しいようなタイプに傾斜する傾向が他の会社でも多いように聞く。
ぼくとしてはなるべく今までにないタイプ、うまく指導して教育すれば伸びるタイプ、ちょっと話し下手でも光るものがあるタイプ、そんな子をあげるようにしているが、人事受けはあまりよくなかったりする。
—— 〻 ——
変わった視点で採用したいから色々な部署に一次面接を依頼しているはずなのに評価軸はあまり変わらないのだなぁと感じる。
ぼくは人間の能力なんて一部の特別優秀な人を除いてどんぐりの背比べだと思っているので基本よっぽどダメだと思わない限りあげるようにしている。
この子はこんな環境だったら活躍してくれるだろうなということも含めて申し送り事項としてびっしりコメントを書くようにしている。どんな子だって活かし方次第なのだ。うちに来たらどんな活躍をしてもらえるのかを考えるとワクワクする。
企業の採用側も自分たちを棚上げして学生を単に比較して優秀かどうかを見ずに、どんなキャリアを用意してあげられるかという意思を持ってとることと、とった人を責任持って育てることを心がけなければと感じるのである。
まぁそれにしても毎回疲れちゃってる時点で人を面接するのはぼくには向いてないなぁ。
keiky.
[参考サイト]
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
