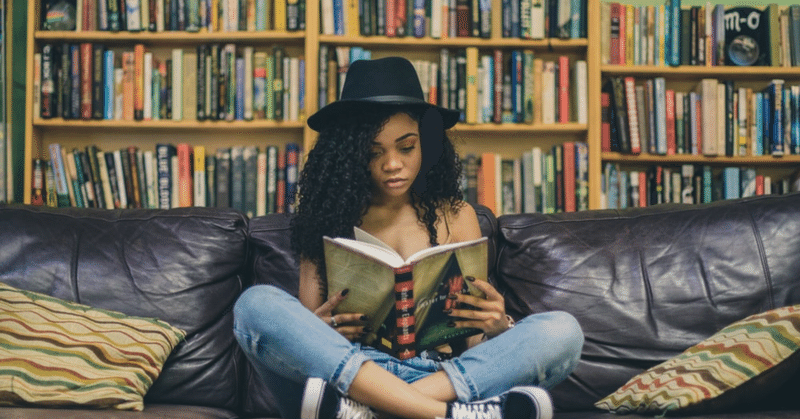
1年間読書を続けて思った、読書の贅沢さについて
こんにちは、カズです^ ^
僕は去年の4月頃から毎日読書をするようになったのですが、これは「習慣化するため」というよりも小さい頃から"単に本が好き"だった僕が今まで以上に本を読むようになったという感じでした。
そこで今でも本を読むたびに思う、"幸せ感につながりそうなポイント"について軽くお話ししていこうと思います。
なのでこの短い記事を見終わった後に今までより読書の時間が贅沢なものになっていたら幸せです。
ぜひご閲覧ください。
本を読むことは贅沢
「読書って贅沢だなあ」って初めて思ったのは去年の夏頃、岡本太郎さんの著書にはまっている頃でした。
当時僕が当時読んでいた彼の本のほとんどは"語り口調"で、
「結局ね、〇〇というのは〇〇ということなんだよ。」みたいな優しい文ばかりでした。
そしてそんな文ばかりを読んでいると、途中から目の前で岡本太郎本人が自分に話しかけているような感覚になっていくわけです。
その時に、「こんな話は岡本太郎と飲みに行かなきゃ聞けない話だったな」ってふと思ったのです。
というのも、著書の中には様々な本やメディアで大々的に主張している彼の考え以外にも、彼の幼い頃の話や、孤独の中で考えたことをはじめ、若き日のパリ留学の思い出話なども細かく聞くことができたからで、
もしこの世界に本がなかったら、本という概念すらなかったら、こんな話は直接本人に会って親密にならないと聞けなかったなあと思うわけです。
これはもちろんどの著者にもあてはまって、すでに亡くなっている方の著書ならいっそう「本というものがあってよかった」と心から思えるでしょう。
他にも、古代ギリシャ哲学者たちの著書を読んでいるとき、「この文は日本からはるか遠くの地ではるか昔に書かれたものだ」と思いながら読むだけでとても贅沢な気持ちになり、文と向き合う真剣さも変わります。
ましてや著者側も2021年日本の令和時代に大学3年に読まれるとは書いている時に思っていなかったのではないかと思って、古い本を読むことのありがたみや凄さを感じることもよくあります。
とにかく、時も国も超えて、偉人や自分が気になっている人に目の前で話を聞かせてもらえるのが「本」の良さだと思うわけです。
そしてそれはとても贅沢なことだなと感じます。
小説は別世界での思い出作り
次は小説に絞ってお話をしていきます。
僕は小学校や中学校で読んでいた小説の世界を今でもすぐ思い出せます。「話の流れ」ではなく、「その小説の世界」を思い出すことができるのが大事なところなのです。
つまり、小説を読みながら頭で思い浮かべた世界はまるで別世界で経験した思い出のように簡単に消えることはなくて、まるで自分が本当にその世界を見たかのような記憶の濃さで頭に残るわけです。
例として僕は中学一年の時に授業で何をやっていたか、部活でどんな練習をしていたかなどは全く思い出せないのに、当時読んでいた藤沢周平さんの『蟬しぐれ』の世界の、「主人公が住んでいた古風な家の雰囲気」や、「田んぼ道の色」、「ライバルの表情」や「彼らが着ていた服」などは簡単に思い出すことができるのです。
ここに小説の魅力が詰まっていると僕は思います。
そしてこんな経験が小説以外でできるのかというと、なかなかできないと僕は思います。
映画であれば世界の雰囲気の正解は目で見えるため想像する必要はなく、現実世界を生きるだけでも小説のように全体に色をつけるような想像はできません。
なので小説の中で、作者の言葉選びの影響と自分の想像力を掛け合わせて自分だけの世界を作ることこそ何より素敵で幸せな行為なのではないかと思うわけです。
加えてこういった時間を過ごすことで普段の想像力も増すように僕は思ったので、頭が凝り固まらないようにするにも小説を読むのは良いと思います。
おわりに
最後まで読んでくださってありがとうございました!
スキ、コメント、フォロー(フォロバ100%)の方もよろしくお願いします^ ^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
