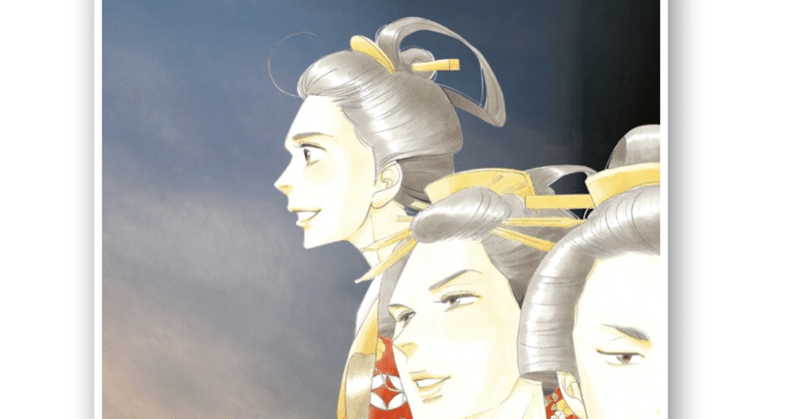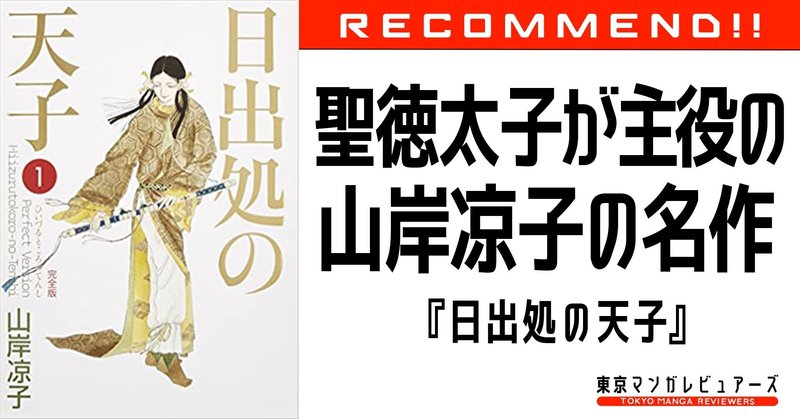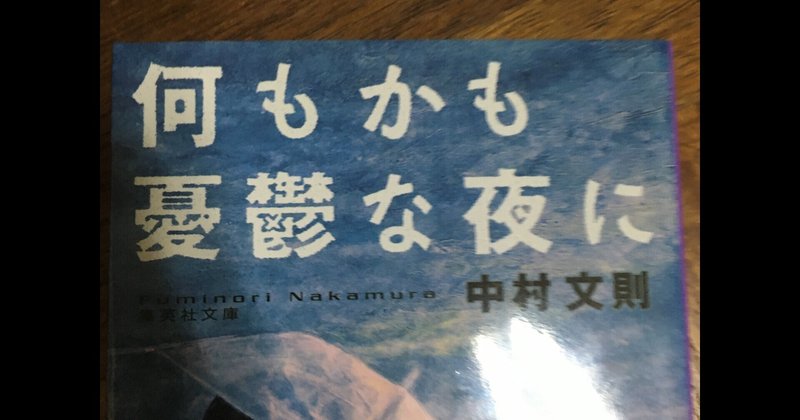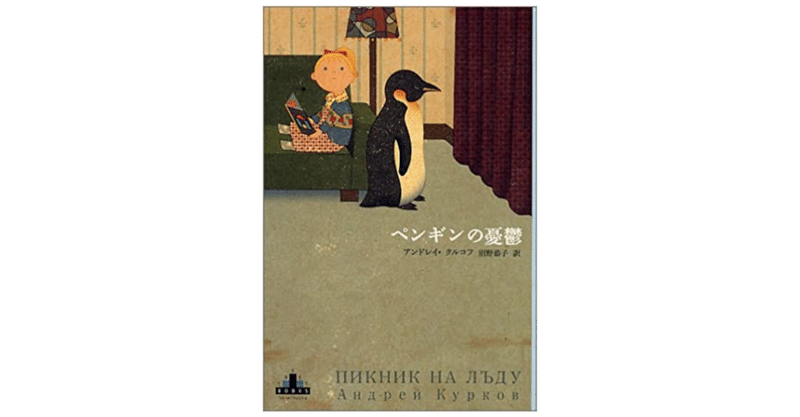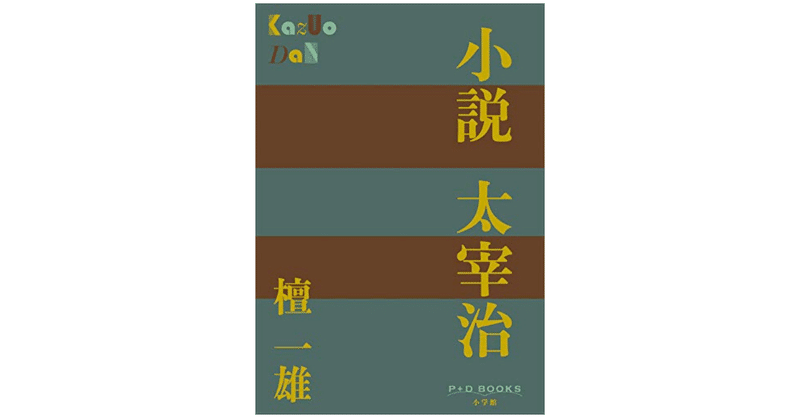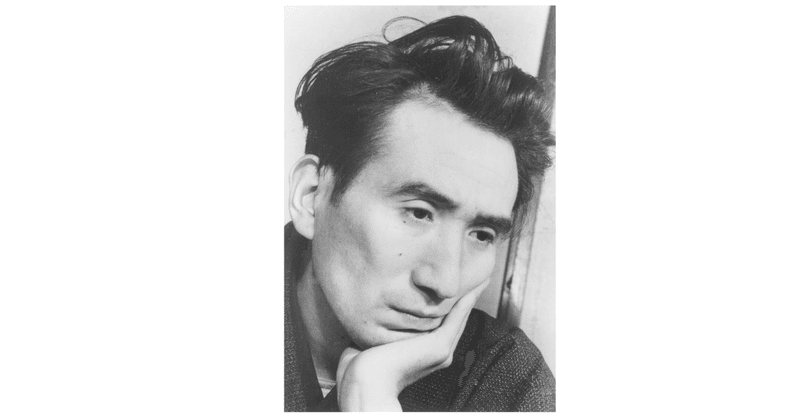#読書感想文
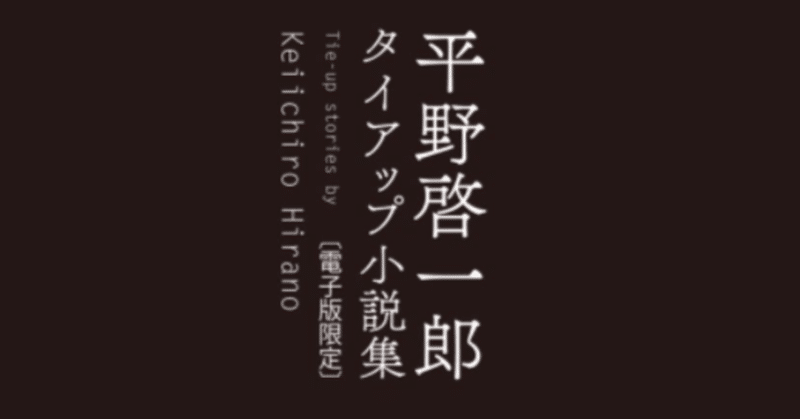
短編集の感想と… : 平野啓一郎 (著)『タイアップ小説集』 / 原田 宗典 (著)『どこにもない短編集』/ 「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。
原田 宗典 (著) 「人の短編集」 kaka.さんの投稿を読んでから直ぐ、原田 宗典 (著)「人の短編集」は一通り読み終わる。kaka.さんがお勧めしたお話はジワっときて良かったし、最初の数話は『なるほど』と思ったのですが、それ以降のお話は流れを追うだけになってしまった。読み物には書き手の書き方により、好き好きが出るのだなと改めて感じた次第。 『人の短編集』は、Amazonであまりコメントもなく、短編集で一番評価の多い『どこにもない短編集』も読んでみた。 うーん、何でだ