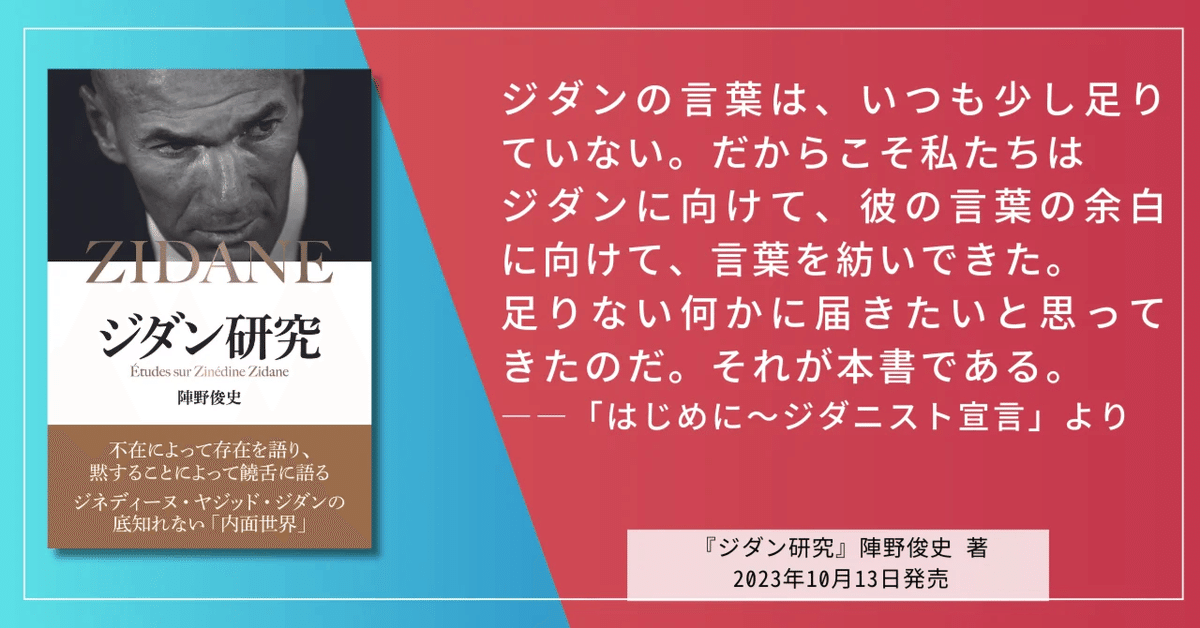
#全文公開 「はじめに~ジダニスト宣言」『ジダン研究』
ジネディーヌ・ヤジッド・ジダンの
底知れない「内面世界」
おかげさまでご好評いただいている
『ジダン研究』(陣野俊史 著)
が10月13日に発売となりました!
一部では「鈍器本」とも話題になっている通り816頁の大ボリュームを費やしたジネディーヌ・ジダンの研究書です。
本日は著者 陣野俊史 氏による「はじめに~ジダニスト宣言」を全文公開!
はじめに~ジダニスト宣言
本書は、ジネディーヌ・ジダンの研究書である。
ジダンは、一九七二年に南フランスのマルセイユで生まれ、ASカンヌでプロデビューを飾り、ジロンダン・ド・ボルドー、ユヴェントスFC、レアル・マドリードCFで活躍したサッカー選手である。フランス代表としても九四年から二〇〇六年までチームを牽引した。また、現役引退後は、一六年以後、二度にわたってレアルの監督を務めた。
私はこのけっして薄くはない書物のなかで、ジダンを複数の文化の交錯する身体として捉えている。サッカー選手としてはもちろんだが、指導者として、あるいは、ルーツであるカビリー文化の継承者として、アルジェリア系選手の第三世代として、そしてフランスサッカーの体現者として、彼を捉えたいと念願した。そうすることでしか彼の全体を捉えたことにならないからだと考えている。
だが、いっぽうでジダンほど寡黙な人はいない。いや、寡黙という言葉は適切ではない。記者会見の席などでジダンは想像以上に口を開く。ただ、彼の語る言葉は、彼に対して私たちが期待する以上であったことはほぼない。すなわち、ジダンの言葉は、いつも少し足りていない。だからこそ私たちはジダンに向けて、彼の言葉の余白に向けて、言葉を紡いできた。足りない何かに届きたいと思ってきたのだ。それが本書である。
***
別に隠しているわけではないが、私はジダニストである。日本語で言えば、ジダン主義者だ。同じような言葉に、「ジズーマニア」(ジズーは彼の愛称)とか「ジダン信奉者」といった語がある(いずれもフランス語では一単語である)。「ジズーマニア」はジダンに関連するグッズを集めたり、ユニフォームをコレクションしたり、練習を近くから眺めたりする人々のこと。そして「ジダン信奉者」とは、ジダンの行動や指導をひたすら賛美する人々のこと。私はマニアでも信奉者でもない。単なるジダン主義者だ。では、ジダニストとは誰か。
ジダンのプレーや言葉を、自分の生きる信条としてきた者のことである。誰にもできないようなボレーを利き足ではないほうの足で決めてみせたり、背後から供給されたボールを右足の甲で数回撫でながら、相手ゴール前に侵入し、GKをかわしてゴール右隅に流し込んだり、そんなプレーを記憶しながら(幾度も反芻しながら)生きてきた者のことである。ヘッドバットの痛みを自身の精神の痛苦として経験した者のことである。彼のプレーに勇気づけられてきた者という、シンプルな言い方もできる。
ならば、別段、ジダンのことをいまさら語る必要などないのではないか? という疑念はあるだろう。現役引退してもうすぐ二〇年である。選手時代を知らない人も増えている。ジダン? ああ、レアル・マドリードの監督だね、という若者たちに向けて何か書き残しておきたい気持ちなどさらさらない。サッカー選手としてのジダンならば、いまになって語る必要はない。動画は溢れている。
だが、事情が変わった。ジネディーヌの父であるスマイル・ジダンが自伝を公刊したことがきっかけである。二〇一七年のことだ。スマイルは独自の朴訥とした語り口で、アルジェリアのカビリー地方での少年時代を振り返り、ミドルティーンで働き口を求めてフランスへ渡り、パリで辛酸を舐め、マルセイユで偶然のようにして家族を持ち、その家庭でカビリーの文化を守ってきたことを書いている。子育てのこと、居を定めたマルセイユのカステラーヌ地区のこと、フランスでカビリーの生活スタイルを守る意味などについて、抑えた筆致で述べる。ジネディーヌの選手としての成功の裏側が、父親の自伝から見えるのである。ジネディーヌがフランス人であると同時にカビリー人である、ということは、いったいどういう事態なのか。父親の言葉から跡づけてみたいと思った。
各章の内容を述べる。基本的には時系列にしたがって書いている。
第一章の「家族の肖像」は、ジネディーヌの父親であるスマイルの自伝の記述に多くを負いながら、カビリーの人スマイルと妻マリカがどのようにして、フランスのマルセイユに居を定め、五人の子どもを育て、ジネディーヌがプロサッカー選手として成長していったかに焦点を当てている。時代としては、二〇〇一年三月の日本代表とフランス代表の試合まで、を第一章の範囲とする。一九九八年のフランス・ワールドカップ優勝や、二〇〇〇年のEURO優勝を含む、選手としての絶頂期までの記述である。
第二章「フランス・カビリー・アルジェリア」では、フランス代表とアルジェリア代表の試合(二〇〇一年一〇月六日)からスタートし、その試合がどれほど特別な意味を持っていたかを述べたうえで、フランスとアルジェリアのサッカー史を紐解く。フランスリーグで活躍していたアルジェリア系の名選手たちが、こぞって祖国独立のためのチームに参加し、世界を驚かせた事件(一九五八年)から両国のサッカー史を眺めれば、ジダンは第三世代に属している。アルジェリア系フランス人のサッカー選手の歴史のなかにジダンを位置づける。
第三章「ヘッドバットの解釈学」では、二〇〇六年ドイツ・ワールドカップ決勝での、ジダンのヘッドバット(以下、「頭突き」という呼称はとっていない)がどれほどの衝撃であり、以後、膨大な学術的研究対象になっているか、を示している。メディア論や社会学、キリスト教学、イスラム学、心理学、そして文学など諸々の領域を横断するようにして、彼のヘッドバットは語られ、研究されている。遠慮なく言えば、退屈な学問的解釈もある。ここで紹介している様々な解釈には、読者を眠りへと誘うものも含まれている。読んでいて眠くなるのは当然なのである。そうした生理的反応を含め、ヘッドバットの解釈学は分厚い。そのことを示したい。
第四章「監督として」では、二〇一六年にレアル・マドリードの監督に就任したジダンの、それ以後の監督業のなかで、何が彼の特徴なのか、そして彼の指導者としてのどんな点が、主にスペインで評価されているのか、を示す。
書法として方針は一つ。複数の声を導くことである。すでに述べたように、ジダンの言葉は多くない。彼の声を補うために、チームメイト(一九九八年にワールドカップ優勝をもたらした選手たちのかなりの数が「自伝」を上梓している)や監督、サッカージャーナリストの文章や書物から多く引用している。各新聞に掲載された市民の声や、識者の発言も可能な限り目を通した。彼ら/彼女らの声の抜粋だけを紹介するのでは歪曲の可能性があるので、できる限り長めに引用した。これは本書のような単行本でなければできないことと考えている。
ジダンをめぐる研究史についても書いておく。ジダン関連の書籍が最初に出たのは、一九九八年のワールドカップでフランスが優勝した直後である。盟友のクリストフ・デュガリーとの共著(未邦訳、九八年)や、小説家ダン・フランクとの共著(原著九九年、日本語訳『ジダン 勝利への意思表示』、二〇〇〇年)がある。フランス優勝の立役者を讃える第一次ブームと言える。
第二次ブームが起きたのは、二〇〇六年のドイツ・ワールドカップ決勝のあと、つまり引退後のことである。評伝が三冊、ヘッドバット事件を中心としたジダン論が五冊、上梓されている(評伝はいずれも日本語訳がある)。文学研究者が書いた、ジダン「理論」を文学作品の読解に応用しようとする変わり種(一四年)を除けば、〇六年から〇八年の間に、ほぼ議論は出尽くした感があった。
だが、前述のとおり、二〇一七年に実父スマイルの自伝『石の道の上で』が刊行されてから、再びジダン関連本は活況を呈している。ジダンが監督として現場に復帰したことも一因だろう。監督論が一冊(一八年)、フランスのスポーツ紙記者によるジダン論が一冊(一九年)、女性の心理学者がジダンの精神を分析した書物が一冊(二〇年)、刊行されている。
つまり三つの大きな波が、ジダンをめぐってこれまで起きたことになる。
右の波は単行本だけではない。発表される論文も、ほぼ三つの波に沿った形で公開されている。その数は、新聞や雑誌に掲載された記事を含めれば数万にのぼる。単行本はすべて読んだ。もちろんすべてではないが、代表的と思われる論文に可能な限り目を通した(英語とフランス語と日本語に限られる。仕方ないことだが、スペイン語のできない身を嘆いた。ドイツ語でジダンをめぐる小説が刊行されていることを確認して入手したが、読解を断念したこともある)。本書にはそのすべてを投入した。読んで知り得たことを可能な限りアウトプットするうちに、右の研究史から立ち上がる書物は厚みを増していった。本書において、二〇二三年現在の、ジダン研究の全体が見渡せるはずである。
したがってこれは、ジダン論でもなければ、ジダン伝でもない(ジダン論やジダン伝のほうがタイトルとしてリズミックで収まりがいいことも重々承知している)。あるいは、ジダンをめぐる小説でもない(フィクションを意図して導入した箇所があることは事実として認める)。ジダンを「研究」するという、選択肢のなかでもっとも地味な作業の結果にすぎない。ただ、「研究」である以上、私の個人的な意見はできる限り制限している。事実を提示し、それをめぐってどのような議論が起こり、決着したのか――まずそれを述べている。そのうえで幾分かの解釈を付す。
あらかじめ述べておきたい点が二つある。一つは表記について。ジダンは、Zinédine Zidaneと書くが、カタカナでできるだけこれを忠実に読もうとすれば、「ズィネディヌ・ズィダヌ」ではないか。異論もあろうが、しかし、いまさら独善的にこの表記をとるわけにもいかない。「ジダン」という呼び方は広く浸透している。「ジダヌ」も考えたが、やめた。理由は、日本語の音の表記は原語の響きとは異なっているかもしれないが、フランスからこんなに離れた国で、ずっと彼は「ジダン」として親しまれてきた。その事実には誇りを持っていいのではないか、と考えたからだ。アジアの東の端で、彼のことを考え続けてきたことの表白として、あえて「ジダン」のままでいようとも思った。事実、本書は、フランスやアルジェリアやスペインではなく、日本に住んでいる者にしか書けない部分がある。小さな自負でもある。
もう一つ。一人称について。日本語の一人称は難しい。おそらく翻訳に際して使い分けることが常道だろう。人物のキャラクターに応じて、「私」「俺」「私」「わたし」あるいは「あたし」など、使い分けていくことが必要とされているのかもしれない。にもかかわらず本書では、一人称は「私」で統一している。ジダンを含め、一般的に言って、サッカー選手の粗野を表現すべく「俺」や「オレ」が多用されてきたと思うが、その事実にはずっと違和感があった。どうしてその人物のことをよく知りもしないのに、語り口に粗野が紛れ込むような仕掛けをするのか? 郊外の貧困層の出身だからか? スポーツ選手は、男は皆「俺」で、女は「あたし」でいいのか? そんな馬鹿なことがあるものかと思っている。だから、本書では原則としてすべて「私」にしている。逆に違和感を覚える場面もあるかもしれない。だが、監督たちの語りの一人称を「私」にしているのに、クロード・マケレレやリリアン・テュラムの一人称を「俺」にする根拠を、私は持っていない。
私のジダニスト宣言は、以上である。
陣野俊史
書誌情報
カンゼンWEBショップでも予約受付中です(¥3000以上のお買い物で送料無料)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
