
「照子浄頗梨」①江戸の黄表紙、地獄巡りの顛末記
「地獄一面照子浄頗梨」(1790刊)は山東京伝(1761~1816)作画の黄表紙。上中下3巻。
地獄の浄頗梨の鏡には、生前の行為が全て映し出されることを題名としている。
黄表紙は大人の絵本として江戸時代に描かれた。絵には有名な浮世絵師もたくさん参加している。
作者、京伝は、江戸時代後半を代表する作家であり、浮世絵師北尾政演としても知られている。作家であり画家でもあった。本作品は、京伝が文も絵もつくっている。
黄表紙は、現代のマンガと同じく、絵も文もできなければならない。絵を浮世絵師に頼むにしても、構図の指示を下絵で出さねばならない。
その作者による、地獄巡りのお笑い道中。
作品の挿絵の一部をアレンジし、文章もわかりにくい過去のものは現代風に意訳して紹介する。
上巻
口上

東西東西、これより世のお子様方へ、ずらり口上を申し上げます。年々草双紙(絵本)をご覧にいれますに、評判もよろしく、ありがとうございます。さて、何かおもしろいネタはないかとさがしておれば、ふと思いつき、昔、小野篁が地獄へ行き来された出来事を、わかりやすくご覧にいれます。筆もまわらぬ作品ゆえ、まだるっこしくお思いでしょうが、まことにお子様方の読み物ですので、大人の方々は長い目でご覧ください。とかく理屈臭いことではなく、ありえない話の無駄話にて、筆の行方もわからぬ戯れで、ひとえに子どもだましのお笑い草でございます。そのための口上、左様に。
小野篁伝
小野篁は平安時代の貴族、小野岑守の長男なり。参議の職についたこともあり、野相公とも呼ばれる。父母に孝行をつくし、身の丈は六尺二寸(186㎝くらい)、物事をよく知っており、習字もうまい。地獄とこの世の行き来をした。ある書に曰く、破軍星(北斗七星の七番目の星)の化身なりと。
一

昔々、小野篁と申す方は、博学秀才で世に知られ、ことに仁徳があることを、地獄の主人閻魔大王、聞きおよび、これは会ってみたいと思い、二人の神を使者にして、迎えければ、篁も、「冥途見物もおもしろかろう」と承知する。
使者「そもそもこれは、あなたが島流しにあったときの使者ではなく(篁は隠岐島に島流しになり、その後許された)、あんまり楽しくない地獄の使者ゆえ、使者一人や二人では申し訳なく、地獄の十王がそろって迎えにまいりましたが、残りの八王は表に待たせております」
篁「地獄といえばちょっと気がすすまないが、地獄めぐりの温泉の旅と思えばどうってことない。俺はまた、この話は夢オチの焼き直しかと思ったぜ」
二

かくして篁は、なるほど地獄見物も新しい黄表紙の趣向なり、昔、朝比奈三郎が地獄巡りをしたと伝えられるが、そのように八大地獄、その中の十六地獄、計百三十六地獄を巡らんと、江ノ島や鎌倉まで行く感じで、何の支度もなく、地獄の十王に誘われ、死出の旅路ではなく、生出の旅に出発進行。
この話を聞いた罪人たちは、篁の仁徳を慕い、皆々六道の辻まで迎えに出る。
死出の旅路は、一里塚が門松なり。これを越せば、だんだん冥途へ近づく。
篁「話に聞くのとは違い、なかなかよい景色じゃ。死んでから行くのじゃなく、生きて行くのはのんびりしたもんだ」
男「道中ご不便だろうと、箸を入れる箸紙をお使いください」
篁「額につけた三角は、サポーターみたいだなあ」
使者「この天気では、三途の川もおだやかでしょう。お昼ご飯は三途の川のお婆の店にいたしましょう」
駕籠屋「ハイハイ」
三

篁は、ほどなく地獄に至り、閻魔王にも対面し、いろいろもてなしにあずかるが、ある日、閻魔王、昼飯を食うとて席を立てば、篁はひょうきん者ゆえ、閻魔王の席に座り、閻魔王の身振りや声をまねて、罪人の裁判をして、周りの皆を笑わせたまう。
篁「鬼というものは、ツノが二本であるはずが、二本差しの武士は野暮だといって一本で歩くそうだな。」
鬼「篁様は、だいぶ閻魔様慣れしていなさる」
鬼「通人の閻魔様ってとこだ」
四
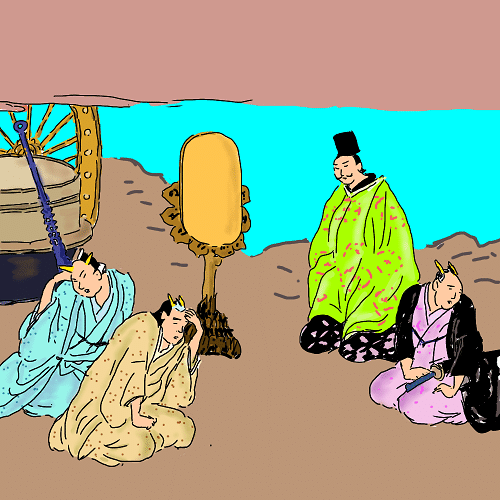
それより篁は、地獄中の拷問の責道具を見物し、いろいろ悪口を言う。
篁「その鉄の棒はなんだ。こんなものを質屋に持って行くとは、とんだずうずうしいやつらだ。それ、火の車を見ろ。いつ燃えたのか知らないが、もう今にも壊れそうだ。地獄の大釜の中には蜘蛛の巣がはっている。罪悪を調べる秤の針は折れてるし、生前を映す浄頗梨の鏡も曇っている。せっかくこの物語のタイトルにしたのに、こんな鏡じゃ使い道がないぜ」
五
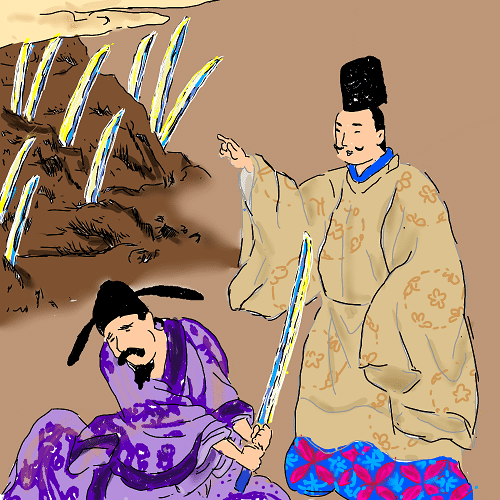
それより篁は、各所を見物したまい、有名な剣の山を見ると、昔は見かけばかりのなまくら刀を植えていたけど、近年閻魔王がはなはだ世話をやいて、名刀友切丸、痣丸、正宗、国行、長船などを集め、残らず植え替えたので、篁は、この山はものすごい値打ちものだと感動する。
篁「この山を娑婆の道具屋に見せたいな」
十王「これは名刀葵下坂ともうし、よっく切れます。これからご覧ください」
篁「これ、冗談をするな。危ねえわ」
ここまでが上巻。
本文は、たった5枚の紙に木版画で印刷したものを二つに折った、10ページの作品。見開きページもあるので、場面としては6場面くらいになる。
つづきは次回のお楽しみ。
中巻へつづく。
その他の黄表紙現代訳は、
その他の黄表紙原本の紹介は、
地獄については、
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
