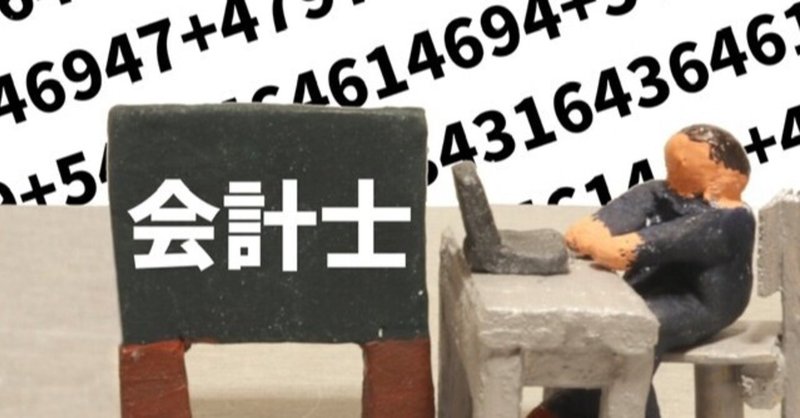
監査法人雑学 〜こんな監査手続いる?〜
USCPAの勉強をしていてふと思い出したので、監査法人時代の無駄っぽい監査手続をご紹介します。
はじめに
筆者は、大手監査法人で、上場会社を含む5社くらいの主査(インチャージ)を何年かやっていました。主査は、担当会社の監査手続全般について計画・実施する現場責任者です。ということで、以下で述べる話は、それほど違和感なく読んでもらえるかと思います。
支払利息のオーバーオールテスト
この記事を書こうと思ったきっかけです。USCPAのAUD(監査論)のテキスト・問題集で度々出てきます。
支払利息と借入金残高(期中平均)を比較して簿外債務の有無を検証する手続です。利息÷借入金の結果と契約上の金利を比較して、乖離が許容範囲内であれば簿外債務はなさそうだと結論付けます。
筆者が監査法人に入所して数年くらいは、こんな手続がどのチームでも行われていました。
でも、よくよく考えてみると、これって意味ないです。利息は基本的に借入先の銀行預金口座から引き落とされるので、支払利息だけを計上して借入金を計上しないなんてことはまずできません。複式簿記すらままならない個人事業主ならいざ知らず。借入金を簿外にするなら、利息の計上も簿外にするのが自然です。
なので、簿外債務があったとしても、利息÷借入金は契約上の金利に一致するのが当たり前です。
いやいや支払利息の計上額の検証は必要だろって意見も中には出てきそうですが、この超低金利下で支払利息に重要性がある会社はまずないでしょう。形式的な基準で重要勘定(※)になってしまったとしても、通常は理由を付けて非重要勘定にします。
※重要性の基準値に一定率を乗じて許容範囲誤謬額を算定し、この金額を超える勘定科目を重要勘定とします。重要勘定には、個別の実証手続が必要です。
仮に実証手続をやるにしても、全部バウチング(証憑突合)しちゃった方が速いケースも多いと思いますが、昔は執拗にオーバーオールテストをやらされました…。
現金実査
リスクアプローチの観点で言えば、多くの会社では、手元現金に金額的重要性はなく、実証手続が不要な勘定科目になるはずです。にもかかわらず、4月1日(期末日の翌日)には、だいたい実査をやらされてましたね。
パートナーがよく言っていた、現金実査をやるべき理由は次のとおりです。
①現金は横領が起きやすい
②牽制の意味でやった方が会社のためになる
①については、財務諸表監査は、不正を発見するためのものではなく、財務諸表全体に対して、重要な虚偽表示がないことを意見表明するために行うものです。少額の横領を発見するために監査手続を設計するのは目的に沿っていません(そもそも実査したところで、横領なんてまず見つかりません)。
兆円企業で、たかだか数十万円の現金がなくなったからと言って、財務諸表全体にどれだけ影響があるというのでしょうか。
②については、本当に会社が喜ぶなら、監査報酬とは別途に報酬をもらうべきです。リスクアプローチから外れる監査手続を、監査報酬の枠組みで行うのは違和感ありですね。
じゃあ別途報酬がもらえるかというと、こんなものにお金を出す会社はまずありません。価値がないからです。ちゃんとした会社なら、自前の内部監査でしっかりチェックしています。
パートナーの中には「バリューを出せ」なんて言う人がいるんですけど、バリューのないところに目が行ってる会計士は割と少なくないです。
普通預金通帳実査
担保に入れてないかの確認だ、なんてことでやってるチームもあります。自分が主査になったチームは、だいたいやめました。
そもそも、銀行に対する普通預金債権は、銀行に承諾のない質権の設定が約款で禁止されていますし、日々変動する普通預金債権は担保に適していないので、質権を設定する実務はほとんどありません。有価証券でもない通帳を差し入れる実務もないと思います(銀行への対抗要件にならない)。
ていうか、預金債権に質権が設定されていれば、銀行確認状に記載されるはずです。
ちなみに、公認会計士試験で民法を選択する人は圧倒的少数なので、監査法人ではこの担保が債権質であることすら知らない人ばかりです。筆者も経済学選択なので、民法は後から勉強しました。法学検定アドバンストコース(最上級)に割と上位で合格しているので、並程度の法学部卒レベルの知識はあると勝手に思ってます(笑)
おわりに
とりあえず思いつくままに書いてみました。色々思い出したらまた書いていきます。
最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。
