
【連載】『わたしが推した神』ACT1-4 ニジンスキー、燃える。
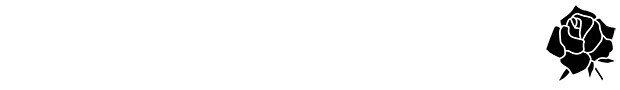
ロモラがなんとしてでもパリ公演に行きたかった理由。
それは、ニジンスキー自身の振付作品の初お披露目だった。
自分で自分の出演作品を振り付ける。
運営サイドが用意した曲を歌っていたアイドルが、はじめて自分で作詞や作曲をして、ギターを抱えて弾き語りをするようなものだ。
観ずには、死ねない。

美しい彩色とデザインの大判のプログラムには、こんなタイトルが記されている。
「牧神の午後」
音楽は、クロード・ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」。ステファヌ・マラルメの耽美的な詩にイマジネーションを受けて作曲された。18年前に大ヒットしてドビュッシーの出世作になったオーケストラ作品である。
登場するのは、女性ダンサーたちが演じる「ニンフ」、そしてニジンスキーが演じる「牧神」。ニンフとは水の妖精、牧神とはギリシア神話の牧畜の神だ。
おいしげる草木や豊かな水流が描かれた幕をバックに、岩の上に寝そべった牧神があらわれる。上半身はほとんど裸で、胸から足先までは、牛のようなまだら模様のタイツをまとっている。ブドウを食べたり、笛を吹いたりしてのんきに遊んでいると、ニンフたちが水浴びのために小川にやってくる。好色な牧神は、岩からおりて彼女たちを追いかける。びっくりしたニンフたちは、小川のほとりを逃げまどう。
追いかけるといっても、まっしぐらに向かっていくわけではない。逃げまどうといっても、四方八方に散っていくわけではない。
おどろいたことに、ニンフも牧神も、舞台の上を横移動しかしない。横顔しか見せない古代ギリシアのレリーフさながらだ。さらに、歌舞伎や能さながらの地を舐めるようなすり足。身体を外向きに開放し、軽やかに見せることを原則とするこれまでのバレエとはかけ離れている。しかも、動作は非常にゆっくり。まるでアニメをスローモーションで観ているかのようだ。
ドビュッシーの淡くぼんやりとしたサウンドとともに、少しずつ、少しずつ、世界が動いていく。
舞台でありながら、のっぺりとした平面の二次元ワールド。
これがニジンスキーのイマジネーション。ニジンスキーのクリエイティビティ。
若き天才ダンサーは、振付においても「神」だったのだ。……
そんな感嘆のため息がもれるなか、不満げな顔をしている観客も少なくなかった。
ほとんど飛ばないのだ。
中性的でエキゾチックなムードもさることながら、ニジンスキーのウリといえば「跳躍力」ではないか。飛ばないニジンスキーなぞ、ジャンプを放棄したフィギュアスケーターのようなものだ。トリプルアクセルでも四回転でもいい。早く、あのすごいやつを見せろ!…………
アクロバティックなテクニックに酔いしれたい人びとは、足をほとんど床につけたまま横移動をくりかえす牧神に、苛立ちをつのらせた。
しかし、観客を待ち受けていたのは、ジャンプどころではない大事件だった。
音楽が終盤に至るころ。
ニンフが落としていったスカーフを拾った牧神は、いとおしそうにそのスカーフを抱き、岩の上に広げて置く。そして、自分の身体をスカーフの上に横たわらせたかと思うと、両手を身体の下にはさみこみ、ふいに全身をびくりと震わせ、身体を弓なりに逸らす。
それは、明らかに性的な慰めの表現だった。
客席はおそろしいほどに静まり返った。
唖然としているシャトレ座の観客たちにまぎれて、まばたきの時間さえも惜しむように目を大きく見開いている娘がいた。
ついこの間までキスで妊娠すると信じきっていたその娘は、いまや男性ダンサーのマスターベーションの仕草を、果てた彼がぐったりと横たわる幕切れを、熱っぽくうるんだ瞳でみつめていた。
バレエの歴史を揺るがす革命が、いまこのパリ・シャトレ座で起きていた。

フランスのバレエの歴史は古い。
最初のブームは17世紀にまでさかのぼる。ブルボン朝の絶頂期を築いたルイ14世は、バレエをこよなく愛した王だった。世界初の舞踊学校を創設し、自らもダンサーとして「太陽の役」を踊ったため、太陽王の異名を持つに至った。
ルイ14世が亡くなり、彼の腹心であった王侯貴族の男性のダンサーが減少すると、プロの女性ダンサーも現れだす。1830年代には、マリー・タリオーニやファニー・エルスラーといった名バレリーナがあらわれ、つまさきで立つトウシューズと、白い木綿糸でつくられた薄く軽やかなチュチュで、本物の妖精さながらに舞台上を舞った。
女性の身体は美しい。男性の身体は醜い。……
そんな価値観が19世紀のパリっ子に浸透するにつれ、男性ダンサーは舞台から追いやられてしまった。その現象に相反するように、客席には男性の姿が増えていく。舞台に立つきれいな女の子たちを、裕福な男性ファンが追いかけ、高価なアクセサリーを贈り、デートに誘い、身体を求める。19世紀後半になると、フランスのバレエは高級風俗さながらの状態と化してしまった。
この有様に幻滅し、フランスを去った男性ダンサーたちは、ロシアに活路を見いだしていった。
『ドン・キホーテ』『白鳥の湖』など、クラシック・バレエの主要レパートリーを築いた大家マリウス・プティパもそのひとりだった。19世紀中盤にバレエダンサーとしてロシアに渡った彼は、帝室劇場で振付家として才能を開花させ、1890年には大作『眠れる森の美女』を発表。若きセルゲイ・ディアギレフにも大きな衝撃を与えた。
プティパのような外国人の力を借りて、ロシアのバレエ界では若い男性ダンサーや振付家が続々と育っていった。ミハイル・フォーキン、アドルフ・ボルム、そしてヴァーツラフ・ニジンスキー……。新時代のロシア芸術をヨーロッパに輸出しようと企んだディアギレフは、彼らを巧みにスカウトして、パリに乗り込んでいった。
ディアギレフのバレエ革命によって変わったのは、舞台の上だけではない。
客席も変わった。女性の観客が爆発的に増えたのだ。
太ももをちらつかせて踊る女の子をブルジョワ紳士が買う世界ではない。お姫様が王子様と結ばれるおとぎ話の世界でもない。エジプトやオリエントを舞台にしたエキゾチックで妖しい世界観。レオン・バクストが手がける色彩豊かでハイセンスな舞台美術や衣装。そして、ロシアの帝室劇場で鍛えあげられたダンサーたちが惜しみなく披露するパフォーマンス。パリの女性たちは、エキサイティングな舞台に心を奪われた。
そうした女性ファンの代表が、ミシア・セールだった。
ピアノの名手であり、パリの文化人サロンの主宰者でもあった彼女は、ディアギレフがバレエ・リュスの立ち上げ前に実験的にプロデュースしたオペラ『ボリス・ゴドゥノフ』にドハマリし、空席のチケットを買い占めて友人たちに「布教」して回った。ディアギレフとは親友さながらの仲になり、パトロン兼相談役の立場でバレエ・リュスにかかわった。
駆け出しのディアギレフに莫大な資金を与えたテニシェワ公爵夫人、イギリスでの巡業に手を貸したリポン侯爵夫人、さらにはイギリスの作家ヴァージニア・ウルフ、ファッション界の巨匠ココ・シャネル……彼女たちも、バレエ・リュスの重要な支援者たちだった。
そうした財力と地位と才覚のある「トップオタ」の陰には、何十倍もの無名の女性ファンがいた。
彼女たちは、ファッションカタログさながらのおしゃれなプログラムを愛読し、『シェエラザード』に登場するターバンやハーレム・パンツ、果ては頭の羽根飾りなどのオリエンタルな衣装を真似した。プレゼントを贈り、楽屋裏で出待ちをし、ダンサーが出演する私的なパーティーにもぐりこむチャンスを得ようと躍起になった。
女性ファンなくして、バレエ・リュスは存在し得ない。
セルゲイ・ディアギレフはそれをよく理解していた。

「牧神の午後」初演の反響を、彼は舞台袖からじっとうかがっていた。幕がおりたとたん、客席の紳士たちが野獣のごとく叫びだす。ある者は熱烈なブラヴォーを、ある者は牧神の痴態を非難するブーブーという罵声を。
天地をひっくり返すような大騒ぎのなか、バレエ・リュスとニジンスキーの挑戦に敬意を示すかのように拍手を送っている女性たちの姿があちこちにあった。
──あなたがたこそが、われわれの味方だ。
彼は自ら舞台へと歩み出た。
「ディアギレフだ」
ざわめきがあがる。ロモラは思わず身を乗り出した。
それは、彼女がはじめてこのバレエ・リュスの帝王の姿を見た瞬間だった。
ダンサーたちの洗練されたプロポーションを見慣れたせいか、ひどく場違いに見える。体型は横にも縦にも大きく、顔も腹も手もでっぷりとしている。ただし、身のこなしは優雅だ。パリの高級ブティックで誂えたとおぼしきシルクハットにタキシード。胸のボタンホールには一輪の花が挿してある。この事態に興奮しているのか、口髭のまわりは真っ赤に上気していた。
「アンコール! アンコール!」
ふいに、客席の一群が声をあげた。一説によれば、それはバレエ・リュスの熱狂的なファンだった女性画家、ヴァランティーヌ・グロスと仲間たちの叫びだった。その勢いに気圧されて、アンチたちのブーブーの声が一瞬やんだ。
──なんたる援護射撃。
隙をついて、ディアギレフは口を開いた。
「もういちど」
教養の高さをうかがわせる、完璧で柔らかなフランス語だった。
「どうぞ、もういちどご覧ください」
騒然とした客席は、だんだんと落ち着きを取り戻していった。ディアギレフは舞台袖に消え、ふたたびフルートが、牧神のパンの笛のメロディを吹きはじめた。

さすがのディアギレフも肝を冷やしただろう。もちろんニジンスキーにマスターベーションの振付を盛り込もうと決めた時点で、炎上するのは想定済みだ。しかしアンチどもを殴り返してくれる支持者もいなければ話にならない。ミシアの助けを得て、彼はあらかじめパリの新聞社や一流文化人に手を回していた。初演前のゲネ・プロには150名もの名士を招待し、レセプションで高いシャンパンやキャビアをふるまった。
こうした戦略が功を奏した結果か、この「ニジンスキー振付作品」の評価は見事なほどに割れた。
『フィガロ』紙は編集長自らが「卑猥」「みだら」という言葉で作品をこきおろし、『ル・マタン』紙は老彫刻家オーギュスト・ロダンの名前を使った絶賛の記事を掲載する。意識の高いパリの文化人たちは、暇さえあればサロンに集い、「牧神」について激論しあった。
ファンを育てることは、アンチを育てること。
むろん、逆もしかり。……
それがディアギレフの戦略だった。
ファンとアンチがぶつかりあって生まれる莫大なエネルギーこそが、バレエ・リュスを時代のトレンドへと押し上げていく。
ただ、ディアギレフにも重大な誤算があった。
ある種の経験不足、ともいえる。
21世紀のプロデューサーならば承知しているであろう「ファン」側の恐ろしさを、彼はまだ理解していなかった。ときとして、ファンはアンチよりも危険な存在になりうることを。そしてファンの暴走は、手塩にかけて育てた芸術を破壊する威力を秘めていることを。

ACT1-5につづく→
←ACT1-3にもどる
←もくじにもどる
【連載】「わたしが推した神」
1912年3月。
わたしは「神」に出逢ってしまった──。
有名バレエ団の絶対的エース、ニジンスキーを
推しすぎて人生を狂わせた女性ロモラの
波乱と矛盾に満ちた物語。
毎週金曜更新中!
(2023年6月追記)
★本作は、大幅改稿を経て、『ニジンスキーは銀橋で踊らない』として5月末に書籍刊行されました。詳しくは下記記事をご覧ください。★
