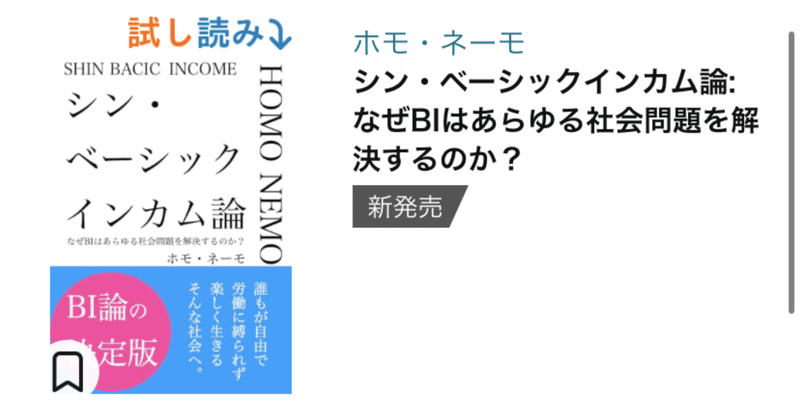- 運営しているクリエイター
2024年1月の記事一覧
行為と欲望についての殴り書き論考【アンチワーク哲学】
■人が欲望するもの可愛い子どもとは誰だろうか?
よく大人の言うことを聞く子? 勉強ができる子? お手伝いをする子? いや、究極の愛されっ子の特徴は、よく食べる子である。
このこと自体、私たちが人間に対して抱いている常識とは思いっきり矛盾する。人は利己的であり、ミニマックスの原理で動くと、一般的には考えられているのだから。料理は、死ぬ思いでかき集めてきた自分の金を削って、せっかくの休日に手間暇を
『シン・ベーシックインカム論』出版!
3冊目の著書を出版した。比較的短めの本なので30分くらいで読める。オススメである。
内容は、ベーシックインカム信者によるベーシックインカムの解説書である。前半は基本的な制度設計に関して整理し、後半ではエモーショナルにBIのメリットを語り尽くしている。読み応えがあるのは後半である。BIに詳しい人は前半を読み飛ばして3章あたりから読んでもらってもいい。
※基本的には以下の記事をベースにしているが、
一を聞いて十を聞き返す
世間では「一を聞いて十を知る」が良いこととされているらしいが、僕はこの風潮に異を唱えたい。
なぜか?
まず、この言葉は3つの意味で捉えることができる。それぞれのパターンを僕なりに分析し、批判を加えてみたい。
1.論理的思考に関する用法「あるところに山田太郎さんがいました」という語り出しを聞いて「山田太郎さんは日本人で、男性なのだろう」という論理的に至極真っ当な推論を展開する能力が高ければ、一
幸福とは、結果ではなく行為にある
「人は幸福に満足することがなく、いつまでも幸福になれない。だから人は幸福など本当は求めていない」といった手垢のついた人生訓は、果たして正しいのだろうか?
僕にとって幸福とは結果ではなくプロセスにある。プロセスとは、要するに行為である。人は行為によって幸福を味わい、結果によって幸福を味わうわけではないと、僕は考える。
このことは、釣りを思い浮かべると理解しやすい。
釣り人は魚という結果だけを追
初詣における神との邂逅
2024年1月1日。
今年は余暇に溢れた年になるように、余暇の神へ祈りを捧げるべく、僕は大阪天満宮へ向かった。
不意に、僕は神からの啓示を受けた。この人生において2度目の出来事である。
「ホモ・ネーモよ。預言者よ。私、ヨカ神の声がきこえるか?」
「あ、いま電車なんですよ‥もう降りるので、ちょっとだけ待ってもらえますか?」
「‥すべては赦される」
「‥」
「‥」
「‥あ、降りましたんでオッケー
自己を手段としてではなく、目的として捉えよ
カントの定言命法「他者を手段としてのみならず、目的として捉えよ」は、重大な欠陥を孕んでいる。
それは、この言葉を押し付けられた本人が手段として扱われてしまうことである。
誰かのために何かを行う場面において、それが「〇〇せよ」という定言命法によって押し付けられた道徳だった場合、それは命令として彼の目の前に現れる。命令される行為は、基本的に不愉快なものである。なぜなら、不愉快でないなら命令される必
みんなで作るニートスピーク
アンチワーク哲学はよく「欲望」「労働」「経済」「怠惰」といった言葉の用法が混乱していることを指摘し、新たな用法を提案している。
となると、もはや言語そのものにアプローチした方がいいのではないか?という気がしてきた。
そういえば僕は大学生のときに人工言語を作ったことがある(その言語は架空の孤島に暮らす人々が使用している設定で、天気と時間帯の掛け算の分だけ挨拶に種類があった。その孤島は極度なムラ社
労働の喜びはなぜ貴重なのか?
労働に関する批判を繰り返していると、稀に出会う反論が1つある。それは「労働には、労働を通じて人の役に立つ喜びを実感できるという魅力がある」というタイプの労働擁護論である。
僕は労働の中に喜びが存在することを認めるにやぶさかではない。実際、僕自身も労働の中で「あ、今人の役に立ったなぁ」と喜びを感じたことは何度もある。
ただ、このこと自体に疑問を投げかけなければならないのだ。なぜ、「人の役に立つ喜