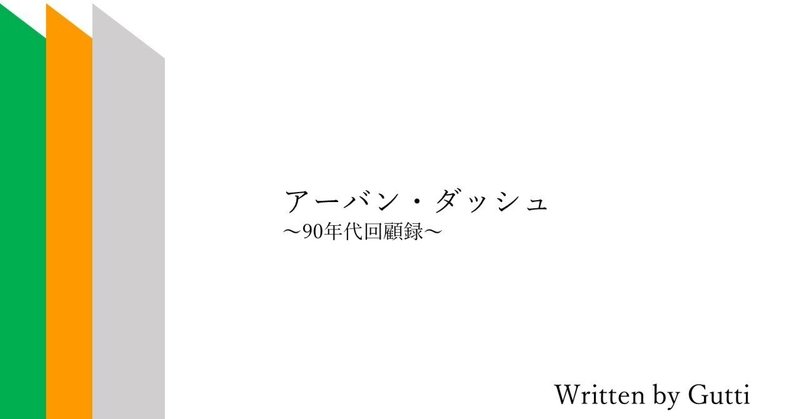
アーバン・ダッシュ~90年代回顧録~ Vol.1 氷河期前のオプティミズム(3話完結)
氷河期前のオプティミズム
日本列島に本格的な氷河期が訪れる前の1990年代後半、高校生だったぼくたちには、笑いと活気だけのオプティミズムが満ち溢れていた。
まだチェリーでしかなかった17歳のぼく(ら)は、名もなき詩を口ずさみながら、辺り一面、それはほとんど無限といっていいまでに拡がっている田園の中の通学路を、錆びついた自転車で一心不乱に滑走している。
その数、ゆうに200台はあったであろう。前傾姿勢で腰を浮かせながら自転車に跨ったチャリ族が、山の中に建てられた校舎から、駅に向かっての通学路を、サバンナのヌーのような勢いで一斉に駆け抜けていく。
山のくだり道を利用して出発するので、追い風に乗ることができれば、そのスピードはほぼ風速と一致する。
ドローンなんてなかった時代だが、この時の光景を上空から撮影するのであれば、それはさながらツール・ド・フランスの競輪のようにも見えただろうし、いやそんな上品なものではない、湾岸道路を我が物顔で滑走する暴走族と見紛うばかりの光景が繰り広げられていたことであろう。
授業が終わり、部活動をやらないぼくら帰宅組の生徒の目的は唯一つ。
それは、15時49分、高崎線本庄駅発「快速アーバン号」上野行きに乗ることであった。
この快速アーバン、当時は1時間に1本あるかないかのダイヤで、この1本に乗れるか逃すかで、帰宅できる時間が大きく左右されてしまう、死活問題であったのだ。
この快速アーバンに乗るために、全速力でペダルをこぐ行為を、ぼくらは「アーバン・ダッシュ」と呼んでいた。ぼくらが勝手に名付けたものではない。
ぼくらの学校の生徒全員が代々受け継いでいる「伝統文化」なのである。
ぼくらの学校は、群馬県との県境である、埼玉県本庄市の緑深い丘陵地帯、通称「大久保山」と呼ばれる小高い山の中にあった。東京ドーム約15個分、東京ディズニーランドの約1.6倍あるという敷地すべてが、ぼくたちの通う学校のものであった。
今でこそ、上越・北陸新幹線「本庄早稲田駅」ができ、駅を降りればすぐに校舎にアクセスできるとのことだが、ぼくが通っていた1990年代にはまだ、新幹線の駅などなかったのである。
最寄り駅は、高崎線の本庄駅。そこから学校までは、歩けば3~40分はゆうにかかる道のりであったから、ほとんどの生徒は、駅から校舎までの通学路を往復するためだけに使用する専用の自転車を所有することになる。
高崎線は、埼玉県大宮駅から群馬県の高崎駅までを結ぶ鉄道で、大宮からは赤羽、上野、東京駅にもつながっている。
東京からでも1時間半を要する田舎校である。首都圏や他県出身の者は、本庄市内にて、複数人がホームステイできる学校公認の合宿施設に入ることを選ぶ。
電車での通学を選ぶ者は、同じ埼玉県の大宮周辺に住むものが多い。上尾、桶川、北本、鴻巣、熊谷そのあたりだ。
ぼくはといえば、千葉の松戸市に隣接する三郷市から、この本庄に通っていた。同じ埼玉とはいえ、その距離、100kmである。限りなく千葉に近い場所から、限りなく群馬に近い場所を移動するのである。
100kmといえば東京から熱海くらいの距離、箱根駅伝の往路、山手線3週分の距離ということらしいので、ちょっとした旅行である。
今思えばよくもそんな距離を通学していたものだと自分でも感心してしまうのだが、ぼくはホームステイという合宿生活では自分の自由が脅かされると勝手に想像していたので、独りを謳歌できる通学生活を選択した。
小学生の頃から、集団生活が苦手なぼくは、部活動すらまともにできなかった人間だったから、共同生活という選択肢は地獄へ行くことと同義であった。
通学することを選んだ人間には、この高崎線での長距離移動という、とてつもない束縛があったのだが、早い時間に大宮に辿りつくことができれば、相応の自由を謳歌することができた。
大宮という埼玉の都は、本庄市とはワケが違うのだ。
そしてなんといっても、大宮からは埼京線という、まさしく「最強」の列車があり、この埼京線に乗れば、池袋、新宿、渋谷と、憧れの東京大都市にいくらでもアクセスできたのである。
ぼくらの遊び場所は、大宮からすぐに池袋、渋谷へと移行していった。新宿は、高校生のぼくらにとってはまだハードルが高すぎた。大人の街というよりは、危険な香りのする街というのがあり、大手を振って踏み込むには躊躇があったのだ。新宿に進出できるようになるのは、大学生になってからのことである。
ぼくらには、渋谷がちょうどよかった。むろん渋谷も、怖くなかったというわけではない。当時はチーマーだとか、B‐BOYといったストリートの文化が流行していて、渋谷はまさにその発祥の地、聖地のようなものであったからだ。安室奈美恵の流行もあり、コギャルという文化もあった。世の女子高生のほとんどが、ダボダボの分厚い靴下、通称「ルーズソックス」を履いて、ストリートを闊歩していた。
街にはいつも、小室哲哉がプロデュースする楽曲が溢れていた。チャートを独占していた小室ファミリーのミュージシャンを、当時のぼくらは「商業主義め」と毛嫌いしていたものだが、最近、40歳になってから聴いた華原朋美の『I'm proud』に涙してしまうということがあり(笑)、やはり彼らの音楽が、90年代のポップカルチャーを象徴していたのだと思いを改める。
ぼくの音楽趣味でいえば、はじまりはBOØWYであり、そこからBUCK-TICK、LUNA SEA、黒夢と、ビジュアル系へと移行していく。
だが、高校生になってからは、それらビジュアル系も含めて、Jポップをまるで聴かなくなった(※パンク路線にいった黒夢だけ例外)。
当時流行していたJポップは好みではなかった。サザン、ミスチル、スピッツも90年代を象徴するミュージシャンであったが、それらに触れるのは大抵、TVドラマのオープニングくらいであった。
Jポップ以外の流行でいくと、当時、アンダーグラウンドから出てきたヒップホップというジャンルもあったのだが、ぼくはNOFXとかランシドといったようなハードコア、メロコアを好んで聴いた。
ファッションなんかも、B‐BOYではなく、よれよれのジーンズを腰履きした、サーフ系のファッションを好んだ。古着にはまり、渋谷はもちろんだが、少し歩いて代官山に行くことで古着を買い込んだ。
当時のぼくらのファッションリーダーは、木村拓哉や、ダウンタウンの浜ちゃんなんかがそうだった。ぼくなんかは、音楽もファッションもビジュアル系からパンク系に移行していった清春をお手本にしていた。
せっかく進学校に行かせたのに・・・と、ぼくの親はよく嘆いていたものだ。ぼくは、都心での遊びに夢中になるあまりに、学校の勉強をおろそかにしていた。成績も毎年毎年、下降していくばかりであった。友人はそうではなかったが、ぼくは受験勉強からの反動で、遊ぶということだけに、自分のアイデンティティを見出していたのだ。
同世代で、すでにデカルトやらカントやらと哲学を読んでいた人間はいただろうし、ぼくの学校にも中上健次を読んでいて俺は文学をやっているから君たちとは人種が違う、とお高くとまっている人間もいた。
ぼくが、哲学や文学に本当の意味で出会うためには、あと2年の月日を必要としたのだが、それまでの2年間、自分にとっては決して無為な時間、停滞していた時間だったというわけではなく、遊ぶことの中で、自分の哲学を磨き続けたといってもよいだろう。かっこつけるわけでも何でもなく、自分にとって、遊ぶことで自分の居場所、自分を支える根拠、それが何であるかを探し続けていたのだ。
とはいえ、傍から見れば、それは暇を弄んでいる人間と何ら変わらないものに見えただろうし、学生という貴重な時間、エネルギーを無駄にしていたと言われても、反論することはできない。親が嘆いていたのも無理はない。
とはいえ、遊ぶといっても、ぼくらがやっていたことのせいぜいは、古着ショップをまわったり、タワーレコードへ行ったり、カラオケをしたり、ビリヤードやボーリングをやったり、時折、女子高生とコンパをしたりというくらいであった。すぐに街での遊びに飽きてしまったぼくと友人のJは、何か大きな「目的」を持った遊びをしないとまずいかも、という思いにかられた。
それで、出会ったのが「波乗り」である。ある時、サーフィンをやってみようぜ、と友人Jが口にしたのである。
続きはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

