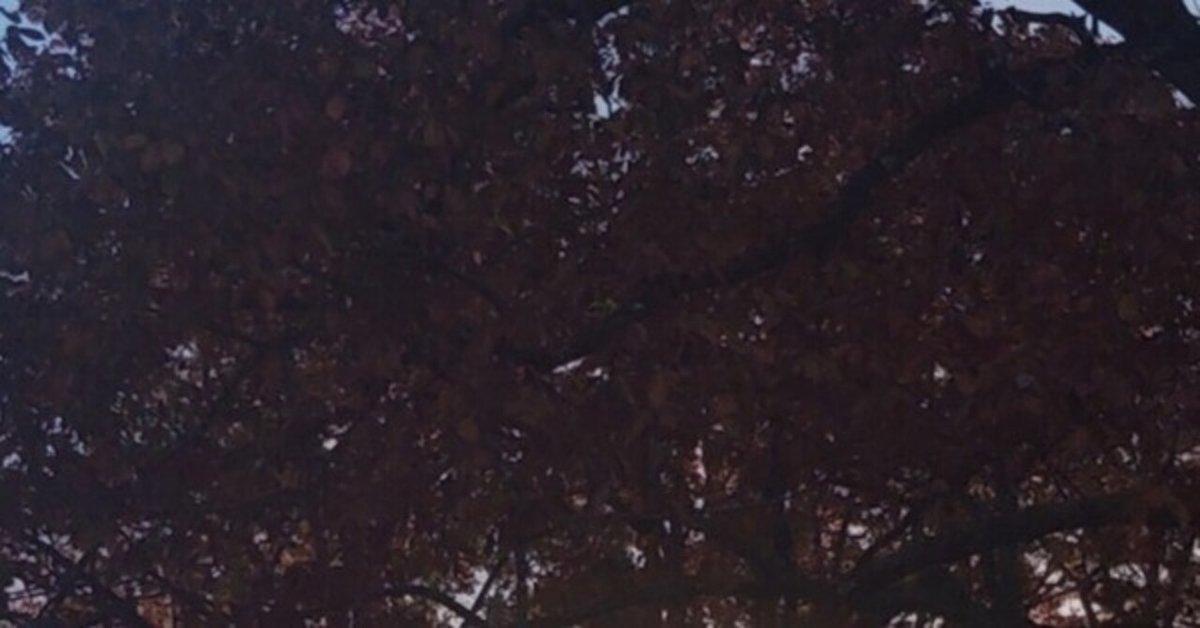
【創作長編小説】天風の剣 第16話
第二章 それは、守るために
― 第16話 血 ―
静かな深い森、わずかに舞い降りる月の光。
弧を描く鋭い閃光、金属音が響き渡る。
「ははは! いいぞ、いいぞ! キアラン……!」
魔の者シルガーとキアランが、それぞれの剣をぶつけ合っていた。
木の根に、草葉に、むき出しの岩に、キアランは足をとられそうになる。
防戦一方だった。シルガーの炎の剣の勢いに、天風の剣は押されていた。
金属音から打って変わって、鈍い音。
「うっ……」
キアランは、激痛にうめき声を上げる。
振り上げたシルガーの右脛が、キアランの脇腹を直撃していた。
どう、と音を立て、キアランは草の生い茂る地面に倒れ込む。
まずい!
キアランは倒れた状態のまま、とっさに身をかわす。
炎の剣が、大地に突き立てられた。そこは、一瞬前までキアランがいた場所だった。
ザッ! ザッ! ザッ!
キアランのいた場所に、矢継ぎ早に炎の剣が突き立てられる。
「どうした! キアラン! このままではあっけなく串刺しだぞ!」
「くっ……!」
キアランは体をばねのようにして飛び起き、そしてその勢いのまま飛び下がった。
鋭い痛みが、背骨を貫くように感じられた。
「うっ……」
冷汗が、額から流れ落ちた。ズキン、ズキンと痛みが脈動する。
しかし、キアランは歯を食いしばり、シルガーに向かっていく。
天風の剣を振り上げて。
「負けるものか……!」
天風の剣が、大きく弧を描く。
火花が散る。
シルガーは、炎の剣で難なく受け止めていた。
「いいぞ……! キアラン! その意気、その闘志だ……!」
シルガーは、笑いながら天風の剣を弾き返した。
「くっ……!」
鋭い剣の突きが、キアランの眼前に迫る。
キアランは大きく後ろに跳ね避ける。バランスを崩し倒れそうになったが、かろうじて持ちこたえた。
シルガーは、笑みを浮かべたまま炎の剣を掲げている。
いつでも、倒せる。そんな余裕からなのか、楽しんでいるのか。今のキアランは隙だらけに違いなかったが、シルガーは先ほどと違い明らかに攻撃の手を緩めている。
シルガーは、声を立てて笑った。
「キアラン! もうおしまいか!」
「くそっ……!」
キアランは、天風の剣を振るう。しかし、空振りに終わる。
思うように体が動かない。剣筋は読まれ、攻撃はことごとく阻まれた。
やはり今の私では、勝ち目はない……!
今までのキアランだったら、そのまま突進し続けていただろう。負けるのならそれも運命、命を散らしても仕方ない、そんな諦めの念を持ちながら、がむしゃらにぶつかっていったに違いない。
しかし、今のキアランは違った。ルーイやアマリアを守るという強い思いがあった。その気持ちが、キアランを揺り動かす。
今、死ぬわけにはいかない……! 今の私にできるのは、なりふり構わずひたすら自分の命を繋ぐ工夫をすること……!
生きていれば、可能性は広がる。キアランはこの場を逃げることに決めた。
さっき来たところ、バームスが待機しているところから反対の方角、すなわち森の奥へ向かって、キアランは駆け出した。
「おや! 逃げるのか!」
シルガーの声が、追いかけるように耳に届く。キアランは、振り返らない。
はあ、はあ、はあ……。
木々の間を縫うようにして走る。なるべくシルガーの追跡、少なくとも直接攻撃から逃れられるように、キアランはひたすら走った。
心臓が早鐘を打つ。
めまいがする。どこをどう走っているのか自分でもわからない。
景色が歪んで見える――。
これは、体力を消耗しているせいなのか――。
違う、そうキアランは気付いた。
森の木々が、白黒に見える。シルガーと戦った、あのときのように。
ここは、今までいた森ではなく、シルガーの創り出した世界……!
ドンッ……!
背中に、衝撃を受けた。
な……。
シルガーの投げた炎の剣が、キアランの背に深く突き刺さっていた。
どのくらい、時が過ぎたのだろうか。
キアランを呼ぶ声が、遠くから聞こえる。
あの声は、アステール……。
なにを叫んでいるかはわからない。でも、天風の剣、アステールは必死にキアランの名を呼んでいた。
体が、動かない。
暗闇にいた。
痛みがない。奇妙なことに、痛みがほとんどなかった。
しかし、自分はものを考えている。と、いうことは、私は、きっとまだ生きている……!
おそらく、まだ死んではいないのだ、そうキアランはぼんやりと思った。
「いい加減、起きないものか」
キアランは、反射的に飛び起きた。
それは、シルガーの声だった。
体は、意外なことにきちんと自分の支配下にあった。自分の意思通り、今まで通り脳の指令に反応し、即座に動いたのだ。
「シルガー……!」
シルガーは、キアランのすぐ隣にいた。
寝ていたキアランの傍で、様子を伺うように座っていたのだ。おそらく、キアランの意識が戻るまで、ずっと――。
「シルガー! 貴様……!」
「そんな怖い顔をするな。私は、恩人だぞ」
「なにを言って……!」
「痛みはないだろう?」
「なに……!?」
キアランは驚きのあまり、絶句した。先ほどと違って意識がはっきりしているのに、あるはずの体中の傷の痛みが、ほとんど感じられない。不思議なことに、シルガーの剣に突き刺されたはずの背中まで――。
「……死に近づくほど痛めつければ、さすがに目覚めると思ったのだがな」
シルガーは、無表情で呟く。
「肉体の極限までくれば、それを補おうとお前の中のもうひとつの血が目覚めると、そう思ったのだ」
「私の中の、もうひとつの血……!?」
「しかし、目覚めなかった」
「シルガー、いったい、なにを言って――」
「お前の体は、そのまま死へ向かおうとしていた。だから、飲ませてやった」
シルガーは、ふっ、と笑った。
暗い森。真っ暗だが、白黒の世界、シルガーの創りだした世界ではない。ふくろうの、不気味な鳴き声がする。
夜風が、シルガーの髪を揺らす。
「飲ませた!? なにを、私に飲ませたというのだ!?」
キアランの叫ぶ様子を見て、シルガーが愉快そうに笑う。暗闇に浮かぶ、白い顔。銀の目は闇の中でも不気味に光り、真っ赤な口が裂けたように吊り上がる。
「私の血、だよ」
シルガーは自分の腕を差し出した。そこには、真一文字に深く切り裂かれた跡があった。
「なにっ!?」
「おやおや、心配しなくても大丈夫だよ、キアラン。魔の者、しかも私のような強力な力を有する者は、傷をごく短時間で修復する。それを証拠に、もう傷口はふさがって――」
「誰がお前の心配などするかっ! 私に、お前の血を飲ませた、だと……!?」
胃の中のものが、せりあがってきた。キアランは苦悶の表情を浮かべながら、激しくえずいていた。
「失礼なやつだな」
「お前、なんてことを……!」
キアランは叫ぶ。しかし、シルガーは面白いものを見るような目でキアランを見つめるだけだった。
「生きてるし、傷もよくなっている。感謝されてしかるべきと思うが……?」
「シルガー!」
「普通の人間なら、魔の者の血は強すぎて即死だ。また、魔の者なら、他の魔の者の血を飲めば、己の持つ力と相手の力の優劣や性質の差によって、薬にも毒にもなる。まあ、毒となる危険性が高いため、魔の者同士なら通常、そんなことはしない。キアラン、特殊で秘めた力の大きいお前の場合なら、きっと強力な薬になると思ったのだよ。そして私の読み通り、お前は生還し、傷もほとんど回復している」
「お前……!」
「そんなに睨むな。まあ、私の血を飲むことによって、お前も色々変わってくるだろうな」
「なに……!」
「もしかしたら、目覚めるのが早くなるのかもしれない」
もう、体に吸収されてしまった。もう、飲んだという事実は変わらない。キアランはうなだれた。虫の声が、なんとはなしにキアランの耳を通り抜ける。
「……貴様は、よくしゃべるな」
言いたいことは山ほどあった。胸ぐらに掴みかかり、抗議したいところだった。しかし、すでに気力が失われていた。力なく首を左右に振りながら、他愛もない心に浮かんだことをキアランは呟く。
「ふふ。まあな。大変興味深い実験だった。面白かったよ。刺激的で、実に楽しい気分だ」
「お前の読み通りにことが進み、ご機嫌で口数が多いというわけか」
「私に、お礼の言葉はないのか?」
「……そんなものが欲しいのか」
シルガーは、立ち上がった。口元には笑みが浮かんでいた。
「まあ、そう噛みつくな。お前は、私の血が入ったことで、体の中のバランスがうまく取れていないはずだ。しばらくは、戦える状態ではないだろう」
先ほどまでは、気にならなかった虫の声。今では、キアランの頭に強く響いていた。
「当分は養生していろ。今、無理やり鍛えようとするより、そのほうが、話が早い。お前の体が安定したとき、もしくは真の力が目覚めたとき、そのときまで――」
虫の声が、止まったような気がした。
「戦える……! 私がお前を倒す……!」
キアランは、腰に差した天風の剣に手を伸ばし、シルガーに斬りかかろうとした。
ドッ!
シルガーは、キアランの胸に肘討ちをくらわせた。キアランは、土の上にふたたび倒れ込む。
シルガーはキアランの胸ぐらを掴み立ち上がらせ、顔を間近に近寄せた。
「ふふ……。いい目をしている。闘志に燃えた、実にいい目だ……!」
「シルガー……。ひとつ、教えろ……!」
「なんだ? キアラン。なにか不安か? 私の血以外、飲ませてはいないぞ?」
これ以上得体の知れないものを勝手に飲まされてたまるか、そう思いながらもキアランは叫んだ。
「私の中のもうひとつの血、それはいったいなんのことだ……!」
シルガーは、ニヤリ、と笑った。ふたたび、虫の声が、ひどく大きく聞こえる。
「もう、自分でも、わかっているのだろう……? キアラン――」
「なにを……!」
「お前は、私に親しみを感じないか……?」
「…………!」
シルガーは、キアランから手を離した。
「キアラン。お前には、とんでもない血が流れている。この私より、もっと強力な、魔の血が、ね……!」
キアランは、自分の鼓動が止まったような気がした。もちろん、それは錯覚に過ぎないのだが――。
シルガーの銀色の瞳――。まるで、月の光のようだ――。
キアランは、立ち尽くす。虫の声しか、キアランの耳には届かない。
「おや。キアラン。お前のお仲間が、もうこの森へ到着したようだ。あの興味深い男とやり合ってみても面白そうだが、今日のところはやめておくとするか」
シルガーは、笑う。
「キアラン。お前があの男を助けようと、無理をするとよくないからな。本当の楽しみはこれからだというのに、うっかり殺してしまってはもったいない」
シルガーは、キアランに背を向けた。一足ごとに、シルガーの輪郭がぼやけ、薄くなっていく。
「私は、気が長いほうでね――」
森の中に、溶け込むように。ほのかに差す月の光のように、淡い銀の光を残しながら、シルガーの姿は消えていく――。
「次に会うときを、楽しみにしているぞ――」
虫の声。どうしてこんなに響くのだろう。頭が痛くなるようだ、とキアランは呆然としていた。
「キアランッ!」
木々の合間から、ルーイ、アマリア、そしてライネが駆けてくるのが見えた。森の中ほどで待機させていたバームスを連れて。
キアランは、身じろぎもせず佇む。
虫の声が、黒の森を覆いつくしていた。
◆小説家になろう様、pixiv様、アルファポリス様、ツギクル様掲載作品◆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
