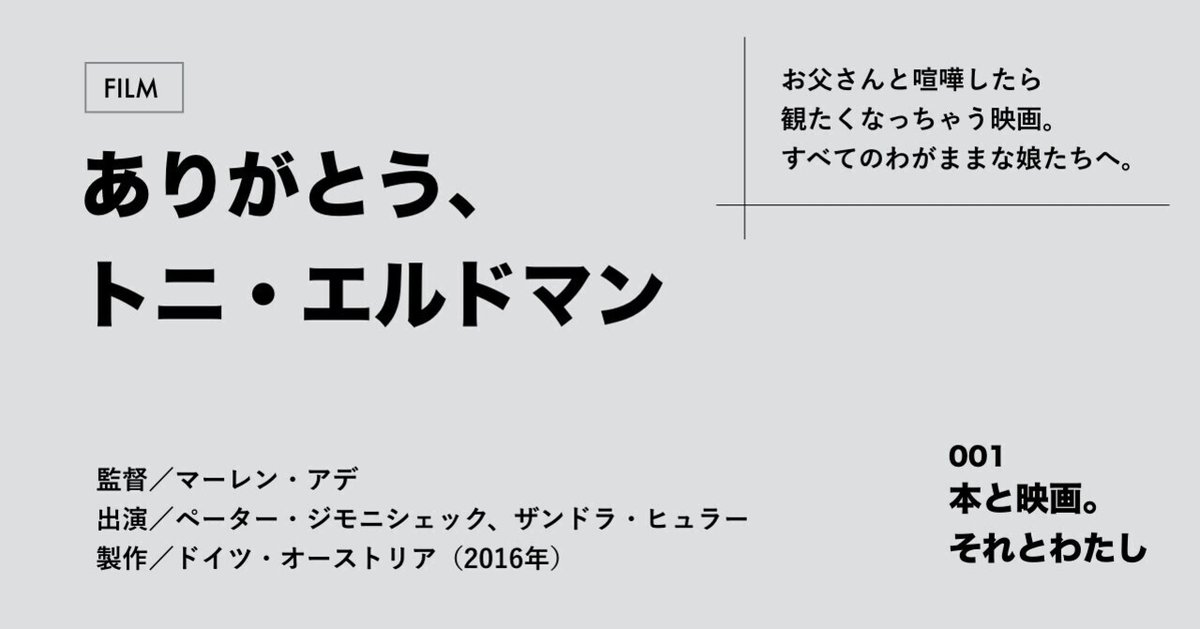
トニ・エルドマンと、父とわたし
お父さんと喧嘩したら観たくなっちゃう映画。すべてのわがままな娘たちへ。
ティーンエイジャーになってから、父とはしょっちゅう喧嘩していた。負けずぎらいのわたしは何か父にいわれるたびに言い返したくなり、口論に発展するのだが、結局言葉では父を言い負かすことはできず、最終的にわたしが泣いて終わるパターンがほとんどだった。母はよくわたしの味方をしてくれたけれど、それでもたびたび衝突し、それは27歳で実家を出るまで続いた。
本作に登場する、父ヴィンフリートと娘イネスの関係もなかなか複雑だ。ドイツを離れてルーマニアに暮らすイネスは、久しぶりに帰ってきたのに仕事の電話ばかり。心配したヴィンフリートは、こっそりルーマニアにイネスを訪ねていく。
そんな父のおせっかいを迷惑に感じたイネスは、父をドイツに送り返してひと安心。しかし、その日の晩、イネスの前に「トニ・エルドマン」と名乗るカツラに入れ歯という出で立ちの不気味な男が現れる。なんと、変装したヴィンフリートだったのだ!
神出鬼没のヴィンフリートに何度も笑いがこみ上げる一方、どこか素人っぽさがあって、急にシリアスになったりする。わたしの父は変装して急に現れたりするタイプではない(そうであることを祈る)が、日本を離れて暮らす娘(わたし)をこんなふうに心配しているのだろうなと思って、ちょっとだけヴィンフリートと重なる。
どんなにたくましく異国の地で生きていたって、どんなに仕事ができてバリバリ働いていたって、父親にとって娘は娘。いつだって心配はつきないし、子のしあわせを願っているのである。
実家を出てから、わたしと父の関係は良好になった。お互い頑固なところが似ているので、同じ屋根の下では近すぎて磁石のように反発してしまっていたのだろう。かといって、今が最適な距離感といえるかどうかはわからない。というのも、わたしはこの映画を見て、父のことをとてつもなく恋しく感じたからだ。
(ここから若干ネタバレ)終盤で、ヴィンフリートにこれでもかと振り回されてきたイネスが「パパ!」と叫び、父親にかけよって言葉なく抱擁を交わすシーンがある。ヴィンフリートにすべてを受け入れてもらったイネスの姿はまるで少女のようで、急速に何かに満たされていく様子がそのワンシーンにしっかりと収められている。感情の波が押し寄せ、わたしはひとり部屋で涙を流した。
ヴィンフリートに抱きしめられたイネスに、本当はただ父に認めてほしかったという自分が重なり、わたしは涙したのかもしれない。そして、外国に暮らして3〜4年が経ったころ、父が言ったことを思い出す。「お前がしあわせなら、別に日本に戻ってくる必要はないと思ってるよ」。ひょっとしたらもう、父はわたしのことを認めてくれているんだろうか。
ありがとう、トニ・エルドマン
監督/マーレン・アデ
出演/ペーター・ジモニシェック、ザンドラ・ヒュラー
製作/ドイツ・オーストリア(2016年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
