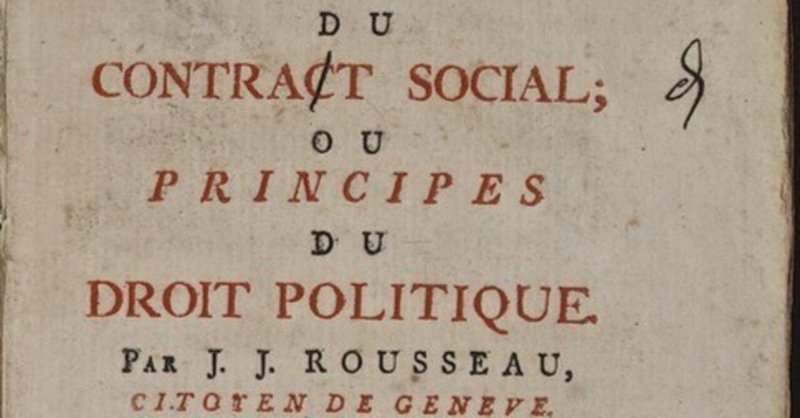
『社会契約論』原典精読02
原典精読の試みを始めましたが、今回から本格的に内容に迫っていくことになりますので、実質的には今回が初回と言ってもよいでしょう。最後までぜひお付き合いください。
今回は第一巻のうちの第一章です。
凡例
①原文は原則として「Wikisource」から引用することとします。今までの記事でルソーの原文を紹介したときには、定評のあるRousseau, Jean-Jacques. Du contrat social, Œuvres complètes, III, Éditions Gallimard, 1964.を出典にしてきたのですが、現状ではGallimard社の『ルソー全集』は手に入りにくく、入手できるとしても価格が高騰していると思われますので、本シリーズの目的を鑑みて、誰にとってもアクセスしやすいものを原文の引用に用いることに決めました。よって、etが&の記号で表記されていますが、このままの表記で引用します。
②日本語については基本的に本アカウントの管理者に文責がありますが、その都度既出の邦訳各書を参考にしています。
③本シリーズでは、上記の①および②のような方法で記事を執筆します。したがって、本文を引用する際に、原文・日本語ともに対応する頁数を示すことは現段階では考えていません。ただし、『社会契約論(Du contrat social)』以外の書籍から引用をする場合にはこの限りではありません。
CHAPITRE I.
Sujet de ce premier livre.
本章は「第一篇の主題」と題されています。ルソーの問題意識がふんだんに詰まった章だと言えるでしょう。
L’homme est né libre, & par-tout il est dans les fers.
この冒頭の文はあまりにも有名です。hommeは「人間」という意味ですが、このhommeを「人間」と捉えることに関して、近年フランス社会では議論が巻き起こっているようです。というのも、厳密にいえばhommeは「男性」という意味で、女性を意味する言葉にfemmeがあるからです。
有名な「フランス人権宣言」でも、第一条に、
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
という記述がみられます。「人間」と言いつつ、「男性」を意味するところのhommeが使われているのです。「万人(Les hommes)は自由(libres)かつ平等(égaux)なものとして生まれた」というときの「万人」に、「女性(femme)」が含まれないのです。これはまずくないか、という議論が現代フランス社会において起こっているのです。
しかし歴史的な文脈に限った話ではありません。こうした問題は、フランス語のなかに他にもたくさん存在します。主語人称代名詞ils、ellesの用法がその好例です。ilsもellesも三人称の複数形です。したがって、男性が3人いる場合は、ilsを用いればよいわけですし、女性が3人いる場合は、ellesを用いればよいわけです。
しかし、男性3人、女性2人の集団だったら・・・?この場合は「ils」を用います。男性の数のほうが多いですから、まだわかりますね。でも、男性1人、女性100人の集団であっても、男性が一人でもいれば、「ils」を用いなければならないのです。
これは、明らかに不平等で、女性をないがしろにしているのではないか、ということで、近年、フランスではこの問題を解決する希望を「包括的書体」(écriture inclusive)に託し、ジェンダーフリーな言語を実現しようとする試みが行われつつあります。
日本語でもそうですよね?・・・そうですよね、と言いつつ、ピンとこない方!僭越ながら、かなり鈍感かも。かくいうこの記事を書いている私は、罪なことに戸籍上も自分の意志においても男性なのですが、男性こそ隠れた差別に気が付かなければなりません。
例えば、「女医」とは言いますが、「男医」とは言いませんよね。これは、暗に「医者」が「男性」であると言っているのと同じです。hommeの例と酷似していませんか?別に、医師は男性に限らないのに、ついつい私たちは「男性的な仕事」と見なしてしまっている。「いや、そんな風に考えてなどいない!」と言いたくなるでしょうけれど、だったら「女医」と言っても違和感がないのはまずくないか、ということに気付いてほしいのです。(看護「婦」なんて言ってる人は、今すぐ比叡の山に籠って修行しなおしてきてください。)
現代は「差別のない平等な社会」だと思っていたら、それは大間違い。差別は、「言語」のような一見してわからないところに、ある種「構造的に」存在しているのです。この構造を解体する(自分の差別意識に気づく)のに、他の言語に触れることは良い起爆剤になるように思えます。
閑話休題。この箇所では、本来自由なものとして生まれてきた人間が、その自由な状態を維持するのではなくて鉄鎖に繋がれてしまっている、と言っています。
自由とは何なのかということに関して哲学的な議論は多く存在していますが、ここで今後の議論を理解するために必要な限りで簡単に述べておくとすれば、ルソーが考えていた自由は、私たちが日常的に「自由」という言葉を使っているときに意味している内容とは大きく異なっているということは重要です。というよりも西洋哲学史上で私たちと同じような意味で自由を使っていた人は稀ではないかと思います(しいて言うならイギリス経験論者が自由という言葉を使うときは近い気がしますが、それでもまだ距離はあります)。
その証拠に、いまの文章に続く文章を見てみましょう。
Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux.
自分を他人(des autres)の主人(le maître)であると思っている人も、実は彼ら(eux=des autres)以上に奴隷(esclave)なのだと言われます。自分はお金をたくさん持っていて湯水のように使うことができるから「自由」だとか、いつでも好きなときにたらふく食べることができることを「自由」と言うんだとか、このように思っている人ほど、自分が金銭欲や名誉欲、食欲の奴隷なのだと気づいていないわけです。
彼らは断じて自由ではない。では自由とは何か。このことはいますぐに述べるわけにはいきませんので、いつか改めてじっくり言及することにします(述べるとしたらおそらく第二篇あたりです)。
Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.
ついつい考えてしまいがちですが、ルソーによれば人間が鉄鎖に繋がれていることの理由を「なぜか?」と問うことはできないと言います。その代わりに「どのように正当化されているか?」を問い質すことはできる。だったらそのように問うてみようではないか。これが第一篇の主題です。
またこれは『社会契約論』全体に通底する主題でもありました(このことは前回の記事で確認済みですね)。
さて、légitimeという語に着目してみましょう。辞書によると、ここで訳出する際に採用した「正当な」という意味に加えて「当然の」という意味もあります。社会における人間の不自由を外部から正当化されるだけでなく、あたかも「当然の」ことであるかのように内面化してはいないだろうか、とルソーは読者に問いかけているような気がしてなりません。
せっかくですのでもう少しルソーについての理解を深めるために、『社会契約論』以外の著作からも似た表現を取り出してきます。
『エミール』第二篇には、
支配することでさえも、世論に服している場合には、隷従することなのだ。なぜなら、君が偏見によって支配している人々の偏見に、君自身が依存しているからだ。
とあります。また『山からの手紙』第八の手紙にも、
自由は、自分の意志を行使することよりむしろ、他人の意見に屈服させられないこと、ひいては他人の意志を自分の意志に屈服させないことに存するのです。支配者であるものはだれも自由であることはできません。支配するとは服従することなのです。
と書かれており、これら複数の記述を照合させれば、ルソーが一貫して人間の自由を問題意識として持ち続けていることがわかるでしょう。自由についてこれ以上長く書くことは本記事の趣旨からは幾分か外れますのでこの辺でやめにします(が機会があったら自由について記事にしてみるかもしれません)。
Si je ne considérois que la force, & l’effet qui en dérive, je dirois ; tant qu’un Peuple est contraint d’obéir & qu’il obéït, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug & qu’il le secoüe, il fait encore mieux ; car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou l’on ne l’étoit point à la lui ôter.
随分長いですが、一気に訳します。
もしも力とその結果だけに注目した場合、ある人民が服従を強いられ、またじっさいに服従しているあいだはそれで構わない。人民がその軛を振りほどくことができるようになり、またじっさいに振りほどくやいなや、なおさらよい状態となる。なぜなら、人民から自由を奪ったのとまったく同じ権利によって、人民は自由を回復したのである以上、人民が自由を奪い返すのは当然であるか、それとも、人民から自由を奪うのはもともと不当であったのか、そのどちらかであるからだ、と主張されるはずである。
さて、ここでフランス語を改めて見てみましょう。Si je ne considérois que la force,と始まっていますが、ここで用いられているのは「条件法」です。条件法とは、事実とは反することについて述べるときに用いられる用法です。つまりルソーはここで述べていることは事実に反する仮定だというつもりで書いているわけです。そう理解した状態で上の文を改めて見てみると、内容がより深く伝わってくるのではないでしょうか。
Mais l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d’en venir-là je dois établir ce que je viens d’avancer.
「社会秩序は聖なるものであるが、自然によってなされるものでは決してない」ということをこの節の最後に述べています。
さて、この箇所を見てもルソーの考える自由が「〜からの自由」とも称される自由や私たちが普段使っている自由とは大きく異なるであろうことがうかがえるでしょう。(何度も蒸し返すようですが)私たちの日常生活レベルで考えている自由は「社会秩序」と相容れないように思えてなりません。ルソーから言わせればそうではないのです。というより私たちの考えている自由は自由とすら言えないのかもしれません(ルソーなら隷属と言うでしょう)。
今回はこの辺で終わりにしましょう。自由がキーワードになってくることを記憶しておいてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
