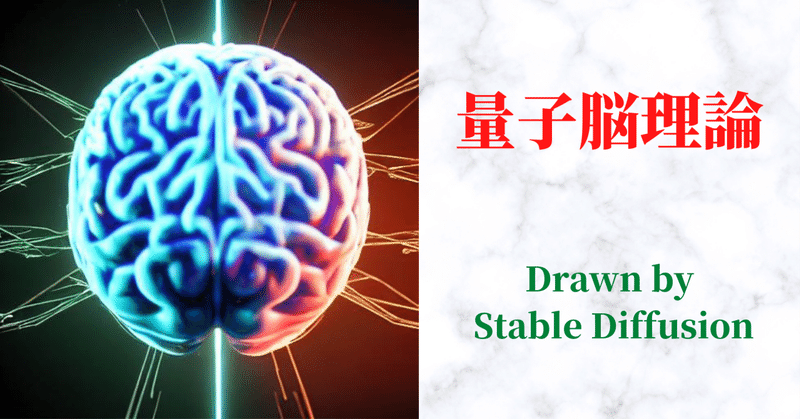
蘇る量子脳理論
意識を含む脳の働きについて、量子力学的な効果が深く関わっているとする量子脳理論は、長らくトンデモ理論のような扱いを受けてきました。
しかし、近年、渡り鳥の磁気感覚や植物の光合成などの生物学的な現象に量子効果が重要な役割を果たしていることが明らかになり、さらに、脳内で何らかの量子効果が働いている可能性を示す実験結果も発表されたことによって、量子脳理論が再び注目を集めています。
今回は、この量子脳理論の概要と関連する最近の動きについて解説します。
1.量子脳理論
量子脳理論とは、脳内の情報処理や意識の発生に量子力学的な効果が深く関わっているとする理論です。
量子脳理論が出てきた背景の一つに、デカルトの実体二元論に対する批判があります。つまり、デカルトの主張のように脳内で物質と精神が相互作用することを認めると、「どんな物理現象も物理現象以外の原因を持つことはない。」という物理的領域の因果的閉鎖性と呼ばれる物理学の基本法則と矛盾するという批判です。

量子脳理論では、この物理的領域の因果的閉鎖性と矛盾せずに、脳内の物質と意識などの非物理的な現象が互いに関与していることを説明するために、量子力学における波動関数の収縮過程の仕組みを解決策として持ち出しています。
量子力学の世界では、量子重ね合わせという不思議な現象があり、オンとオフなどの複数の状態が同時に存在することができます。量子コンピューターも、計算処理を高速化するために、この量子重ね合わせ現象を利用しています。
また、波動関数の収縮とは、この複数の状態が共存する量子重ね合わせ状態を表す波動関数が収縮して、ただ1つの状態を表すようになることを言います。
代表的な量子脳理論として、2020年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスの数理物理学者ロジャー・ペンローズ教授とアメリカの麻酔科医スチュワート・ハメロフ氏が提唱した組織化された客観的収縮理論(Orchestrated Objective Reduction Theory)があります。この理論は、略して、Orch OR理論とも呼ばれています。

現在の量子力学において、標準的な解釈であるコペンハーゲン解釈によれば、波動関数は観測によって収縮するとされていますが、ペンローズ教授は、波動関数の収縮が観測と無関係に起きると主張しており、このような理論を客観的収縮理論と呼びます。特に、ペンローズ教授は、重力によって波動関数の収縮が起きると主張しています。
ペンローズ教授は、1999年の著書「皇帝の新しい心」において、脳内の情報処理には量子力学が深く関わっていると主張し、「素粒子には、それぞれ意識の元となる基本的で単純な属性が付随しており、脳内の神経細胞にある直径約25nmの微小管で波動関数が収縮すると、その属性も同時に組み合わさって、高度な意識が生まれる。」と、その理論を説明しています。
また、ペンローズ教授は、意識のある主体が観測することによって波動関数の収縮が起こるというコペンハーゲン解釈に異議を唱え、逆に、客観的なプロセスである波動関数が収縮する過程で意識が生み出されるのだと答えています。
そして、客観的収縮(OR)から生まれた意識の最小単位が微小管→神経細胞→脳という階層構造によって組織化(Orchestrate)されると、クオリアのようなマクロの意識になるというのです。

ただ、意識の元となる基本的で単純な属性が具体的にどういうものなのか、なぜその属性が組み合わさると意識が生まれるのかについて、多くの人が理解できるような十分な説明がされていないため、ペンローズ教授らのOrch OR理論を懐疑的にとらえる研究者が多いのが現状です。
さらに、一般的に量子効果は、量子が安定する絶対零度近い極低温でナノ秒レベルの極めて短い時間しか働かないため、常温で比較的長い時間、量子効果が持続することが求められる量子脳理論のような仕組みは難しいのではないかと批判されています。
こうした批判に対し、ハメロフ氏は、生物学上の様々な現象が量子効果を利用していることが明らかになってきてており、Orch OR理論を根本的に否定できた人はいないと主張しています。
2.量子生物学の発展
近年、様々な生物学的現象に量子効果が関係していることが明らかになり、量子力学と生物学を融合させた量子生物学という新たな分野が成長してきています。
(1) 渡り鳥の磁気感覚
冬になると、スウェーデンの森林地帯から地中海に数千キロも飛んでいく渡り鳥のヨーロッパコマドリは、地磁気の方向と強さを感知できる特殊な能力を持っていることが知られています。
普通の磁石の100分の1程度の弱い磁力の地磁気を感知するこのヨーロッパコマドリの能力に量子効果が利用されていることが分かってきました。

1978年にドイツ人化学者のクラウス・シュテルン博士が「鳥のコンパスには、量子もつれ状態にある遊離基のペアが使われている。」という説を提唱しました。
量子もつれとは、光子や電子などの量子のペアが、互いにどんなに遠く離れていても、片方の量子の状態が変わるともう片方の状態も瞬時に変化するという現象です。
通常の分子は偶数個の電子を持ち、これらの電子がペアを作っていますが、適当なエネルギーが与えられると、結合が切れて、量子もつれ状態にある不安定な電子のペアを作り出すことがあります。この量子もつれ状態の電子のペアのことを遊離基のペアと呼びます。
その後の研究で、この遊離基のペアが磁気感覚を生み出すメカニズムが段々と明らかになってきました。
ヨーロッパコマドリの網膜細胞にある青い光の光子を吸収するタンパク質のクリプトクロムが光を吸収すると、遊離基のペアを作り出します。
この電子のペアは不安定なので、電子同士が再結合して、磁性を持たない一重項状態または磁性を持つ三重項状態になるのですが、それぞれの状態になる確率は、その電子ペアの方向に対する磁場がなす角度に強く影響されるため、普通の磁石の100分の1と弱い地磁気の磁力にも鋭敏に反応できるというのです。
こうした反応が網膜細胞で処理されていることから、ヨーロッパコマドリは、地磁気を見ることができるのかもしれません。
また、こうした磁気感覚は渡り鳥だけの特殊な能力ではなく、多くの動物が磁気感覚を持っている可能性も出てきました。
通常、人為的に量子もつれ状態を作り出す場合には、極低温で短時間しか量子もつれ状態を維持することができませんが、自然の生物が細胞の内部という高温で複雑な環境の中で、壊れやすい量子もつれ状態を長時間維持しているのは驚くべきことです。

(2) 光合成
植物の光合成でも量子効果が利用されていることが研究によって明らかになってきました。
植物は、太陽光のエネルギーを用いて、二酸化炭素と水からでんぷんなどの有機物を作り出していますが、この光合成による光エネルギーの利用効率は極めて高く、人間の技術では真似ができません。
光合成を担う葉緑体の中では、光エネルギーによって電子の放出が起こり、その後の複雑な化学反応に使われています。
その時の光から電子へのエネルギー変換効率は9割以上となっており、この高い変換効率を実現するために量子重ね合わせという現象が利用されているというのです。
量子重ね合わせは、光子や電子などの微小粒子が同時に別々の場所に存在するなど、相反する状態を同時に実現できる不思議な現象です。
この量子重ね合わせが光合成のプロセスの中で起きており、植物がこの現象をうまく利用して、高いエネルギー変換効率を実現しているのではないかと考えられています。
2010年に、カナダのトロント大学のグレゴリー・ショールズ教授の研究チームが光合成に量子効果が利用されている証拠を確認できたと発表しました。
葉緑体の中では、光を受け取るアンテナの働きをする集光タンパク質から、主要な化学反応を担う反応中心と呼ばれる部分にエネルギーが伝達されており、いくつものルートが存在します。
研究チームは、1000兆分の1秒(フェムト秒)のレーザーパルスを集光タンパク質内の個々の分子に当てる方法によって、エネルギーが別々のルートを同時に伝わっている現象を確認しました。
光合成では、量子重ね合わせによってエネルギーが複数のルートを同時に伝わることによって、結果として最も効率のよいルートを選択し、極めて高いエネルギー効率を実現しているというのがこの研究の結論です。

実は、ショールズ教授らの研究以前にも、マイナス180度以下という低温状態で、緑色硫黄細菌の集光タンパク質内で量子重ね合わせが起きていることが確認されていましたが、今回の研究では、一般的な海藻類を用いた常温での実験が行われ、常温でも量子重ね合わせが起きていることが確認されました。
常温でも量子重ね合わせが起きることを証明した今回の研究成果は、太陽電池のエネルギー変換効率の改善や常温で動作する量子コンピューターの実現に繋がっていく可能性もあり、多くの分野において非常に重要な意義を持つ成果です。
近年、渡り鳥の磁気感覚や光合成以外にも、呼吸のメカニズムや動物の嗅覚、酵素反応など様々な生物学的現象に量子効果が関係していることが報告されています。
こうして、幅広い生物学的現象に量子効果が関係しているという認識が広まったことから、脳の働きに何らかの量子効果が作用していても不思議ではないと考えられるようになり、量子脳理論がトンデモ理論と見なされる障害が一つ取り除かれました。
3.脳内で量子効果が働いていることを示す実験
先月(2022年10月)、アイルランドのダブリン大学の研究チームが量子重力の存在を証明するために考案されたアイデアを用いて、人間の脳が量子的な機能を持っていることを突き止めました。
このアイデアは、正体が分かっている既知の量子系を利用し、それを未知の系と相互作用させて、量子もつれが発生すれば、未知の系も量子的であると判明するというものです。
研究チームは、今回の実験で脳の水分の陽子スピンを既知の系として使用し、量子もつれが発生したスピンを検出する特殊な手法で磁気共鳴画像装置(MRI)による測定を行い、その結果、脳波の信号の一種である心拍誘発電位(HEP)に似た信号を捉えることに成功しました。

HEPのような信号は通常のMRIでは測定できないため、今回の信号が脳内の陽子スピンと量子もつれを起こしていることから初めて測定できた、つまり、量子的機能を持つこれまで測定できなかった脳内の信号を検出することに成功したと結論づけられています。
今回の実験結果は、脳内の高温で湿った環境では、量子もつれや量子重ね合わせのような量子効果は持続しないというこれまで量子脳理論への批判として主張されてきた意見を否定できるかもしれません。
実験によって、今回発見された信号のタイミングや強度がHEPと同様に、意識の働きと相関関係を持っていることが分かりました。また、この信号が短期記憶の心理テスト結果と相関していることも明らかになりました。
したがって、今回の発見は、単に脳内で量子的な信号が確認されたというだけではなく、脳内の量子的機能が人間の意識の働きや短期記憶の能力とも関係している可能性があるという点が重要です。
研究チームのクリスチャン・カーケンス博士も、「今回観測された量子効果が私たちの認知的・意識的な脳機能の重要な部分となっているかもしれない。」と指摘しています。
4.微小管で量子効果が発生していることを示す実験
ペンローズ教授らのOrch OR理論では、脳の神経細胞内の微小管で波動関数が収縮することにより意識が発生するとしています。
微小管は、細胞の骨格として細胞の構造維持や運動を受け持ち、細胞内の物質輸送の足場としても使われている細胞内に回路のように張り巡らされた直径約25nmの管状の組織で、チューブリンと呼ばれるタンパク質からできています。また、細胞分裂の際に現れる星状体や紡錘体の主体も、この微小管です。

Orch OR理論が成立するためには、微小管の中で量子効果が発生することを証明する必要がありますが、これを支持する研究結果が2022年4月にカナダのアルバータ大学の研究チームなどから発表されました。
アルバータ大学の研究者たちは、細胞内の微小管にエネルギーの高い青色の光を照射して、量子効果が発生するかどうかを確認する実験を行いました。
実験の結果、照射された光が微小管に捉えられ、その半分が数百ミリ秒から1秒以上経過した段階で放出される遅延発光が発生していることを確認しました。遅延発光は、量子効果の結果として生じることから、微小管で量子効果が発生していると推定できます。
また、数百ミリ秒から1秒という遅延の範囲は、意識が発生するタイムスケールとも一致します。
これまで、微小管で量子効果が発生したとしても、一般的に量子効果はナノ秒レベルの極めて短い時間しか持続しないため、意識が芽生えるほどのタイムスケールには達しないと考えられてきましたが、この実験によって、微小管内で起こる量子効果が意識の発生につながる可能性が示されました。
さらに、アルバータ大学の研究者たちは、意識を奪う効果のある麻酔薬が微小管における量子効果にどのような影響を与えるかを実験しました。
研究者たちが微小管を麻酔薬にさらして、同様に青色の光を照射する実験を行ったところ、麻酔薬にさらした場合は、遅延発光の遅延時間が約5分の1に短縮されることが判明しました。
一方で、神経に対して同じ抑制効果があるが、意識は奪わない抗痙攣薬に微小管をさらした場合には、遅延発光に影響はありませんでした。
この実験結果は、麻酔薬が微小管に作用して量子効果を妨げている可能性を示しており、ここから、微小管で起こる量子効果が意識の発生と関係していること及び麻酔薬が微小管の量子効果を妨げることによって意識を奪う効果を発揮していることが推測されます。
同時期に米国のプリンストン大学で行われた研究でも、アルバータ大学と同様の研究結果が示されました。
プリンストン大学の研究者たちも、微小管にレーザー光を照射する実験を行い、微小管の特定の場所にレーザー光を当てると、微小管を介して、予想より遥かに広範囲に電子の励起状態が拡散していくことを発見しました。
また、微小管に麻酔薬を加えた場合、この異常な微小管の振る舞いが抑制されることを発見しました。
これらの実験結果も、アルバータ大学と同様に、微小管で起こる量子効果が意識の発生と関係している可能性を示しています。
5.まとめ
ペンローズ教授は、ブラックホールの存在の理論的証明などでノーベル物理学賞を受けた偉大な物理学者ですが、彼の量子脳理論は、「ミステリアスな意識とミステリアスな量子力学を安易に結び付けたものにすぎない。」などと、多くの科学者や一般の人達から批判されてきました。
また、量子効果は、量子が安定する絶対零度近い極低温で極めて短時間しか維持できないと考えられていたため、脳内の高温で湿った環境で、意識の発生や持続に耐えられるほど長時間、量子効果を維持することは無理だとされてきました。
しかし、近年、渡り鳥の磁気感覚や光合成などを始めとして、様々な生物学的現象に量子効果が関係していることが明らかとなり、生物内の高温で湿った環境でも量子効果が維持できることも判明して、脳の働きに何らかの量子効果が関係していても不思議ではないと考えられるようになってきました。
さらに、最近の研究で、脳内で量子効果が働いており、それが脳の働きと関係している可能性があること、微小管の中で量子効果が発生し、それが意識の発生と関係している可能性があることが実験によって示されました。
もちろん、現在は、可能性の段階なので、脳の神経細胞内の微小管で発生した量子効果が意識の発生を引き起こしているという量子脳理論が証明された訳ではありません。
そして、脳内の量子効果が意識の発生に関係していたとしても、それが意識の発生を生み出すメインのメカニズムではなく、間接的に影響を与えているだけかもしれません。
特に、ペンローズ教授らの主張する組織化された客観的収縮理論(Orch OR理論)は、波動関数は観測によって収縮するという現在の量子力学の標準的な解釈(コペンハーゲン解釈)を否定する量子力学の世界が天動説から地動説に変わるような革命的な理論であり、そう簡単に証明されるようなものではありません。
また、波動関数の収縮と同時に意識が発生するというメカニズムも、現在の物理学で説明できるレベルの話ではなく、新たな物理理論を生み出さなければ十分な説明はできないでしょう。
しかし、Orch OR理論が正しいかどうかに関わらず、脳内で発生した量子効果が脳の働きに何らかの影響を与えている可能性は、無視できないものとなっており、脳内の量子効果の計測及びそれが脳の働きに与える影響の研究と、それらを踏まえた量子脳理論の再検討は、今後の科学の重要課題となっていくでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
