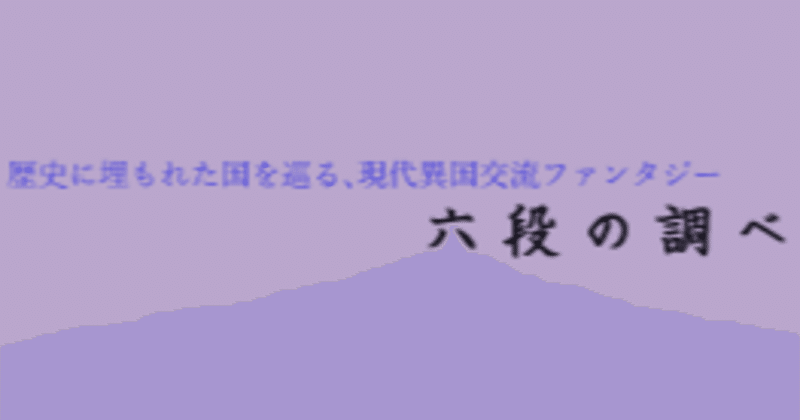
六段の調べ 急 二段 二、建国祭の前奏曲
前の話へ
序・初段一話へ
祭りに行く約束をした翌朝、清隆は信と学校の教室へ向かっていた。四階まで続く階段を上る途中で、少し先にゆっくりと段差を踏み締めている少女の後ろ姿を見つける。胸下辺りまで伸びた髪は一つにまとめており、黒い色が妙に重く見える。
「せっかくだからさ、八重崎もお祭りに誘ってみない?」
信の提案に清隆は頷く。彼女も気分転換をすれば、いくらか調子が良くなるかもしれない。真っ先に段を駆け上がった信が声を掛けるのかと思いきや、彼は八重崎を通り過ぎて踊り場まで行ったところで振り返り、清隆に笑みを向ける。どういう訳か、自分に頼みたいようだ。
その意図が掴めないまま、清隆は八重崎にそっと歩み寄った。こちらを見る彼女は、口角こそ上がっているが瞳が若干虚ろだ。祭りについて教えると、他に誰か来るのか尋ねてきた。答えようとして階上を見上げると、信の姿がない。
「信と北道雄が行くことになっていて、後は妹が検討している。シャシャテンと山住も来るかもしれない。……連れが多いのは、嫌か」
彼女は諸田寺に行きたがっていた時、同行者を気にしていた。知り合いがいると動きにくいのだろうか。
「人目が最近、ちょっと苦手になってね。でも清隆くんが誘ってくれたんだから」
八重崎が低い声で返す。前までは少年に似た声質だったが、近頃はそれよりも曇り気味で聞き取りにくくなっている。目もやたらと左右に動き、周囲を気にしているようだった。
「ああ、瑞香の人って着物だったよね? わたしも浴衣なら持ってるけど……」
「別に俺は普段通りの恰好で行くつもりだが――着物も良いかもしれない」
ふと彼女の浴衣姿を見たいと頭によぎったが、即座に振り切る。また連絡することを決めると、八重崎は逃げるように教室へ足を進めていった。その速さに置いていかれ、清隆は立ち止まったままでいた。誘いには乗ってくれたものの、無理やり同意させてしまったのではないか。本意でなかったのなら申し訳なく思いつつ、清隆は段差を上がり始めた。
祭りの当日、昼前にまず待ち合わせたのは、北の家前だった。何やら準備に手間取っている女性陣より先に、清隆と信は北と合流する。彼は倉橋から貰ったという祭りの行程表と地図を渡してくれた。民が女王へのお目見えを許される参賀の行事、そして鳳凰「降臨」は、日本でいう午後四時辺りに御所の庭で行われるそうだ。
「でもシャシャテンさんって、確か御所に入っちゃいけないことになったんだよね。見に行けるのかな?」
「それは北殿、屋敷の内へ入らぬのであれば障りなかろう」
突然の声に清隆たちが振り返ると、いつもより身なりをしっかり整えたシャシャテンがいた。白い打掛には、片喰の文様が光に当たってうっすらと見える。そして緑っぽい小袖には水芭蕉が裾辺りに大きく描かれている。
少し遅れて下駄で歩きづらそうにやって来ているのは、妹と八重崎だった。妹は赤い鬼灯と鳳仙花の柄が入った白い浴衣で、明るい色の髪はいつも通り後ろで結んでいるだけだ。一方で八重崎は、この季節らしい青と緑の紫陽花を配した紫がかった着物ながら、首から下げたストラップの先端を襟の中に収めている。髪はシャシャテンに借り、また結ってもらった簪でまとめている。
「……やっぱりおれたちも、瑞香にふさわしい恰好すればよかったかな?」
まさに花のような女たちの姿に、信がぽつりと呟く。その言葉に触発され、清隆もこれから彼女たちと並んで歩くことが気まずくなってきた。ところで、シャシャテンの立ち入りが禁じられたのは建物の中だけで良かったのだろうか。清隆の疑問をよそに、居候は手を前に突き出す。
「さて、城秀と会うのはいつぶりかのぅ……。私は先にあやつと待ち合わせておるから、各々方は好きに楽しんで良いぞ」
結界が手繰られ、都の入り口である羅城門が前方に見える場所へ下り立つ。既に大通りは人で賑わっており、何とか歩ける場所が見当たるほどだった。シャシャテンは山住が待っていると話す所へ向かい、北も行きたい場所があると言って去ってしまった。瑞香が初めてであるはずの北を一人にしても大丈夫だったか。清隆が彼の背を眺めていると、北から貰った地図を見ていた美央が口を開いた。
「……じゃあ、わたしも気になるところへ行くから」
「あ、待って! 一人じゃ危ないよ!」
門とは反対側へ歩きだした美央を、信が慌てて追う。結果的に清隆と八重崎が残されてしまった。
「先輩は、興味のある場所はどこかないか」
「あまり瑞香のことは知らないんだけど……」
そういえば、八重崎が瑞香を訪れたのは二回目でしかなかった。それも、今は土砂に埋もれた寺の中を重点的に見ただけだ。すっかり忘れていたと恥じながら、清隆は大通りに目をやる。今日のために準備されたであろう屋台が並び、何かを焼いているような香ばしい匂いも漂ってくる。まずはこれらを巡ってみようと、清隆は八重崎を連れて門をくぐり抜けた。
懐に手を入れ、シャシャテンから借りた巾着があるのを確認する。瑞香で使える貨幣は最低限だけ、この中に入っている。奢ろうと思えばいつでも出来たが、八重崎は店先を軽く見るだけで商品を買おうとはしなかった。
前後左右から進んでくる人を避け、地図で示されている大通りの真ん中辺りまで来る。ここで陽気な笛や太鼓の音が先から聞こえてきた。人々が立ち往生している隙間を覗き込むと、赤い絨毯に座る楽師たちが囃子を演奏している。これには八重崎も足を止め、食い入るように見つめていた。
「先輩はどうして、吹奏楽を始めようと思ったんだ」
一曲が終わった後に、清隆は尋ねてみた。八重崎は歩いている人を注意深く避けて答える。音楽自体に興味を持ったきっかけは、小学生の時に友人から北のコンサートに誘われたことだった。進学して吹奏楽部に入り、あまり希望楽器もなかったので勧められたバリトンサックスを始めた。体力には自信があり、重い楽器を持っても苦にならなかったという。
「五年間やってきたけど、やっぱり吹けなくなるのは寂しいね。仕方ないんだろうけどさ」
再び始まった演奏を見、清隆は小さく頷いた。雅楽ならではの唸るような独特の響きが、周辺に満ちていく。その音に負けじと、八重崎へ聞こえるように清隆は問い掛けた。
「シャシャテンが結婚するってこと、前に話したよな」
「え、シャシャテンが? 誰と?」
八重崎は驚いたようにこちらを見、きょとんとしている。もしかしたら既に言ったつもりになっていたのかもしれない。反省しつつ、清隆は来年の三月にシャシャテンと山住が結婚式を行い、そこで両親の所属する楽団が演奏する予定だと教えた。その式で、今回は特別に外部からも奏者を募集していると思い出し、八重崎へ参加してみないか誘う。
「俺も何とか親から許された。練習期間は少ないが、出るつもりだ。先輩もどうだ。案外、上手く吹けるかもしれない」
「そうかな……? じゃあ、わたしも一緒に出るよ」
八重崎の答えに満足し、清隆は再び演奏に耳を傾けた。そこに袖を掴まれ、強く引っ張られる。清隆が振り向くと、八重崎が俯いて頭を片手で押さえていた。どうやら人混みで気分が悪くなってしまったようだ。地図で大通りから横に伸びる小道を確かめ、清隆は八重崎を伴って囃子の場を離れた。
人気の少ない、道の先にある屋敷の軒先で休む。慣れない着物で歩き回っていたこともあってか、八重崎は日差しを避けるようにして影の中でしゃがみ込んでしまった。
「……ねぇ、ここって本当にわたしと清隆くんしかいないよね?」
額の汗を拭う彼女に、清隆は周りを探ってから肯定する。今ばらけている信たち以外に、瑞香を教えてはいないとも伝えた。
「思ったんだけどさ。わたし、瑞香で起こった事件って話に聞くばかりで、ちゃんとしたことはほとんど知らないんだよね。お寺で生田くんが死んだっていうのも、最初はぴんと来なかったし」
思わず頭痛がして、清隆も隣に腰を落とした。今年の初めにあった騒ぎについては、自分が八重崎を気遣って日本に留めたのだ。しかしそれが、逆に彼女へ負担を与えていたのではないか。自分はやはり、思わぬうちに人を傷付けている。
八重崎も、瑞香に興味があったのだ。かの国にまつわる話を、彼女は割と熱心に聞いていた。自分はその思いを踏みにじってしまった。今度彼女が関心を持ったものがあれば、参加させてやるべきかもしれない。
「……先輩、すまなかった。諸田寺に行きたかっただろうに、俺が勝手に――」
「いいよ、もし土砂崩れに巻き込まれていたら大変だったし。……きみと一緒にいることで――」
後半の言葉は、よく聞き取れなかった。やがて八重崎がゆっくりと立ち上がろうとし、清隆もそれを手伝う。少し顔色の良くなった彼女から、何か気になる場所はないか聞かれた。懐に入れていた紙を取り出し、清隆はついて来る八重崎を窺いつつ歩き始める。
地図を頼りに、大通りから遠くに流れる川沿いを歩く。人混みの熱気も冷め、河原に漂う空気は心地良い。やがて川に架かる橋のそばに、黒い石で出来た碑を捉えた。それを前に手を合わせている人を見ながら、清隆は持っていた紙――去年の夏に山住から届いた知らせへ目を落とす。
清隆より少し背の高い碑に記されていたのは、この辺りで処刑が行われた旨だった。諸田寺にいた人々を四辻姫が捕らえ、尽く刑に処した際の慰霊碑だ。やはりあの事件は本当だったのかと、清隆は唇を噛み締める。
合掌していた町人が清隆たちに気付き、当時の様子を語ってくれた。僧侶だけでなく一介の民もこの河原に並べられ、野次馬が眺める中で首を斬られたのだと。それを哀れに思った人々が、寄付し合ってこの碑を立てた。
去年から、この処刑場が使われる機会が増えたらしい。四辻姫は刑罰を強化し、以前ならそれに当たらなかったであろう者も死罪になることが多くなった。聞くところによると、大友によって廃止されていた拷問も再開されている。治世は安定しているが、どうもきな臭いものがあると懸念して、町人は通りを歩いていった。
「先輩は牢に入れられた時、そこの壁を蹴り開けていたよな」
慰霊碑を見つめ、清隆は昨夏の出来事を振り返る。あの行動によって何十人かが脱獄し、儀礼に参加していた人全員が殺されるには至らなかった。彼女のおかげで、救われた命があった。それでも八重崎は碑をぼうっと眺めるだけで、自分が人を助けたと実感できていないように見える。
多くの人が死を迎えた、不吉な場所に連れて行くのがいけなかったかもしれない。清隆は八重崎に声を掛け、次の場所へ向かおうと促した。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
