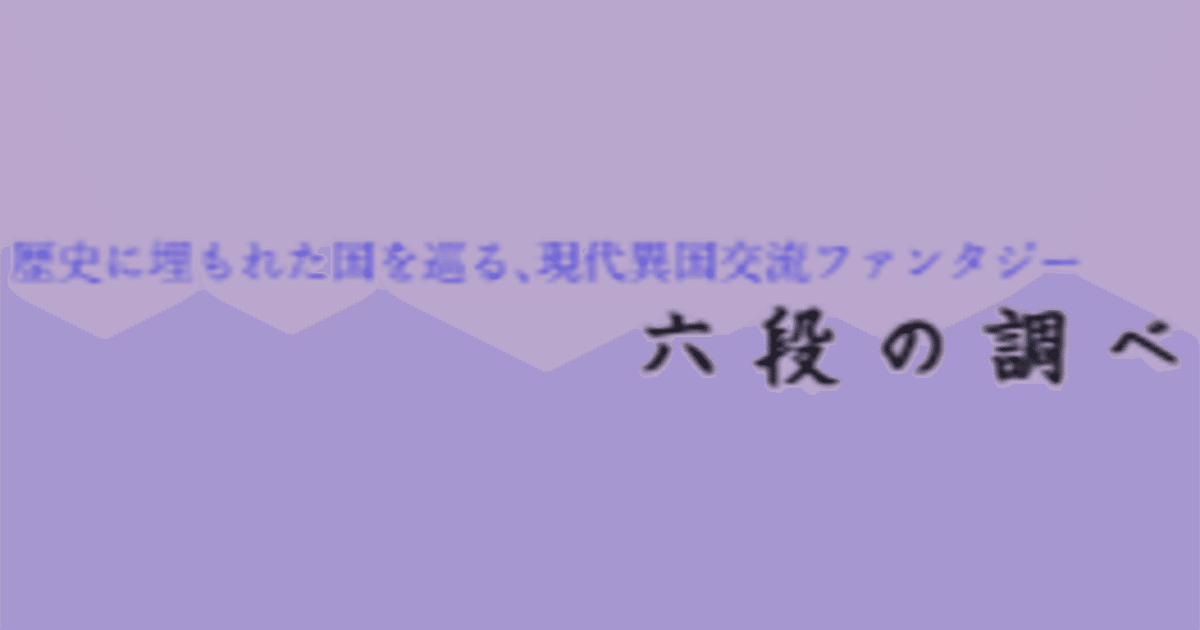
六段の調べ 破 初段 一、慕わしい人の名は
前の話へ
序・初段一話へ
「一つ尋ねるが。誓い言を反故にされんとしておった八房の犬が伏姫のもとへ上がり込んだ折、蹴倒したものは何だったかのぅ?」
宮中の常御所でくつろぐ女王の問いを受け、女官は昔読んだ本の内容を思い出した。周りでは誰も古典を原文で読んでいなかったが、趣味が高じてあの長い物語に耽っていたのだ。その実力を今、この新天地で試されている。
「筑紫箏でございますね。姫が『枕草子』を読んでいたところでしたか」
女官がさらさらと答えると、主である四辻姫は喜ばしげに何度も頷いた。知人を頼り、ほぼ掟破りの手段でここへ仕えることになった。主はこの国に身寄りのない自分を保護し、下積みから始めるしきたりではまず考えられない、女王のそばで世話をする役目をいきなり与えてくれた。さすがにそこまでの立場になるとは思わなかったが、何とか瑞香で生きていく最初の関門は突破できた。
ここ十年間国を治めていた大友正衡は、ひと月ほど前に崩御した。代わって即位した四辻姫は、薄雪山での幽閉生活を経て御所に戻り、再び統治を始めている。その合間に私室で、彼女はこうして女官を呼んでは知恵試しをしてきたのだった。
「しかし、そなたの学は深いのぅ。よほど多くの書を嗜んできたと見える」
脇息に左腕を載せて笑い掛ける四辻姫に、女官は育ってきた国での暮らしを話した。子どものころからから古典に興味があったが、周囲には奇異な目で見られ、からかわれていた嫌な記憶も明かす。
「別に何を言われようが、そなたが気に病むことはない。日本がどうであれ、ここでは知っていて悪いものではないからな」
そう励まされた後に会話が途切れ、女官は思わず主から目を逸らす。ここで働き始めて数日、まだ距離の取り方が分からない。昔も今も、人との会話は苦手だ。その上、高貴な家柄に相応しい調度――絢爛な飾りの施された文机や葛籠が置かれているこの部屋自体にも威厳が感じられる。そしてそれに包まれている自分が押し潰されそうな気がして、余計萎縮してしまうのだ。
「ところでそなた……あの男に惚れておるのか?」
ここで出るとは思わなかった名に、女官は姿勢を崩しそうになった。その者は会う度にちらりと見るだけだったが、周りにそこまで推測されているとは。即座に否定しても、迫った方が良いと主に押されてしまった。知り合ったばかりで、さすがに時期が早過ぎるだろう。恥ずかしさのあまり袖で顔を隠した女官に、女王が声を立てて笑う。
「分かった、そなたはそなたが思うようにすれば良い。私も無理はさせぬ」
いつの間にか女官も、四辻姫につられて小さく笑い声を漏らしていた。それも収まり、部屋は静かになる。鳥のさえずりさえ、室内には入ってこない。
「そういえば、そなたはここに来てから不死鳥を見たことがあるか?」
四辻姫の問いに、女官は首を振る。思えば不死鳥の国と聞いてここに来たが、いまだにその姿を目撃していない。いつもならこの部屋にも、彼らの鳴き声がよく聞こえると女王は言う。
「さてはこの国から姿を消したか? しかし十三羽全てがか……?」
四辻姫にも、はっきりしたことは不明なようだ。また新しく状況が判明したら教えると、彼女は女官に退室を許す。一礼して去った後、女官は目の端に若者が歩いているのを捉えて足を速めた。廊下を進み、密かに慕っていた者を追い掛けようとする。しかしあっという間に誰も見えなくなってしまい、仕方なく女官たちの部屋へ戻る。鳳凰が羽を広げたような形の御所で、今までいた所がそのほぼ中心に位置し、向かっている先は西側にある。覚えるのも一苦労な構造の中を急ぎで進んでいると、息が切れそうだった。
ようやく目指す部屋が見えた辺りで、少しずつ速度を緩める。あまり人とすれ違わないことに、ほっと息をつく。女王の指摘が、幼いころに覚えた歌を口に出させた。
「恋すてふ――」
新年度が始まり、シャシャテンが平井家に来て一年が経過した。吹奏楽部も休みで早く帰れた土曜日の午後、清隆は居間から二階へ上がろうとして、向かいの襖が少しばかり開いているのを認めた。室内をそっと覗くと、居候が故国・瑞香より届いた手紙を読んでいる。やはり伯母の四辻姫が出したものだろうか。彼女も女王に即位して忙しいはずで、いつも姪を気に掛けている暇もあるまい。
和室から視線を外し、階段へ足を向ける。そこに襖が勢いよく引き開けられ、近くにいたことを驚くシャシャテンとぶつかりそうになった。
「何じゃ、そこにおったのか? ちょうど良い、美央を呼ぼうとしておったのじゃ。そなたも部屋に入っておれ」
慌ただしい階段の足音を聞きながら、清隆は畳の一室へ入る。瑞香の調度で揃えられたこの光景も、すっかり馴染みあるものになった。
春の暖かい日が差し込む窓のそばに座っていると、シャシャテンが美央を連れて清隆の隣に腰を下ろさせた。丁子色の髪を明るく光らせ、妹は黙って指示に従う。
「本当は信も呼びたかったのじゃが、奴も急では困るであろう。それに肝心なのは明日じゃからな。今日はただ、そなたたちにはどうしても言っておかねばならぬと思っただけじゃ」
わざとらしく大きな咳をし、シャシャテンは文机に置かれた手紙を清隆たちに見せ付ける。いつものようにうねった崩し字で書かれているかと思ったが、文面は幾分字体が直線的でしっかりとしている。旧字体で読みにくい字もあるものの、これまで四辻姫からとして届いた文よりは内容が分かりやすい。
「これはな、あの山住城秀から送られたものなのじゃ」
その名にはぼんやりと心当たりがあった。シャシャテンが日本に来る前から思い合っていたという人物だ。四辻姫やその周辺の話題が多かった分、彼についてシャシャテンが話すことはあまりなかったが。
「それで、奴が私たちにこの家で話がしたいそうじゃ。近ごろ瑞香で広まっておる、梧桐宗なるものについてじゃとよ」
思いがけない来客の予定に、清隆は耳を疑う。わずかにしか話を聞いてこなかった者がいきなり自分たちの前に現れるとは、すぐ実感できない。そして清隆には、もう一つ疑問があった。山住が伝えたがっている梧桐宗とは何なのか。
「怪しき教えを信ずる者たちと言うべきかのぅ……。何でも、不老不死を目指しておるらしいぞ」
「そんなこと、本当に達成できると思っているのか」
清隆の問いに、シャシャテンも首を傾げている。不老不死は目指す人こそいたと知っているが、成功した例は一度も聞いていない。夢のような話が、そもそも実現するのか。
そして不老不死の話に、清隆はまた別の事件を想起した。去年の秋、日本を怪雨や通り魔で騒がせていた組織「越界衆」は、不老不死を願うような紙をばら撒いていた。長である伊勢千鶴子が死亡した後もあの組織はしばらく活動していたが、先日四辻姫が即位した後に解体されたとシャシャテンに聞いた。しかし同じ不老不死を求めているらしい「越界衆」と梧桐宗には、関係がないようには見えなかった。早速清隆は、居候にそれを尋ねる。
「よく覚えておったのぅ。恐らく、奴が明日に教えてくれるであろう」
少なくともシャシャテンは、現時点でほとんど知らないと言い切る。梧桐宗は今まで細々と活動していたが、大友の死後になって急に大きく動きだしたという。それに四辻姫が危機感を持ち、臣下に対処を命じた。山住はまず、故国を離れているシャシャテンに現状を詳しく報告するため派遣されるそうだ。
「しかしせっかく日本に来るのじゃから、私は奴にそなたたちのことも知ってもらいたいのじゃ。伯母上にも恩人と伝えておるしのぅ」
そこで信にも会わせたいと話すシャシャテンを、いったん押し留める。まず彼に予定が空いているかを聞かなければならない。清隆は信に連絡を入れ、シャシャテンの事情を話した。
『えっ、山住さんって……ああ、シャシャテンの! わかった、行くよ!』
逸っているような声が、呆気なく急用を受け入れた。向こうの迷惑になっていないか不安に思いつつ、清隆は通話画面を閉じる。どうやら信は、シャシャテンと瑞香で親しい山住のことを、知りたくてたまらないようだった。
「それで二人とも、城秀の何やかやを聞きとうはないか?」
「別に何も?」
真っ先にそう発したのは、妹だった。人間関係に興味のない彼女は、身近な居候の思い人も眼中にないようだ。その返事が予想外だったのか、シャシャテンの表情が固まったまま清隆へ向けられる。黙っているが、何を問いたいのかはおのずと理解できる。
「知りたいことはあるが……明日会えるんだろう」
「そのためにあらかじめ聞いておきたいことはないかと言っておるのじゃ!」
袖を振って叫ぶシャシャテンにせめて何か言いたいと、清隆は質問を考える。知らないことが多いはずなのに、なかなか頭に湧いてこない。ようやく浮かんだのも、ここ一年を踏まえての感想じみたものだった。
「シャシャテンは山住よりも四辻姫の話をよくしていた気がするが、山住にはそれほど興味がないのか」
「そんな訳がなかろう! 話す時分を見失っていたのじゃ。伯母上が教えてくださることの方が、そなたたちには大事かと思ってのぅ」
確かに清隆たちは、主に四辻姫の手紙を発端として、日本で瑞香と絡む事件に関わってきた。それに彼女の情報には、瑞香の現状とされることが記されていた。――朝重家が持っていた資料にまつわる騒ぎのように、うやむやで終わった件もあったが。
「奴の書いておったことも、ほぼ伯母上と変わらぬものが多かった。加えて我ら内々に留めておきたい話もあった。……ところで、前から気になっておったが」
シャシャテンは膝を進め、清隆と美央の目を順番に見ていく。それからこちらの耳が痛くなるばかりに怒鳴り付けた。
「そなたたちは良い年をしおって、まだ人を思うことも知らぬのか!」
兄妹二人に揃って相手の影がないと、居候は勘付いていたらしい。気になる人はいないか迫られ、清隆も美央も同じ答えを告げる。それを聞いた瞬間、シャシャテンは落胆したように肩を落とし、ついには畳へ音を立てて倒れ込んだ。
「そうじゃ、清隆。そなたに香をたきしめて文――年賀状じゃったかを届けた者がおったろう。あの者は――」
「先輩のことか。あの人は違う」
吹奏楽部に入る前、その態度から年上と誤認してしまった同級生・八重崎についても、清隆はそうだと受け入れない。彼女が自分以外にも香り付きの年賀状を送った可能性もある。
八重崎の名が出てきて、清隆は彼女にまだ瑞香を教えていないと気付いた。大友に狙われた件で心配させた彼女に、事実を伝えなければならないと考えているうちに、時間が経っていたのだ。しかしどのように言ったら納得してくれるだろうか。目の前で寝転がったままの女が居候してきた時も、しばらく瑞香を信じられなかった自分を振り返り、清隆は軽く俯いた。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
