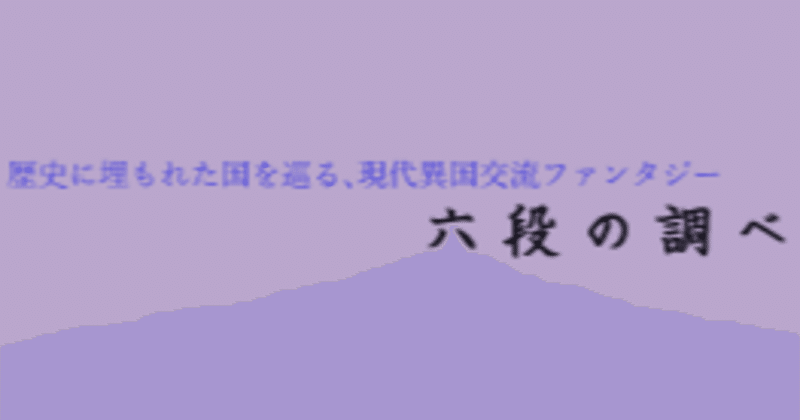
六段の調べ 序 三段 二、宮部玄
前の話へ
序・初段一話へ
屋敷の扉前では、何人かの門番がシャシャテンを見るなり頭を下げた。彼らの視線を受けながら、清隆は玄関で靴を脱ぐ。冷たい木張りの廊下には、山より吹く肌寒い風が吹き込んでくる。左右に並ぶ部屋は青竹で出来た簾――青簾によって中が見えない。突き当たりの部屋から女官と思しき人々が出てきて列を作り、シャシャテンに礼をした。彼女に続いて清隆たちが通り過ぎると、女官の多くはひそひそと声を立てる。それが陰口を言っているようにも聞こえ、清隆は密かに腹を立てた。
「そなたたちが珍しいのじゃよ。衣も瑞香とは異なるからのぅ」
シャシャテンにそう言われても、清隆はすぐ受け入れられなかった。やがて廊下の角にある大広間向かいの部屋へ案内される。シャシャテンが青簾の先に声を掛けると、女の返事が聞こえた。声の主が四辻姫だろうか。
合図があったら入るよう清隆たちに言い、シャシャテンはそっと青簾を上げる。そして次の瞬間、彼女の姿は見えなくなっていた。髪先が部屋に残るほど長い女が廊下に飛び出し、シャシャテンに覆いかぶさっている。
「むつ、会いたかったぞ! どこか患ってはおらぬか? 日本の者から無下に扱われてはおらぬか?」
シャシャテンが止めるよう言っても抱き付いたたままの女に、清隆たちは声を失う。彼女は何者か疑問に思っていると、ようやく解放されたシャシャテンに伯母の四辻姫だと紹介された。やり過ぎと思えるほど姪を心配する様子からは、かつての為政者であった威厳とは別の恐ろしさを感じさせる。『芽生書』奪還にあたって、これから彼女を協力者とすることに清隆は若干の不安を覚えた。
帳台に移って座し、態度を改めて名乗る四辻姫に清隆たちは頭を下げる。赤い袴の上に衣を何枚も重ね着た元女王は、こうして見ると風格がある。部屋の調度は、平井家にあるシャシャテンの部屋とも似ていた。引き出しに金銀で模様の描かれた箪笥や葛籠が配され、そして文机には読みかけらしき手紙が広げて置かれている。内容が気になったが、四辻姫が慌ててそれを懐に隠してしまった。
「そなた達のことは、むつから聞いておるぞ。姪が日本で難儀をさせてはおらぬか?」
「むつ」というのが六段姫であるシャシャテンのことだと気付き、清隆は答えに迷って返した。
「少しやかましいですが、瑞香の話を聞けるのはためになっています」
「やかましいとは何じゃ!」
すかさず突っ込んできたシャシャテンを見て、息災そうだと四辻姫が喜ぶ。しばらく笑っていた彼女だったが、やがて本題に入るべく表情を険しくした。
「さて、『芽生書』じゃが……そなた達にはまず、都に行ってもらいたい」
ひと月ほど調べて分かった現在の所持者は、宮部玄という箏教師だった。かつては大友にも重用されていた楽師だったが、二年前から都で町人に箏の手ほどきをしている男だ。誰もが聞き惚れる音色を奏で、箏を好む者は皆、彼のもとへ向かうという。身分問わず教えてくれる故に、彼の手習いには多くの人が訪れているようだ。
「奴は如何なる時でも、箏を習いたいと言うのであれば快く手ほどきをするそうな。そこでじゃ、そなた達には手習いを受ける者の振りをしてもらいたいのじゃよ」
『芽生書』は手習い場の中にあり、具体的な隠し場所は分かっている。既に四辻姫から正体は伏せて予定を入れており、宮部の隙を突いて巻物を持ち帰ってもらいたいとのことだった。教え子に扮するとはいえ、箏を弾くという点に信が首を傾げる。
「怪しまれないやり方だとは思いますけど……おれ、楽器できないからなぁ。清隆のほうがずっと上手いんですよ。お箏もずっとやっていて――」
この男は実際に聞いてもいないのに「上手い」などと言っているのか。やたらと自分を持ち上げる信を清隆は止めようとしたが、四辻姫には感心された。
「まだ日本にも箏を嗜む者がおったのじゃな。喜ばしきことじゃ。きっと宮部も舌を巻くやもしれぬ」
過大評価されている気がして、清隆はじっと信を睨んだ。それも無視して、隣人は初めて触れる楽器への不安を隠さず四辻姫に訴える。しかし元女王は聞かず、結局うなだれながら信も都行きを了承した。
「しかしそなた達は、珍しき有様じゃのぅ。これでは宮部にも怪しまれかねぬ」
四辻姫が廊下に向けて声を掛ける。彼女は入室した女官に、町人に見える衣を三つ持ってくるよう頼んだ。シャシャテンも王女だと勘付かれないよう、身をやつす必要があるらしい。
女官が着物を運んだ後、清隆たちはシャシャテンと離れて空いた部屋へと案内された。奥には掛け軸や空の花入れがあり、床下に炉が埋まっている。茶室なのか気になったが、清隆が尋ねる前に女官は姿を消してしまった。
「着物って、どうやって着るんだっけ?」
渡された衣と帯を広げるもてこずる信を見ながら、清隆も着付けが出来ず手を止めていた。和服を自分だけで着た経験はない。とりあえず着物を羽織ったものの、続きが分からない。このままシャシャテンや四辻姫を待たせるのも迷惑だ。清隆は廊下に顔を出し、たまたま歩いていた女官に声を掛けた。着付けを手伝ってもらう中、一人で服も着られないことを笑われる。清隆は自分の不勉強を恥じ、着替えている間も軽く俯いていた。
再び不死鳥に乗り、都の入り口だという羅城門の前に着く。柱の朱色が鮮やかな二階建てのそれをくぐると、市井の賑わいが清隆の耳に入ってきた。行商人がものを売り歩き、道の左右には店棚が並んでいる。人々の身なりは整っており、それぞれ笑顔を浮かべながら日常を謳歌しているように見える。しかしその裏で、人知れず苦しんではないだろうか。
シャシャテンはここへ行く前、大友を非常に悪く評価していたが、それを一方的に信じも出来ない。しかしこの平和な情景だけで瑞香の全てを理解することも、浅はかなように清隆は感じた。
「この辺りものぅ、戦と地震で荒れておったそうじゃ。それをここまでよくぞまぁ……」
気になった店には片っ端から行こうとするシャシャテンを引き留めつつ、清隆は不死鳥の背で見た海辺の光景を思い出して息をついた。都から離れた場所はともかく、ここは人が多く栄えているようだ。道にはごみが一つもなく、井戸も備えられている。もっと町中をよく見ようとするうちに、清隆はシャシャテンたちから離れていた。
「もし、そこのお方。よろしければわたしとお茶でもいかが?」
後ろから袖を引かれ、清隆は振り返る。こぎれいな着物に身を包み、髪を高めに結った町娘が茶店を指差している。用があると言って断ると、どこへ行くのか聞かれた。宮部のもとだと返すなり、娘は感嘆しながら彼の世評を嬉々として語りだした。手習い場から流れる音だけでも、宮部が優れた楽師だと分かるらしい。
「嘘ではありませんよ。ぜひあの方から多くを学んできてくださいね!」
町娘が去った後、今度は腕を取ってきたシャシャテンに清隆は引き寄せられた。瑞香の女は積極的だと言う彼女の話が、今の出来事で何となく納得できた。しかし全員が全員ではないだろう。そう思いつつ、なるべく話し掛けられる隙を見せないよう、清隆はシャシャテンたちとぴったり歩いた。
宮部の営む手習い場は、都を東西に分ける大通りの北部にあった。一見両隣の店と変わらぬ平屋建てで、縦格子の小さな窓からは畳の敷かれた広めの空間が見え、琴柱の立てられていない箏が壁に何張かもたせ掛けられている。その奥には別の部屋へ続く障子があり、宮部はこの先にいるかもしれないとシャシャテンが呟いた。
細かい柄の入った小袖をきっちり着ながら、大通りで見掛けた女たちと違って長い髪はまとめていない。これでも町人の装いだと屋敷を出る前に言い張っていたシャシャテンは、襟元を整えてわざとらしく咳をし、暖簾の下がる戸を叩く。手習いを希望したいと彼女が大声で頼むと、四十にならない程度に見える風貌の男が顔を出した。前髪の右側だけを少し長めに伸ばし、垂れ気味の目は温和な印象を与えている。宮部は快く清隆たちを中に入れ、畳の上へ並んで座らせた。
「ようこそお越しくださいました。あまり見ない方でございますね。お名前は?」
前に座す教師に促され、清隆たちに続いたシャシャテンが偽名で通す。宮部はこちらを怪しむことなく、箏爪を取ってくると言って奥の部屋へ入っていった。帯を斜めに結んでいるその背が障子で見えなくなった後、シャシャテンが壁に寄り掛かっている箏を数え始めた。右から六番目の箏を指差すと、彼女はそっと立ち上がって壁と箏の間に手を入れる。すぐに取り出したそれには、見覚えのある巻物が握られている。シャシャテンが懐に押し込んで元の位置に座った直後、宮部が戻ってきた。
彼が見せた小さな箱に入っていたのは、清隆が中学時代に習っていた箏のそれとは違う、幾分細長い箏爪だった。各々の指に合うものを選ばせてから、宮部は壁の楽器に目をやる。
「わたしが教えているこちらの箏は、筑紫箏と呼ばれています。わたしはこれを若き折からやっておりまして――」
二時間ほどして、正座で痺れた足を震わせて手習い場を出た信は、窓の格子に手を突いた。そのまま、落ち込みを隠さない。彼はなかなか練習について行けず、糸の場所も分からなくなった末に宮部から笑われたのだった。
「小僧、散々じゃったのぅ」
気の毒に思っているのかも分からないシャシャテンは、懐に手をやって誇らしそうにしている。とりあえず『芽生書』は得られたのだから安心だと言い切る彼女を見ながら、清隆はずっと浮かんでいた疑問を零した。
「あんな見つかりそうな場所に置くのは、逆に怪しくないか」
『芽生書』が重要で簡単に盗まれて困るのなら、宮部は奥の部屋に保管すべきだっただろう。それを誰でも見つけやすそうな所に置くなど、逆に盗んでくれと言っているようにしか見えない。むしろ取られることを望んでいて、裏で何かを企んでいるかもしれない。
懸念を持ったまま、先を行くシャシャテンたちに遅れないよう清隆は足を速める。その直後、筑紫箏を手引きした男の声が背後に聞こえた。
「どうやらお望みが叶いましたようで、姫様……」
清隆たちは振り返り、宮部が外に出ているのを認める。彼が履く下駄の足音が、少しずつ迫ってくる。
「聡いのはお一人だけでございましたか。今さら気付かれても、もう遅い。姫様は既に、罠に掛かっておられます」
シャシャテンが言い返そうとした時、気が付けばすぐ近くにいた宮部が彼女の片腕を掴み、指笛を強く吹き鳴らした。昼下がりの光が一気に遮られ、翼を広げた巨大な鳥が下りてくる。それが不死鳥だと清隆にも分かった瞬間、シャシャテンも空いた手で指笛を長く吹いた。そして懐に手を入れ、『芽生書』と共に念のため持っていたのであろう短刀を清隆たちに投げた。すかさず腕を伸ばした清隆は、短刀を受け取りは出来たが、『芽生書』には届かなかった。落ちた巻物を宮部が拾い、袂に入れる。そのまま彼はシャシャテンの袖を引っ張り、自身の呼んだ不死鳥に乗せた。シャシャテンの抵抗も聞かず不死鳥は飛び去り、宮城の方へ飛んでいく。
「宮部、これはどういうことだ」
戸を開けて中に入ろうとする宮部に、清隆は問う。箏を教えていた時と同じ穏やかな顔と声で、教師は答える。
「陛下からのお頼みでございます。姫様は間もなく、瑞香ではほぼ十年ぶりに行われる責め苦をお受けになりましょう」
シャシャテンの呼び寄せた二羽の不死鳥が来たころには、宮部は手習い場に戻っていた。不死鳥に事情を話すと、まず四辻姫の屋敷に戻るよう勧められた。清隆はすぐにでもシャシャテンのもとに行きたかったが、信に止められる。
「気持ちはわかるけどさ、シャシャテンの場所も知らないのに助けに行くなんて無理だよ。ここは四辻姫さんに、作戦を練ってもらったほうがいいんじゃない?」
確かに彼女の案で、『芽生書』の入手には一度成功した。姪の危機とあらば、彼女もすぐ動いてくれるだろう。清隆は頷き、薄雪山へ戻ることにした。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
