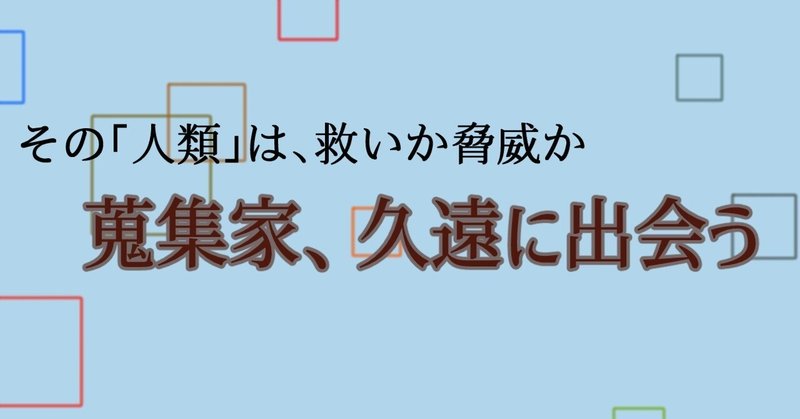
蒐集家、久遠に出会う 第二章 一、国蒐構は止まらない
前の話へ
第一章一話へ
年の瀬が迫ろうが、国際蒐集取締機構の人間に予断は許されない。二十六日であるこの日も、所沢雲雀は捜査対象の団体を押さえるべく通勤していた。日本支部に蒐集団体「早二野」捜査部が誕生したのは、「楽土蒐集会」の騒ぎが終結して間もない十一月の半ばだった。以前の捜査時に「早二野」と接触していたことを買われ、所沢は長として新たに配属された五人の部下と共に、団体の集中的な捜査といずれの逮捕を任された。地上三階にある専用の部屋で長机を囲み、今日は全員でここ最近あった「早二野」の動きを確認する。
近ごろの「早二野」は「蓬莱継承会」の施設で蒐集を行っていたかと思えば、彦根直なる人物と関わっているという。そして姫路好古の住むアパート周辺を、構成員である屋久島真木が探っているのを見掛けた情報も届いた。恐らく蒐集前に行う偵察だろう。
「そしてこの彦根・姫路双方に共通する点として、久遠研究所という施設に属していたことが明らかになりました。姫路好古は既に退所したそうですが」
正面の部下が報告するのを、所沢はじっと耳に入れる。何を研究しているのか問うと、久遠と呼ばれる人造人間のことだと返された。話を聞く限り、ただの人に似せたロボットのように所沢は感じる。その容姿も動作も人のものと変わらないというが、いまいちぴんと来ない。工場などで使われているロボットとどこが違うのだろう。
彦根が頼んだと思われる件の前に、「早二野」が蒐集していた品を振り返る。あの茶運び人形は、「蓬莱継承会」のもとにあったものを盗んでいた。普段はそうやって別の団体から美術品やらを得ている「早二野」が、今回は何のために久遠を作る者と関わっているのか。ここは率直に、彦根へ聞いてみるのが良いかもしれない。異世界を匂わせるような発言をしなければ、一般人が原則へ触れることを防げるだろう。
「――ということで、私が久遠研究所へ直々に赴くことにします。皆さんはここに残って、『蓬莱継承会』にまつわる調査を継続してください」
「待ってください、所沢さんだけ頑張らなくても良いじゃないですか!」
隣に座る部下が言うのに続いて、残りの四人も一斉に同行を求めた。部屋の奥側にある机の角から彼らを見回し、所沢は息をつく。今の仲間たちは、「楽土蒐集会」捜査時に関わっていた者よりずっと良い。真面目に働いていたか怪しかった人々とは違い、しっかりと仕事をこなしている。いずれ「早二野」の逮捕にも至れるだろう。そして蒐集家がさらなる罪を犯す前に、やってほしいことがあった。
「『早二野』はいずれ、『蓬莱継承会』とも本格的に関わることになるかもしれない。悪い人なんて言っていた『楽土蒐集会』の品を集めている組織だから、また突っ掛かりに行くでしょう」
まだ「蓬莱継承会」を追う捜査部が設立されていない中、未然に被害は防いでおきたい。「早二野」と同時に「蓬莱継承会」を叩ける期待をいったん抑え、所沢はここへ留まるよう部下へ求めた。彼らに何度止められようとも振り切る。外へ出てこの目で現実を確認して持ち帰る方が、部屋で報告を待ち続けるよりずっと良かった。
そうして一人で電車に乗る間、所沢はこれから向かう久遠研究所を調べていた。スマートフォンの小さな画面に映る人間そっくりな存在の写真を、指で拡大して凝視する。公式だと思われるサイトでは、研究所が人工知能と最新技術を統合させた結晶として、久遠の名を伏せて紹介していた。施設内らしき机や器具の並ぶ背景の前に、久遠は佇んでいる。睫毛や爪といった細かい部分まで人間そのものであり、これが人工的に作られたと言われても信じられない。
だがじっと写真を見ているうちに、所沢は不自然な点に気が付いた。身長こそ差はあれど、体型はどの久遠も似たり寄ったりなのだ。痩せ過ぎも太り過ぎもない標準的な姿で、男女の違いも分かりづらい。大元は機械だから、見た目の問題は関係ないのだろうか。それにしては顔立ちが割と整っているように思えるが。
まばらに乗客が乗る車両の中で、所沢は周りに聞こえないよう息をつく。何気なくブラウザの画面を一つ前へ戻し、サイトのトップページへ移る。ぼうっと眺めていた画面の一点に、ふと所沢は引き付けられた。同時に汗が額から吹き出しそうになり、喉が渇いていく。換気している窓から冷たい風が入るのも気にせず、文面を何度も読む。もうすぐ降りる駅だというのに、久遠研究所を訪ねる際には事前予約が必要だと今になって判明してしまった。
改札を出ると、目立った高層ビルのない代わりに自然や小さな商店の目立つ穏やかな風景が眼前に広がった。気を取り直し、所沢は制服を整えて歩きだす。自ら行くことを申し出たからには、収穫もなしに部下たちのもとへ引き返すなど出来ない。駄目元でも久遠研究所へ押し掛け、今日が無理なら出直せば良いのだ。喫茶店などのある駅前の通りを抜けてしばらく道を行き、やがて周りに建物のほとんどない辺りに辿り着いた。町の活気からぽつんと取り残されたように、その施設は大部分が枯れかけた草地の上に鎮座していた。
ここが久遠研究所であると確かめ、所沢は三階建てのそこへ入る。受付で国際蒐集取締機構の者として捜査を行っていることを伝えると、職員が戸惑いを見せた。やはり一般に知られていない組織を説明するのは骨が折れる。しかし捜査のためならと、予約もなしに関係者へ会うことを間もなく許された。
一階の応接室に、面会を求めていた彦根直が現れた。急な来訪と呼び出しを謝り、所沢は相手と揃ってソファーに座る。テーブルを挟んで向き合う男に、自分の役割と蒐集家の詳細を教え、「早二野」と関わったか率直に尋ねた。
「はい、あの方たちにはお願いを申し出ました。といっても、昨日の夜に行われたそれは失敗したと先ほど聞きましたが――」
「蒐集活動、ということで間違いありませんね?」
所沢の念押しに、彦根は顎を掻いて頷く。彼が「早二野」へ蒐集を求めた品は、到底現実味の持てないものだった。何でも、実際に生きていた人間をそのまま模倣した久遠だという。改めて、久遠という人造人間は自ら思考を持って動き、生命維持に必要な食事などを除く人間の活動を自動で行うことを聞いた。この世界の技術を集めても、それが叶うだろうか。ふと湧いた疑いをひとまず隅に置き、所沢は別の質問をする。
「彦根さんはその『早二野』を、どこで知りましたか?」
「友人に教えられた……こちらのアプリです」
その友人が異世界人を妻にしていると伝えて、彦根はスマートフォンの画面を見せてきた。表示されている内容に、所沢は顔をしかめる。国際蒐集取締機構でしか知られていないはずの蒐集家にまつわる大きな動きや、異世界で起きた事件の見出しが並んでいる。試しに開いてみると、詳細を記した文まで現れた。この「新世界ワイド」は、異世界の情報を伝えるメディアアプリとのことだ。
「……原則崩壊も、ここまで来たか」
小さく呟き、所沢は胸がちくりと痛むのを覚えた。自分が思う以上に、異世界を知られることを防ぐ対策は遅れていた。国蒐構という組織自体、現実で蒐集家が起こす事件はともかく、ネットを介した情報の行き来を止めることには積極的でなかった。技術の発展に対応が追い付かず、結果的に後回しとなったのだとも聞く。彦根のように蒐集家と縁のなかった人もこうして情報を手に入れるとは、いずれ起こることだとは思っていた。もはや異世界を行き来する存在は、昔から懸念されていた蒐集家だけではないのかもしれない。
戻ったら上層部へ伝えるべきか、所沢の脳裏に迷いが駆け巡った。蒐集家以外の人間を問い詰めるのは、駄目だと判断されかねない。彦根が異世界の件に触れたことは、国蒐構とは違う別の機関が絡む可能性もある。あまり思い出したくない組織がよぎり、所沢はわずかに下唇を噛んだ。
「――刑事さん。わたしがその蒐集家に依頼をしたということは、わたしも犯罪に加わったとして逮捕されるということでしょうか?」
彦根に言われて、所沢はひとまず首を振る。「早二野」は結局、二条元家なる久遠の蒐集に失敗した。それならこの件には、もう関わらなくて良いのだろうか。だが「早二野」自体を追うことは、もちろん続けなければならない。情報開示への感謝を告げると、彦根は深く頭を下げて部屋を出て行った。
所沢も国蒐構の施設へ戻ろうとして、扉を開けて入ってきた人物に姿勢を正した。日焼けをしているのか生まれつきか、浅黒い肌を艶やかに光らせた長身の女が入ってくる。それに続いて彼女より背の低い、複数の花びらが縦に垂れ下がったような桃色の髪飾りを付けた男が小さく何度も礼をし、所沢の前に立つ女の隣に並んだ。
「この度は私どもの部下が勝手をしてしまい、申し訳ございません。わざわざ捜査のためにご足労をお掛けしました」
深志百花と称する女に、所沢は挨拶をしてから名刺を渡す。深志が怪訝にそれを眺める中、隣の男が慌ただしく小さな紙を差し出してきた。久遠研究所所長という文言を、所沢は二度見する。
「すみません、所長は紙でのやり取りに慣れていないもので――。名刺交換のアプリなんて、入れてないですよね?」
申し訳ながらに肯定すると、男は深々と頭を下げてきた。それを窘めた深志が、彼を秘書の林長時だと明かす。
「宜しければ、ぜひ我が研究所を見ていただきたいのですが……お時間はございますか?」
深志に聞かれ、反射的に所沢は受け入れる。そのまま所長と秘書直々に、大規模な建物を案内されることになった。久遠に内蔵する機械や表面を覆う肌をロボットが製作する現場から、何やら流通がどうのと聞こえるリモート中心の会議まで、短い時間ながらも見学する。これほどの施設が都心部を離れた場所にあることが、所沢には驚きだった。そしてここへ来る前から薄々勘付いていたことを、深志ははっきりと伝える。
「私たちがこの世界で普及を目指している久遠は、私の故郷である能鉾で誕生したものです。いくら硬い掟があろうとも、いずれ久遠がこの世界で人々の役に立つことを私は確信しています」
「……あなたは、ご自分の行いが原則に引っ掛かることを承知で活動を続けているのですか?」
機械の製造過程が見える窓のそばで、所沢は問う。異世界の情報や物品を持ち出して広めようとすることは、この世界では禁じられている。深志たちは異世界と縁がありつつものを手にする蒐集家ではないそうなので、国際蒐集取締機構が今後介入することは考えられないだろう。だがそれとは別に、最近ごたごたしている統制局の方が動くかもしれない。懸念が取れないままでいると、深志が強い語気で反発した。
「私たちの動きを止められる筋合いはありません。この世界を良くするために、久遠を広めようとしているのですから。既に異世界の存在は、貴方がたが追っている蒐集家以外にも知られているのでしょう? 異聞秘匿原則など、もはや過去のものではないでしょうか?」
一重の中にある黒い瞳で睨まれ、所沢は言い返せなくなる。先ほど見た「新世界ワイド」が蒐集家以外に使われていることが、頭の中をよぎった。体が全く動かなくなった捜査官へ、研究所の所長はさらに続ける。
「科学が、機械技術が発展すれば、どの世界もより良いものになります。現に私の故郷たる世界は、そうやってどこよりも先進的で優れた場所となっています。ここだって遅れてはいけません。仮に久遠を利用すれば多くの問題が解決するでしょうに、なぜそれを躊躇うのですか? 今この時にも、労働や家事によって人間は体力や精神を消耗させられているというのに!」
次第に声を大きくして息巻く深志は、どこか危なっかしかった。頼りにしている科学や技術を、妄信しているようでもある。あの世界の住人は、機械文明こそ発展へ導く最上のものだと豪語してならない。いつぞや耳にした話を、所沢はこの場でひしひしと理解するに至った。
腕時計をちらりと見ていた林が、そろそろ時間だと小声で告げる。落ち着いた態度を取り戻した深志は、今後の捜査をねぎらって踵を返していった。すらりとした体型を目立たせる黒のズボンから、音を立てて何かが落ちる。気付かずに秘書と去り行く深志の後ろで、所沢はそれを拾って目を凝らした。
ぱっと見る限り、ヘアピンで留める形式の髪飾りだった。だがピンの部分は歪んでおり、本来なら髪を挟む部分がくっ付いて離れなくなっている。桃色の花びらが縦に並んだ装飾も形がいびつで変色しており、焦げ目がいくらかあった。二人の姿が遠くへ消えそうになり、所沢は急いで駆け寄った。
「あの、こちらは深志さんのもので間違いないでしょうか……?」
振り返った深志が所沢の手元を見、驚いた様子で品を受け取る。所長と共に、林も丁重に礼を述べる。彼の揺れている髪飾りを一瞥し、所沢は息を呑む。案内人たちが去った後も疑問が脳内を巡って止まらないまま、やがて短く唸った。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
