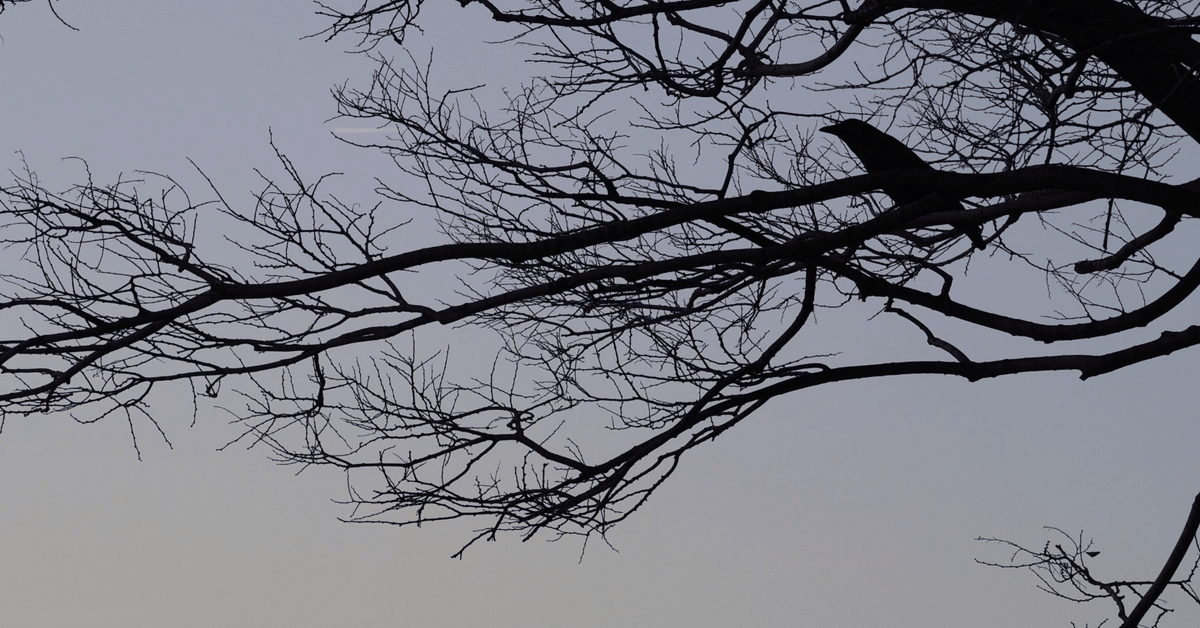
王冠の行方
『体験それ自体が権威である。ただしこの権威は自らを断罪しなければならない。』
この言葉の意味が最初は分からなかった。しかしながら、今ならば少しだけでもこの謎めいて文に一筋の解釈を乗せることが出来る。
体験とはつまり、新たなる境地に達することである。昨日まで見たことの無かった景色に、昨日まで目覚めなかった朝に、昨日まで信じられなかった天体の公転面に、私達が対面した瞬間の事を『体験』と言えるのかもしれない。体験は、それ自体が権威に対しての急所をえぐる槍になり得るものだ。
権威とはつまり、他者を圧倒する力である。人々に威光を示し、上下の感覚器官を生じさせるものだ。昨日まで続いた法律は明日であっても有効であり、昨日まで存在した山と海は揺るがぬことなくあり続け、昨日まで崇めていた人称は変わること無く崇め続けられる。権威とは上下を作り出し、そして一定の秩序を生み出す存在である。
体験と権威はそれぞれ相対すると考えられてきた。今でさえももしかしたらそうだと、私は思っているかもしれない。だが、ここで一つ思考を整理しておこう。体験それ自体が権威となるのはなぜなのかの根本的な構造を見つけなければならない。
権威は持続を要求する。それは一秒の持続ではなく、人が想像しうる時間と呼ばれるものの、なるべく長くなるような尺度の時間を要求する。曖昧な定義だが許してほしい。だが、ここではっきりと宣言しておくべきことは、例えば、狭い山中の小屋で30日間継続した王権は、それは王権ではないという事だ。
権威は持続を要求する。それは明日の民衆の腹を満たすことが出来なくとも、明日には川の魚が垂れ流される毒によって死滅したとしても、揺るぐことがない威光を権威と呼ぶ。破滅が確約されていない権威は存在していないと思うが、その破滅がいつ来るか分からないというのがまた権威の一つの特徴でもある。つまり破滅による転覆の来る瞬間が、きっかけが起こらない限り永続的に続く。この性質を、権威の半持続性と呼ぶ。
また権力に属する若者が、放蕩の末に、どこぞの阿呆と添い遂げ、国外で自国の国民の税金をつかいながら居を構えたとしても、根本的に権威が揺るぐことがないのは、権威それ自体に力が無いからだ。このから言えることは、権威はそれ自体に力が無くとも、それに影響されるものに対して一定の秩序を作り出す作用があり、その秩序こそが権威と服従者の間に引かれている繋がりでもある。つまり、裸の王様を掲げているのは、掲げていることによって、服従者は(ある程度に)潤滑に物事を運べる利点があるのだ。自分ではかぶれない王冠であっても、自分達が暮す空間に王冠がある事自体が、被れない者達に多大な利益を生み出している。つまるところ、権威は目に見える形で存在しなくとも、それを信じる者達の心、服従者の心、王冠をかぶれない者たちの心、の中に存在しているのだ。この性質をまとめると、権威の有効性と呼ぶ。
面白いことに権威の半持続性と有効性は互いに影響を及ぼし合っている。明日も続くから権威は有効であり、今日有効であるならば明日も続くだろうという具合に、互いに互いが助け合う循環の構造になっている。
それでは、体験の側に立ってこの権威を潰すことを考えよう。
ある一人の少年を生贄として差し出そう。この少年は酷く過酷な環境で産まれた。教育は幼少期から始まり、上下関係は父親の高圧的な克己心から煽りを受け、弱者へといたわりは年の離れた病弱な兄への周囲の態度から学び、自己矛盾の中にある自己を片付けのできない母親から刷り込まされ、他者への絶対的な隔たりをまた違う兄から教え込まされてしまった。
この少年にとっては生きる社会が狭すぎた。家の中ではただ日々不満を垂れる家族の一員の気持ちを考え、学校では無為に等しい教育を施される。それが延々と続く日を思い出してほしい。罵声と狂乱が繰り広げられる日々は少年にとって痛ましい事実として心に刻み込まれたが、親と教育者モドキが施した『あなたは、まともだから』とその言葉を胸にして、『もっと我慢できるよね?』と投げかけられる呪詛を生命の源として生きてきた。
少年の心にはいつしか、『この環境で余裕があるのは自分なのだから、もっと自分に無理を強いるべきだ』と考えていた。事実として、この呪いにも似たマインドは一定の効力を持っていた。無意味に見える勉強に己を忘れて取り組み、自分が最も欲しい遊びの経験を忘却へと追いやることに少なからずの年数を費やすことが出来た。自らが望みに蓋をすることによって、過酷な環境を乗り越え、強いられる苦境に順応することができるようになっていった。
その代償として、少年はまだ何も知らぬ頃には日常的に繋がることができた「生きる」という事を忘れていく羽目になった。今日何かを食べるのは、今日のどの瞬間にも兄弟が狂乱の声を上げながら家の中を駆けずり回るのに備えるためになり、今日何かを学ぶのは、明日のどの瞬間のために自らの地位と学績をもって弱者を助けるためだと信じるようになった。つまるところ、少年は現在の時間に生息できなくなった。既に行動の規則が未来に起こる事態のための、つまり未来に自らが存在しているためと、一般的に肯定されている『権威』の前に自分を差し出したことになった。
少年は悩んだ。未来に自分や自分の環境が好転するために、自らが生きる現在の時間を亡きモノとして扱わなくてはならなくなったのだ。そしてこの未来のために現在を捧げるべきだという『権威』があまりにも強烈で、否定できなく、そして広くこの世界で認められている様相が少年の居場所を叩き潰していた。
今日より明日。今日より明日へ。よりよく生きるために。
この言葉はどこにも矛盾なく、人が頷ける言葉だろう。少年もこの言葉に自らの首を、厭わず縦に振っていただろう。
明日より今日この瞬間。明日よりも今日、この一日。よりよく生きることなど知らぬのだから。
この言葉にはどこかしら、不安に陥る自分か、もしくは享楽的に人生を無為に費やそうとする傍若無人な男の姿を想起させる。このような男を少年は嫌悪していた。事実として少年はこの世の一部として存在している、博徒、もしくは賭博なるものが諸悪の根源であるとさえ思っていた。
『未来によりよく生きるために』と、この権威から逃げるべき体験を少年は自らに及ぼさなければならない。体験は権威に相対する。この強力すぎる権威に少年はどのようなカウンターを及ぼしたのだろうか?
この先に語ると、この少年は権威に対抗できうる体験を経験できなかった。いやできなかったと言っていい。繰り返すが、権威には有効性がある。自分にとって凄まじく障害になり得る権威でさえも、それによって多大なる幸福を得ている人間がいる以上、少年の反駁は意味を無くしてしまうからだ。権威には「無矛盾性」があるのではなく、ひたすらに「有効性」がありそして「半持続性」がそれを裏打ちしていたからだ。少年が、「生きるのが面白くないです」と上奏しても、「でも、お前の友達は生きていて楽しそうだけどね?」と一蹴され続けた。彼は健気にも「自分の体験」を権威にぶつけ続けた。結果として少年は自らの生命を著しくやせ細らせることによって、悲劇的に生命を延命させることに成功した。
「自分の体験」は権威には著しく弱い。「自分の体験」も体験の一種なのではあるのだが、権威を揺るがすどころか、むしろ権威を強力にしてしまうきらいがある。何故ならば、権威とは少数の人間において成立するものではなく、大多数の人間の曖昧な承認によって結論づけられるからだ。権威は、むしろ、個人の感覚と経験をより強く圧倒しながら粉砕するのを好む。集団を形成する権威は特にその傾向が強い。そのような環境において、苦しむ人間に対して集団は囁きかける。
「お前は苦しんでいるが、お前よりも苦しんでいる人間は数多くいる」
もしくは、
「お前は苦しんでいるが、それを乗り越え、輝かしい場所へと向かった人間を数多くいる」
もしくは、
「お前は苦しんでいるが、その苦しみは幻だ。お前と同じ立場でも笑っている人間は数多くいる」
もしくは……。
とにかく少年が戦いを挑んだ権威は、その性質が強固であると共に、有効に働く権威によって動いている社会で何にも疑いを持たない他人でもあったのだ。自らの体験が集団へと還元されない権威の環境。そして、集団からの影響のみが自らに降り続く権威の環境。少年はそこで潰れてしまった。
彼を弁護するつもりは無いが、今にして思うと少年に違う道を指し示すことを、私は出来ただろう。「そんなに深く考えるな」と「そんなに苦しい場所に自ら飛び込むな」と「そんな自分を許してやろう」と。だが現実として少年は無尽蔵の苦しみへと誘う権威に従い続け、自らを滅ぼす運命を受け入れてしまった。
少年は深くため息をつき、数年の間ベットの上で、眠りにつくことになった。生命としての活動のほとんどを放棄して、閉じこもることによって彼は精一杯の権威への異議申し立てを行った。服従しないという体験を経験することはできなかったが、彼は権威の中の最低の立場にとどまることによって、最低限の異議申し立てを行っていた。
覚醒と夢想の狭間に彼は軸を揺らし、平等に分配された時間をふいにし続けた。
眠りの間、少年は「自分の体験」が権威にとっては紛れもない嘘であるが、自分自身にとっては紛れもない真実であることに気が付いた。自らの体験を自らが否定することは彼にはできなかった。それほどまでに彼は懐疑的ではなく、そして観念的でもなかったからだ。
一つの発想の転換は、さらに多くの天啓をもたらしていた。
少年は自らの体験によって異議申し立てを行った事を後悔していた。
彼自身の天啓によれば、もし権威が「自分の体験」を受け入れ形を変えるか、それか「自分の体験」によって滅ぼされた後に何が残るのかを見せていた。そこに広がる光景は、「自分の体験」の形をした権威そのものだった。体験は権威を殺す槍になり得るが、もしその槍が敵を突き殺してしまったならば、次なる権威は槍となってしまう。さらに言えば、もし槍が突き殺さなくとも、「この槍こそが正当性をもつ」と宣言してしまえば、「槍=体験」が自らの「権威」となってしまうのだと気が付いた。
ここでもう一度思考を整理しよう、体験と権威は相対する概念だと考えていた。だがこの前提こそに大きな矛盾が潜んでいたのだ。体験が正当であると宣言してしまえば、それは権威となにも変わらなくなってしまう。
権威の『未来をよりよく生きるために』と相対する体験の『現在に自分は存在していたい』という主張は、それこそが怒りを込めて正当であると宣言してしまえば体験は権威に墜ちてしまうのだ。
では、少年はどうするべきであるのか?という問いに今やっと答えることが出来る。
結論はこうだ。
『あなたはゆっくりと慌てずに、自らの生命を賭けて生きるのだ』
権威に服従するのではなく、そして自らの体験を権威として槍に錬成することもなく、個人と社会との間を、知り得るモノと知りえないモノの間を、ただ自らを賭すように生きるのだと。確定しない未来に対して、現在に生きる少年の感覚器官をベットして、生きてみるのだと。
もはや、少年は自分に正当性があると怒りをもって宣言することはないだろう。そして、他者が敢行する怒りを持った正当性の宣言も排除するだろう。もはやどこにも軸はなく、ただ確定しない未来を現在にできうる遊戯をもって、自らをベットしようととしか思わないだろう。どうかこれを読む君も、ゆっくりと慌てずに命を賭けてもらいたい。命と時間を、費やし、投資し、犠牲に捧げて、価値あるものとして交換するのではなく、まったく違う次元として賭して貰いたい。遊戯の中で立ちあがる、生命の沸騰をもう一度思い出して欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
