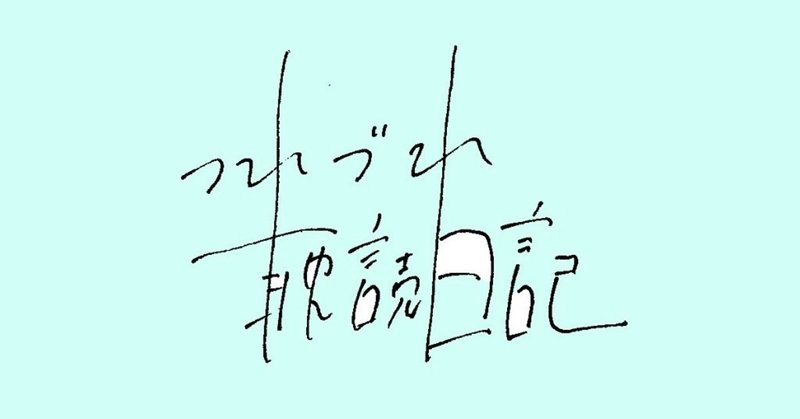
#3 ろうそくと人魚と泡と
夏も盛りである。こうも暑くては外に出られぬ。いやはや参った。
この夏はまだ一度も海に行けていない。ベタ塗したような青さの空を眺めながら、夏ボケの頭の隅で、海を思い浮かべる毎日である。
前回あれだけ海について力説していながら、この有様である。やれ体力の低下だ、人混みが嫌いだなんだと理由をつけて、近年では夏場の海への足が遠のいている。やはり夏を感じるには海だ、とすっかり刷り込まれた海馬が叫び声をあげるのだが、それに負けじと腰はどっかりと重く座して動こうとしない。動かざること山の如しである。やはり海と山は相容れぬのか。ええい、うるさいうるさい。
これではいかん、と発起してみるも、こんな夏真っ盛りに海など行っては、人の波でサーフィンをすることになりかねないし、人口密度が高い場所は遠慮したいところ。そもそも炎天下に身を晒すと分かっていながら外に出る気なぞさらさら起きない。プライベートビーチでも持っていれば話は別だが、生憎そんな洒落たものは持っていない。うむむ。
ひとり黙考しているときに、友人から声がかかった。もう少し時期をずらして海に行かないか、というお誘いである。もちろん海水浴などではなく、砂浜で黄昏るだけである。それならば海水浴場でなくてもよいし、人影少ない穴場でも問題ないし、陽が落ちるころの夕涼みに最適だろうということで、あっさりと予定が決まった。嬉しいかぎりである。誰にも見られぬことをいいことにひとり三日三晩宴をしてはしゃぎまわった。出不精の人間が持つべきものは、やはり友である。ありがとう友。これからもよろしくな友。
そうしてまた、夏ボケの頭で海に思いを馳せながら過ごしている今日この頃である。
夕暮れの海はいつも物悲しい。どこか侘しく、郷愁に満ちている。
日中あれほど燦燦と太陽に照らされ海水浴に来た人の活気と熱気とで、聴覚的にも視覚的にもやかましいばかりの砂浜だが、ひとたび日が暮れると突然静寂が訪れる。疲れ知らずに見える子どもたちも親に抱かれて夢の中。恋人たちは甘い夜を過ごすために帰路につく。潮が引くように、人もまた引いてゆく。薄紫の空の向こうに夕闇が広がる頃、ぽつりぽつりとまばらに海岸に残された人影は、哀愁を誘う。
その寂しさが、私は好きなのである。
陽が沈み、コバルトブルーから墨のように深い黒色へ姿を変えた海を眺めていると思い出すのは、小川未明の「赤いろうそくと人魚」である。
小川未明といえば、日本の児童文学を牽引した人物であり「日本のアンデルセン」と称される童話作家だ。代表作といえば「赤いろうそくと人魚」「金の輪」などがあげられるが、かくいう私が未明の作品で一番最初に触れた作品も「赤いろうそくと人魚」であった。
小学三年生の頃、通っていた学習塾の夏休みの課題に含まれていた読書感想文。課題図書は未明の「赤いろうそくと人魚」だった。課題を出した講師はなかなかに慧眼であったに違いない。その時に母が買ってきてくれた新潮文庫の『小川未明童話集』は、10年以上たった今でも大切に手元に置かれている。
当時の私は感想文に「人魚がかわいそう」と書いたらしい。
「赤いろうそくと人魚」は、陸で育てられた人魚の娘の姿を描いた童話である。
欲に目が眩み、慈しみ育てた人魚の娘を休みなく働かせ、最後には売り払ってしまう老夫婦。それは、人間は優しく慈悲深いものだと信じ、娘の幸福を願い陸に娘を産み落とした母親人魚の目にどう映ったか。信じたものに裏切られた怒りとその根底にある悲しみが、海の大暴風雨となり、また娘の色づけた赤いろうそくを不吉な災難の象徴に変質させてしまった。
けれど、己で見聞きしたわけでもないのに人間が優しいと盲信した母、確かではないのに「人魚は不吉である」と他人の戯言を鵜呑みにした老夫婦、両者は対立しているようでいて表裏一体、似た者同士ではないだろうか。娘の意志に関係なく勝手に選択を下したという点で、彼らは同類である。
母は娘の幸福を願い、人間の世界で彼女が生きることを願った。
では、彼女の幸福とは、一体何か。そんなものは彼女にしか分からない。母の子を思う愛が必ずしも娘の幸福に繋がるとは限らないのだ。
産みの親と育ての親の都合でなすすべなく生を翻弄された無力な娘は、誰かを責めることもせず、只々純真で心根が優しい故にどこまでも悲しい存在だ、と当時の私は感じたのだろう。それをなけなしの語彙力で「かわいそう」と評したのである。
今でも感じることは概ね変わっていない。あれから何度も「赤いろうそくと人魚」を読み返している。歳をとり、己の身の可愛さ故に他者を切り捨てる人間の姿や、親が子へかける願いの心を少しは知った。知ってもなお、いや、知ったからこそ、読み返す度に彼女は幸福であるだろうかと詮無いことばかりを夢想する。
ただ、娘を運んでいた船が海に沈んだのだから、彼女は海へ還ったに違いないのだ。
それを私は羨ましいと思う。
人魚の童話といえば、アンデルセンの「人魚姫」を連想する人は多いだろう。
陸の人間に恋をした人魚姫は、恋を成就させることなく最後には泡となって消えてしまう。悲しいお話だと人は言う。けれど正直、喜劇か悲劇かについては興味がない。
彼女は自身で「泡になって消える」という選択をしたのだ。陸の人間に恋をすることも、海の魔女と契約することも、王子を殺さないということも、全て彼女の自由意志の選択結果であり、選択の末に泡となって消えたのだから、仮に諦念や失望を抱いていたとしても、きっと己を「かわいそう」だなんて思わなかっただろう。
美しいお話だと思う。つまらないほどに綺麗である。
ただ、最後は泡になって海に還った彼女を、やはり私は羨ましいと思う。
幸福というなれば、死後暗く冷たい土の下に埋められるよりも、地球の循環というサイクルから外れ姿も残さず泡となって透明な海に溶けて消えることの方が、己にとってはどこまでも幸福であるか知れない。
夕暮れの海岸に腰かけ、水平線が滲み空と海が同じ濃紺に染まりゆくのを眺めていると、そんなことを考える。
だが、目下の幸福はクーラーの効いた部屋で読書に勤しむことである。酷暑続きの今日この頃、下手に外に出ようものなら泡になる前に直射日光に焼かれ蒸発して消えてしまうわい。やれ恐ろしや恐ろしや。やはりグラスに注いだサイダーの泡でも数えながら、海に思いを馳せる方が向いているかもしれぬ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
