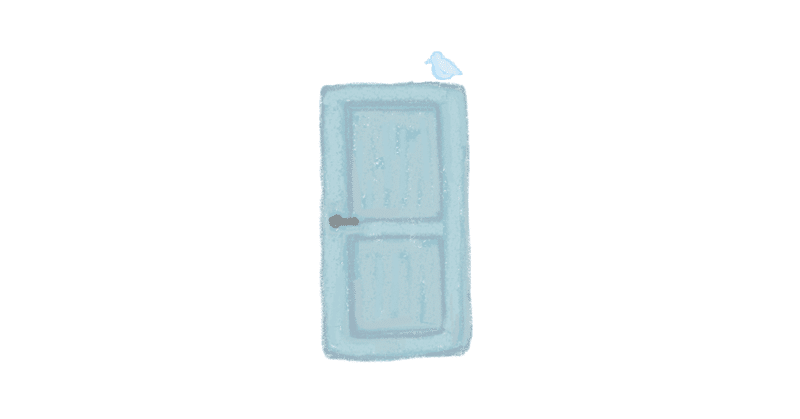
にほんごの詩の自由
いま、「詩」を眺めたり、読んだりすることが楽しいです。
昨年から興味を持ったので、「ビギナー」と言われそうですが。
でも「詩」は知識として学ぶものじゃないように思います。
「学術論文」と「詩」とで最大の違いは?
それは「意味」がはっきりしているかどうか。
もう一つは「自由」があるかどうか。
じゃあ、どちらが「楽しい」か。私は断然「詩」ですね(価値観の違いはありますが)。個人的に未知の世界ですし、「意味」が一つかどうか、わからない。グーグルで検索しても「言葉」の「意味」しか教えてくれません。
1 詩とは言葉遊び
谷川俊太郎は、詩とは何かという問いに、詩そのもので答えるしかないと言っています。
かんかんづくしを たずねたら
みかん きんかん さけのかん
おやじやかんで こはきかん
すもうとりはだかで かぜひかん
さるはみかんの かわむかん
これは音に出して読みたい。気持ちのいい言葉ですね。語尾を「かん」でそろえています。「おやじやかんで こはきかん」というフレーズは笑えますね。
じつは日本語って、意外と「遊び」があるみたいです。次の文は、ドイツ語と日本語の間を行ったり来たり創作活動をしている多和田葉子さんの言葉です。
あとがき
ものは分断のしようで、いろいろな顔を見せる。今、ワープロで「ぶんだん」を漢字変換しようとしたら、まず「文壇」が出た。わたしは全くそのようなものについて書く気持ちはなく、…(略)。
例えば、「あとがき」という言葉について言えば、「あとが・き」と分ければ、後に来るのが樹、という意味になり、一神教や啓蒙主義を突き抜けて樹木信仰に到着する。「き」には「気」や「機」や「器」などいろいろあるから、…(略)…あれやこれやいろいろ眺めまわすことのできるところがいい。
また、「あ、とがき」と分ければ、劇のセリフばかりにばかり耳を傾け、芝居の筋に心を奪われている時に、ちょっと視線をずらして、ト書きを読み、「あ、ト書き」と驚いているようにも聞こえる。…(略)
そういうわけで、あとがきがどのようなものなのか分からないうちに、あとがきを終りにしたい。
これは多和田さんのエッセイで実にじつに興味深い指摘です。そもそも彼女は「美しい日本語」などというものを信じていません。不完全な日本語なので「穴」だらけのチーズだという比喩が面白い。
「あとがき」という言葉をあえて分断して、本来の意味からずらすことで日本語の可能性を広げています。多和田葉子さんならではの視点が面白いです。最後の文にも、そこはかとないユーモアを感じます。彼女自身、日本語を楽しんでいるかのようです。

2 中国語の詩は遊べるか
今年やりたいことの一つである香港文学の翻訳なのですが、香港の友人から香港文芸サイトを教えてもらい、詩を眺めています(まだ翻訳には行っていません)。
当たり前ですが、すべて漢字。
そこで感じたのは日本語による「詩」は「遊び」の要素が多いのではないかということです。
まず、日本の詩では「ひらがな」を使うことが多いように感じます。あえて「ひらがな」を使って、ふんわりした「ふんいき」をかもしているのかもしれません。文字の選択でいろいろな気持ちを伝えることができます。
また谷川俊太郎さんのように言葉遊びが無限にできそうですし、多和田葉子さんのようにわざと誤解することもできます。
それはワープロで変換候補が相当あるように、「ひらがな」だけでは意味を限定できないからです。日本語には和語・漢語・外来語とがあって、漢語の比重は大きくて、近代に西洋の概念を導入するのに近代漢語をたくさん作り(中国に逆輸出しました)、文明化を進めたのです。
だから、日本語は海外からさまざまな文化を輸入したおかげで、豊かな言葉を楽しむことができると言えそうです。
一方、中国語ですが古代中国語から現代中国語まで長い歴史があります。
ざっくりとした話ですが、日本人が使う辞書を見ればわかりやすいです。いわゆる漢文を読むための、いわゆる漢和辞典、そして現代中国語を話す上で便利な倉石武四郎『現代中国語辞典』という分け方ができます。前者は親字が部首別で、後者はピンインで配列されています。つまり、発音で検索できるところが倉石辞典の優れた点です。
言い換えれば、古代以来、教養として中国語を学習するような文語と口語としての現代中国語なのかという違いです。
さて、「詩」についてはどうでしょうか。古代の詩は基本的に「書き下し文」として訓読するので、返り読みをしました。じゃあ、現代の詩はというと古風な書き言葉のようにも書けるとは思いますが、自分のセリフのような話し言葉が多いように思います。
香港文学の場合には、広東語を用いた詩の場合、香港独自の漢字表記や発音の要素もあります。
おそらく中国の漢字は意味が比較的に限定されるので、谷川さんや多和田さんのように「ひらがな」で「遊ぶ」ということはないかも知れません。でも中国語の詩にも「オノマトペ」はありますし、もしかしたら、漢字の中に身をひそめているかもしれません。
詩とは何か。
詩そのもので答えるしかない、ということだとしたら、自分で詩を作るということが大事なのでしょう。今までは顔をしかめて、「うーむ」とか言って、読んでいたかも(もしや眉間にシワが寄っていたかな)。
いくら言葉を尽くしてもお互いの気持ちは伝えられないのだから、開き直って、楽しく「詩作」していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
