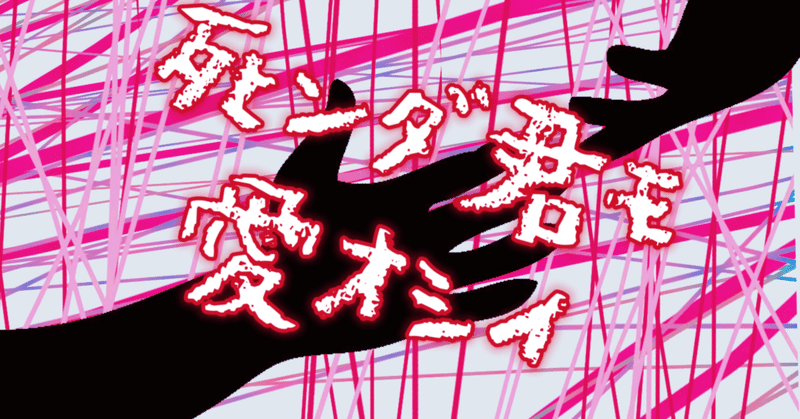
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第8話
Prev……前回のお話
アズサは時々、友達と遊んでくると言って出掛けたが、友達の話なんて一度も聞いたことがなかった。まあ、元々秘密の多い奴だし、友達の話を聞かせてくれることなど期待もしていなかったが、どんな友達だったのかは今でも非常に気になっている。正直、友達と仲良く遊ぶアズサは想像できなかったし、実際、「友達と遊んでくる」と言いながら怪我をして帰ってきたこともあった。いったい何があった? 心配して問い詰めると、なぜか逆ギレして、そういう時の殺気立ったアズサは手が付けられなかった。怪我をしていないまでも、「友達と遊んだ」帰りはいつもピリピリしていたのを覚えている。なあ、金魚。これも間違いじゃないか?
――たしかに。
「たしかにって。なんだよ、そのリアクション。こういうのじゃないのか? 間違い探しってやつは」
――そんな感じで合ってます。その答えは?
「答え?」
――間違いの答えを見つけてくださいね。
栞さんはそう言うと、ひらりと宙を舞って、水槽に飛び込んだ。ぽちゃんと澄んだ音がして、虹色の水滴が跳ねる。今日の水槽は、キラキラと宝石のようなものがたくさん底に沈んでいた。
もうすぐ朝の7時に差し掛かるところ。シャワーを浴びても相変わらず体は怠くて、頭もすっきりしない。出勤までまだ時間に余裕があったため、例の「間違い探し」について、考えていた。考えれば考える程、間違いだらけで、もはや正解がない。しかし、わかってきたのは、探すべきものは「間違い」ではなく、その答えなのだ。あるのか? そんなものが。そしてそれが今更わかるものなのか?
出かける準備を済ませ、「いってきます」と声を掛けたが、栞さんの反応はなかった。気まぐれなところは、アズサ譲りなのだろうか。
どしゃっ。
マンションのロビーを出た瞬間、上から大きなスイカが落ちてきた。足元で無惨に潰れている真っ赤に熟れたスイカを眺め、これが頭に当たっていたらと考え、ぞっとする。頭上を見上げてみたが、怪しい気配は何もない。自然に落ちてくるわけがないのだ。スイカの季節じゃないし。こんな立派なスイカ、どこで手に入れたというのだ。しゃがみ込んで、よく見てみようとしたら、「ずしょっ」と重量感のある音と共に、再び一矢の側にスイカが落下して砕けた。溢れた汁がアスファルトの溝を伝う。まるで露わになった傷口、いや、開かれた内臓のような砕けたスイカから、「にゃー」と鳴き声が聞こえた。ここは危険だ。スイカは一矢を狙っているのかもしれない。かち割れるのはスイカではなく一矢の頭だったかもしれないのだ。それでも、「にゃー」が気になる。逃げるべきとわかっていながら、一矢は頭上に注意を払いつつ、しゃがみ込んだままスイカをまじまじと眺めていた。通行人が妙な顔で一矢を振り向く。恐らく、「にゃー」が聞こえていないのだ。でもおかしなことに、どこからどう見ても、砕け散ったスイカの残骸。
カション。
不意に、近くから聞こえた耳馴染みのある音に、一矢は顔を上げた。この音は、よく知っている。立ち上がって、辺りを見回す。誰だ?
カション。カショ。カショカショ。
音の出所を探るが、見当たらない。アズサ? なわけないか。なら、誰が……? 自分は狙われているのだろうか。この音は間違いなく、アズサが持っていたNikonのカメラのシャッター音だ。
曇天の下、朝特有のひんやりする風に吹かれて立ち尽くす一矢。
しかし、もうシャッター音も、「にゃー」も聞こえなくなっていた。
なぜ亜季の父親の個展にアズサが来ていたか。アズサはただの偶然だと言っていた。亜季のことなど、忘れていたと。そんなはずないだろとも言い切れないのは、アズサもまた、カメラマンだったからだ。たまたま見知らぬ同業者の作品を見に来ただけ? 絶対にないとは言えない。だが、アズサが実際にどんな仕事をしていたのか、詳しく知ることはできなかった。ただ、Nikonのカメラを使って、なにかを撮っていた。なにを撮っていたのだろうか。アズサが所属していた会社は小さな不動産屋で、ファッションとも広告とも関係なく、編集の仕事でも、アートの仕事でもなかったのに、アズサはカメラマンだったのだ。まあ、おかしくはないのか。土地や建物の写真は必要だろうし。小さな不動産屋のカメラマン。それにしては、金回りが良かったと思うけれど。
「おはよう、広川。昨日はどうだった?」
「どうって……まあ、いい気分転換になった」
自販機から出てきた缶コーヒーを取り出しながら、返事をする。「そうかそうか」と、朝から嬉しそうであり、満足そうな佐倉の顔を拝み、オフィスに入ろうとしたら背後から声を掛けられた。
「あ、あの……昨日なにかあったんですか?」
一矢と佐倉が振り向くと、ショルダーバッグを前に抱え込んだ木橋が立っている。
「ああ、おはよう、木橋さん。昨日こいつに俺の友達を紹介したんだよ」
「え……はあ……そうなんですか……お友達……」
「あ、男ね、高校の同級生」
「あ、ああ! そうですか!」
なんだよ、この会話……わざわざ木橋に報告しなくてもいいだろう。そもそも、こいつはなにが聞きたかったんだ? 自分も紹介してほしかったとか? そんな感じには見えないけれど……どうも木橋という女がわからない。ごくごく普通の、真面目で大人しめの女の子だと思っていたのに、今はなんだか恐ろしい。一矢は先日の紙袋から飛び出した黒い手を思い出し、身震いした。そういえば、佐倉は大丈夫だったのだろうか。同じものをもらったはずだが、その後アレについて話すことはなかった。でも、奈津美が好物だと言っていたし、早めに食べていれば魚マスカットが黒い手に進化することもなかったのかもしれない。だとしたら、放置してしまった自分にも責任があるか。
缶コーヒーをデスクの脇に置き、PCを起動しながらチェアにゆっくり腰をおろす。
「さーせん、広川さん」
声に振り向くと、入社二年目の井田獅子だった。獅子と書いて「たいが」と読むのは、ただ単純に彼の親が獅子の意味を勘違いしていたからで、こういうのはキラキラというか、なんと言えばいいのだろう。少し同情するところもある。
「こないだのアレ、あそこに送っちゃっていいっすか?」
「えっと……」
こいつの言語はわかりづらく、聞き直してもどうせ意味ないので、自分の頭で解読する。井田が現在担当しているのは三つ、そのうち一矢が直接絡んでいるものはロゴデザインの仕事だった。とはいっても、直接のやり取りは井田に任せていて、一矢は最終チェックをするだけである。井田の仕事に関しては色々と不安もあるが、まあ、大丈夫だろう。
「ああ、よろしく」
「っす」
オレンジの短髪、耳の脇の辺りをポリポリと掻いて、井田はふらふらと軽い足取りで去っていった。その後ろ姿を眺めながら、なんとなく胸騒ぎがする。なんだろう。そうだ、あのロゴは先日チェックした時に少し引っかかるものがあったのだ。しかし、調べても類似デザインは特に見当たらなかった。なにが引っかかるのだろう。一矢はしばらく腕を組んで考えたが、もやもやは晴れない。こういう根拠のない勘は、意外と無視できないもので、根拠がないようで、実は恐らく根拠があるのだ。でも、どうしても今はそれが何なのかわからなかった。GOサインを出すのは早まったか? まあ、もしもなにかあったら、その時に自分がどうにかしよう。
「おつかれ」
ポスン、と一矢のデスクになにかが置かれた。紙袋。……紙袋だと!?
つい反射的に警戒してしまい、見上げると佐倉の笑顔があった。そうだよな、佐倉の声だったもんな。
「なんだ? これ」
恐る恐る中を覗く。
「お前、昼飯まだだろ? 奈津美がお前の分もって。普通のサンドイッチだけど」
「おお……これは嬉しい」
「今日だけだからな。あいつが弁当作るなんて滅多にない」
「わかってるよ」
よかった、本当に普通のサンドイッチのようだ。店以外で、他人が作った物を食べるのはいつぶりだろう。ご丁寧にパックのリンゴジュースまで添えてある。勿論、果汁100%だ。
思わず一矢が顔を綻ばせると、佐倉はフッと笑って近くにあった折り畳みの椅子を引き寄せ、隣に座った。
「え、なに?」
「一緒に食おうと思って」
「えー……」
「別にいいだろ? 飯くらい一緒に食ったって」
「女子社員かよ」
「あ、そういうこと言うの、ここだけにしろよ? 色々問題になるから」
「はいはい」
とは言ったものの、やっぱりどう考えても二人並んでサンドイッチを食べるのは抵抗がある。おかしいだろ? 普通なのか? さっさと食っちまおう。
「あーもう、そんな慌てて食うなよ」
「別に慌ててねぇよ」
卵サンドを頬張りながらも、慌てて食ったところで自分の席はここだし、結局は佐倉が満足するまで仲良く並んでお喋りするしかないのだと諦めた。そして普通の卵サンドが妙に美味い。
「奈津美はさ、簡単な料理しか作らないし、そんなに上手くないし、でも意外と料理が好きなんだよな」
佐倉は手に持ったハムサンドの断面を眺めながら、まるでなにかを懐かしんでいるようだった。
「父さんが生きてたら、色々教えてやれたんだろうけど。俺もオムレツくらい、教わっておけばよかったな……とか、時々思う」
ごくり、と卵サンドを飲み下しながら、一矢は少し戸惑った。仲良く並んでお喋りどころではないな。オフィスでのランチとは思えない重めの内容。佐倉もそれに気づき、慌てて明るい笑顔を作った。
「まあ、オムレツなんか、教わらなくても作れるけどな!」
「いや、俺は作れない」
「そ、そっか……お前結構自炊してんのに……」
少し間があってから、ふたりともなんだか笑いが込み上げてきた。特に笑うところではない。佐倉は恐らく亡くなった父親のことを思っているし、一矢はアズサのオムレツを思い出していた。なにも面白くはなかったけれど、こういう時はなんとなく笑っておくのが正解だ。
「ははは……はあ……。美味いな、うちの嫁サンド」
「普通に美味い」
「そう、普通なんだよな」
「普通がいい。安心する」
「そうだな。伝えとくよ」
微妙な雰囲気の食事を終え、立ち上がりながら「あ、そうだ」と佐倉が振り向く。
「静流とは、連絡先交換した? 教えようか?」
「交換したから大丈夫」
そかそか、と嬉しそうな佐倉。
「思ったよりだいぶいい奴だった」
「だろ? よかった」
一矢はデスクの周りを整理して、午後の作業に備え始めたが、隣に立つ佐倉は遠い目をしながらまだ話し足りないようだった。
「あいつとは一時期、一緒に暮らしてたことあるんだよ」
「え? そうなのか」
意外な情報に一矢は顔を上げる。一矢が知り合った頃の佐倉は実家暮らしだったし、両親が亡くなってから、大学を卒業後にすぐ奈津美と結婚した。誰かと一緒に暮らしているとは聞いたことがなかったと思うけれど。
「ああ、高校の時、少しの間だけだけど。うち、部屋が空いてたから静流が行く場所なかった時期に預かってたの」
「へえ、それで信頼関係があったんだな」
「いや、別に……だから信頼関係が築けたわけじゃない。静流がまともな奴だったからだよ」
「え? ああ、うん」
なんか変なこと言ったか? と一矢は首を捻る。わざわざ否定するところではないのでは。そんな一矢に気づいたのか、佐倉は付け加えた。
「一緒に暮らしても、信頼関係が築けない奴だって、いるから」
「まあ、そうだろうな」
まさか自分とアズサのことを言っているのだろうか。いや、流石にそんなことを言う奴ではない。佐倉の顔を見ると、唇を噛んで表情が翳っていた。ふと、奈津美が言っていた言葉が頭を過る。
「お母さんに愛人がいたらしくて……知宏はその愛人に毒を盛られたんだってずっと言ってるの」
一緒に暮らしていたのだろうか、その愛人と。だとしたらそれは地獄だな、と勝手に推測して勝手に同情した。
「お前に奈津美がいて、よかったよ」
真相が解らないなりに、心から思ったことを一矢が口にしたら、なぜか佐倉は気まずそうな顔をした。
「ああ、うん、ごめん……」
なぜ謝るのか。こいつ今日は様子がおかしいな。いや、朝はいつも通りだった。昼飯を食べるまでは、いつも通りのお節介だったはず。父親の話からか。数日前に奈津美から聞くまで、佐倉がまだ苦しんでいることを知らなかった。佐倉が話さなかったからだ。
謝る必要なんかないのに。つらい時に力になりたいと思うのは、自分だって同じだから。
来週、大晦日の投稿はお休みするので、これが年内最後の投稿となります。
次回は年明け、1月7日(日)を予定しています。
2023年、3月にnoteを開設してから、多くの方にお読みいただき、そして応援していただき、大変お世話になりました。ありがとう!!
来年もなにとぞ、よろしくお願いします。
メリークリスマス…よいお年を!!
Next……第9話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
