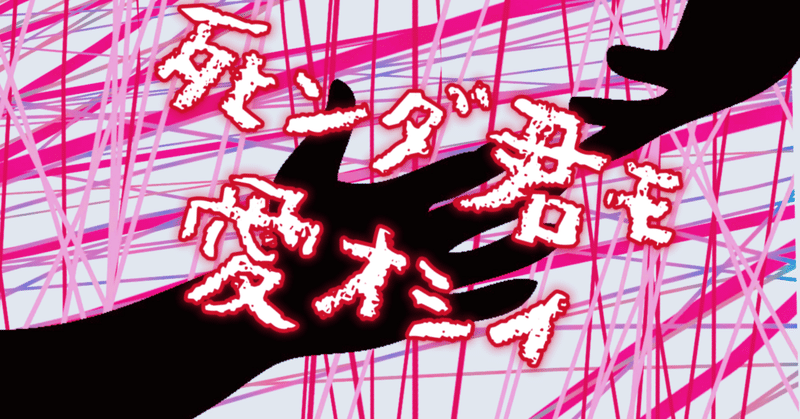
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第7話
Prev……前回のお話
ほんの少し話しただけだったが、一矢はだいぶ気持ちが軽くなっていた。元々、楽になりたいと思っていた訳でも、救いを求めていた訳でもなかった。それでも、ふと我を取り戻す、こんなきっかけが必要だったのかもしれない。多分、自分を含め、周囲が見えなくなっていた。佐倉が心配していたのも、そういう余裕のなさが危うく見えていた所為だろう。
「なにも失うものはないと思っていたんだ。俺のすべてはあいつにくれてやったし、そのアズサは俺のものにはならなかった。最初から俺の手元にはなにもなかったんだ。だから、あいつが死んだって、同居人が出て行ったってくらいで、日常に大きな変化はないと思っていた」
そこまで言って、一矢は黙った。黙ってみると、ハードロックなBGMと、それを搔き消すくらいの酔っ払いたちの声が聞こえる。自分の頭の中が、なんだか場違いな気もする。でも、そんな一矢を静流は真剣に見つめていた。
「実際は違った?」
「いや」
少しの間。再び訪れる騒がしい沈黙。一矢は大きく息を吐く。
「やっぱり大きな変化はない。アズサは幻だったのかもしれないな。最初からいなかったのかもしれない。そのくらい、この世界にはなにも残っていないんだ」
「そうか」
そう言いながら、静流はテーブルの上の木の筒に入った紙ナプキンを寄越した。
「空っぽになっちゃったのかな」
わかっている。なにも残っていないのは、どこかに大きな穴が空いているからで、本当はどこもアズサで溢れていた。静流から渡された紙ナプキンで乱暴に目の周りを拭うと、くしゃっと握り潰した。手の中に湿り気を感じる。おかしい。アズサが死んでから、泣いた記憶なんかないのに。いや、覚えていないだけで、気づかないうちにみっともなく泣いていたのだろうか。こんな姿、アズサには絶対に見せることはできなかった。
「お水頼む? 結構飲んだけど。大丈夫?」
「ああ、そうだな、じゃあ……」
「フードは? お腹いっぱいになった?」
トイレから戻ったら、あれやこれやと勧めてくる静流に気圧される。久しぶりに息子が田舎に帰ってきたお母ちゃんかよ、と苦笑する。
「たしかに、少し飲み過ぎたかもしれないな。変な奴に絡まれないように気を付けないと」
「はは、飲み過ぎて絡んじゃうのはわかるけど、飲み過ぎても普通は絡まれないよ」
「いや、実際酷い目にあったんだ。こないだの日曜なんだけど」
なになに、と首を傾げて静流が聞く。
「S三丁目のホームで熊に絡まれて――」
「熊に? 熊みたいな人?」
「いや、熊。口しかねぇんだ」
一矢はその時のことを思い出して、溜息をついた。
「そいつが仲間呼んで面倒なことになって……てるてる坊主が来るわ、なまはげが追ってくるわで、結局終電逃したんだよ」
「えー……」
静流は複雑な顔をしている。そりゃそうか。実際にあの状況を見ていないと、理解は難しいかもしれない。
「まあ、今日は大丈夫だと思うけど。あの時は日本酒がまずかったんだ」
いや、美味かったけど、とくだらないことを言いそうになり、飲み込んだ。変なテンションになっている。まあ、悪い酔い方ではないかもしれないが、自分らしくない。反省すべきだな。
「また、飲もうよ。いつでも連絡してね」
席を立つ前に、静流は名刺を差し出した。受け取ったカウンセラーの名刺をしばらく眺めてから、一矢も仕方なくカードケースを取り出す。差し出されたから名刺交換はするけれど、なんだかモヤモヤする。こいつが築こうとしている関係性がいまいち掴めない。妙な違和感を覚えながら、一応、会社の名刺を雑に手渡した。
「あ、違う違う! そうじゃないんだ、ごめん。なんか誤解させたかもしれない」
「え?」
「ほら……俺たち、フルネームも碌に知らなかったから……。仕事の名刺が渡したかった訳じゃないんだけど……なんかごめんね」
「いや、そんなことは別に気にしてなかったけど」
そう言いながらも、モヤモヤした違和感はこれだったと納得した。
「これ、俺のLINE。よかったら登録してね」
静流がQRコードの画面を差し出す。最初からこれだったとしても、それはそれで違和感があったかもしれない。今まで経験したことのない微妙な関係性に戸惑いつつ、LINEも交換した。
平日だというのに、思った以上に遅くまで飲んでしまった。駅に着き、時刻表を見て急に慌ただしくなる。この時間、次の電車に乗るか逃すかでは大きな違いだ。
「あ、電車くるわ! じゃあ、またね、一矢。連絡する!」
静流は手をひらひらと振って、反対のホームへと去っていった。どさくさに紛れて一矢って言ったな、あいつ。「友人として」のアピールだろうか。もういいのに。よくわかったから。
人前で、アズサの話をして涙を見せてしまった。こんなこと、アズサに知られたら、心底不快な顔をしただろう。好きなだけ恋人を翻弄しておいて、好意を向けられることに嫌悪感を抱いていた。それでいて試すようなことをしてくる、とんでもない奴だ。今までいろんなことをしてやって、その度アズサが嬉しそうな顔を見せていたのは、恋人の愛情を感じていたからではなく、支配欲が満たされていたからに過ぎない。
「ずっと許さないでいてよ」
憎しみから始まった関係。アズサは憎まれることに安心を得ているようだった。許すことを許されず、俺はずっと憎み続けなければならなかった。
「愛されるの得意じゃないって、知ってるでしょ」
そう言われた時には既に、ずっと抱き続けていたどす黒い感情は、別の感情に変わってしまっていた気がする。それが愛という類のものと認識する前に、アズサから先手を打って拒否された。自分の感情を見失ったのは、間違いなく、その頃からだ。芽生えた感情をアズサからも否定され、自分の中でも否定するしかなかった。亜季を失ってから仇敵だったアズサに溺れてしまうなんて、死んだ亜季に顔向けができない。だから、アズサと憎しみという感情で繋がるのは、都合がよかった。いろんなものを誤魔化しながら、いつしか、なんとなく傍にいることが当たり前になったけれど、まさか後に恋人という関係になるなんて、お互いに思いもしなかった。でもそれはきっと、アズサにとっては特別なことではなくて、体の相性がよかったとか、なにかと都合がよかったとか、最後までただそれだけだったのだろう。心の繋がりを感じたことは、一瞬もなかったから。殺されかけたことは、何度もあったけれど。
そこまで酔っていた訳でもないのに、どうやって帰ってきたか、よく覚えていない。本能とは大したもので、頭はどっかに行っていても、無意識に帰宅してしまうらしい。そう考えると便利なような、恐ろしいような。この家に囚われているような、不気味さも感じる。玄関のドアを開け、なんとなく落ち込んだ気持ちで「ただいま」と呟いた。
「オカエリ」
リビングから明かりが漏れている。今日はもう遅いし、勘弁してほしい。佐倉に顔色が悪いと言われて反論したが、顔色が悪くてもおかしくはない。ここ最近、睡眠は一応とっているはずなのに、ゆっくり休めた感覚はなかった。
恐る恐る扉を開くと、リビングの中央に、バスケットボールくらいの大きさの心臓が、脈打ちながら浮いていた。ドクン、ドクン、ドクン、ドクン……。神秘的な淡い紅に光る心臓。思わず見惚れてしまう。力強い鼓動が耳の奥に響く。なぜか息が上がっている。目頭が熱い。
そんな一矢の視界を遮るように栞さんが水槽から飛び出し、まるで大迫力のVR動画のように、その体は一瞬のうちに巨大化して、宙に脈打つ心臓を丸呑みした。
はぐっ……。
正体不明の衝撃に、一矢は思わず膝をついた。なにが起きた? 肩で呼吸をしながら、頭上を見上げると、アズサが冷たく見下ろしていた。
「アズサ……」
思わず手を伸ばすと、鮮やかに煌めく金魚が指先を擦り抜ける。
――おかえりなさい、イチヤさん。
「ああ……。ただいま」
なあ、アズサ。俺と出会ったことで、お前の人生、少しはマシになったのか? 結局死を選んだってことは、一緒に生きる価値はなかったんだろうな。お前がなにを考えて生きて、なにを考えて死んだのか、理解できる日が来るのだろうか。今更、理解したとして、それに意味があるのだろうか。お前はそれを、望むのか?
望むかもしれないな。死んでもなお俺を囚えて生殺しにでもするつもりか。いったい、遺書になにを書いたんだよ。お前の人生が間違いだらけだったって、そんなのよくわかっている。どの間違いを探せって? でもまあ、暇潰し程度に、お前のことを思ってやってもいい。ついでに言うと、お前と出会ったのが、俺の最大の間違いだ。
あれは、5年前の11月5日。
なぜ日付まで覚えているのかって、亡くなった亜季の誕生日だったからだ。亜季の父親はカメラマンで、その日、個展を開いていた。亜季の写真を展示すると聞いていたから、俺も少しだけ顔を出すつもりだった。午後の用事が長引いて、俺がギャラリーに到着したのはもう夕方に差し掛かる頃だったのに、客は全然入っていなくて少し気まずかったのを覚えている。亜季の父親が食事でも行こうと言っていたから、待っている間手持無沙汰で、入口にあった芳名帳とかいうのを、なんとなく眺めていたのだ。最後の客。「アズサ」とだけ、記載されていた。まさかあのアズサ? 梓柚希なのか? 葬式も来なかったあいつが、ここに来たって? まだ近くにいるかもしれない。迷う暇もなく俺はギャラリーを飛び出した。どこから来たのかなんて勿論知らない。車で来ていたらアウトだが、とにかく、駅へと向かう道を走る。でも顔も知らないのに、会ってわかるだろうか。普通に考えて、わかるわけがなかった。だからといって、追う以外の選択肢はなく、正体不明のアズサを追った。会ってどうする? 亜季を死に追いやった奴だ。捕まえたら簡単には逃さない。どうにかして徹底的に罪悪感を植え付けて、一生苦しませることができないだろうか。その方法は会ってから考えればいい。とにかく捕えよう。
人通りも少なく、ギャラリーと駅の間にはだいぶ距離があった。息を切らしながら走ったが、もうとっくにアズサは去った後かもしれない。さっきすれ違った人がアズサだったかもしれない。そんなことを考えながら、歩道橋を駆けあがった瞬間。
目の前を行く後ろ姿が間違いなく「アズサ」だった。なぜわかったのだろう。光っていたような、周囲の音が消えたような、なにかが異質だったのだ。
「アズサ!」
咄嗟に叫んだら、そいつはゆっくり振り向いた。歩道橋の上。車の音。煙たい風。「なに?」と答えた迷惑そうな顔のアズサが、目を瞠るほど美しく、残念ながらあの時の衝撃は今も忘れられない。全身黒い服装で、まるで喪服のようだった。その後、アズサとつき合ってわかったが、アズサは普段あまり黒い服を着ることもなく、あの時が特別だったのは間違いない。亜季のために? アズサがそんなことをするだろうか。とにかく、黒い服に身を包んだその姿は、妖艶な天使にも悪魔にも見えたが、今ならわかる。あれはやはり悪魔だった。
一瞬怯んだが気を取り直し、「亜季を殺したのはお前だ」とか、「絶対に許さない」のようなことを叫んだが、眩しそうにこちらを見ているアズサは笑っていた。
「はは、夕日を背負ったヒーローみたい」
その後どうしたっけ。頭に血が上った俺は、掴みかかったかもしれない。とにかく、アズサはずっと笑っていた。なにがおかしいのか。
亜季が死んだのは交通事故だ。殺したのは飲酒運転をしていた中年男だ。そんなことも、アズサはきっと知っていた。お前が殺しただなんて、こじつけによる八つ当たりに過ぎない。そんな俺が滑稽で、笑っていたのかもしれない。
「殺したくなったらおいでよ。いつでも歓迎する」
そう言って、名刺のようなカードを渡し、じゃあね、と微笑んでゆっくり去っていった。追いかけることもできたけれど、追いかけたところで何もできない。全てにおいて、惨敗だった。
リベンジのつもりだっただろうか。あの時の自分がなにを考えていたか、よくわからない。もう既に、毒牙にかかっていたかもしれない。出会ってからしばらくして、カードに書いてある番号にかけてみた。それでアズサの部屋に行って、なにをしたんだっけなぁ。気づいたら何回もアズサの部屋に通っていた。首を絞めて殺そうとしたかもしれないし、抱いたかもしれない。
とにかく、あの日、馬鹿みたいに未だ見ぬアズサを追いかけたのが間違いだった。こんなことになるとは、思わなかったから。
出会わなければよかった?
あんなクレイジーな堕天使、出会わなければ一生後悔していただろう。
Next……第8話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
