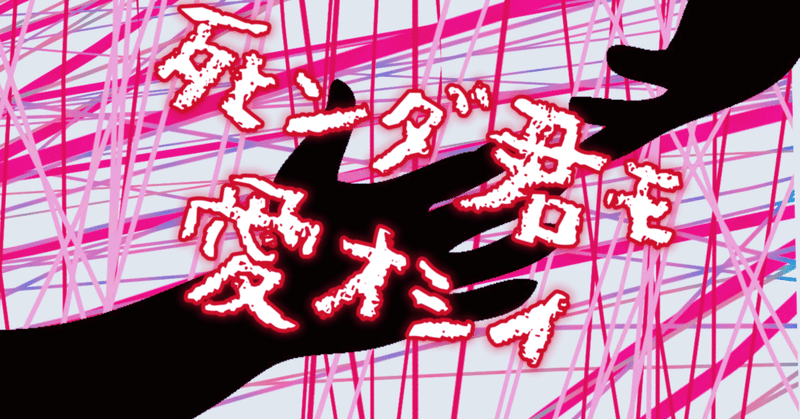
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第6話
「ねえ、知ってる? 明日、誕生日なんだけど」
アズサは年に何回か、突然、そんなことを言う。恐らく、気まぐれなのだろう。嘘だと分かっていながら、毎回しっかり祝ってやった。高級レストランや、有名店のケーキ、夜景の見えるスイートルーム……そんなものは前日に用意できる訳もなく、いつも間に合わせだったけれど、できる限りのことをしてやった。アズサが好きだと言っていた小さなカフェ、欲しがっていた厚手の毛布、下手な手料理で饗応したことも何度もある。アズサの満足そうな顔を見て、溜息をついたものだ。
「誕生日、ちゃんと覚えててよね」
残念ながら、記憶している。今まで祝ったアズサの誕生日、すべて。
たしか、去年の今日も、誕生日だった。その日は朝から雨が降っていて、アズサは天候からくる頭痛で不機嫌になっていた。雨の日は、なるべくアズサに近寄りたくなかったが、誕生日だから仕方ない。前日に急遽決定したその誕生日のために、会社の近くでショートケーキを買って帰った。去年に入って三回目ともなれば色々とネタ切れで、プレゼントは会社の近くで青い傘を買った。何の変哲もない普通の傘だったけれど、丁度その時流行っていたアニメ映画「バギッシュ」の記念モデルで、限定50本の貴重な傘だったはず。たまたまタイミングよく入手できたとはいえ、だいぶ割高だったのに、よく見ないと気づかないくらいに柄の下の部分と、ネームバンドに模様が入っているだけで、ぱっと見、ごくごく普通の青い傘だった。多分、アズサはそれなりに喜んでいたと思う。でも、ほんの数回使っただけで、すぐに傘立てに置き去りにされた。元々アズサは、ビニール傘ばかり使う奴だったから、限定の傘なんて性に合わなかったのかもしれない。
そんなことを思い出しながら、今日もアズサのいない日常を送る。アズサがいてもいなくても、穏やかで平和な日常は訪れない。わかっている。気分的な問題だ。
「顔色、悪いぞ。ちゃんと寝てるか?」
PCの画面を睨んでいたら、佐倉が横から首を伸ばして覗き込んできた。不意を突かれて、一矢は咄嗟に変な声を上げそうになり、すぐに飲み込んだ。
「適当なことを言うな。背後から忍び寄って顔色なんて分かるわけないだろ」
再び画面に目を戻して、作業を続ける。
「適当じゃないよ。今朝からずっと、顔色悪ぃなぁって様子見てたから」
佐倉の言葉を聞き、一矢は溜息をついて椅子ごと佐倉の方を向いた。
「あのなぁ。こんなこと言いたくないけど、いい加減にしてくれ。口開けば大丈夫か、大丈夫かって、善意だろうから仕方ないって我慢してたけど、仕事の邪魔までするつもりかよ。ここ最近、お前とまともな会話した記憶、ないんだが」
静かに怒りを込めた一矢の口調に、佐倉は動揺しながら慌てて弁解を始めた。
「たしかに……たしかに俺が悪かった。よく考えたらほんとに俺はしつこかった。それは反省してる、心から。……んでもな、お前ほんとに酷い顔色だぞ。なんていうか……触ったらゾクッとしそう」
そう言いながら佐倉は一矢の頬に恐る恐る触れる。
「あ、思ったより温かかった」
「はぁ」
溜息と共に項垂れる一矢。隣でもう一度、「悪かったよ」と佐倉が呟くのが聞こえて少し心苦しくなった。いい奴ってタチが悪い。
「あ、そうだ、本題なんだけど」
「本題? さっさと言ってくれ」
腕と足を組んでいる一矢の隣にしゃがみ込み、椅子の肘掛けに手をついて話す佐倉は、社長の姿とは思えない。しかし、こういう気取らない姿勢が、周囲の人間に好感を抱かせるのだろう。
「今夜、静流が空いてるって言うから紹介したいんだけど、どうかな」
「ああ……」
「あ、友達として! 変な意味はないから! 静流にも、ちゃんとそう言ってあるから」
「はあ……」
ちゃんとそう言ってある、というのもおかしいだろう。普通、友達を紹介するのにそんな言い訳はしない。恐らく、静流って奴も、カウンセラー的なものが求められているのだと、分かった上でやって来るのだ。面倒なことにならないよう、今夜会ったら、それで終わりにしたい。
「あ、いたいた」
仕事を早めに切り上げ、佐倉と一矢がオフィスビルを出ると、すぐ右にある小さな広場で少女の銅像をしげしげと見つめている男がいた。佐倉に気づくと、笑顔で手をぶんぶんと振っている。遠目に見ても、すらっと背の高い男。一矢も身長は調子のいい時なら178㎝ほどあるが、この男は更に高い。そして妙な存在感。
「やあ! どうも、どうも!」
屈託のない笑顔で手を差し出され、戸惑いながら一矢が右手を出すと、その男は両手で握り三回振った。思った以上に厄介な奴かもしれない。まだ一言も挨拶をする前から、一矢は帰りたくなっていた。
「話しやすそうな奴だろ? こいつが大原静流。高校の同級生」
「ああ……どうも。広川です」
最近プライベートで自己紹介する機会なんてなかったから、一矢は少し変な気持ちになった。こんな街中の小さな広場で、大人の男三人が何やってんだか。
「いやぁ、会えて嬉しいよ」
心底嬉しそうな静流を見て、一矢は怪訝に思った。佐倉から何を聞かされているか知らないが、自分と大きな温度差を感じる。
「知宏が友達を紹介してくれるって言うからさ、楽しみにしてたんだよね」
なんだか調子が狂うな……。純粋に友達を作りに来たのか? まあ、それでいいんだけど。構えていたのは自分だけだったのだろうか。
「この近くにビールが美味しい店があるんだよ。知ってるかな。そこ行こう!」
イギリスの大衆酒場風のレストラン「パブロフのワン」は、オフィスビルから歩いて三分ほどの、細い路地の裏にあった。入ってみると随分賑やかで、もう出来上がっていそうな人がちらほら見える。静流は店主と顔見知りっぽく、少し話して奥のボックス席に通してもらった。
「こんな店があるの知らなかったよ。静流が好きそうな店だな」
「楽しくお酒が飲めたらいいかなと思って」
一矢は少し安心した。重めの話をするような店の雰囲気ではない。純粋に楽しく酒を飲む席ならば、気が楽だ。もしかしたら、この店のチョイスも静流の配慮かもしれない。「気楽にいこうぜ」というアピールだったりするのだろうか。もしそうだとしたら、かなりのやり手に違いない。
「かんぱーい!」
「はあ」
ごくごくと喉を鳴らしながら黒ビールを飲み下す。「うっまー」と笑う静流の顔を見ていると、最近の自分がいた世界とは違う世界に来たような錯覚をしてしまう。こんな日常、忘れていた。
「あ、これ! 美味いから食べて。あと、これも。取って取って」
大きな唐揚げが乗った皿を突き出してくる。こいつ、初対面だよな? 遠慮なく、ぐいぐい来るけど。一矢が若干引いているのに気づき、佐倉がフォローに回った。
「こいつ、昔からすげぇ世話焼きでさ。周りが放っとけないっていうか、構いたがるっていうか……」
「ああ、ごめん。悪い癖、出てた?」
静流が慌てて唐揚げの皿を置く。
「いや……全然悪くないけど……よく考えたら広川とあんまり相性はよくなかったかも。はは」
「えっ」
佐倉の言葉にショックを受けている様子の静流。たしかに、相性は最悪だ。ただでさえ佐倉の過保護っぷりにうんざりしていたのに、更に面倒な奴が出てきたとは。だが、「ええー」と言いながら戸惑っている静流を見たら、なぜか笑いが込み上げてくる。
「いや……そんなんでカウンセラーなんて、できるものなのか? 世話焼きは絶対まずいだろ」
笑いながら一矢が言うと、なぜか静流は得意そうな顔をした。
「そこはプロだから。ちゃんと一線引くよ。仕事は、別」
「まあ、そうか」
まだ笑っている一矢を見て、佐倉が微笑む。
「広川が笑うの、久しぶりに見たな」
たしかに。今だって、なぜ笑っているのかよくわからない。多分、気が抜けたのだろう。周囲の人間が気を遣い過ぎて、息が詰まりそうだった。仕事は別、と言っている静流は、今はプライベートであり、友人としてここに居るのだ。だから、世話焼きだろうと、このままでいてほしい……ような気もする。
「まあ、けど。これでも深入りはしないようにしてるんだよ。世話は焼いちゃうかもしれないけど、心には入り込まないから。安心してよ」
「それはありがたい」
悪い奴では、なさそうだ。
「あ、ごめん! 俺もう帰らなきゃ」
スマホを見ながら、佐倉が財布を取り出す。
「は?」
一矢は呆れた声を上げたが、静流はあまり気にしてなさそうな顔をしてポテトサラダを食べていた。
「奈津美を迎えに行かなきゃいけなくって……ごめん!」
「お前、最初からそのつもりだっただろ」
一矢が言うと、「まあまあまあ」となぜか静流が宥める。こいつの立ち位置がいまいちわからない。
「大丈夫だろ? 見てたら意外と気が合いそう」
佐倉は三千円をテーブルに置いてから、パイントグラスに少し残っていたビールを飲み干し、立ち上がった。
「じゃ、また明日な! 静流、また連絡する」
「あいよー」
「はあ」
初対面の男とふたりで残されたが、思ったほど居心地は悪くなかった。静流が勝手に話してくれるし、自然に話を振ってくるから、余計なことを気にせず、気楽に会話ができた。肩が軽い。そして意外なことに、この店は居心地がよかった。陽気な酔っ払いとノリのいいBGMで騒がしい店内。こんな場所にいても、アズサのことは頭から離れない。でもなぜかそれが心地よい。上手く説明できないけれど、平常心でアズサのことを思える自分に、どこか安心するのかもしれない。
「知宏から聞いてたけど、結構酒強いんだね」
「いったい、なにを聞いたんだよ」
「いや、大したことは聞いてないけど。酒が強いってことくらい」
「嘘つくな」
弱くもないが強くもないし、それしか聞いてないってことはないだろう。
「気を遣わなくていい。たぶん、それが大原の良さなんだろ。俺は今日会うまで誤解してたんだ。もっと、こう……話聞いてやるよ、って感じで来るのかと思ってたんだけど、全然そんな感じじゃないし。不思議だな。話さなくてもいいんだって思ったら、なんだか話したくなってくる。これがカウンセラーのテクニックなのか?」
「そんなんじゃないよ」
静流は少し笑う。わははは、という遠くの席の笑い声が響いている。太った女性店員が席の間を縫いながら寄ってきて、「お待たせしましたぁ」と生ソーセージの盛り合わせがふたりのテーブルに置かれた。
「俺はただ、知宏がよく話してた広川って友達に会えるのが嬉しくて、一緒に美味い酒が飲めて、来てよかったなぁって、ただそれだけ。今のところね。違ったらごめんだけど、広川は『聞いてほしい』んじゃなくて『話したい』んじゃないのかな。だったらたぶん、俺じゃなくてもペットとかだっていいはずだよね。それでも、今俺の前で『なんか話したいなー』って気分になったんなら、話してみてよ。ペットだと思って。あ、ペット飼ってる?」
結構いい話をしているのに、最後が「ペット飼ってる?」だったことに、少し笑ってしまう。
「あー……そうか。俺は話したかったのか。たしかに、金魚と話してたな」
「金魚、と?」
「ああ、うん。あいつもアズサが恋しいのかもしれない」
静流は黙って一矢を見つめた。本当だ。話したい。あの朝のこと、出会った時のこと、出会う前のこと、いや、違うな。そうじゃない。
「恋人を、亡くしたんだ。アズサっていう――」
「うん」
「無慈悲で、性悪で、本当に、酷い奴だった。今思い出しても、腹が立つ」
「うん」
「だけどどうしようもなく愛おしくて、自分の感情がわからないまま一緒に暮らした。二年間。その果てに、俺を置いてあいつは自殺したんだ」
わははは、と遠くの席の笑い声が再び響く。
「結局、最後まであいつが何を考えていたのかもわからないし、自分がずっとなにを感じているのかもわからない。身が捩れる程の強い感情があるけど、それがなんなのかもわからないんだ」
大きな黒い瞳を少し細めて、静流は一矢の話を聞いている。聞いてもらっているのではなく、一矢がただ話をしているだけだった。それを静流が聞いている。ただ、それだけ。
「だから……アズサの遺書を探すことにした。どこかにあるんだ、間違いが。金魚がそう、言っていた」
「金魚が……」
「おかしいか?」
「いや……どうだろう」
「おかしいよな、わかってる。あの金魚がなにかを企んでいる可能性も、勿論あるんだ」
一矢は深い溜息とともに、手に持ったパイントグラスをじっと眺めてから、ひと口、喉を鳴らして飲んだ。
「せめてもう少し、あの金魚と信頼関係でも築けたらやりやすいんだけどな……」
わはははは、という笑い声。こんなに落ち着いて話ができるとは思わなかった。構え過ぎだったのだ。悪くない。とても、穏やかな気分だ。
Next……第7話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
