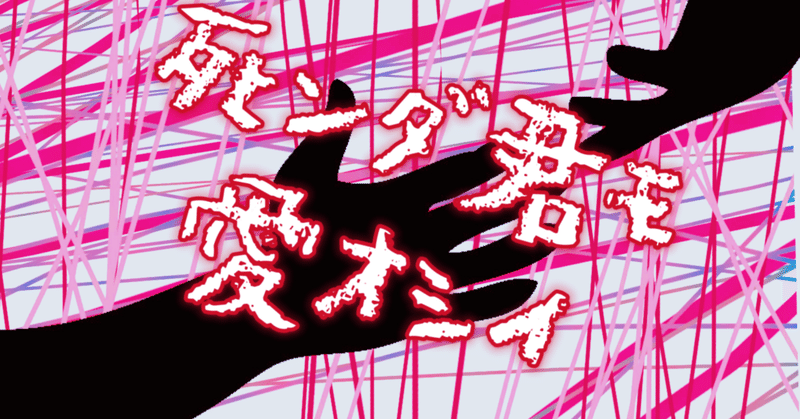
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第9話
Prev……前回のお話
お元気ですか? 先日は色々とありがとう。私の方は少し、落ち着きました。一矢さんは大丈夫でしょうか。きっとあなたはとても優しい人なので、心配です。
もしお時間があったら、週末にお食事でもいかがですか? 一矢さんとふたりで、お話がしたいです。
「あ、一矢さん! こっちです」
柔らかい笑顔で小さく手を振る女性。一矢は小走りで寄っていき、彼女の前で立ち止まると軽く頭を下げた。
「先日はどうも……。花絵さん」
土曜の昼。S駅西口で一矢を待っていたのは梓花絵、アズサの姉である。数日前に連絡が来て、ランチを共にすることになった。彼女とはアズサの葬式以来で、ふたりで会うのは初めてだ。一矢にとって、今一番会いたいような、会うのが怖いような相手だった。
ふわっとした花のような雰囲気を纏う彼女は、アズサの姉とは思えないほど物腰が柔らかい。可憐で小さなお姫様のような彼女だが、家庭環境を考えると複雑な気持ちになる。一矢にとって、アズサの両親は二度と顔も見たくない相手であり、恐らく向こうも同じだろう。アズサとはだいぶ昔に疎遠になったと聞いていたが、花絵は今も両親と繋がっている。簡単に人との繋がりを絶たないのも、穏やかな彼女らしさと言えるのだろうか。
天気の話とか、体調を気遣ったり、当たり障りのない会話をしながら少し歩き、花絵のおすすめの洋食屋へ向かった。「ホワイトブランコ」と書かれた看板の横に、花かごの乗ったお洒落なブランコが飾られていて、可愛らしい洋食屋だ。しかし、ホワイトブランコ……ブランコって日本語じゃないのか? なんて考えて、一矢は少しもやもやしながら、店のドアを引いた。カランカラン、と浮かれた音を立ててドアベルが鳴り、庭園がモチーフになっている店内に進む。場違いじゃないか? いや、お姫様の付き添いだから構わないのか。自分にとって、居心地の良さそうな店とは思えないけれど。
「一矢さん、ここのハンバーグがとっても美味しいんですよ」
白と緑のテーブルクロスの上にメニューを広げ、花絵が細い指でハンバーグを差した。アズサも手が綺麗だったな、なんてつい思い出してしまう。一瞬思考回路が脱線しそうになったが、無邪気な顔で、一矢の反応を待っている花絵に気づき、じゃあそれで、と返事をした。花絵は一矢に笑顔を見せてから、店員を呼んで、ゆっくり丁寧に注文をした。アズサだったら腕を組んで、一矢が注文するのを当たり前のように待っていただろう。想像して、一矢は小さく笑った。そんな一矢を見て、花絵は意味も解らず、ふふ、と笑った。そして、寂しそうに呟く。
「なんだか、おかしいですね。一矢さんとふたりでこんなところにいるなんて」
「そうですね」
自然とふたりは俯いてしまった。アズサの影を挟んで向かい合っているふたり。一矢にとって、同じ痛みを感じている唯一の人間が花絵だった。あんなに美しく誇り高かったのに、死を悲しむ人間がたったふたりしかいないなんて。
「お渡ししたいものがあるんです」
そう言いながら、花絵は手提げのバッグから布の袋を取り出した。不思議そうに見ている一矢の前で、その袋から小さなカメラを取り出し、テーブルにゆっくり、静かに置く。
「これ、先日警察の方からお返しいただいて……柚希の遺品なんですけど」
一矢は黙って、その小さなカメラを手に取った。そういえば、念のため警察が遺留品としていくつか預かっていると聞いていたが、このカメラもそのひとつだったのだろう。電源を入れてみると、カメラのボディに画像が表示された。充電は残っていたのか。
「一矢さんが持っていてくださる方が、いいかと思いまして」
ごくり、と喉を鳴らし、一矢は無言で表示されている画像を見つめていた。長いこと、そのまま身動きがないので、花絵は少し背筋を伸ばしてカメラを覗き込む。
「ああ、そうなんです。数枚しかデータがないんですけど、この夕日、綺麗ですよね」
「夕日?」
「え? あ、はい、夕日の写真。違いました? 夕日の写真しか残ってなかったと思うんですけど……」
再び体を乗り出してカメラを覗き込む花絵の姿を、一矢はぼーっと眺めた。夕日の写真だと?
「……ありがとうございます。じゃあ、預かっておきますね」
そう言うと、一矢は小さなカメラの電源を切り、ぎゅっと両手で握りしめた。
「それにしても、あの子、カメラの仕事しているって聞いていたからもっと立派なカメラを使っているのかと思っていたんですが……」
「ああ、これはあいつがいつも使っていたカメラではないです」
「あ、やっぱりそうなんですか?」
「あいつが使ってたのはNikonの……」
そこまで言って、黙る。やはり、あの部屋にあるのだろうか。アズサの部屋には、死後もほとんど足を踏み入れていない。確認した方がいいものも、もしかしたら残されているかもしれないな。
「お待たせしました、ブランコ特製ハンバーグでーす」
ジュージューと魅力的な音を立てながら、鉄板に乗ったハンバーグがふたつ運ばれてきた。そして見るからに美味しそうな焼き立てパン。色んな蟠りが胸に残っているけれど、とりあえず、今はご馳走を味わおうか。
「ふふ、いかがですか?」
「ああ、とても美味いです」
勧められるままにハンバーグを選んだが、たしかにこんなものを食べたら自分も他人に勧めたくなってしまう。ナイフを入れた時の肉汁に視覚的にも刺激され、まだ微かに油の跳ねる音を聞きながら口に運んだ弾力のある肉の食感。弾力がありながらも柔らかい。口に広がる、深みのある肉とソースのハーモ……
「一矢さん」
「え? あ、はい」
一矢が目を開けると、花絵は口を押えて笑っていた。
「いえ、ごめんなさい。目を閉じたまま、止まっていらっしゃったので、つい」
「ああ、すみません」
自分はそんなみっともない姿を見せていたのかと、恥ずかしくなった。まあ、それほど美味いのだから仕方ない。目の前にいたのがアズサだったら、脛を蹴り上げられていたかもな、なんて思ってから、また無意識にアズサと比べてしまったことに、申し訳なくなる。
「柚希も好きでした、このハンバーグ」
花絵が呟いた。
「そうだと思いました」
食後に一矢はコーヒー、花絵はレモンティーを注文した。店内のBGMを聴きながら、クラシックの流れる店でハンバーグなんて食べたのは初めてだったと、妙な余韻に浸る。
「柚希が、私に大切な人を紹介してくれるのなんて初めてでした」
大切な人ではなかったような気もするが、一矢もアズサが姉に会わせてくれるとは思わなかったので、その時は心底驚いた。
「ただの気まぐれだったかもしれません」
「ふふ、そうかもしれないですね」
それでも、花絵は間違いなくアズサの「大切な人」だったから、紹介してもらえて震えるほど感動したし、花絵が素敵な女性でありがたかった。アズサのそばに彼女がいてくれるということが、一矢にとっても心強かったのだ。
「あんなだから誤解されるけれど、悪い子じゃ、なかったんですよ」
「そうですかねぇ……」
「そんなこと言って……一矢さんが柚希を見る目はとても優しかったですよ」
「ええ……?」
戸惑う一矢に花絵は微笑んでいた。
「だから、初めて一矢さんにお会いした夜は、涙が止まりませんでした。あの子のそばにいてくださって、本当にありがとう……」
そう言った瞬間、花絵の大きな瞳から涙の珠が零れ落ちた。一度零れると止まらなくなり、ぽろぽろと頬を伝い、花絵は顔を両手で覆った。花絵の気持ちが痛いほど伝わってくる。それとともに、今こうして目の前で花絵がアズサを思って涙を零していることが、一矢の心を救っていた。
しばらく、そのままの状態で時間が過ぎてから、一矢はハッと我に返り、慌ててショルダーバッグを漁った。お姫様が泣いているのに、ぼーっと眺めてしまった。小さなタオルハンカチを握りしめ、そっと花絵に差し出した。いや、まて。ずっとバッグに入れっぱなしになっていたけど、涙を拭いても大丈夫か? 変な臭いとかしないだろうか。しかし、「ありがとうございます」と受け取った花絵の顔はもう、いろんな液体でぐちゃぐちゃだった。再び一矢はバッグを漁り、ポケットティッシュを取り出すと、それも差し出した。「ふふ、すみません」と言いながらそれも受け取る花絵。一矢は視線を逸らしたまま、「いえ……」と小さく呟いた。
「落ち着きましたか?」
「はい、もう大丈夫です」
恥ずかしそうに笑う花絵の目の周りは赤く腫れていた。右手をぱたぱたと振って顔を扇いでいる。一矢は気づかないふりをして、窓に目を向けながらコーヒーを口に運んだ。いくらお洒落な店でも、こんな都会では窓の外にいい景色など用意はできない。窓の向こうに見えるのは白いブランコの後ろ姿だけだった。
「これ、今度洗ってお返ししますね」
「捨てちゃっていいですよ」
「そんなわけにはいきません」
両手の上に乗せた一矢のタオルハンカチを眺めながら、花絵はゆっくり話した。
「一矢さんはどこまでご存知かわからないけれど……柚希が勘当されたのは、柚希のせいじゃないんです」
どこまでもなにも、両親とは仲が悪いとしか聞いていなかった。
「子どもの時は、母は柚希を溺愛していたんです。その頃から母は、精神状態が良くなかったんだと思うのですが、父や私のことも見えないくらい、柚希のことで頭がいっぱいでした」
アズサの幼少期なんて想像したことがなかったが、きっと天災的に可愛かったのだろう。
「でも、柚希が中学に入った頃から、母の様子がどんどんおかしくなっていって、柚希に当たり散らすようになったんです。なんだか、あの子に対して強いコンプレックスを感じるようになったみたいで……。それでも柚希はずっと冷めた態度で怒ることもなかったので、それもバカにされていると感じたらしく、また当たり散らして。もちろん、私も父も止めたのですが、柚希は柚希で冷静に母を煽ったりするので、もう、毎日地獄のようでした」
アズサの様子が想像できてしまい、胸が痛む。
「母は入退院を繰り返すようになって、次第に父も柚希のせいで母がおかしくなっていると考え始めてしまって……。柚希が高校生の時、母とやり合って、ついに警察沙汰になったんです。もちろん、母が悪かったのですが……実際、静かに煽り続ける柚希も少し不気味でした。でも、あの子をあそこまで追い込んだのは私たち家族なのに、全ての原因をあの子に押し付け、まだ高校生の柚希を両親は勘当したんです」
「高校生を勘当?」
「ええ、まあ、表向きは柚希が自立するために家を出た、という形にして、両親が学校も辞めさせて家を追い出しました」
「そんな……」
全然知らなかった。一方的な溺愛、執着からの勘当なんてものを子供の頃に経験したら、たしかに愛されるのが怖くなるかもしれない。理解できないアズサの言動にも、理由があったことを今更知った。今更だ。自分なりに、アズサのことを理解しようと努力したつもりでいたが、全く及ばなかった。本当に努力していただろうか。理解の及ばないアズサに魅力を感じていた面も、あった気がする。
『悪いけど、貴女とは違う世界に生きてるから』
『愛だとか恋だとか、虫唾が走る』
『もう二度と顔を見せないでね』
告白した亜季に、アズサが言ったセリフ。亜季から聞いた時は、プライドが高く、人を見下したとんでもない奴だと思った。まあ、実際それは間違ってはいないかもしれないけれど、事情を知ってみたら解釈は全く異なってくる。アズサはあの後すぐに退学していたから、時期的にはまさに修羅場だったのだ。
頭を抱え込んで黙っている一矢の前で、花絵もしばらく黙っていた。
「やっぱり……知りませんでした、よね」
「なにも……知りませんでした……」
知ろうとしなかったんだ。きつく閉じた目から涙が滲み出る。高校生のアズサの背中が目に浮かぶ。アズサ。今すぐ抱きしめたいのに。
「一矢さん。今日は、ありがとうございました」
「こちらこそ」
西口の前でお互い、頭を下げる。なんだか気まずかった。花絵もきっと、似たような気持ちを抱えている気がする。
「また近いうち連絡します。ハンカチもお返ししたいので」
そう言って、微笑む花絵の瞼も鼻の頭も、まだ少し赤かった。
今日一日で、アズサに近づいたのか、遠ざかったのか、どちらだろう。憎み続けるなんて、自分には無理だ。そんなの、わかっていたことなのに。アズサに激しく拒絶されても、正面から愛してやればよかった。
揺れる電車のドアに寄りかかりながら、一矢はバッグからアズサのカメラを取り出した。電源を入れる。映し出された画像は歩道橋の上、夕日を背に立っているあの日の一矢の写真だった。
あけましておめでとうございます。
実際明けてみたらおめでたくないことも沢山ありますが、自分の現状を変えることができるのは今後の自分と信じて、今年も気合いを入れて精進したいと思います。
昨年は大変お世話になりました。
今年も大変お世話になります。
同志の方々、noteを、創作活動を、末永く共に楽しみましょう。
読者の方々、これからも末永く楽しんでいただけるよう、精一杯、できる限りのことを尽くします。
いつもありがとう!!
2024年も、どうぞよろしくお願いします!!
Next……第10話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
