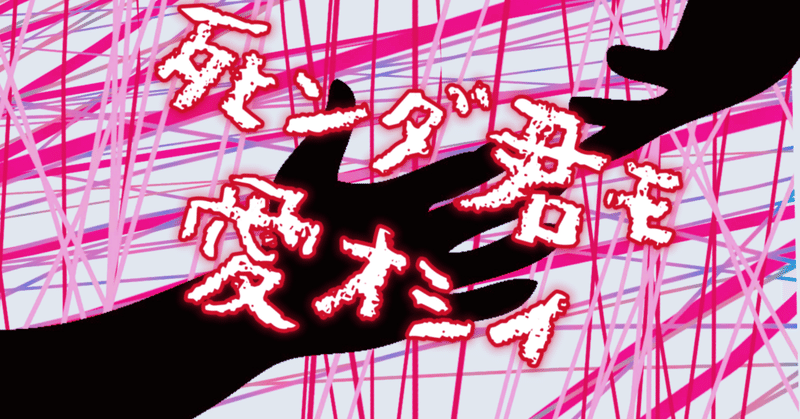
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第10話
Prev……前回のお話
亜季にアズサが放った言葉。
『悪いけど、貴女とは違う世界に生きてるから』
『愛だとか恋だとか、虫唾が走る』
『もう二度と顔を見せないでね』
冷たく亜季を突き放したことには違いない。このセリフだけでなく、追い打ちをかけるように、亜季がプレゼントした花を毟って食べたらしいから、やはりアズサがしたことには悪意がある。それでも、このアズサの言葉の意味を、俺たちは誤解していた。なんならSOSだった可能性すらある。いや、アズサに限ってそれはないか。好意を寄せてきた亜季に弱音を吐くような奴ではない。ただ、亜季のことを高い位置から見下していた発言ではなかったってこと。そしてタイミングが最悪だったということ。高校生の俺はずっと片思いしていた亜季を見ていたからこそ、傷ついて泣いている彼女のためにアズサが許せなかった。実際にアズサに出会ってみたら元々こういう奴なんだって諦めもついたけれど、俺にとっての最期の亜季がアズサにフラれた亜季だったことが、多分許せなかったんだ。結果的に、アズサの言葉通り、亜季は二度と顔を見せることはなかったし……。だから、想像もしなかった。当時のアズサのことを。好意を寄せられることに嫌悪感を抱く理由も、その後退学することになった事情も。
そんなこと、今更知ってもどうしようもないが……なんにせよ、これって間違い探しの答えじゃないのか? なぁ、金魚。
――そのようですね。
「え? ほんとに?」
――それも間違いのひとつかもしれません。
「これがアズサの遺言ってことなのか?」
――いいえ、間違い探しはただのゲームです。
そうだった、この金魚に「お前は何者なのか」と尋ねた時に、アズサの遺書だと答えたのだ。栞さん=アズサの遺書ならば、このゲームは遺言の前座のようなものなのか? しかし……詮索を許さず、秘密主義だったアズサが、本当に間違い探しなど、望むのだろうか。
一矢が首を捻っていると、栞さんはキラリと輝き、一矢の目の前をゆらゆらと上昇していくと、真っ暗なリビングの天井に張りついて明るい月になった。細かい月の欠片がチラチラと降ってくる。一矢は月になった栞さんを、間抜けな顔で見上げた。
「じゃあ、ゲームは俺が勝ちってことでいいのか?」
――まさか! これはほんの一部。なんの真相も見えていないのに。
真相? そんなものがあるのなら、たしかに何も見えていない。思っていたより面倒なゲームになりそうだ。しかし、例えばアズサの死についての話ならば、目撃者もいて、自殺には間違いないのだ。今更、実は犯人が……などという他殺の線は考えられない。ミステリー小説の世界じゃないんだから。
「真相ねぇ……」
一矢は呟きながら、肩に積もった月の欠片を払うと、煌びやかな音を立てて光の粒が舞った。その光の粒たちは、空中で消えることなく、ゆっくりと広がり下に落ちてゆく。再び一矢が月を見上げると、月になった金魚が優雅に空を泳いでいた。
たしかに何も見えてはいないが、ひとつ気づいたことがある。
告白してきた子の前で花を毟って食べるのは、やっぱちょっと変だよな。
「ところで……」
梓花絵と食後のコーヒーを飲みながら、店を出る前に、どうしても聞いておきたいことがあった。
「栞さんという名前の方をご存知ですか?」
「栞さん、ですか?」
確信はない。しかし、金魚の名前にしては些か響きが生々しい気がするのだ。
「うーん、私の周りには多分いらっしゃらないけれど……その方がなにか……?」
「いや、アズサがつけた金魚の名前なんですが……」
「ふふ、金魚さんの名前は知りませんでした。素敵な名前ですね」
「ああ、はい……まあ」
――アズサはどんな人間でしたか?
リビングの青い空を泳ぐ月が、欠片を散らしながらコロコロした声で尋ねてくる。
「どんなって……」
頭に浮かぶアズサの顔。思えば、意外と表情豊かな奴だった。人を馬鹿にしたような笑顔、支配欲が満たされた笑顔、冷酷な笑顔、誘惑に使う笑顔……碌でもねぇな。笑顔は腹立つが、怒っている顔は可愛かった。本気でキレている時は命の危機すら感じたが、アズサは適度に怒らせておくくらいがちょうどよかった。花絵の話を聞いてわかったことだが、アズサは元来あまり怒る人間ではないのだ。冷静に相手の神経を逆撫でするのが得意で、感情をぶつけることは多分苦手だった。その代わり、ガチでキレたら手が付けられない。だから、程よく怒るなんてことは、アズサにしては至極まともな人間らしい行いで、誰にでも見せる顔ではなかったのだ。
ふと、ごく稀に見せたアズサの怯えた顔が頭を過った。実際になにかに怯えていたかどうかは、わからない。本人に聞いたら、間違いなく否定するだろう。でもイライラと神経を尖らせて、一矢に当たる様子は、怒りとは違うものを感じた。そう、「友達」に会った帰りとか。大抵そういう夜は、手荒く抱けと強要してきた。もっと非道くしろと要求されても、応えることはできない。理由などひとつもわからなかったけれど、そんなアズサが可哀想だった。
友達……。いったい、誰だったのだろう。アズサの葬式にも、それらしい人は現れなかったけれど。会って、なにをしていたのだろう。まるで脅迫でもされているかのような……アズサのことを脅迫なんてできる奴がいるのか?
――勝手な妄想しないでよね。
「アズサ……?」
一矢が声の主を見上げると、夜空に浮かぶ鮮やかな朱色の栞さんがじっとこちらを見つめていた。
――どうかしましたか?
「今、お前……」
――イチヤさん、だいぶ疲れているようですね。
――可哀想に……今日はもう、おやすみなさい。
「え……?」
ブラックアウト。
なんてことだ。気が付いたらリビングのソファで寝落ちしてしまっていた。時刻7時半。窓から射す陽の光、無駄に爽やかな鳥の鳴き声、元気に張り切った車のエンジン音から、どうやら朝らしいことを知る。ここら辺に囀る鳥なんかいたか? いや、問題はそれではなくて……。
スマホの画面をもう一度確認する。月曜。月曜だと? 日曜はどこに消えた? おい!
一矢は立ち上がり、無意味に部屋を見渡してから、頭を抱えて考えた。梓花絵に会ったのが土曜の昼。で、その日の夜に金魚となにか話したのは覚えている。なにを話したのかはちょっと今思い出せないが、それは後でゆっくり思い出すとして、その後の記憶がない。うっかり寝落ちして、丸々一日寝続けるなんてこと、あるか? それだけ疲れてたってこと? 嘘だろ? しかし、不思議なほど体が軽い。頭はパニクっているが、すっきりしている。……っていうのはおかしいが、なんて言うんだろう、混乱は混乱でも、糸が絡まるような混乱ではなく、脳内でテキパキとボケとツッコミが働いている混乱というか……とにかく、じゅうぶんな睡眠、休息が取れたのは間違いなさそうなのだ。まあ、それならいいか、日曜がどこかに消えても。もう十月も後半になるのに、ソファなんかで寝てしまっては、風邪をひいてもおかしくない。腰やらどこかの関節やら傷めてもおかしくはなかった。なのに、上質な深い眠りから覚めたような爽快感。細かいことを考えるのはやめよう。そう、細かいことを考えている時間はない。なぜなら、会社に遅刻するからだ。
一矢はダッシュでシャワーを浴びて、あっという間に出かける準備を済ませた。良質な睡眠のおかげで無駄な動きがない。今朝の栞さんは普通の金魚だったので、普通の金魚の餌を撒く。いつもの一矢なら、こんな日は朝食を諦めるが、今日の一矢はひと味違う。冷蔵庫に古いゼリー飲料が入っていたのを覚えている。いつ買った物かは思い出せないが、腐ることもないだろう。こういう時のために買ったのだ、多分な。
結局、いつも通りの電車に乗ることができた。朝から既にひと仕事終えた気分だ。頭がすっきりしていると、なにもしていなくても達成感を味わうことができるらしい。電車に乗ってしまえば、後は余裕を持って出勤するのみ。もう焦ることもない。そう考えながら、いつも以上にゆっくりと、朝の街並みを眺めながらオフィスビルまでの道を進んでいると、視界の端に不穏なものを捉えた気がした。なんだろう、胸騒ぎがする。今一瞬、なにかが見えた。はぁ、嫌だ……。でも目を逸らす訳にはいかない。仕方なく一矢は立ち止まり、目の前のコインパーキングをゆっくり見回してみる。胸騒ぎの素は――。
「最悪だ……」
コインパーキングの横のブロック塀に貼られた子どもの絵。「すてきな町」をテーマにしたコンクールの受賞作らしい。見覚えがある。正体はこれだったのか。普通気づかねぇよ、こんなん。自分だって気づかなかったフリをしたい。って訳にもいかないよなぁ……。とりあえず、あいつをしばかなければ。
「井田!」
オフィスに足を踏み入れるなり、一矢は叫んだ。各々仕事の準備に取り掛かっていた社員たちが、驚いた顔で振り向く。
「えっと……井田君はまだ出勤してませんが……。いつもギリギリなので」
井田と同期の女子社員が答えた。一矢の様子を見て、社内に緊張が走っている。
「おいおい、どうした? 朝からなんの騒ぎだよ」
佐倉が椅子から立ちあがり、怪訝な顔をして寄ってくる。一矢は答える代わりに、大きな溜息をついた。
「あいつ、またなんかやらかしたか?」
「ああ……」
面倒なことになった。自分にも責任がある。
「あ、すげぇ、よく気づいたっすね」
遅刻ギリギリに出勤した井田獅子に、先程スマホで撮った写真を見せると、感心した様子で、拍手でもし兼ねない勢いだった。
「よく気づいたっすねじゃねぇよ。お前なにしたかわかってんのか? 子供が描いたデザイン、パクってんじゃねぇよ!」
「はっはっはっは」
「佐倉、笑ってる場合じゃねぇだろ!」
「いやいや、これをロゴに使っちゃうっていう発想、なかなかないよね。……へぇ、なるほどねー」
佐倉は一矢のスマホを手に取り、興味深そうに画像を眺めている。ここは社長に厳しく問責してほしいのに。
「え、でも、著作権的にはギリセーフっすよね?」
「そういう問題じゃねぇだろ……プロとしてのプライドとかねぇのか、お前は」
「特にないっすね」
「はあ……」
こいつに任せたのが間違いだった。
「とにかく、先方に謝罪して、作り直しだ。お前はもういいから、柿谷に引き継いでもらえ」
「え、いいんすか?」
「いいんすか、じゃねぇよ。普通は俺にやらせてくださいとか言うとこだろ。謝罪には俺とお前で行くからな」
「げ、わざわざ行くんすか?」
「わざわざ行くんすよ。誰のせいだと思ってんだ。お前を連れて行かない方が絶対安全だってわかってるけど、そういう訳にはいかないからな。自分が担当したものは責任とれ」
「なんか今日、広川さんめっちゃ喋るっすね」
「殴られたいのか?」
「いや、たしかに今日の広川、久しぶりにキレがいいな」
「佐倉まで何言ってんだよ」
とは言ったものの、言われてみれば自分でも今日の説教にはキレがある気がしてきた。やはり、しっかり睡眠をとったおかげなのだろうか。こんな状況なのに、気分は悪くない。
「謝罪の電話は俺が入れるから、連絡先送ってくれ。どこの仕事だっけ?」
「あー、えっと、メーリングエステートっすね。不動産屋の」
「そんな会社、リストにあったか? もういい、自分で確認する」
「さーせん」
一矢はやっと自分のデスクに辿り着き、PCを立ち上げながらテキパキと準備を整える。井田のせいで缶コーヒーを買い損なった。とりあえず、まずは謝罪の電話を入れてからだ。
ファイルを開き、直近の顧客リストを確認する。えーっと、これか。
「ホワイトメール・エステート……?」
どこかで聞いた。気のせいではないと思う。当然、井田のチェックをした時に目にしていてもおかしくはないのだが、その時には気づかなかったのだ。今ならわかる。冴えた頭で考える。覚えのある不動産屋といったら、やはり、あれだろう。
鞄を漁り、財布を取り出す。名刺入れではなく、財布のポケットにしまっている一枚の名刺。なぜか秘密にしたがって、この名刺を手に入れるのに苦労した。
ホワイトメール・エステートは、アズサがいた会社だった。
Next……第11話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
