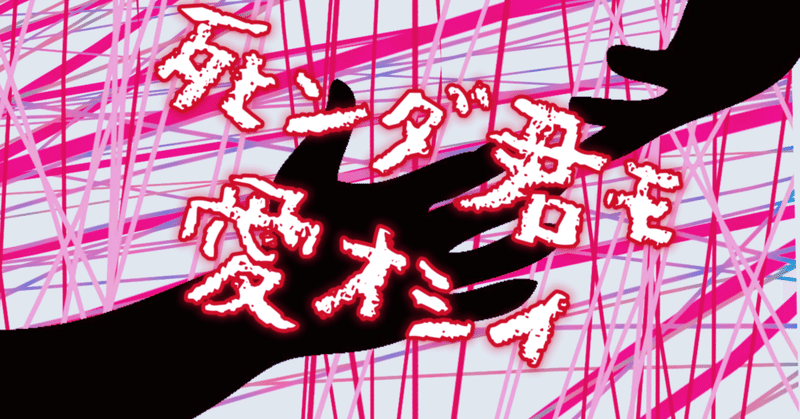
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第11話
Prev……前回のお話
午前中に謝罪の電話を済ませ、その日の午後に菓子折りを持って直接向かうことにした。一矢の会社からだと電車を乗り継いで五駅。アズサが働いていた不動産会社ホワイトメール・エステートはHヶ谷の駅から歩いて五分の場所にあった。とはいえ、ごちゃごちゃしてわかりづらい細い道を進み、やたらと歩道に駐輪してあるし、そもそも井田が腹を壊したとか言って会社を出るのが遅れたために、余裕がなくなった一矢は焦りと緊張で季節外れの汗をかいていた。
ロゴの依頼を頂いた会社に、あろうことか子どものデザインをパクった前代未聞の粗悪品を納品してしまった。今回はその謝罪に行くのだ。担当者を連れて、一矢は会社の代表として謝罪に行く。勿論、目的はそれだけのはず……なのだが。今の一矢の頭の中は別のことでいっぱいだった。仕方ないだろ? 働くアズサのことをよく知る人間に会いに行くのだ。こんなチャンス、今までなかった。
「あ、ここじゃないっすか? なんか汚ぇけど」
「おい」
一矢は井田の頭を叩いた。しかし実際、綺麗とは言い難い。ガラス張りの外観はもっと明るい印象にできるだろうに、なんだか陰気臭いし、全体的に薄汚れている。一面に貼ってある物件の間取り図すらも最新のものなのか怪しいほどだ。しかし、ガラス扉の横に小さく「ホワイトメール・エステート」と書かれたピンクのステッカーが貼ってあるので、間違いないだろう。ここがアズサの職場か……。名状しがたい思いが込み上げる。
扉に手を掛けようとして、一度井田を振り向いた。
「なんすか?」
「いいか、お前は余計な口を利くな。謝罪の時だけしっかり頭を下げて、可能な限り黙ってろ」
「了解っす」
ふう……と大きく息を吐いてから、一矢は重いガラス扉を引いた。
「失礼します」
そろそろと中に入る。静かなBGMが流れる店内に、人の姿は見えない。思った以上に狭く、接客用の長いデスクがL字型にあるだけで、小さな椅子が五つしかないところを見ると、そんなに繁盛している不動産屋ではなさそうだ。まあ、あの外観じゃなぁ……。店員すらいないのだろうか。一矢がもう一度、挨拶の声を上げようとした瞬間、「ゴン!」とどこか下の方で鈍い音がした。
「いでッ!」
音と共に呻き声がして、L字型のデスクの下から気の弱そうなメガネの男の顔が覗いた。
「あれ? すみません、ちょっと大事なものを落としてしまって……へへ」
「ああ、大丈夫です、お探しください」
一矢が声を掛けると、すみませんね、とまあまあ申し訳なさそうに言いながらメガネの男は再びデスクの下に潜った。
「ご相談ですかぁ?」
デスクの下から声が聞こえる。おいおい、どんな接客だよ。まあ、こちらは客ではないが。そもそも、頭を下げに来ているのに、謝罪相手が地べたを這っているのは決まりが悪い。
「いや、えっと……リストランテ・デザインの者ですが」
「レストランの方?」
佐倉が紛らわしい会社名を付けるから、こういった無駄なやり取りが度々生じる。
「いえ、デザイン会社のリストランテ――」
「ああ! ロゴの!」
はい、と答えながら、一矢はもごもごした。デスクの下にいる姿の見えない相手に謝罪をするのは失礼にあたるだろうか。やはり顔を見て頭を下げなきゃダメだよなぁ。でもこんな状況で話しかけられてしまって、会話を交わしているのに謝らないのもどうかと思う。
「ほんと、この度は――」
「あったぁ!」
嬉しそうなメガネ男の声に、「あ、よかったですね」と小さく返した。
「へへ、結婚指輪……失くしたら家を追い出されちゃうとこでした」
サイズを合わせて作った物だろうし、外さなければ職場のデスクの下に落とすようなものでもない気がするが、まあ、そんなことはどうでもいい。
「ああ、すみません。デザインの方ですよね?」
メガネは左手の薬指に指輪を嵌めながらそう言うと、「ちょっとお待ちくださいね」と言いながら、奥の方へ消えていった。見えない扉の向こうで、微かに話し声が聞こえる。そしてすぐに、「こちらへどうぞ」と案内された。
「この度は誠に申し訳ございませんでした」
扉をくぐるなり、頭を下げると「まあまあ、お座りください」と頭上から野太い声が降ってきた。
「今日は社長がいなくてラッキーでしたね」
野太い声の主は腹回りも太く、シャツのボタンがはち切れそうな大男だった。通された奥の部屋は埃っぽく、資料の束が乱雑に幾つもの山を作っていて、少し煙草の臭いがする。安っぽいソファとローテーブルが置いてあるところを見ると、一応、応接室なのだろうか。
「ま、社長はこんなことじゃ怒らないですけどね……優しいから」
怒るか怒らないかは知らないが、どの道社長の耳には入るだろう。一矢はなんとなく、再び頭を下げた。
「あの……コーヒー……失礼します……」
消え入りそうな女の声に振り向くと、消え入りそうな年齢不詳の女がいつの間にか隣に立っていて、一矢と井田の前にuccの紙コップに入ったコーヒーがそろそろと差し出された。「どうも」と言いながら、井田がコーヒーを啜る。しっかり謝罪する前に手を付けるなよ、と思いながらも、段々この井田の図太さが羨ましくなってきた。
「あのロゴ、社長結構気に入ってたから残念がるだろうなぁ……。でも似た絵が見つかっちゃたなら仕方ないですよねぇ」
「申し訳ありません……」
正確には似た絵が見つかったのではなく、パクったものなのだから申し開きの余地もない。しかもどこかの小学校に通う子供の絵。下げた頭を上げることも憚られる。
「まあまあまあ。もっといいデザインを用意していただけたら問題はないし。社長にはなんとか言っておくから大丈夫ですよ」
「ええ、それはもちろん、ご用意させていただきます」
「最初にいただいた候補の中に便箋みたいなのもあったでしょう? あれも社長は気に入ってたから、ああいう感じでいいかもですね」
「ああ、あれですね。社名の『ホワイトメール』をイメージしたデザイン」
「そうそう」
こんな時に、ふと、頭に蘇る記憶。
「ホワイトメールって変わった名前だね。なんか意味あるの?」
以前、無理矢理アズサから名刺を手に入れた時、会社について尋ねてみた。
「さあ……特に意味はないんじゃない。うちはブラックだよ」
アズサから聞き出せた話はこれくらいで、それ以上は教えてくれなかった。秘密にしたいというより、あまり話したくないようだった。ブラックという割には、残業もそれほどなさそうで、ブラックの意味がわからなかったが、アズサが自分の職場に誇りを持っていないことは、なんとなくわかった。そして今、思いがけずその現場にいる。仕事は暇そうに見えるし、野太い男の話を聞く感じ、どこがブラックなのかわからないが、アズサ的には何かが引っ掛かっていたのかもしれない。
「では、そんな感じで」
「はい、再度資料が纏まり次第、こちらからお送りさせていただきます」
なんとか話がつき、やっと一矢は紙コップのコーヒーに口を付けた。当たり前だが、冷めている。このuccのインスタントコーヒーは、アズサが朝によく飲んでいた。こんなものですら、一矢には入れてくれず、「自分で入れなよ」と冷たく突き放し、窓際に立ってひとりで飲んでいた。お湯を注ぐだけなのに! そしてお湯は沸いているのに! 悔しかったから、一矢はこのコーヒーを飲むことはなかった。多分、今初めて飲むのではないか? アズサがいた、この職場で。
「あの……失礼ですが」
立ち上がりお暇しようとして、一矢は足を止めた。
「梓柚希という社員が……いたかと思うのですが」
「えっ……」
野太い男は顔を強張らせた。そりゃそうか。つい最近自殺したばかりの人間。こんな小さな会社なら、きっとよく知っていただろう。
「ああ、すみません。私、生前少し親しくしていたもので……」
一矢が言うと、野太い男は「ああ」と表情を少し緩めた。
「柚希ね……。謎の多い子でしたね。あいつ全然話さないから詳しくはわかりませんが……柚希は社長のお気に入りでした」
「お気に入り?」
「ええ、なんでも、行く当てのない柚希を社長が拾ってきたとか」
「ああ……」
「柚希にとっては恩人だったんでしょうね。社長のために一生懸命働いてましたよ」
まさかこんなことになるとはね、と呟きながら、野太い男は俯いた。
恩人か……。アズサにも誰かに恩を感じる心があったとは。正直意外だった。メガネに見送られながら、やはり変わらず客のいない不動産屋を出て、日の当たらない細い歩道に出る。
「柚希って、あれっすか、亡くなった恋人?」
「うわっ!」
突然背後から井田の声がして、飛び上がるほど驚いた。
「おま、お前、いたんだな。静かだったから忘れてた」
「黙ってろって言ったの、広川さんじゃないすか」
「ああ、まあ、たしかに」
黙っていたからといって存在に気づかないわけはないのだが、途中からアズサのことしか考えていなかった一矢の視界には、静かな井田の姿は輪郭のぼやけたオブジェのようにしか映らなかったようだ。
「よくやったな」
「なにもしてないっすけど」
「お前にしては上出来だ」
一矢は井田の背中をポンポンと叩いた。
「で、さっきの柚希って――」
「なんだあれ」
「え?」
細い歩道にはみ出て駐輪されている自転車を避け、向こうを覗くと、薄汚い花壇に潜り込んでいる男がいる。何かを探しているようだ。
「ねぇ~シン君、もういいよぉ」
男のそばに立って、少しだけ周りを気にしながら声を掛ける若い女。
「ぜってぇ見つけっから、黙って待ってろって」
あんな手入れの行き届いていない花壇の中に、何をどうやって落としたのか知らないが、きっと大事なものなのだろう。ついさっき、こんなシーンを見た気がする。手伝うべきか? いや、見知らぬ男女にそんな義理はない。しかし、何を探しているのか少し興味がある。あの花壇から、いったい何が出てくるのだろう。
「どうしたっすか? 広川さん」
背後にいる井田が、なぜか立ち止まる一矢に声を掛ける。
「あったぁ!」
「ほんとぉ? 見せて見せて」
「やべぇ、マジで消えたかと思ったわ」
男が花壇に埋まっていた上半身をヌボッと引き抜き、誇らしげに手のひらの上のものを見せる。一矢はこっそり首を伸ばして覗き見て、ヒッと声を上げた。まるまる太った大きな幼虫が手のひらの上で蠢いている。その幼虫は更にムクムクと膨らむと蛹のようなものに変わり、忽ちその背中を割って翅が伸び出て、美しい蝶になった。その艶やかな蝶は大きなTシャツくらいまで育ち、花壇男の手のひらから飛び立つと、ばっさばっさと音を立てながらどこかへ羽ばたいていった。
「シン君、ありがとぉ~。大事にするぅ」
「おぉ、頼むぜ、給料三か月分だからな」
三か月分の給料が羽ばたいていったけれど、どうやって大事にするのか……、いや、今のは魔法だったのか? 手品? 手品に給料三か月分かけたのか、この男は。すっげぇな。こんな場所であっさり披露しちゃってよかったのか?
「おい、見たか、今の」
一矢は興奮気味に井田を振り向いたが、井田は横を向いてスマホを眺めていた。
「え? なんすか?」
マジか。こんなに側にいたのに、今の衝撃を分かち合えないなんて。
「はあ……。お前って、ほんと井田だな」
「なんすか、それ」
「もういい。さっさと帰るぞ」
「広川さん」
「なんだよ」
「駅、反対っすよ」
「……早く言えよ」
ばっさばっさと、先程の蝶が羽ばたく音がした気がして、一矢は頭上を見上げた。秋の雲が漂う、よく晴れた空だった。
「シン君~、ひつまぶし食べたいなぁ」
「ふはは、いいぜ~、今日は奢ってやるよ」
「やったぁ、特盛ね!」
Next……第12話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
