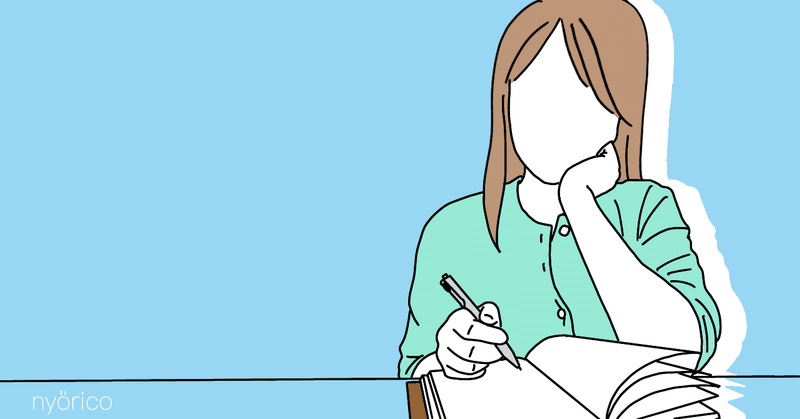
248.勉強が楽しかった小学生の頃の先生たち
勉強が楽しいと特に感じていた時代がありました。
小学六年生の頃です。
基本的に勉強は好きですが、なぜ特にその頃が楽しかったのでしょうか?
勉強の内容が難しくなかったから、でしょうか?
中学になると算数は数学になりますが、変わらず数字と計算は続きます。
国語、理科、社会は、古文や古典や現代文、生物や物理や化学、歴史や地理や政治など細分化されます。
ただ、小学生の国語算数理科社会という4科目は、そうした世の中のすべてを包括しているほど広かったともいえます。
では、初めて知る内容ばかりだったから、でしょうか?
しかし小学生にとって初めて学ぶという点は、高校で初めて微分積分を学ぶときと、さほど変わりません。
そして学ぶ内容も、全小学生はだいたい同じです。
大きな違いはなんだったのかと考えたところ、一つの結論に至りました。
先生です。
「塾に行ってみては?」と促してくれた小学四年生時の担任の先生
小学生の頃、正直学校の勉強が難しいと感じたことは一度もありませんでした。
テストに困ったことも、覚えられない、わからないといったことも、たったの一度もありません。
友達と遊びに小学校に行っていたぐらいの感覚だったのを覚えています。
そんな僕を見てなのか、小学四年生時の担任の先生が保護者面談のときに、僕の母にこうおっしゃったそうです。
「塾に行かせてみてはいかがですか?」
学習塾へ通う提案をされたそうです。
中学受験というのは、親にとっても当時はとても現実離れした、他人事のような世界だったでしょう。
両親は互いに地元の中学校に進学して、最終学歴だけ見ると父は高卒、母は専門学校卒です。
ただ中学受験は、その先の高校進学だけでなく、大学進学も視野に入れた挑戦の一つになってきます。
親からしても、未知の世界のはずでした。
母がいろいろ調べてくれた結果、僕は「成基学園」という学習塾の入塾テストを受けることになりました。
このときはまだ、僕は母の動きも先生の助言も知りません。
ただ僕を自由奔放にさせてくれていた当時の学校の先生、特に小学四年生から六年生にかけて一番やんちゃな頃を見てくれていた担任の先生には、とても感謝しています。
名前ももちろん、はっきり覚えています。
今振り返ってもとてもいい思い出のある先生方ばかりでした。
さて、そんな僕は小学五年生になって、いよいよ入塾テストを受けます。
入塾、といっても受験も塾も存在自体を知らないわけですから、なんだかよくわからないまま足を運んでいたように思います。
当時の入塾テストはIQを計測するような内容で、勉強とはまた違った頭の使い方をする問題が並んでいました。
こういった問題は子どもの頃から得意で、結構手応えを感じてテストを終えます。
結果も手応え通りだったようで、ぜひ入ってくださいと言われて入塾したのを記憶しています。
ただ、塾に入ったからといって何がどうなるかはまったく想像はついていませんでした。
本気で生徒の結果に向き合う塾の先生たち
塾での初めての授業は社会でした。
歴史の授業で、縄文時代、高床式倉庫という言葉が黒板に書かれていたのを見て、僕はこう思います。
「日本の昔って、勉強するものなんだ」
兄妹はいましたが長男なので、僕の少し先をいく身近な存在はいません。
故に小学校では六年生から習う「歴史」という分野を学ぶことは、当時小学五年生の九月の段階だった僕は知る由もなく、そもそも勉強する内容自体に驚いていました。
算数の授業では、因数分解という考え方を習います。
僕はこう思いました。
「もっと早く教えてくれよ……」
計算が楽になりますから、もっと早く知りたかった、なんてことを思っていました。
塾のクラスは4つに分かれていて、最初は一番下のクラスから入ります。
定期的に小テストがあり、成績が良い状態をキープしていると上のクラスに上がる、という仕組みでした。
僕は一番下の4クラスからのスタートです。
1クラスには難関中学に挑戦する人ばかりがひしめいているようでしたが、難関中学に行くぞ!なんて気概は入塾早々ありませんので、特に興味はありませんでした。
当時は壁に、クラスアップにつながる小テストの成績が上位5名から10名分、貼り出されます。
最初の勉強の原動力は、その壁に貼られたランキングに名前が載るのが嬉しかった、ただそれだけでした。
文字通りゼロスタートだったので、そこから自分でも驚くほど成績は上がりました。
小学五年生の九月に入塾するのは一般的には遅く(一年数ヶ月で受験を控えることになるため)、周りの同い年の友達はもっと前から入塾している人ばかりでした。
そんな中、みるみる成績を上げて僕はすぐに3クラスに上がります。
そうすると周りの人も3クラスの人ばかりで、人も学ぶ内容もちょっとレベルアップするんだな、と思っているうちにトントン拍子で2クラスまで上がりました。
(難関中学は志望校にはなかったので、成績があっても1クラスなは上がれませんでした。特別な難関校の対策をしていたのだと思います。)
そのあたりから感じていたのは、先生のありがたさです。
科目の中では算数が苦手でしたが、夏休みに3日間の特訓コースがあるといって応募したところ(今思うとこれも親がお金を出してくれていました。結構な費用だったと思います。)、本当に3日間で見違えるほど算数の成績が上がりました。
これには本当に驚きでした。
3日間、ほとんど丸一日勉強するのですが、苦痛ではなく、算数の担当の先生がめちゃくちゃ優しい男性で、楽しく、ただひたすらに一生懸命勉強したことを覚えています。
小学六年生になると、一週間のうち火木土日が塾の日になります。
火木は学校が終わってからなので、塾が終わるのは21時を超えるのですが、その後に国語の先生に質問に行って迎えに来てくれた親を待たせる、なんてことも日常茶飯事だったそうです。
毎週日曜は、先生がクラスにつきっきりで、9時から12時でテスト、昼休みを挟んで夕方まで解説、その後なんとその日のテストが採点されて返ってきて、20時まで解説や振り返り、というとんでもないスケジュールをこなしていました。
しかも昼休みは確か20分間だったと思います。この頃に看護師の母親並みに昼食を早く食べる力が身につきました。
今ではもうできるかわからない一日の過ごし方です。
こうして僕ら生徒も一生懸命勉強していましたが、それはひとえに本気で向き合ってくれる各科目ごとの先生たちのおかげでした。
もちろん第一目的は合格ですが、単に受験に受かることだけでなく。
単に記憶すること、新しい知識を増やすことだけでなく。
ただ点数を上げるためのスキルテクニックでもなく。
人として、小学六年生という大人からするとガキンチョたちに、本気で向き合ってくれていた、その想いが伝わってきました。
テストを返して、何点以上だった人は耳を塞いで、と言われて、それ以外の人に怒鳴るぐらい思いっきり喝を入れていた理科の先生もいました。
その先生は普段の授業はユーモアに溢れてとても面白く、笑いの絶えない授業が好評で、塾でも大人気の先生でした。
そんな先生が、自分の子どもでもないのに、本当にこれでいいのか、このままでいいのか、と生徒たちを本気で叱っている姿は、当時理科は得意で耳を塞ぐ側だった僕の記憶に、今でも残り続けています。
この頃は、勉強法も学びました。
勉強するという感覚も、この塾や先生の教えを通して養いました。
結果第一志望の中学校に受かりましたが、たくさんのことを体感で学ばせてもらった一年間だったと思います。
よき師をみつける
書いていたらいろいろ思い出してきました。
濃い一年だったんだなと思いますが、同時に今自分のことも思い返してみます。
こうした先生という存在は、社会人になるといなくなります。
会社の上司や先輩だったり、あるいは何かしら勉強されているならその分野の講師の方、そういった人たちが自分の学ぶ人となっていきます。
独学で何かを立ち上げた方もいらっしゃるかもしれせんが、基本的には誰かの何かから学んで、今の自分がいるという場合が多いのではないでしょうか。
どの世界でも大成するのに大切なのは、学ぶ人を決めること。
『金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント』に書かれている「ラットレースから抜け出すための七つのステップ」に、似た内容が書かれています。
五つ目のステップ「よき師を見つける」。
「プロにはみんなコーチがついている。アマチュアにはコーチが付かない。」と書かれています。
未来を変えるためには「考え方」を変えなければならない、とも散々書かれています。
ただ師匠を選ぶなんていうのはおこがましいので、すでに理想の未来像に到達している方を師匠として見つけ、弟子入りにいく。
それが師匠と弟子という関係性では健全なものだと思います。
プロ野球選手でも、若手は一流選手とオフシーズンに一緒に練習をしたいですと申し出ます。
どうやったら見つかるんだという、探すマインドではありません。
師匠を見つけるには、そもそも理想とする姿を設定すること。
それが人生を変える一歩かもしれません。
学びたいです、と申し出たときは、さらに大きな一歩を踏み出していると思います。
僕も大きく変化させ、大きな結果を手にするために、まだまだ学び続けます。
あの頃の勉強のように、明るい未来を見据え、本気でやればきっとなんでも楽しく一生懸命日々を生きられるでしょうから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
