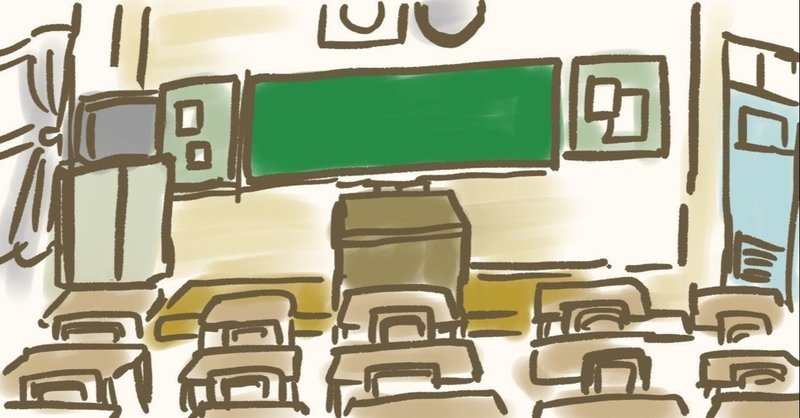
【学級経営】望ましい学級集団をつくるために大切にしたいこと。
「人間関係は複雑」と言われている割には、「単純な判断で関係を構築しているな。」と感じているJUNです。
僕が昔から集団生活が苦手なのは周知の事実だとは思いますが、そんな子どもこそ、意外と「集団の雰囲気」や「グループ内の力関係」などを冷静に見て把握している場合が多いものです。
僕自身も集団生活が苦手だからこそ身に付けられた力として、「人間観察力」と「話しかけないでオーラ」の2つは誇れるのではと密かに思っています。
そして、「学級の人間関係のバランス」を取ることに関しても、関東選抜くらいにはなれるのではないかと自負しております。以前の記事にも書いたような気がしますが、学級を安定させるには、「より良い学級をつくりたい。」という子どもたちの集団を「学級何てどうでもいい。」集団よりも多く保っておく必要があります。いわゆる学級崩壊は、「どうでも派」が「より良く派」を上回った状態です。
「どんなに頑張っても2割の人には嫌われる。」
と言われているくらい、教師がどのような人物でどれだけ子どもたちのために力を尽くしたとしても、届かない子どもたちもいるのです。ですから、「全員を!」という目標を掲げて夢を語るのは自由なので良いと思いますが、少なくとも「より良く派」を与党として保っておく必要があるのです。
前段が長くなりましたが、本日はこんな話題。「安定学級を築くこつ。」や「集団を組織する上で気を付けたいこと。」をまとめましたので、参考にしていただけたら幸いです!
▶絶対にやってはいけないこと。
さて、まずは「集団を組織する上で絶対にやってはいけないこと。」を書いていきます。
ずばり、やってはいけないこととは、
「2つのグループによる対立構造。」
を作り出すことです。
ひと昔前では、「競争こそ命!」、「切磋琢磨すべし!」的思想により、競い合って高みを目指そうという指導が流行っていたことは間違いありません。
「男子対女子」のような二項対立構造を作ってしまうことで、切磋琢磨というようりは、「つぶし合い」のような戦いが生じでしまいます。人間は、
「二項対立になった瞬間、自分のチームに肩入れして、必要以上に相手チームを敵視してしまう。」
という特性があります。
あなたにも、普段は仲が良い友達なのに、2チーム対抗〇〇大会になると必要以上にライバル視してしまったことはありませんか。小学生くらいだと、勝負が終わった後も、引きずってけんかしてしまうこともあります。普段は、あんなに仲が良いのに不思議ですよね。
このように「どれだけ仲の良い友達同士でも、二項項対立の敵になった瞬間から様子が変わる。」ということが言えます。
簡単なゲームでさえも絶大な効果を発揮してしまうので、学級経営の際は、ご注意ください。
▶人間関係を向上させる方法。
では、個性的なメンバーが自分のもてる力を存分に発揮できるような「安心学級」をつくり出すために効果的な方法も紹介しますね。それは、
「協力場面の設定。」
です。
やはり、より良い人間関係を構築する際、「協力」に勝るものはないのです。
おもしろいのは、
バスで隣同士になるのを嫌がるほど対立が激化していた2つのグループが、キャンプファイヤーをみんなで準備したことで、帰りのバス内では仲良くなっていた。
という事例もあるほどです。
この事例からも分かるように、
「何かしら『協力』して作業を行うことが、仲を深めることにつながる。」
という結果が分かっています。
ということは、教師や大人が子どもたちの関係性をもっと良くしたいと思うのであれば、
「みんなで協力しないと実現しないような課題。」
を常に意識して設定することが必要なのです。
しかし、過去の記事にも書いたように「グループ活動」というのは、なかなか奥が深いものです。
ざっくり言うと、目的は共通でも、「自分の活動」を一人ひとりが確保して取り組めるようにする必要があります。そして、その努力が成果となったときに、「僕の〇〇が、成功に一役買った。」という「個の達成感」をもちつつ、「みんなが努力したから成功までたどり着けた。」という「集団としての達成感」を獲得することで「僕は集団の中の大切な存在であり、僕が所属している集団は最高だ!」という満足感となり、結果的に「集団としての仲を深める」ことになるのです!!
▶まとめ。
本記事では、「仲を深めるには『個』を大切にした協働作業を!」という内容をまとめました。
やはり、皆さんもうすうす気がついていたように「誰かと協力して何かを達成した。」という経験は、互いの仲を深めていくのです。
公立学校は、まだまだ集団指導が続きそうです。そんな学習形態だからこそ、「共通の目標設定」にこだわり、「協働場面」を意図的、計画的に設定していきましょう!!
いただいたサポートは、地域の「居場所」へ寄付させていただきます!
