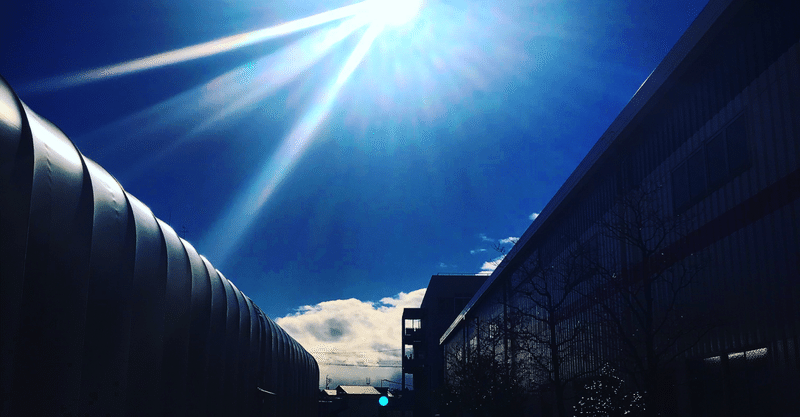
夢をかなえる経営計画「会社を元気してて、黒字化を実現する最強ツール」③著者:赤岩 茂
【3Point】
①経営計画
経営計画というと一般的に「数値計画」を思い浮かべますが、実際の経営実務においては、具体的な経営活動の結果、その数値をいかに実現していくかが課題なのです。そのための方針等が明示されていない、単なる数値計画は役に立たないといっても過言ではありません。経営計画書には、少なくとも次のような事項を記載すべきです。
1.我が社の存在意義
2.我が社はどこに向かおうとしているのか
3.そのために、何をすべきか
4.今年の重点課題は何か、それをどのように具現化するか
5.具体的に何をすべきなのか
②経営理念を浸透させよ!
経営理念を確立した経営者は全身全霊を込めて、その浸透に意を用いるべきです。
経営理念を浸透させる段階は次の3つに分けることができます。
(1)経営理念を落とし込め
社内に経営理念を掲示するだけでなく、朝礼や会議での「経営理念の唱和」が有効です。声に出すということは、各自の潜在意識に落とし込むことを意味します。大きな声で毎日繰り返し唱和することが大切です。
ただ、これを空念仏にしないように、不定期に「経営理念確認テスト」を行うのも浸透度合いを確認するために有効的です。このテストは。経営理念を記述させ、かつ、日常業務の中でどのように実践しているかを書かせるのもです。
情報の価値を決めるのは受け手ですので、いくら経営者側が情報を発信しても、受け手である社員が確実に受け止めなければ情報は伝わりません。このためにも、社員の理解度テストは有効な手法です。
(2)経営理念に基づく行動指針を作れ
経営理念の字面を覚えているだけでは効果はありません。次の段階では「行動指針とする」ことが大切です。
例えば、活気ある企業風土を保つために、挨拶の意味(心を開く、相手との架け橋を作る)といった本質を社員が理解した上で、自主的にするのと、ただ形だけでしているとでは相手に与える印象も異なります。
(例)【わが社の「元気のよい挨拶」の定義】
●立ち止まり、相手の目を見て
●大声で、はっきりと
●礼は四十五度の角度ですること
と具体的な指針を示した方がよいです。
(3)経営理念を念頭に行動指針に従って実践せよ
理解しても実践されなければ意味がありません。社員に実践を促すには次のような手段が有効です。
【1】まず経営者自身が経営理念を順守せよ
経営者自身が意思決定したり、行動したりする場合、経営理念に照らし合わせて妥当かどうかを検討し決定する習慣をつけましょう。仮に経営者が明らかに経営理念とは正反対と受け取られる行動を続けると、社員はその企業の判断基準は、すべて社長自身にあるとして、経営理念を重視しなくなってしまいます。
【2】日常業務の中で、成功事例・失敗事例を公表せよ
社内の会議等で、各社員の日常業務での成功例と失敗例を公表すると、知識・体験の共有化ができますが、そのような場合に、「経営理念」に照らし合わせてどうだったか、という視点から分析するようにすると、理念の浸透・実践の上で大変有効です。
【3】社員の採用選考時の留意点
中国の歴史書である司馬光著『資治通鑑』によれば、人物を採用する場合、才徳兼備の人を採用すべきであるが、才子(才能は優れているが人間性が未熟な人)と愚人しかいない場合には、むしろ愚人を採用せよ、と説いています。人間が成長する場合、土台がしっかりしていなければなりません。このしっかりとした「人間性」があれば「技術力」は教育でまかなうことができます。
③「戦略とは、現状からのビジョンへと誘う架け橋である」
いくら現状を見つめなおし、壮大なビジョンを策定したとしても、ただ願っているだけではビジョンの実現は叶いません。実現するためには、現状からビジョンに至る「架け橋」「ロードマップ」を作成し、それに沿って行動していかなければならないのです。
ビジョン(未来)から現在を見つめ直すことで、経営課題が見えてきます。例えば、3年後に、新事業を展開しようと意図したとします。現状ではそのための経営資源である新事業を担う人がいません。この「人がいない」状態を解決すること、すなわち、「人的資源の強化」が経営課題になるのです。
(課題:例)
●お客様は誰か
●お客様が必要とする商品・サービスは何か
●具体的にどのように提供するか
など
【1Action】
[発見]
中小企業にこそ経営戦略は重要。
市場における自社の位置づけを確認することが大切です。
常に中小企業はシェアがトップの企業に優れたモノ・サービスを同質化戦略(模倣)をされてしまうことが課題としてありました。
「すぐに模倣される」「うちは経営資源がない」「人がいない」と中小企業は嘆くのではなく、創意・工夫で差別化を図り、売れる商品を特定市場に投入し続けるべきなのです。
成長を辞めた衰退がはじまります。だからこそ、成長を止めてはいけないのです。そこで成長し続ける組織にデザインしていかなければならないのです。共通の目的(経営理念)を実現させる、経営環境に適用させる、企業行動(事業活動)を効率的に運営するために経営者は組織を設計する必要があるのです。
1+1=∞
組織を活かすも殺すも経営者の采配次第なのです。
[行動]
「何を変えたらうまくいくのかを常に考える」ことこそ、自分を変えるヒントがあります。
何かを変えるという作業は苦しいものです。その変える作業として前に進めるのは2つあります。
1つ目は楽しむ(わくわく感)です。
コロナによって会社に行かないでリモートワークになったり、学校では対面授業から自宅学習になったりと、大きな変化がありました。そこで強制的に変化を強いられ、働く従業員、学生は苦しい思いをしたと思います。そんな急な変化にうまく適応した人の特徴は、その変化の中に楽しめる所、わくわくできる所はどこにあるかを見いだせた人なのです。
詳細はYouTubeのリンクからご覧ください。
【全編公開】今こそ発揮すべき中小企業の「底力」とは?小西美術工藝社社長 デービッド・アトキンソン氏、WAmazing社長 加藤史子氏らが徹底討論!
https://youtu.be/tZ1GU8UZgiM
[気づき]
ビジョン実現のために自分は何をできるのかを考える。
周りを活気ある環境にしたいのなら、自分から大きな声であいさつするなの具体的に行動しなくてはならないと思いました。
【1Episode】
「100万人に1人」の存在になる方法
今回のキーワードは「差別化」する重要性について記述してきました。
そこで、人材としても差別化して唯一無二の存在になる方法を説明していきます。
ある分野で集中して仕事をして、100人に1人の希少性を確保することです。
違う分野で仕事をして100人に1人の希少性を確保できれば、もう掛け算すれば1万人に1人の希少性を確保できたことになります。
(計算式)
100分の1×100分の1×100分の1=100万分の1の希少性が実現!
1つの仕事をマスターするのに、人間は一般的に1万時間かかると言われています。(マルコム・グラッドウェル著『天才! 成功する人々の法則』(講談社))
1万時間取り組めば誰でもその仕事をマスターできるということです。その分野で100人に1人くらいの希少性は得られれば、あとはもう1つ別の分野で100人に1人になることで、100万分の1の人材になれるのです。
1つの分野でトップになること大切ですが、100人に1人を目指して掛け算して自分を差別化することも大切なのです。
自分は何と何を1万時間やってどんな人材になりたいですか。
具体的に何をすべきか考えるきっかけになれば嬉しいです。
【経営計画を活用し、成果を上げるために必要な事項】
計画とは?
最終的なゴールに向かってその方法や手順を組み立てる作業です。
つまり、ゴールをイメージできて、はじめて計画できるのです。
例えば、富士山を登ろうと目標にしたとします。
富士山を登るという目標が同じでもどこから登るかは、自分次第です。麓から登るという選択肢もありますし、途中まで車でいくという選択肢もあります。もし、別の選択肢で登りたい場合は、別の方法で登る方法を計画して、新しいイメージをつくることも大切です。
大切なのは、目標達成までの道のりを順序立てて、考え、何を最初にやるかを決めることが有効な計画を立てる方法です。
計画を立てる上での順序
❑計画を立てる上でやらなければならないこと挙げる
❑それを整理し、順序よく並べる
上記の2つのフェーズがあるのです。
この2つを意識して経営計画を立てることが肝要になってくるのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
夢をかなえる経営計画 ―会社を元気にして、黒字化を実現する最強ツール https://www.amazon.co.jp/dp/4924947768/ref=cm_sw_r_li_api_glt_i_14JQDVR4Z03KB57ZGXHA
怒らない技術 嶋津 良智 著
https://qr.paps.jp/QdVe0
ぼくに寄付するとよいことがあります。 サポートして下さった方、本当にありがとうございます。
