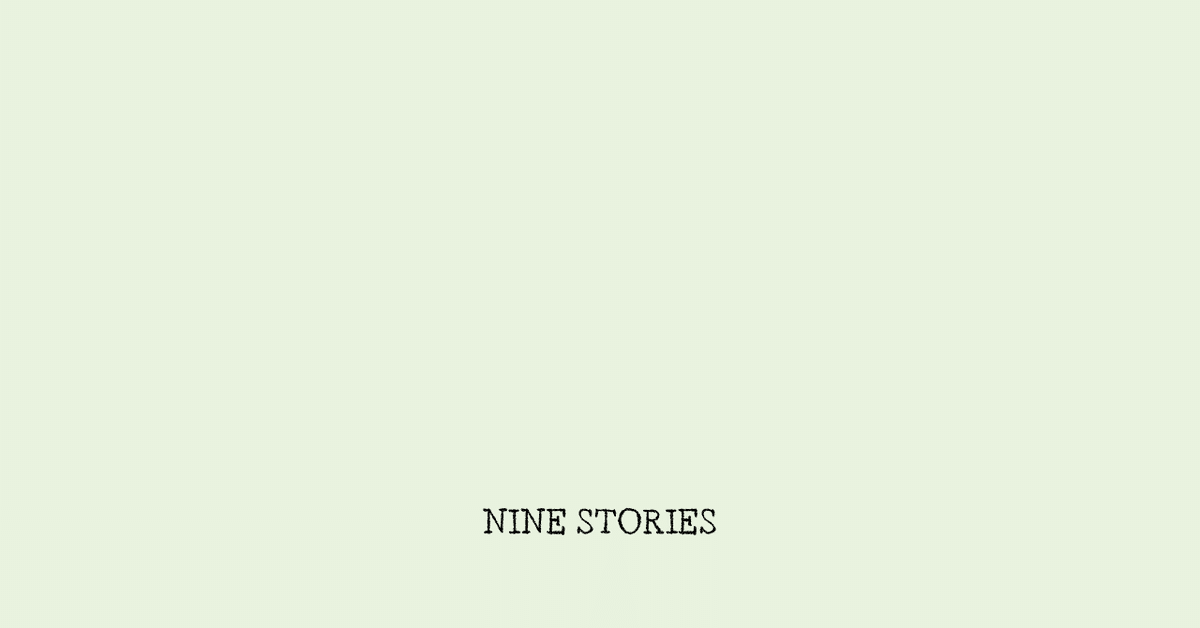
ナイン・ストーリーズ Ⅶ 午後
午後
昨晩、思いついたとても良い小説の話を、朝起きたらすっかりと忘れていた。
あまりにも良い話なので絶対に忘れることはないだろうと踏み、メモを取らなかった。後悔は先に立たない。
朝からハサミに糸を巻いたり、お風呂に入ってみたり、逆立ちをしてみたりしたがどうにも思い出せない。思い出したのは、あまりにも良い話だったと言うことだけ。仕方がないので諦めて、朝食をとる事にした。
冷蔵庫を開けるとハムと胡瓜と、使いかけのトマトパサータがあった。キッチンに転がしていたゴーヤと、近くのドラッグストアでまとめ買いをしたインスタントのフォーを戸棚の中で見つけた。ううん、と考えた後、鍋を手に取った。玉ねぎとパプリカ、茄子、ゴーヤ、にんにくを刻み、オリーブオイルで炒め、パサータを入れ、タイムとオレガノを振って煮込む。20分ほど煮たら、塩で味を整える。胡瓜は薄くスライスし、バターとからしを少し塗った食パンにハムとともに挟んだら、4隅をカットしてなじませる。塩味のインスタントのフォーには塩もみしたゴーヤと鰹節をぱらりとかける。ラタトゥイユを煮込んでいる間にテーブルに行き炭酸水を開け、フォーとサンドイッチを食べる。
昨晩は飲みすぎてしまったので、身体が塩分とカロリーと熱いスープを欲していて、ひと口食べる度に身体の組織に素早く吸収されていく。あーあ、せっかくダイエットしてたのに。サンドイッチのからしは良い塩梅だし、フォーのゴーヤはカリリと苦く、美味しい。ラタトゥイユはくつくつと小気味よく煮込まれている。
何が私をそうさせるのか、最近妙に泣き上戸である。歳のせいなのかもしれないし、世の中のせいなのかもしれない。不安であることは確かだけれど、その度にとてもめんどくさい女になっている自覚はある。
大丈夫だよ、と彼は言う。
数年前に、世界の終わりと言う小説を書いた。それは女の子と男の子の他愛のない話だったのだけれど、とても気に入っている話の一つとなった。
彼らは小さな場所で愛し合い、慰め合い、許し合い、受け入れ合う。星や猫たちや長靴やオムレツを、すべて。
梅雨が明けた、とても暑くて天気の良い月曜日。カーテンを開けて観葉植物たちに水をやり、シャワーを浴びて洗濯機を回す。熱いコーヒーを淹れ、テーブルについてPCを開く。原稿用紙に向かい、ふと窓を見る。近くの公園の木々。ブルーの空。レースのカーテン越しに透けて見える、まるで夢みたいな景色。彼は今、どこで何をしているのだろう。今日はこんなにも良い天気で、世界はこんなにも美しいのに。
ベランダに干した布団のシーツの端が、風に揺れた。
先月末、彼に会った。ほとんどひと月ぶりの逢瀬の間、私たちは笑い、ふざけ合い、確かめ合ってみた。何を?愛とか、そういうものを。おそらく。(そうだと思いたいと思っているが、それも私の勝手な理想かもしれないと時たまに感じる。)
彼の瞳は変わらず澄んでいて、昔見た願いの叶う大きな岩に登った話や、先月食べたラーメンの話、育てている植物の話などをうつぶせになったまま聞かせてくれた。私は時に目を閉じながら彼の話を隅々まで聞いていた。正確には、様々なことを話す、私の好きな、彼の声を。
彼の肌は柔らかく滑やかで、目をつむると彼の声や匂いや感触が、脳に直接流れ込んでくるように感じる。私の好きな時間。なのに、もう彼はいない。まっさらなカレンダーと睨めっこをしてみたが、すぐに止めてしまった。
模様替えをした。古い木のテーブルは足が一脚壊れかけていたし、飼っていた猫にとがれたままの椅子は、角の革がボロボロになっている。どちらもうっすらと埃をかぶっているので、水拭きで丁寧に拭いてあげた。窓を開けると心地よい風が流れ込み、レースのカーテンを揺らした。テーブルと椅子を寝室から隣の部屋へ移し、ベッドの向きを変え、本棚を整理した。カポーティやサキ、サリンジャーでいっぱいの前列を剥がすと、たくさんの詩集が出てきた。コクトーの本を取り出し、前列に並び直した。猫のポストカードは私のお気に入りで、冷蔵庫に貼ってある。
靴を磨き終わったあと、炭酸水を飲み切ってしまったため、外へ出る。外はとても暑く、眩しい。熱くなったアスファルトの上をビーチサンダルで歩くと、砂漠の上を歩いているような気分になった。もちろん私は砂漠に行ったことがないし、アスファルトは硬くて嫌な匂いがする。
歩いて数分のところにあるコンビニの中は涼しく、見慣れた店員がレジの奥に座って、携帯電話を眺めている。恋人からのメッセージだろうか。いつも無表情の彼は時に笑顔になる。一番奥の棚へ向かい、パックの焼きそばと、お気に入りの銘柄の炭酸水を数本、オレンジのかごへ入れる。ピンクグレープフルーツとレモンとオレンジと、脂肪を抑える何かの入ったもの。オレンジは数日前に見つけたのだけれど、とても美味しいので気に入っている。どういうわけだか、このコンビニにしか売っていない。レジで会計をする時にふと、いつも彼が吸っている銘柄のタバコを見つけた。
心がきゅっと、音を立てる。
ーDans la bulle de savon le jardin n’entre pas.Il glisse autourー
私もまた、彼の周りをくるくると回っているのだ。
焼きそばを温め、炭酸水の蓋を開け、簡単な昼食をとる。どういうわけか、朝から食べてばかりいる。よほど昨晩の酒が効いているらしい。椿色をした紅生姜が舌上でピリリとした。キャベツは甘くて美味しい。パックの焼きそばは何故こんなにも美味しく感じるのだろうかと不思議に思う。原稿用紙はまだ真っ白なままだ。
炭酸水をごくごくと飲みながら、昨晩思いついた話を思い出そうとしてみるが、やはりうまくいかなかったので諦めることにした。完全に。物事には道理があるのだから、無理なときはきっぱりと諦めるしかないと思っている。どんなにその話が最高の話で、酒をやり過ぎるほどだったとしても!
おそらく酒はただの飲み過ぎで、おそらく彼への当てつけの一部なのだろうけれど。
彼のことを考えてみる。
細い腰、柔らかい声、綺麗な瞳、美しい爪。朝起きたときの、うっすらとした髭と白い肌。口癖。
-右目のほうが、お姉さんだね。
ある日彼が言った。
ー左目の方が、幼い。
私の前髪を指で分けながら彼が続けた。
ーみんなは普段、君のお姉さんの部分しか見ることができないんだね。
きっと私は始終、きょとんとした顔をしていたと思う。そして何故だか、ほっとしたような、安心したような気持ちになっていた。
彼はそんなふうに時々私を混乱させたり、安心させてくれる。ずっと欲しかったものも、欲しくないようなものまで、様々な欠片たちを私の上に降り注ぎ、それを抱きしめた私を残して見えなくなってしまう。
ーMon oreille est un coquillage Qui aime le bruit de la merー
部屋は暑く、買ってきた炭酸水も残り3分の2になってしまった。Tシャツにシャンブレーのショートパンツの姿でも体中に汗をかく。あいかわらず真っさらな原稿用紙と、やわらかな木漏れ日のあたる室内。とても許された午後。PCを閉じて、テーブルに突っ伏し目を閉じる。目を閉じると色々な音が聞こえる。隣の室外機のゴウンゴウンというノイズ。風がカーテンを揺らす音。どこかで子供たちの声が聞こえる。パタパタと、駆け足で走り去る音。鳥のさえずり。冷蔵庫のうなり声。
ー私の耳は海の音を憶えているのだろうか。
大丈夫だよ。
彼が言う。
何も気にしなくていいよ。安心して、其処にいて。大丈夫だから。
いつでも。
お気に入りの曲を聴く。
小さな頃から好きなこの曲は、実に色んなヴァージョンがある。オリジナルだけでなく、クラプトンや、最近ではあの黒人の歌手にもカヴァーをされていた。
一度、彼が来たとき、私のスピーカーからは終わりなくこの曲が流れていた。彼も5回目くらいに気がつき笑った。ベッドにいる間もずっと、その曲は繰り返し繰り返し、私の部屋に流れていた。
彼は丁寧に曲の構成を説明してくれ、その後に私のギターで演奏してくれた。
綺麗な、綺麗な音。ネックの少し曲がっている自分のMORISがこんなに美しい音を奏でることができるなんて、それまで私は知らなかった。私はさらに彼のことが好きになったことを実感した。
今はオリジナルのヴァージョンが小1時間、ゆっくりと私の午後を満たしている。ラタトゥイユの火を止め粗熱を取った後、タッパーに移して冷蔵庫に入れる。
暑いので窓を閉めてエアコンをつけ、ベッドに入る。
私のベッドは一年中、掛け布団と毛布と薄いブランケットがかけてある。
冬は暖かいし、夏はエアコンで寒いのでちょうど良い。枕は三つあり、固いもの、柔らかいもの、普通のものと揃っていて、首の弱い私は毎日、その日のコンディションに合ったものを選ぶことができる。枕もとには必ず本があり、それは一冊だったり二冊だったり、時には漫画だったりする。
枕の下へ手を入れると、お気に入りの作家の小説が出てきた。真ん中あたりで栞を引いてある。少し読んだけれどまったく何のことだか分からないので、ページを戻ると、ほとんど最初のページ近くに戻ってしまった。
主人公は旧い時代のトルコにいて、遺跡を探している。その街には失われた文化や神々がたくさん息づいていて、時にその場所の匂いを感じるような気持ちになる。砂埃、パン、家々の壁、道端の雑草、神聖な夜の香り。
彼の髪に触れる。肩、睫毛、首筋。私たちは裸で抱き合い、彼も私の髪や頬に触れる。目線、表情。熱くて冷たいもの。恍惚。
突然すべてが泡になり溶けていく。私は彼を見失ってしまう。
外は暗くなっていた。窓の外の家々に明かりがついている。いつの間にか眠ってしまったみたいだ。立ち上がり、カーテンを引き、炭酸水の残りを飲んだ。
熱いシャワーを浴びた後、冷蔵庫からラタトゥイユと冷えた白ワインを取り出し、夕食にする。胃の不快感もすっかり消えている。テレビをつけ、古い映画を観る。
トイレに行った後、携帯を開くとメッセージが届いていた。送信者の名前を見て、自分が待ち侘びていたことに気づく。文章もないメールに、写真が一枚だけ添えてある。
満天の星空。
波の音がふいに、蘇った。
fin.
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
