
『現代人は鬱になって当然?』ー「スマホ脳」A.ハンセン(著)
・増加する精神病患者
「ADHD」「発達障害」。これらは最近、聞くことの増えた病名(症名)だと思います。
これまで個人の短所として片付けられてきた症状に病名がつき、広く認知されたことで、救われた人もいるのではないでしょうか。
厚生労働省によると20年前と比較して、精神を病んでいる日本人は増加しています。
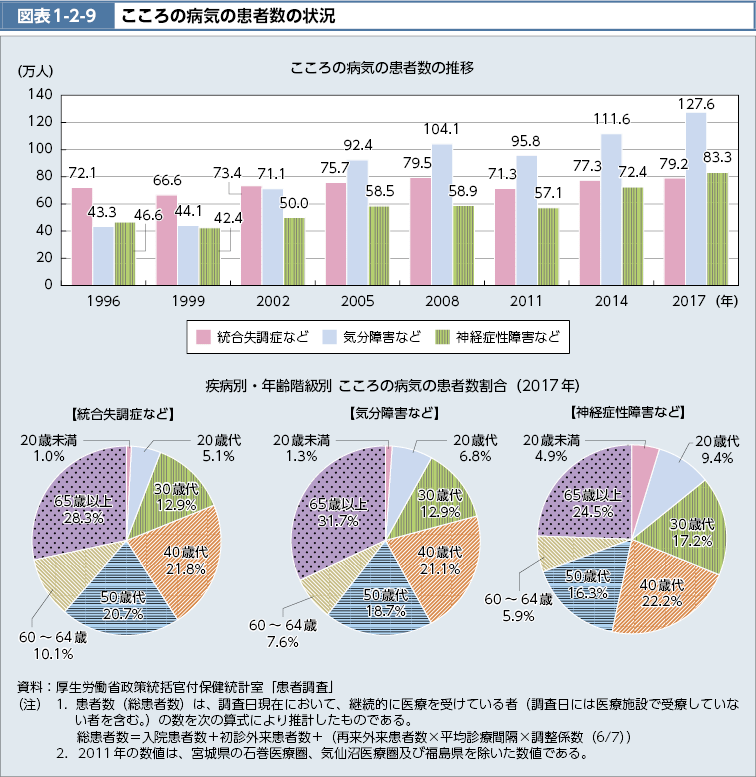
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/18/backdata/01-01-02-09.html
人々の精神が不安定化している現状は今後も継続すると考えられ、メンタルヘルスの重要性も議論されています。
本書の著者、アンデシュ・ハンセン(Anders Hansen)は精神科医として、この問題に向き合ってきました。
著者が参加した国際的な学会でも、精神病患者が増加傾向にあるのは話題になっていて、「人々の精神が不安定化している」という現状は世界的な問題のようです。
では、なぜ精神病患者が世界的に増加傾向にあるのでしょう?
本書では、その原因が「スマホ」である。この仮説のもと、議論が展開されます。
・スマホが「こころ」を破壊する
・鬱はあなたを命の危機から守ってる
どうしてスマホのような最新技術が、人間の精神に悪影響を与えてしまうのか?
著者は、「生物が進化していく時間」と「現代社会が進歩する時間」のズレが理由だと述べます。
私たちは(中略)数千年で―いや、数百年かもしれない―周囲の環境を著しく変化させたのだ。数千年というと永遠のように聞こえるかもしれないが、進化の見地から見れば一瞬のようなものだ。その結果、私たちは今とは異なった環境に適応するよう進化していまい、今生きている時代には合っていない。
著者によれば、私たちの遺伝子は、まだ中世か近代の社会に適応しようとしており、現代にまで進化が追い付いていないというのです。
著者にとって、現代社会に遺伝子レベルで適応できていない人間が、スマホを利用すれば、精神病になるのは当然だといいます。
本書では、バーンアウト(燃え尽き症候群)患者の話が出てきます。
膨大な仕事をこなした後に向かったバカンス先で、突然何もできなくなってしまったというものです。
なぜ、こういう症状が発症したのか?
患者は理解できていませんでした。発症の原因は、長期のストレスから体を守るための防衛反応であると指摘します。
鬱や燃え尽き症候群のような精神病は、ストレスに対する防衛反応。すなわち、「ストレスを抱える現場から離れろ」という脳からのメッセージなのです。
ストレスに深刻な影響を受けた人の多くは、実はそれまでに何度も警告を受けている。不眠、お腹の不調、感染症にかかりやすい、歯ぎしり、短期記憶の低下、苛立ちなどだ。
あなたは今、健康ですか?
著者は、鬱にならないためのヒントをくれているので参考にしてみてください。
・スマホはあなたを不安にさせる
では、なぜスマホが悪影響を与えるのか?
スマホは、利用者に便利さと娯楽を提供する道具ではないだろうか?
著者は、現代人はスマホ依存症となったことで、スマホによる「不安」と「ストレス」を抱えやすくなったと指摘します。
スマホは私たちの生活を大きく変えました。
インターネットで世界と繋がり、スマホはアプリを通じて、あらゆる情報や人とアクセスできるようにしました。
もはや、スマホのない生活は考えられないくらいです。
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上では、「いいね」を求めて様々な投稿が日々されています。
インフルエンサーの登場によって、私たちはTikToker、Youtuber、Instagramerの投稿に夢中です。
スマホはあらゆる欲求を満たすための道具となり、私たちが手放すことはありません。
ゆえに、スマホがないと不安になります。一日SNSを見ずに、生活することができる人は少ないのではないでしょうか?
通知がくると気になります。気になっている状況は、「期待」や「不安」といった緊張状態を発生させます。
この状況。スマホに生活をハッキングされている状況を、著者はスマホによる精神への悪影響と語るのです。
ゆえに著者は、スマホから距離をとろうと警鐘を鳴らします。
(前略) デジタル化のおかげで知能を効率的に使えるようになり、想像を絶するような創造性も与えられたかもしれない。しかし毎日何千回もスマホをスワイプして脳を攻撃していたら、影響が出てしまう。注意をそがれるのが慢性化すると、その刺激に欲求を感じるようになる。刺激自体が存在しないときにまで。小さな情報のかけら―チャットやツイート、フェイスブックの「いいね」―を取り込むことに慣れれば慣れるほど、大きな情報の塊をうまく取り込めなくなる。それこそが、複雑化する社会でいちばん必要なことのはずなのに。
・スマホを捨てらない私たちはどうする?
著者の言いたいことを、強引にまとめてしまうと、「デジタル・デトックス」なんです。
著者は最後の章で、スマホに依存する生活から、「自然」を意識した生活に変えていこうと述べています。
これは、メンタルヘルスの現場では言われていることです。
結局、「『運動』しな『森林浴』しな。スマホもいいけど、外で遊ぼうぜ」という割と平凡な結論に着地します。
この本のおもしろさは、スマホという技術が、人間の脳と精神に与える悪影響について、力説している点にあると思います。
・最終的には精神論? (私の所感)
最近、著者の本が続々と翻訳されているので、流行りなんでしょうね(笑)
本書のような、デジタル技術の悪影響について論じる本は、メタバースなどが普及するにつれ、もっと増えてくるのではないかなと思います。
単純な反テクノロジー本というわけではなく、テクノロジーとバランスをとって付き合おうとい結論は、無難ですよね(笑)
・2つの疑問点
本書の中で、疑問に思った箇所を2つほど書いて終わろうと思います。
1.「精神病患者が増えている」=「スマホが問題」という命題
であるならば、「(今)精神病患者ではない人」=「スマホと距離が(現状)適切」ってことだよな~と。
じゃあ、脱スマホというよりも、技術を利用する人の規律の問題になっていくのではないか?
また、「Pokomon Go」が心の健康にいいという記事があるように、スマホと健康に関する議論は、変化するかもしれません。
ようするに、スマホは「毒にも薬にもなるんじゃね?」って話です。
2.「自己防衛」=「自殺」?
最も疑問なんですけど、「長期のストレスが原因で、バーンアウトになった症例の話」の部分で、「バーンアウト=鬱」と著者はしてるんですよね。
で、「鬱になる=自己防衛」って構図で話は進むんですけど、じゃあ「鬱が原因で自殺した例は、どう説明すんの?」ってなるんですよね。
自殺既遂者に対する調査からは、うつ病等の気分障害が自殺の要因として特に重要であることが明らかになっており、厚生労働省における自殺対策においても、その中核となっているのはうつ病対策です。
(最終閲覧日2024年2月7日)
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html
「自己防衛としての症状が、自殺って本当?」って思うんですよ。
ストレスからの解放という点で見れば、自殺は現代社会のしがらみから解放されると言えるので、納得なんですけど。
自己防衛の観点で見ると、違和感があるんですよね~。防衛できてないし、自己防衛だったら「生」にこだわると思うんですけどね。
で、これが現代社会に適応した一つの人間の進化の形だとしたら(=進化したから、自己防衛で自殺)、結構ヤバくない?って思うんですよね。
結構、強引な論点の展開だったかもしれませんが、気になったのでm(__)m
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
