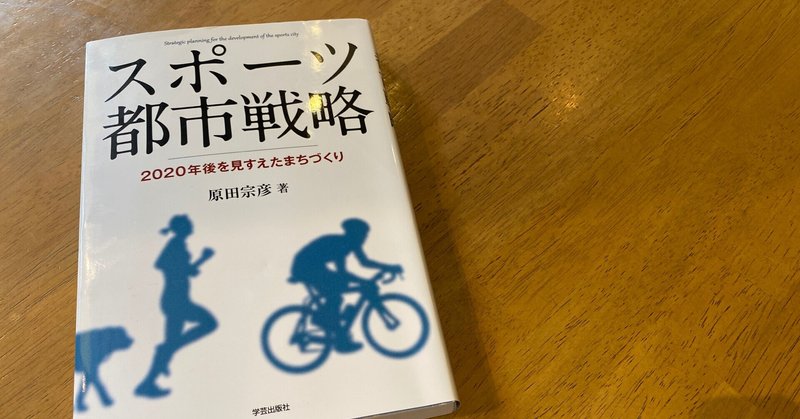
『スポーツ都市戦略』を読んで
この本では2020年後を見据えたとなっているが、オリンピックの有無に関わらずスポーツの視点を持ったまちづくりは重要だ。
健康は日本人に関わらず重要なテーマで、健康であるためにはスポーツに親しむための環境が本当にあるかが問われるからだ。そのためにはまちそれぞれの土地の特性や自然、立地…個性に合ったスタイルを実現する必要がある。
まちによってはそういった理由から立地がそぐわないのでスポーツに注力しないというのも一つの答えだと思う。
僕が印象的だったのは第6章の「スポーツに親しむまちづくり」だ。僕の興味関心は見事にこの章に集中していた。以下、気づきを幾つか。
都民のスポーツ実施率とそこからの提案
東京都生活文化局が毎年行う調査「都民のスポーツ活動に関する世論調査」(2015年2月)によれば、東京都は2007年39.2%→2014年60.5%と1.5倍に。そのうち、もっとも行われているのは「ウォーキング・散歩」であり、2011年56.5%→2014年70.2%に。また、「ランニング(ジョギング)」は2011年11.8%→2014年15.0%と増加している。
続き質問ではスポーツ・運動の実施場所を尋ねているのだが、「道路・遊歩道」70.8%、「広場・公園」29.2%との回答がある。
東京都では2020年までにスポーツ実施率70%達成を目指しているという(この本は2016年発行)その中で、著者は以下のように指摘(P.182)している。
「今後、電線の地中化や遊歩道の段差解消、そして自転車専用道路の設置など、身体を動かしたくなるまちづくりに向けた戦略的なスポーツ都市計画が起動しない限り、スポーツ参加率をさらに向上させることは困難である。」
スポーツ達成率だけでなく景観の側面からも電柱地中化は望まれるし、自転車専用道路は交通の安全という側面からも必要だ。スポーツ推進だけでない側面も大きくあるのでこれらは東京に限らず推進されるべきだ。
電柱・電線の地中化について
著者の指摘(P.182)にもあるが、
「歩道に突き出た電柱は、スムーズな歩行の障害になり、美しい景観を阻害する要因にもなっている。 (中略) 歩道から電柱が撤去され、街路が無電柱化されることにより、景観の改善と防災面の強化とともに、車椅子の移動、街歩き、ウォーキング、ジョギングがスムーズになるなど、健康志向のまちづくりにとって大きな利点が生まれる。」
個人的にはこれにベビーカーも付け加えたい。
身体活動に適した近隣環境
健康づくりの視点から見ても、アクティブな生活には、アクティブなライフスタイルを誘発する生活環境が必要である。犯罪が多発し、緑がなく、スポーツ施設もない殺伐とした建造環境では、街路で運動やスポーツしようとする気持ちさえ芽生えない。その一方、緑が豊かで景色が良く、車を気にせず自転車に乗れ、気軽に野山を歩けるフットパスや歩道があれば、アクティブな生活を送ることが可能になる。ただ日本の場合、近隣公園の数は増えたものの、その多くがアメリカのポケットパークのように規模が小さいため、野球禁止、ボール投げ禁止、サッカー禁止など、安全を重視するあまり、球技に対して過剰は規制がかけられているのも事実である。(p.188から引用)
公園の利用規制に関しては安全重視というよりもシニアなどの別の世代からの声が大きいのではないかと推察するがいずれにせよ制約が多い公園があるのは事実。
逗子に関して言えば、第一運動公園というグランドと野球場を備える公園があるが園路は歩行用とし、3名以上のランニングは禁止という不可解なルールがある。公園利用に限ったことではないが細かなルールを設けることは息苦しさにつながり、本質的な利用から遠のく。それよりも創意工夫してお互いに楽しむ余地を残すことこそ本来と僕は考える。
アクティブトランスポーテーション
アメリカコロラド州コロラドスプリングスの話題が出てきて嬉しかった。何せ、ここは2009年からレース出場のために毎年のように通った都市であり、オリンピックスポーツセンターなど先進的な取り組みを行う施設がある。そのコロラドスプリングスで行われている取り組みだ。
アクティブトランスポーテーションとは?
エンジンやモーターに頼る人間にとって受動的(パッシブ)な移動ではなく、徒歩、ジョギング、スケートボード、あるいは自転車や車椅子を交通手段として、自分の力で積極的(アクティブ)に移動すること。
しかしながら、このようなキャンペーンも、思わず歩きたくなる、あるいは自転車ジョギングで走りたくなる緑豊かな環境が整備されていなければ、個人の行動誘発に結びつくことはない。さらに、歩道や街路、樹木や風景、そして街並みや景観の整備とも密接な関係がある。(P.193)
と著者は指摘するが、一貫して述べられていることはスポーツに親しむまちづくりは自転車や歩行者に優しいまちであり、景観に配慮した街であると常々感じる。
この本を読んでいて度々ドイツのまちづくり、イタリアのまちづくりの本を思い出した。
どこを切り口にするにせよ、大きな絵図ともゴールをしっかりと描かなくければ実現は程遠い。
こういうことを書くと道幅が…建物が…と出来ない理由が多々出て来るのだと思う。その上でどこからなら手をつけられるか?どうすれば実現できるか?というスタンスで向き合わない限り何も変わらない。
詰まるところ、まちごとに特性を理解しその特性にあったまちづくり、加えて端子眼的でなく長い目で見た先々の変化を視野に入れたまちづくりをしていくことが改めて重要だと感じた。
【今後の予定】
6/20(日)ジュニアトレイルランニングスクール〜逗子のローカルトレイルを走ろう〜
9/26(日)第6回NAGANO Jr TRAILRUN in 富士見高原
10/17(日)第13回TOKYO Jr TRAILRUN兼-U15ジュニアトレイルランチャンピオンシップ
11/7(日)逗子トレイル駅伝2021兼U-12ジュニアトレイルランチャンピオンシップ
「RUNNING ZUSHI」
逗子市内池子の森自然公園内400mトラックを拠点にしたランニングチームです。
Facebookページ
instagram
最後まで僕のnoteを読んでくださりありがとうございます!!
「スキ」や「フォロー」していただけると励みになります。
過去のnote記事はこちら
最後まで読んでくださりありがとうございます。僕の経験や感じていること考えをいろいろと書いていきます。noteの記事を通じて一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです!「スキ!」や「サポート」はとても励みになりますので、宜しければ応援の気持ちも込めてよろしくお願いします!

