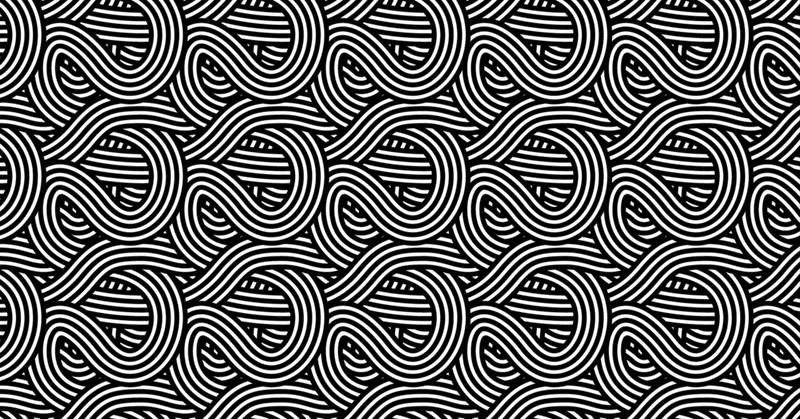
違うよと言ってくれる人
2024年5月24日(金)朝の6:00になりました。
今日の真理が、明日否定されるかもしれない。
どうも、高倉大希です。
叱ってもらえるうちが華だよ。
ときどき、こんな言葉を耳にします。
耳にするたびに、なんじゃそれと思っていました。
叱るという行為を、正当化しすぎているような気がするからです。
「わたしのために叱ってくれてありがとう」
こんなふうに言わされている子どもたちを見て、違和感しかありませんでした。
権力とは何か、を一言で言うならば「状況を定義する権利」であるとする考え方が、私には最もしっくりきます。具体的に言うと、その状況において何が良い/悪いとされるのか、どんな行為が求められて/禁止されるのかを決める権限を持っている、決めることが許される立場にいるということです。
叱ってもらえるうちが華だよ。
大人になって、この言葉の意味が半分だけわかるようになりました。
きっと、違うよと言ってくれる人のありがたさを意味しているのだと思います。
いわゆるイエスマンに囲まれても、つまらないという話です。
ものごとは、否定があってこそ前進します。
他者から違うよと言われることで、考える必然性が生じるのです。
バフチンによる対話の定義がどういうものかというと、「いつでも相手の言葉に対して反論できる状況がある」ということです。(中略)どこまでも続いていくのが対話の本質であって、別の言いかたをすると、ずっと発言の訂正が続いていく。それが他者がいるということであり、対話ということなんだとバフチンは主張しているわけです。
たしかに、肯定だけのコミュニケーションは退屈です。
どうしても、だからどうした?と思ってしまいます。
違うからこそ、おもしろいのです。
違うからこそ、考えるのです。
もちろん肯定も、なくてはならないアクションのひとつです。
一方で、違うよと言ってくれる人の存在がありがたいことも事実です。
「みんな違っていい」は対立を覚悟することであって、「心をひとつに」はそれとは真逆の考え方です。繰り返しになりますが、多様性を心の教育で解決できると信じている教育は乱暴すぎます。共通の目的を探しだす、粘り強い対話の力こそ必要だと思っています。
違うよと言われたときに、必ずしもそれを受け入れる必要はありません。
違うよと言われることは、あくまでも考え直すきっかけです。
考えて、受け入れるもよし。
考えて、さらに否定を重ねるもよし。
叱ってもらえるうちが華なのかは、まだはっきりとはわかりません。
しかし、違うよと言ってくれる人の存在は間違いなく華なのだろうと思います。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。

