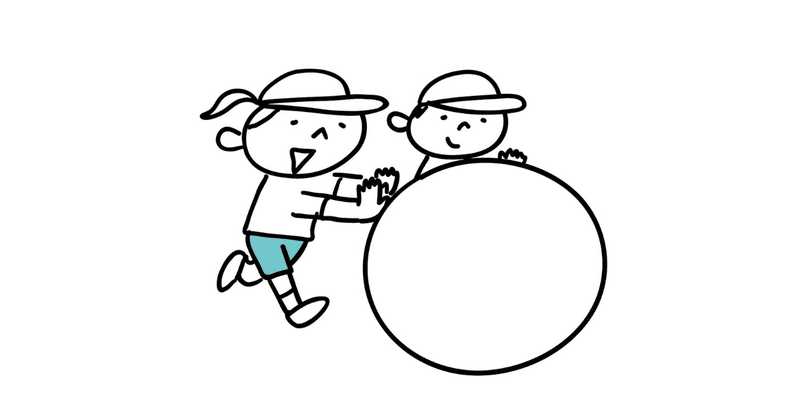
「やる気スイッチ」は確かに大事 でもやる気とスイッチは分けた方がいいと思っている理由
このCMご存知でしょうか?
全国で流れているのかな、このCM…
やる気スイッチ 君のは、どこにあるんだろう~
見つけてあげるよ〜 君だけのやる気スイッチ〜♪
このCMを見るたびにモヤモヤしてしまうmomomiです。
今回はやる気スイッチについて考えてみます。
初めにお断りしておくと、私はこの塾とは一切関わりがなく、塾もCMも批判する意図は全くございません。
ただの暇人のたわごととしてスルーしていただければ幸いです。
やる気スイッチとは何か?
たぶん、CMを見る限り、この文脈で言われている『やる気スイッチ』とは子どもの好奇心を指しているものと思われます。
子どものスキが好奇心に火をつけ → やる気がわき → 勉強する!
親は なんて、素晴らしい!となるわけです。
確かに一つの理想形ですよね。
子どもが興味を持ったものに夢中になり、それが勉強に繋がる。
結果的に自主的に勉強するようになる。
すべての親はおそらくこの願望を持っていて、だからCMのキャッチコピーとして成り立つと推測します。全く正しい。
子ども時代はドーパミン神経系を育てる時期
子ども時代は意欲を育てる時期、スキをたくさん見つけよう!
ハマる体験、夢中になる体験をたくさんさせよう!
よく聞きます。
これはドーパミン神経系の働きを介しています。
つまり、ドーパミン神経系を良い意味で鍛えましょう、ということですね。
何かにハマっている状態のとき、脳の中では、「ドーパミン神経系」が働いています。ドーパミン神経系は、興奮したり、快を感じたり、達成感を得たり、褒められても活動することが知られていて、報酬系と呼ばれることもあります。恋をしても、ごちそうを食べても、危機を回避しても、何かを達成しても、美を感じても、結局ドーパミン神経系が働きます。ドーパミン神経系は快感の主役であり、ハマりの主役でもあります。
文中にもありますが、褒められるとやる気になるのもドーパミンの作用によるものです。
褒められると嬉しい!だからもっとやりたくなる!というもの。
このとき脳の中では、下記のようなことが起こっています。
報酬系は脳の奥の腹側被蓋野(ふくそくひがいや)から側坐核(そくざかく)を経由して前頭葉(ぜんとうよう)に向かっています。もう1つのドーパミン神経系は黒質(こくしつ)から線条体に向かっています。線条体の腹側(下側)には、快感系のドーパミン神経が線条体にアクセスする場所があります。ここで放出される「快」と線条体の「行動」が結び付き、それが繰り返されると、線条体は予測的に発火するようになります。これが「ハマっている状態」です。
要するに線条体を発火させることがポイントです。
線条体ってどこにあるの?という方のために下図を張っておきます。

ゲームに依存してしまうのも、スマホを手放せないのも基本的にはすべて一緒です。ドーパミン神経系を何に働かせるのか?の違いだけだと思われます。
頭のいい子は質の良い体験でドーパミン神経系を刺激している
本を読むことが好き、体を動かして遊ぶことが好き、この子たちはこういう体験が自分にとって快であることを知っているから、親に言われなくても本を読み、外で遊ぶことができます。
そこから発展して勉強や運動することに繋がっていく。
勿論、遺伝の要素が半分程度入るので、環境だけが問題ではありません。が、遺伝と環境が基本のセットなので、格差は広がります。つまり、遺伝的にそういった好む家庭は、積極的に環境を整える可能性が高いためです。
一方で親が与えてあげられる機会が少なかったり、いろんな家庭の事情により、結果的に体験の幅が狭くなってしまうとこういったことで『快』を知る機会自体が失われることもあります。
十分に読書や運動での『快』の経験を積む前にゲームやスマホといった刺激が強すぎるコンテンツで『快』を味わいすぎてしまうと、地味で繰り返しが必要な快は感じにくくなってしまいます。
うちはコロナ禍のせいで予定より早くswitchを与えたため、若干失敗した気がしています。運動は好きですが、あーあ。
やる気スイッチの何がそんなにモヤモヤするのか?
というわけで、子ども向けの塾のCMとしてはおそらく問題ないのに、なぜmomomiはモヤモヤするのか、という本題に入ります。
それは私が「やる、やらない」と「やる気」は全く別の話なのに混同している人が多い、と感じていることが最大の原因で、「やる気」と「スイッチ」とを意図的に結び付けられることに対してもやもやするからです。
やる気がないから、やらない
やる気があるから、やる
一見因果関係がありそうに見えますが、本当にありますか?それ。
やりたくないから、やらない
やりたいから、やる
こちらは因果関係があると思います。
やらないのはやりたくないから、ならいいんです、別に。
似たバージョンでやるとできるは別モノだ、というのもありますが、今日は割愛します。
ちなみにこの話を小4の息子にすると、非常に嫌な顔をされます。
あ、ドーパミン神経系の話はしませんよ。
まぁ確かに面倒なママですね。
やる気とスイッチは切り離した方がいい(というか楽)
というわけで、やる気とスイッチは切り離そう!と提案したい。
だって歯を磨くのにやる気いりますか??
お風呂に入るのにやる気いります??
人によってすごく苦手な人はやる気ないと無理です、という方もいると思いますが、作業まで落とし込めば何も考えなくてできることは意外と多くあります。
私にとってやる気に頼って行動するというのは、大玉転がしのイメージです。
いろいろ混ざって大変になったもの(=大玉)を頑張ってよいしょ、よいしょと押していくイメージ(下図)
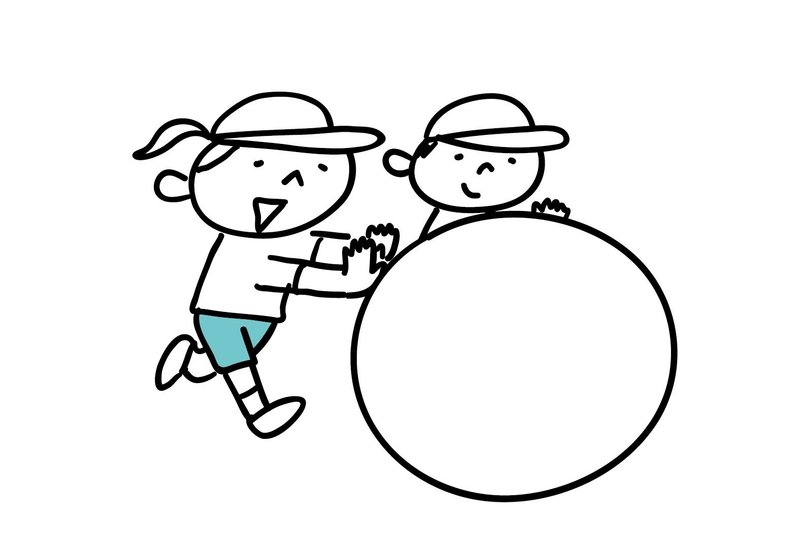
それはやっぱり大変ですよね。
運動会で大玉転がしするのは悪くないけど、日常ではやりたくない。
ただ、苦手な分野では私だって今でも大玉転がししちゃいます。(反省)
仕事ができる人、優秀な人は大玉を分解しタスク化するのが得意
仕事ができる人、たくさん数をこなせる人を見ていると、びっくりするほど仕事ややることを分解し、タスク化して管理している人が多いです。
小さな作業レベルにまで落とし込むことで、考えなくてもできることとしっかり考えることにまず分ける。
やる気やエネルギーは、しっかり考えるべきことを考えるときに使う。
イメージはこんな感じです(下記写真)ビー玉転がしのイメージ。

頭を使うのは主に下記の3つですが(しっかり考える必要がある課題は別にしています)、大して頭を使わなくてもゴールにたどり着けることもあります。たどり着かなかったら、また失敗した場所からやり直そう!
①大玉をビー玉サイズまで課題を小さくする
②ゴールにたどり着くために必要な橋を考える(作業レベルに落とし込む)
③ゴールにたどり着くように橋を設定する(上から下に流れるようにする)
私もそんなにタスク化するのが得意ではありませんが、だいたいである程度のレベルまで行ける気がします。
途中で詰まって嫌になったときは、一度投げ出して寝ましょう。
でも、みんな大玉転がしする方を選択する人が多い気がします。
どうして・・・?
終わりに momomiの悩み
私が今悩んでいるのは、今日つらつら書いたことをうちの小学生にどう伝えたら伝わるのか?ということです。もしくは、どこまで教えて、どこまで気づくまで放っておくのが良いのだろうか?ということ。
自分で気づくまでほっておいて、AHA!体験をした方が身になりそうな気もします。
ただ私は大人になってだいぶたってから気づいたので、気づくのが遅すぎたことは少し後悔。。。
誰か教えてくれたらよかったのに。
子育てはいつも、どこまで教えてどこまで突き放すのが良いのか、が本当に難しいです。部下の育成もそうでしたが。
大人の場合は、しばらく様子を見てあまりに言い訳が多くてやらない部下の場合は言ってしまうことも多々ありました。
だって仕事だから、お金もらっているんだから、みんな仕事しようよ!
と思っていましたよ。正直なところ。
でも、子どもはこれからの時間の方が長く、長期的に見てどちらが良いかはけっこう悩みます。
ただ一つ言えるのは、サクサクやってもらった方が母の精神衛生には良いです。間違いなく。
読んでくださって、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
