
絶望してアカデミアを離れた哲学院生が今の会社に出会ったら希望がもてた話
このnoteを書いたのは西田さん.
……なんだかライトノベルのようなタイトルになってしまいましたが、今回は私が大学院を離れる決心をして就職先を探し、そして今の会社Empathと出会うまでのことについてお話しようと思います。
人の「心」を測る研究
私は学部から修士課程まで、社会学を専攻していました。具体的には、大規模な質問紙調査から得られたデータを使って統計的分析を行い、社会と人の「心」の関係を探る研究をしていました。ある程度社会学についてご存知の方にとっては、社会心理学と社会階層論を合わせたようなものだといえばわかりやすいと思います。
ここでいう人の「心」とは、たとえば「○○は望ましいことである/良くないことである」といった価値観、「○○が好きだ」といった態度などのことです。社会調査では、対象者には自分の「心」を「1:そう思う、2:どちらともいえない、3:そう思わない」などの数値として評価してもらいます。また、対象者の学歴、経済的状態、居住地域などの社会的属性も回答してもらいます。

それらの「心」と社会的属性についての回答の関係を統計的に分析することで、たとえば「学歴が高い人ほど○○な価値観をもっている」といった結果を導き出します。こうした研究は、最終的に「社会的な事柄のどの部分に介入すれば、人の『心』がどんなふうに変化するのか」を明らかにして、その知見を政策や教育制度づくりに活かすということにつながっていきます。
人の「心」についての根本的な問い
そんな人の「心」研究をするなかで、自分の目の前にはどうしても考えざるを得ない問題が出てきました。それは、「どうやったら適切に、正確に、人の『心』を測ることができるのだろうか?」という、心理学にとって非常に重要で、最も根本的な問いでした。
修士2年目のころには、この問いに本格的に取り組まなければ社会と人の「心」について自分が知りたいことを知ることはできないと考えていました。しかしながら、この新しい問いに取り組むには、大きな障壁がありました。
「人の『心』を適切に、正確に測定するためにはどうしたらよいか?」
「そもそも人の『心』なんて測定できるようなものなのだろうか?」
それは、このような根本的な問いは、大学院生には釣り合いのとれない問いである、ということでした。というのも、博士課程3年ほどのあいだに論文を2、3本書いた業績を手に、早めに研究機関に就職するべき(そうでなければ食い扶持を確保できない)大学院生にとって、複雑で難しく、かなりの時間を要し、そして現行のアカデミアの慣習* からも否定はされずとも称賛はされないようなこの問いを研究テーマにするのは、明らかに得策ではなかったからです。
*こちらの記事でも紹介したように、心理学には「これまで提唱されてきた有力な仮説を支持する結果となった論文は採択されやすいが、分析の結果仮説を支持できなかった論文は採択されにくい」という発表バイアスがあるといわれています。また、これらの「発表される」研究では、伝統的に使われてきた測定法を踏襲することが多く、「この測定法によって、本当に測定したい『心』が測定できているのか」という根本的な問いについて再検討されることは多くはありません。こういった状態を、ここではアカデミアの慣習と呼んでいます。
アカデミアと自分のキャリアへの絶望
そうして修士を終えるころには、私は研究者としての自分の今後のキャリアをまったく描くことができなくなっていました。
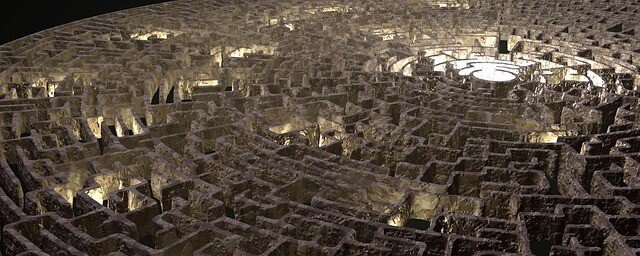
この問題に取り組むには、実証的な社会学や心理学ではなく、哲学を本格的に研究するべきだということ。しかし今から哲学をやるなら、あと3年間でどこかの大学に就職するということはおそらく不可能だということ。それから、正直アカデミアに残り続ける気力が失われつつあったこと。でも、研究を続けたい気持ちはたしかにあったこと。
そんなふらふらな状態で、自分の将来に少し絶望していた時期がしばらく続いたあとに出会ったのが、Empathでした。
Empathとの出会い
当時のEmpathでは、音声データから顧客満足度を推定する機械学習モデルの刷新をしようとしていました。こちらの記事でも述べたように、私はインターンとしてそのプロジェクトに参画して、心理学的な知見をもとに推定モデルの構築に携わりました。立場はインターンでしたが、プロジェクトでは異分野の社員や他のインターンの人たちとともに、対等に議論を行い、より良いものを作ると言う経験ができました。
このプロジェクト、そしてEmpathが提供する感情解析AIについて考えることを通して、私は「人の『感情』とはなんだろうか? どうやって測定したらよいのだろうか?」と考えるようになりました。
やっと見えてきた希望
そしてこのときやっと、私は研究者としての自分のキャリアに希望がもてるようになりました。
感情についてのこのような問いは、私がずっと抱いていた「人の『心』を適切に、正確に測定するためにはどうしたらよいか?」という問いの一部を構成するものであり、同時に、感情解析AIをつくるEmpathが会社として問い続けるべき問題でもあったからです。
研究をやる場所がアカデミアではなくたって、自分は研究ができるし、研究しいていいんだ。自分が研究していることが、なにかの、誰かの役に立つんだ。そう思えたことで、とても救われたのです。

今、私はEmpathという企業で哲学研究に取り組んでいます。
上で述べたような感情に関する哲学研究はもちろん、音声や言語を処理する情報工学を哲学的な視点から考察するという研究も開始しました。
これらの研究を続けることで、「企業のプロダクトやサービスに哲学を活かす」という事例を積み上げたいと思っています。今よりもっと哲学とビジネスの掛け算の可能性が広がれば、ビジネスパーソンと哲学の出会い、そして哲学研究者と企業の出会いがもっと増えるのではないか。そんな希望をもって、私は研究をしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
