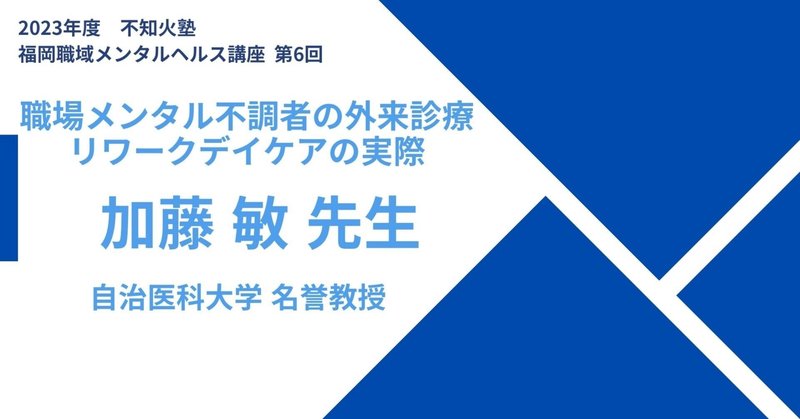
今だからこそ知っておきたいリワークデイケア-共に分かち合うとは-
厚生労働省が定義する5大疾病のなかに、精神疾患があるのをご存じでしょうか。
精神疾患を有する総患者数は約419.3万人おり、外来患者の総数と共に増加傾向にあります。(厚生労働省「患者調査」より)
不知火塾 第6回目は、自治医科大学名誉教授 加藤 敏先生による「職場メンタル不調者の外来診療・リワークデイケアの実際」がテーマでした。
長期休職者も年々増えておりリワークの必要性が高まってきているなか、リワークデイケアの実際を学んでみませんか。
不知火塾の詳細はこちら
次回は9月8日(金)
「職場のアルコール問題の解決」
(米沢 宏 先生)
次回案内はこちら
リワークデイケアの実際

加藤先生が現名誉院長を務める小山富士見台病院のデイケア・リワークデイケアの実際を説明いただきました。
デイケア・リワークデイケアの趣旨
1.大地にしっかり根ざす体を回復することを目指す
2.一緒に農作業をしたり、共に作品を作るなどしてメンバーやスタッフと同じ時を分かち合う
3.自身の病いを振り返り、文章に著す⇒担当医・スタッフと話す
4.誰にでも備わっている自己回復力(レジリエンス)を醸成する
リワークデイケアの目標は①規則的なデイケア(生活リズムの確立やミニ社会への参加)②自身のメンタル不調の振り返り③職場復帰と段階的に設定されているとのこと。
そのなかで、メンバーの個別性・自主性・自由を尊重することをデイケアのコンセプトにされていらっしゃいます。
利用するプログラムをメンバーが自分で決めているということが特徴的で、加藤先生はメンバーを信用することが大事であると話されました。
小山富士見台病院のリワークデイケアでは、個別の活動に加えて共同での園芸や農作業があることが印象的でした。
プログラムを自由に選んだり、皆で自然に触れたりすることが、レジリエンスの醸成にもつながっていることを学びました。
リワークデイケアを経て服薬の減量・中止、終診になるケースや、復職・再就職事例の詳細も共有いただき、事実に裏打ちされた説得力のあるお話でした。
リワークデイケアの意義ー身体面ー

毎日、職場に行く代わりに家から出て、スタッフ、仲間と一緒の時間を過ごし、散歩や作業をすることに意義があり、それらの活動によって「身体」の次元での主体の組みなおしができると話されます。
生活における2つの態勢:裂開相と内閉相
加藤先生は、ソト(外、共同世界)へ開かれ他人の「まなざし」にさらされることを裂開相、ウチ(内、家)に閉じて一人になり他人の「まなざし」から回避することを内閉相と説明されます。
通常はその2つのバランスがとれていますが、精神疾患患者は極端な裂開相と内閉相の状態にあるとのこと。
リハビリテーションは治療者と連帯し、裂開相と内閉相のバランスがとれた状態になることを目的とし、それが社会生活につながるとご指摘されました。
リワークデイケアの園芸作業では複数のメンバーやスタッフが一緒のモノを作り、収穫した作物を一緒に食べるといった共同作業をしており、連帯を強化する側面があるそう。
他のメンバーやスタッフと連帯し共に分かち合うことが、メンバーの共同性・社会化に繋がり、生きられる身体が生成されると述べられます。
リワークデイケアの意義ー言語面ー

自身が職場で体験したメンタル不調を言語化することも、プログラムの一つとのこと。
加藤先生の学術書を読み、感想を書いたり、内容についてデイケアスタッフや医師と対話をしているそうです。
言語化することで自己の足場を再生する歩みができると述べられます。
学術書と照らし合わせ、メンタル不調を振り返りながら、病識を得ることが安心につながることを事例を合わせて紹介いただきました。
専門用語の多い学術書を読み、自身を振り返ることは高度な心的緊張を要す作業ですが、仲間・スタッフがいる場があること、担当医師やスタッフを宛名にすることが作業の促進要因にもなるとも。
その作業の効果・意義を下記のようにまとめられました。
● 自分のメンタル不調が自分だけの体験でないことを知り孤独感が軽減・消失する
● メンタル不調の過程を理解し病識を得られる
● 休職することを正当化でき安心できる
● 強烈な孤独のなかで、生活史を振り返り言葉で著すことが心的外傷後の成長につながる
● 教養を身に付け、人間的成長が得られる
医師やスタッフがデイケアメンバーから教わることも多く、それが相互承認になり、実り多い精神療法になっているとのこと。
メンバー、医師、スタッフが共に学び、成長し、新たな人生観を紡ぎ出しているとおっしゃいます。
加藤先生は、メンバーと一緒のモノを見る、共に分かち合うことが対話に通じると述べられました。
講座のなかで"止まり木"としてのデイケアという表現が心に残りました。
職場復帰後、休みの日にデイケアに参加する事例や調子を崩したときに気軽に参加する事例も多いそう。
自身のメンタル不調の経緯を振り返る作業は負担が大きいと思いますが、医師やスタッフとの信頼関係が構築されているためメンバーは安心して作業ができるのだと感じました。
だからこそ、復職後もメンバーにとって休める”止まり木”になっているのだと思います。
貴重なお話をありがとうございました。
不知火塾の詳細はこちら
次回は9月8日(金)
「職場のアルコール問題の解決」
(米沢 宏 先生)
次回案内はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
